
�s���̊��́A�����ꊪ�ɂ܂Ƃ܂��Ă������A
�i������ܑ�Z�E�`�_�T�t�i�P�Q�T�R�`�P�R�R�R�j���A
�Z�\���{�̐��@�ᑠ��Ҏ[�����Ƃ��ɁA�㉺�ɕ����A
�B����t�͈̏ȉ��������ɂȂ����Ɠ`�����Ă���B
�����ł͒���ȁu�s���v�����i�S�Q�X���i�j���Q�������A
��P���i�`��P�T���i���ugyouzi3�v�ŁA
��P�T���i�`��Q�X���i���ugyouzi4�v�ʼn���������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����P
�^�O���c�̐������y�́A�ʎᑽ�����҂̋����Ȃ�B
�q�C�O�ڂ̑��A���̕��Ⴂ���܂����݂̂Ȃ���A
�_�����������Ȃ�̛ӘQ�Ȃ�Ƃ�����B
�s�m�̂��ɂɂ������Ƃ��A�g���������܂�}�ށA�����Ђ��ׂ��炸�B
����ЂƂւɓ`�@�~����̑厜���Ȃ��s���Ȃ�ׂ��B
�`�@�̎��ȂȂ邪���ɂ�������A
�`�@�̕ՊE�Ȃ邪���ɂ�������A�s�\���E�͐^�����Ȃ邪���ɂ�������A
�s�\���E���ȂȂ邪���ɂ�������A
�s�\���E�A�s�\���E�Ȃ邪���ɂ�������B
���Â�̐��������{�ɂ��炴���A���Â�̉��{����������ւ�B
���̂��ɂ����̂��Ƃ���������B
�~����̎��ȂȂ���ɁA���^�Ȃ��|�����B
�~����̕ՊE�Ȃ���ɁA���^�����|�Ȃ��B
�Ȃ��������̍��y�������āA
��M���悻�قӂāA��C���ւčL�B�ɂƂÂ��B
�g�D�̐l���ق��A�Еr�̑m���܂�����Ƃ��ւǂ��A�j�Ҏ��^����B
���݂�肱�̂����A�����l�Ȃ��B
���Ȃ͂�����̕��ʔ��N�����㌎��\����Ȃ�B
�L�B�̎h�j�l��Ƃ��ӂ��́A����������Č}�ڂ����Ă܂�B
���Ȃ݂ɕ\���C���ĕ���ɂ������A�l�V���Μ��Ȃ�B
���邷�Ȃ͂��t�𗗂��ċӉx���āA�g�ɏق��������Č}�������Ă܂�B
���Ȃ͂����̂Ƃ��\������Ȃ�B
���F
�s���F ���s�����̕ێ��B�C�s�̎����B
�@���@�Ɖ����̕ێ��B
�^�O�F �����̕ʖ��B�_�O�A�k�U�A�U�U�ɓ����B
�^�O���c�F �����ɑT�������炵��
�����T�̏��c�B����t�B
�������y�F �����̃C���h���瓌���̒����ɓn���������ƁB
�ʎᑽ�����ҁF���d�ޗt���҂��琔����
���\����ڂ̋��c�w���ҁB
���C���h�̔g����K���̏o�g�ŒB����t�̎t�Ɠ`������l�B
�����i���傤���傭�j�F�������܂��߂邱�ƁB
�O�ځF�O�N�B�ڂ͂Ƃ��̈ӁB
���F �����Ԃɂ��Ƃ��Ă����B
�~���Ӗ����A�܂��Ό����Ӗ�����B
�����܂��F �炢�A��V�ł���B�@
�_���F �@�_�Ɖ��ƁB�@
�ӘQ�F �댯�ȑ�g�B
�}�ށF �@���}�ȘA���B
����F��������L��A��������l�X�B
�����F �������B�@
�悻�قӁF ������������A����������B
�L�B�F �L�B�{�B�L���ȏ邨��т��̕t�߂̒n�B
��]�ɗՂ݁A�O���Ƃ̌�ʂ������Ƃ������J�����B�@
�ƂÂ��F �Ƃǂ��A�����蒅���A�B����B
�g�D�F �g��������D�B�֑D�B
�Еr�i����т傤�j�̑m�F ��Ђ␅�r�����������āA
�펞�t�m�̗p�ɂ��Ȃ��Ă���m�������B�@
�j�ҁF ���̋L�^���i��l�B�@
���^�F �L�^���������Ȃ����ƁB
����F ���̎���i�T�O�Q�`�T�T�V�j�B���͍��̖��B�@
���ʔ��N�����F �T�Q�V�N�B
�h�j�F �����B�n���̒����������B�@�@
���F �o��̗�B���q�ɑ���ڑ҂̗玮�B�@
�}�ځF �o�}���Ă��ĂȂ��B�@�@
���v�F ���݂��Ȃ��Ȃ邱�ƁB�@
�\�F�N��ɂ��Ă܂�̕����B
�閧��K�v�Ƃ��Ȃ����̂������B�@
�C���F �����A�����������B
������F �\���グ��A�\���B
�Μ��i�����j�F�܂��߂ɋ߂邱�ƁB�@
�Ӊx�i���j�F �@�@��낱�Ԃ��ƁB�@
�}���i�������傤�j�F �łނ����ď��҂���B�@
������
�����T�̏��c �B����t���A�����C���h���瓌�̒����ɗ����̂́A
�ʎᑽ�����҂̋����ɂ��B
�q�C�O�N�̔N���́A���̕���̒ɂ܂��������łȂ��A
�_���̏d�Ȃ�댯�Ȕg�Q�̗��ł������Ǝv����B
���m�̍��ɓ��낤�Ƃ��邱�Ƃ́A
�g�̂Ɛ�����ɂ��ޖ}�l�ɂ͎v�����Ȃ��B
����͂Ђ�����A���@��`���Đl�X������~����
�Ƃ����厜�߂��琶�܂ꂽ�s���ł���B
�@��`���鎩�Ȃł��邩�����ė����̂ł���B
�@��`���鐢�E�ł��邩�����ė����̂ł���B
�S�Ă̐��E�͐^���̓��ł��邩�����ė����̂ł���B
�S�F���͎��Ȃł��邩�����ė����̂ł���B
�S�F���͂����S�F���ł��邩�����ė����̂ł���B
�����ɐ��܂�悤�Ƃ��������{�łȂ����Ƃ����낤���B
�����̉��{������ł��邱�Ƃ�W���邾�낤���B
���̌̂ɁA��t�͂��̂悤�ɃC���h�������ė����̂ł���B
�����ɒ��l�X�i����j���~�����Ȃł��邩��A
�����^�킸�A����邱�Ƃ��Ȃ��B
�����̍��ɕʂ�������A��D�𐮂��A��C���o�čL�B�ɓ��������B
���D�̐l�͑����A��t�ɐ����m�����������̂����A
�������j�Ƃ͋L�^���Ă��Ȃ��B
���݂����̎���m��l�͂��Ȃ������B
����͗��̎���̕��ʔ��N�i����T�Q�V�N�j�㌎��\����������Ɠ`������B
�L�B�̒����J�V���A�B����t���N��̗�������Č}�����B
�ނ͏�t���������ĕ���ɐ\���グ���B�J�V�͋������M�S�ł������B
���̕��ʔ��N�i����T�Q�V�N�j
�����T�̏��c �B����t�͔ʎᑽ�����҂̋����ɏ]���āA
�����C���h���瓌�̒����ɗ����B
�@ ���̗��͕���̒ɂ܂��������łȂ��A
�_���̏d�Ȃ�댯�Ȃ��̂ł������B
�c�t�����́A���@��`���Đl�X������~�����Ƃ����B����t�̑厜�ߐS���琶�܂ꂽ�s���ł���
�ƒB����t�̍s���ɂ��ďq�ׂĂ���B
�B����t�ɂ��Ă͕Ɋޘ^��]�e�^�̌��Ă�
���グ���Ă���̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B
�i�]�e�^��Q�� �B���f�R���Q���j�B
�i�Ɋޘ^��P�� �B���f�R�������Q���j�B
�����Q
���c�A���˂ɂ�����ė����Ƒ�������ɁA�����ƂӁA
�u���A���ʂ��ߗ��A����A�o���ʂ��A�m��x���邱���A
�����ċI���ׂ��炸�A���̌������L���B�v
�t�H���A
�u���тɌ��������B�v
��H���A
�u���̈Ȃɂ����������B�v
�t�H���A
�u����͒A�l�V�̏��ʁA�L�R�̈��Ȃ��B
�e�̌`�ɐ��ӂ��@���A�L���嫂����ɔ��B�v
��H���A
�u�@���Ȃ邩����^�̌����B�v
�t�H���A
�u��q���~�ɂ��āA�̎�����Ȃ��B
���̔@���̌����́A�����Ȃċ��߂��B�v
�閔�₤�A
�u�@���Ȃ���ꐹ�����`���B�v
�t�H���A
�u�f�R�����B�v
��H���A
�u���ɑ���҂͒N���B�v
�t�H���A
�u�s���B�v
��A�̌傹���B�t�A�@�̕s�_�Ȃ��m��B
���ɂ��̏\���\����A�Ђ����ɍ]�k�ɂ䂭�B
���̂Ƃ��\�ꌎ��\�O���A���z�ɂ�����ʁB
���R���ю��ɋ��~���āA�ʕǎ����A�I���ّR�Ȃ�B
��������ǂ��A鰎���s�тɂ��Ă��炸�A�͂��ׂ��������炸�B
�t�͓�V���̙�����Ȃ�A�卑�̍c�q�Ȃ�B
�卑�̉��{�A���̖@�Ђ��������n����B
�����̕����́A�卑�̒�҂Ɉ��̂͂��ׂ�����ǂ��A
���c���������ނ邱���날�炸�B
���ɂ����Ă��A�l�����Ă��B
�Ƃ��ɕ�x��?掂��~�����A�ɂ��܂��B
�������t���אS������ނ�ɂ��炸�A�����ɂ�����B
�����̂��Ƃ��̌������ق��Ƃ��ւǂ��A
���n�̐l���A�����q��̎O������ьo�_�t�̂��Ƃ��ɂ����ӂ́A
�����Ȃ�A���l�Ȃ���Ȃ�B
����Ђ͂����ӁA�T�@�ƂĈ�r�̖@����J�����邪�A
���]�̘_�t���̏��]���A���c�̐��@�����Ȃ�����ׂ��Ƃ����ӁB
����͕��@���q�����ނ鏬�{�Ȃ�B
���c�͎߉ޖ�����\�����̒��k�Ȃ�B
�����̑卑���͂Ȃ�āA���n�̏O�����~�ς���A
����̂������ЂƂ������邩�����B
�����c�t���������A���n�̏O���A�����ɂ��Ă������@���������ށB
�����Â�ɖ����̍��ɂ�Â�ӂ݂̂Ȃ��B
���܂��炪���Ƃ��̕Ӓn�����̔�ёՊp�܂ł��A
�����܂Ő��@���������Ƃ�����B
���܂͓c�v�_�v�A��V�����܂ł���������A
�������Ȃ���c�t�q�C�̍s���ɂ����͂��Ȃ�B
���V�ƒ��ƁA�y���͂邩�ɏ���A�����͂邩�Ɏא�����B
��E�͂̑厜�ɂ��炸���́A�`���@���̑吹�ނ��ӂׂ����݂ɂ��炸�B
�Z���ׂ�����Ȃ��A�m�l�̐l�܂�Ȃ�B
���炭���R�Ɋ|�����邱�Ƌ�N�Ȃ�B
�l�����NJϔk����Ƃ��ӁB
�j�҂�����K�T�̗�ɕҏW����ǂ��A�����ɂ͂��炸�B
�����������`���鐳�@�ᑠ�A�ЂƂ�c�t�݂̂Ȃ�B
���F
���ˁF �]�h�Ȃ̒n���B�ŏ���e���ɋ��ˋ�������A
��A�]�J�����˕{�Ɩ��t�����B
�ʂɌ��N�ٖ̈��ł���Ƃ�����������A
���݂ł͓싞�̉�̂Ɏg���Ă���B�@
�����F���̕���B���͂T�O�Q�N����T�T�V�N�܂ő����������B
����͂��̑��c�J��
�i���傤����A�S�U�S�`�T�S�X�A�݈ʁF�T�O�Q�`�T�S�X�j�B
�n�ߍւ�贏B�ɂ�����n�������ł��������A��ɒ�ʂ�D���đ��ʂ����B
�Ⴂ������w����D�݁A�������̌����ɂ��w�͂����B
��������i�̖d���ɉ���ĉ쎀�����B
�݈ʂS�W�N�B�@

�}�P�R ���̕���@

�}�P�S �@�B����t�@
�x�F �m��ɋ��̏؏��^����B�@
���F ���ׂĂ��B
�I�F ���邷�B�L�Ɠ����B
�l�V���ʁF�@ �l�ԊE�E�V��E�̏����ȉʕ�B�@
�L�R�V���F�@ �ϔY���N�������B
��q���~�F ����Ȓq�d�������ɍs���킽�肵�����~���ł��邱�ƁB�@�@
�̎����F �g�̂����̍�ׂ������Ȃ��Ă����R�Ɉ��肵�Ă���A
����̏�Q���Ȃ����ƁB�@
�����Ȃċ��߂��F �����I�Ȃ��������Ƃ����w�͂ł�
���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�@
�����F �@���Ҏߑ����������^���B�@
���`���F�@�ł���{�I�Ȑ^���B
�f�R�����F ���X���X�Ƃ��Đ_��I�ȉ������Ȃ��B
�s���F �m��ʁA�킩��ʁB
�B����t���g�A���Ȃ̖{���i�^�̎��ȁj�����t�ŕ\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�@
�̌�F �����܂����Ƃ邱�ƁB�͂��ƌ�邱�ƁB
�@�F �@���A�Ƃ��A����A�@��A���������B
�]�k�F �g�q�]�̖k���B
���z�F �����̖k�Ɉʒu���A��������������܂������B
�����E�㊿�E�����E��鰁E�@�E�ܑ�Ȃǂ��������������s�Ƃ����B
���~�F �@���͂���ɏZ�ށA���肸�܂�������B���~�͎~�h�B
鰎�F 鰂̍��̍���B鰂͉����̖��B
�k鰂Ƃ���鰂Ƃ��Ăς�A�S�O�O�N����T�R�T�N�܂ő������B
�s�сF �т͎���B
�s�т͎t���╃�Ɏ��Ă��Ȃ��̈ӂŁA�s�q�̈ӂ�\�킷�B�@
������F �@�C���h�ɂ�����l�̊K���̂����A
���Ɉʂ���N�V���g���A�K���B�����E���l�̊K���ł����āA
�x�z�K�����Ӗ�����B��͎푰�B�@
���n�F �Ȃ�čI�݂Ȃ��ƁA�K�n�B
��x�F ��x�O���B�k�C���h����T�O�W�N�ɗ��z�ɗ����m�B
�ܗj�E�ӓߖ����ƂƂ��ɖk鰎���ɂ������\�I�Ȍo�T����ҁB
�B����t�ւ̎��i����A��t�̓ŎE���͂������Ɠ`�����Ă���B�@
�~���F�@�Ƃ߂�A�ւ���B
�������t�F ��鰂̑m�ŁA�\�n�o�_�̖|��ɎQ�^�����̒��ߏ������A
�܂��l�����̋����ɂƂ߂��B
�B����t�̓ŎE���͂������Ɠ`�����Ă���B
���l�F �l�����������l�B
��r�F ��̋ؓ��B
�@�@ �����F �������������ƁB
��ёՊp�i�Ђ������������j�F �є�����Ԃ��Ă�����̂�
���Ɋp���͂₵�Ă�����́B�����B�@
�y���F ���y�I�Ȏd������B
�����F �n���I�ȕ����B
�NJϔk����F �ǂɂނ����ĊϏƂ����Ă���o�������m�B
�j�ҁF ���j�ƁB
�K�T�F ���T����K���邱�Ƃɂ���āA
���T�ȊO�̉��炩�̖ړI��B�����悤�Ɠw�͂���l�X�B
��i�̌�����
���c �B���́A���˂ɓ������ė��̕���ɉ�ƁA����͐q�˂�
�u���͑��ʈȗ��A�������āA�o���ʂ��A�m��x����Ȃ��A
��������Ȃ��قǕ��@�ɐs�����ė����B
����ɂ���Ăǂ�Ȍ��������邾�낤���H�v
�t�͌������A
�u���ׂĉ��̌������Ȃ��B�v
����͌������A
�u�Ȃ������������̂��B�v
�t�͌������A
�u���̂悤�Ȃ��Ƃ̌����́A�l�ԊE��V��E�ɉ����鏬���ȉʕ���A
�ϔY�̌����ƂȂ���̂��B
�e���`������̂ɏ]���悤�ɁA�L��Ƃ��Ă��^�̂��̂ł͂Ȃ��B�v
����͌������A
�u����ł́A�܂��Ƃ̌����Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��H�v
�t�͌������A
�u����Ȓq�d���܂ǂ��ɋ���A���炩�ȐÎ₪�����邱�Ƃł��B
���̂悤�Ȍ����́A���Ԃŋ��߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�v
����܂��q�˂��A
�u�ł͕��@�̐��Ȃ���̐^���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��H�v
�t�͌������A
�u�S�������Ɛ���n���āA�}�l�����l�������B�v
����͌������A
�u���ƑΘb���Ă���A���O�͈�̉��҂Ȃ̂��B�v
�t�͌������A
�u�m��܂����B�v
����͎t�����������Ă���̂��킩�炸�A
�t���܂�����Ƃ͋@�����K��Ȃ����Ƃ�m�����B
�����Ŏt�́A���̂P�O���P�X���ɖ����ɗg�q�]�̖k�֍s���A
���̔N�̂P�P���Q�R���ɂ͗��z�ɓ��������B
�����āA���R�̏��ю��ɗ��܂��ĕǂɌ������č����A
�I���ّR�Ƃ��Ă����B
�������A鰂̍���������ŒB���̂��Ƃ�m�炸�A
�����p�Ƃ��ׂ��������m��Ȃ������B
���c�B���́A��C���h�̉����̏o�g�ŁA�卑�̍c�q�ł���B
�卑�̉��{�ł́A���̖@���v�����K�n���Ă���B
�����̕����́A���̂悤�ȑ卑�̒鉤�Ɍ�����ƁA
�p�����������Ƃ����邪�A���c�͐S�����Ȃ������B
���̍��i�����j���̂Ă��A�l�X���̂ĂȂ������B
���ɕ�x�̔�掂��Ă�����ɂ����A���܂Ȃ������B
�܂��������t�̎אS�����܂��A�������Ƃ��Ȃ������B�@
���c�ɂ́A���̂悤�Ȍ������������A���n�i�����j�̐l�Ԃ��A
�����ς畁�ʂ̎O���@�t��o�_�t�̂悤�Ɏv�����̂́A
�܂��Ƃɋ����ł������B
���̍��i�����j�̐l�Ԃ����l�ł��������߂ł���B
����l���v���ɂ́A
�u�T�@�ƌ����Ĉ�̋���������Ă��邪�A
���̂ق��̌o�_�̎t�����̌��������A
���c�̐������@���A���Ǔ������̂��낤�B�v�ƁB
�@����͕��@��ς�ɉ��������҂̍l���ł���B
���c�́A�ߑ������\����ڂ̐����Ȍ�p�҂ł���B
�����̑卑�𗣂�āA���n�̐l�X���~�ς������c�ɁA
�N��������ׂ邱�Ƃ��ł��邾�낤���B
�������c���C���h���痈�Ȃ���A
���n�̐l�X�́A�ǂ����ĕ��̐��@���������邱�Ƃ��o�������낤���B
�����k�ɖ����̌o���̋����ɔς�킳��Ă����������������낤�B
���݁A��X�̂悤�ȕӒn�����ɏZ�ށA
�тɕ����p���ڂ����悤�Ȗ��J�̎҂܂ŁA
�����ɐ��@�����Ƃ��o����B
���ł͔_�v��A���̘V�l����q���Ɏ���܂ŕ��@���������Ă��邪�A
����͗v����ɁA���c���q�C���Ė@��`�����s���ɋ~���Ă���̂ł���B
�����C���h�ƒ��ł́A���y��ꡂ��ɗD����A
�K���ɂ�ꡂ��ɐ��ׂ̈Ⴂ������B
�����̗�钆�͑�E�͂̑厜�߂��Ȃ���A
�@����`������吹�҂ł��������ׂ��ꏊ�ł͂Ȃ��̂��B
���c�͏Z�ނׂ�����������A�m�l����Ȃ̂ŁA
�Ƃ肠�������R�Ɏ~�܂��ċ�N���߂������B
�l�X�͔ނ̂��Ƃ�
�u�NJϔk�����i�ǂ��ςȂ��獿�T����o�������m�j�v�ƌ������B
���j�Ƃ́A�ނ��K�T�҂̕��ނɕҏW�������A�����ł͂Ȃ��B
�����畧�ւƑ��`�������@�ᑠ�i���@�̐^���j��`�����l�́A
�c�t�B�������ł���B
�������ł͑�ꕶ�i�ɑ��������T���c ���B���̍s���ɂ��āA
���ɕ��B���Ɨ��̕��镐���J��
�i�S�U�S�`�T�S�X�A�݈ʁF�T�O�Q�`�T�S�X�j�̖ⓚ�ɂ��ďq�ׂĂ���B
�@ ���j�Ƃ́A�B�����K�T�҂̕��ނɕҏW�������A�����ł͂Ȃ��B
�����畧�ւƑ��`�������@�ᑠ�i���@�̐^���j��`�����l�́A
�c�t�B�������ł�����B���̐����Ɠ`�@�������]�����Ă���B �@
��Q���i�̕��͂��Ղ����������₷���B
�����T�̏��c �B����t�ƕ���̖ⓚ�ɂ��Ă�
�Ɋޘ^��]�e�^�̌��ĂɎ��グ���Ă���̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B
�i�]�e�^��Q�� �B���f�R���Q���j�B
�i�Ɋޘ^��P�� �B���f�R�������Q���j�B
�����R
�@ �Ζ�̗ъԘ^�ɉ]���A
�u���B���A���ߗ����鰂ɔV���B���R�̉��Ɍo�s���A���тɘߏB
�ʕlj�������߂Ȃ�A�K�T�ɂ͔B
�v�������Đl ���̌̂𑪂邱�Ɣ����B
���ĒB�����ȂďK�T�ƈׂ��B
�v��T�߂́A���s�̈�Ȃ�̂݁A�����ȂĐ��l��s���ɑ����B
���������̐l�A�V���ȂĂ��B
�j�̎ҁA���]���ďK�T�̗�ɓ`�ˁA�͖؎��D�̓k�ƌނȂ炵�ށB
�R���嫂��A���l�͑T�߂Ɏ~�܂�݂̂ɔA������ �T�߂ɈႹ���B
�Ղ̉A�z���o�łāA������ �A�z�ɈႹ���邪�@���v�B
�������߂ĒB�����������A�����₤�A
�u�@���Ȃ���ꐹ�����`�B�v
�����ĞH���A
�u�f�R�����B�v
�i��ŞH���A
�u���ɑ���҂͒N���B�v
���H���A
�u�s���B�v
�B�������ĕ����ɒʂ����炵�߂A
�����������̎��ɉ����āA�\���������炵�߂��B
�Ζ�ъԘ^�@�o�͌d�^
���F
�Ζ�o�͌d�^�i�����͂����j�T�t�F ���͜d���B���B�������̐l�B
�\�l�̎��A����������A�\��̂Ƃ����x�B�Ζ�̗ݓ����ɏZ�݁A
�܂����B�̐������ɏZ�B
��A��������n�݂��Ă���ɏZ���A�P�P�Q�W�N�����B�N�T�W�B
�ъԘ^�A�T�ёm��`�O�\���A���m�`�\�Ȃǒ������ɂ߂đ����B�@
�ъԘ^�F�@ �o�͌d�^�T�t���ъԋ��m�Ƌ����ŁA
�Ðl�̌��s�E��`�E���P�E�v�ꓙ�A�O�S�]�����W�߂����́B
����Ȃ�A�P�P�O�V�N�Ɋ��s���ꂽ�B
�Ζ�ъԘ^�Ƃ��Ă�Ă���B�@
�ߏ�i�����傤�j�F �߂͂悹��A�����B
�ߏ�͎�����悹������̈ӁB�|���ɓ����B���@�ɐ������邱�ƁB�@
�����i���j�F �����ɓ����B���T�̂��ƁB
�́F ���Ƃ��A�����B�@
�͖؎��D�V�k�F �͂ꂽ������������D�̂悤�ɁA
���ɓI�ȋ֗~��`�ɓO���Đ����̖����������Ă��܂����A���B
�ށF �Ȃ��܁A�������A���ށB
�T�߁F�@ ����dhyana�̉��ʁB����ł͒�A�×��Ƃ����B
�����ŐS�����h���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ������̏�Ԃ��w��
�S�g���ύt���W�����肵����ԂɒB���邽�߂��ґz�@�B�T��B�@
�ՁF�@ �Պw�B�A�z�̓�̗͂������Ƃ��Ė��ۂ̕ω����l����B
����Ɋ�Â��ĉF����I�Ɋώ@���A�l������������w��B�@
�A�z�F�@ �V�n�̊Ԃɂ����Ė��������̗́B
�����F�@ �n���̌��t�B�����ł͒�����B
��R���i�̌�����
�o�͌d�^�T�t�̒���ł���ъԘ^�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u���B���́A���ߗ��̍�����鰂̍��֕������B
�����Đ��R�̂ӂ��Ƃɍs���A���ю��ɐg�����B
�B���́A�I���ǂɌ������č��T���邾���ł��������A
����͒P�Ȃ�T��̏C���ł͂Ȃ������B
�����ԁA�l�X�͂��̈Ӗ��𐄂��ʂ邱�Ƃ͂Ȃ������B
�����ŒB����T����C������҂ƍl�����B
���������T��Ƃ́A�����̏C�s�@�̒��̈�ł���B
�ǂ����Ă���ŁA���̐��l�������s�������Ƃ��o���悤���B
�����������̐l�́A���̂悤�ɍl�����̂ł���B
���j�Ƃ�������ɏ]���A�ނ�T����K������҂̕��ނɕ��ނ��A
�͂��₦���D�̂悤�Ȏ҂����Ɠ���Ɉ������̂ł���B
�������Ȃ���A���̐��l�́A�T�肾���Ɏ~�܂炸�A
�������T��ɔw�����Ƃ͂Ȃ��B
����͈Ղ��A�z�̓�C����o�āA
�������A�z�ɔw���Ȃ��悤�Ȃ��̂ł���v�B
���̕���́A���߂ĒB���ɉ�������ɐq�˂��A
�u���l�̌�������`�̐^���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��H�v
�t�͓������A
�u�S�������ƊJ���Ė}�l�����l���������Ƃł��B�v
����ɕ���͐q�˂��A
�u�}�l�����l�������̂Ȃ�A���Ȃ��͈�̉��҂Ȃ̂��H�v
�t�͓������A
�u�m��܂����v�B
�����B���������̌��t�ɒʂ��Ă��Ȃ���A
�ǂ����Ă��̎��ɁA���̂悤�ȑΉ����o�����ł��낤���B�v
���̕��i�ł͊o�͌d�^�T�t�̗ъԘ^��
���p���đc�t�����̈Ӗ����c�_���Ă���B
�u�����ɓn���������B���́A
������鰂̍��֕����A���R�̂ӂ��Ƃ̏��ю��ɐg�����B
�B���́A�I���ǂɌ������č��T���邾�����������A
����͒P�Ȃ�T��̏C���ł͂Ȃ������B
�������A�l�X�͂��̈Ӗ��𐄗ʂ����A
�B����T����C������K�T�҂ƍl�����B�@
���������T��́A��C�s�@�ɉ߂��Ȃ��B
�K�T�҂ƌ������t�ŁA
���̐��l�������s�������Ƃ��o���Ȃ��ɂ�������炸�A
�����̐l�́A���̂悤�ɍl�����̂ł���B
���j�Ƃ�������ɏ]���A�ނ�T����K������҂̕��ނɕ��ނ��A
�͂��₦���D�̂悤�Ȏ҂����Ɠ���Ɉ������B
�������Ȃ���A���̐��l�́A�T�肾���Ɏ~�܂炸�A
�������T��ɔw�����Ƃ͂Ȃ��B
����͈Ղ��A�z�̓�C����o�āA
�������A�z�ɔw���Ȃ��悤�Ȃ��̂ł���Əq�ׂĂ���B
���R�̂ӂ��Ƃ̏��ю��ɐg�����B���͏I���ǂɌ������č��T���邾���������B
�����Ől�X�͒B����T����C������҂ƍl���A
�T����K������K�T�҂̕��ނɕ��ނ��A
�͂��₦���D�̂悤�Ȏ҂����Ɠ���Ɉ������B
�㔼���ł́A���̕���ƒB���̉�b���Љ�A
�u�����B���������̌��t�ɒʂ��Ă��Ȃ���A�ǂ����Ă��̎��ɁA
���̂悤�ȑΉ����o�����ł��낤���B�Əq�ׁA
�B�����P�Ȃ�K�T���ł͂Ȃ��A�A���������@�̐^���ł���T��`���邱����\�ߌv�悵�Ă�������
��������w���̂��ƍl���Ă���B
���̕��i�ł������ɓn�������B���̍s���ɂ��ďq�ׂĂ���B
�B����t�ƕ���̖ⓚ�ɂ��Ă͕Ɋޘ^��]�e�^�̌��ĂɎ��グ���Ă���B
�i�]�e�^��Q�� �B���f�R���Q���j�B
�i�Ɋޘ^��P�� �B���f�R�������Q���j�B
����4
�@����������Ȃ͂��A�����鰂ւ䂭���Ƃ����炯���B
���R�Ɍo�s���ď��тɘߏB
�ʕlj������Ƃ��ւǂ��A�K�T�ɂ͂��炴��Ȃ�B
�ꊪ�̌o��������������ǂ��A���@�`���̐���Ȃ�B
����������j�҂�����߂��A�K�T�̕тɂ�ʂ�͎����Ȃ�A���Ȃ��ނׂ��B
�����̂��Ƃ����Đ��R�Ɍo�s����ɁA������Ă��ق�A���͂�ނׂ������Ȃ�B
����̂����날��A���̎��������낭����B
����̂����날��A���̉�������B
�����Ȃق킷�ꂸ�A����������l���ق��B�����l�Ƃ��ӁB
�c�t�̑剶�́A����ɂ�������ׂ��A
�c�t�̎����͐e�q�ɂ�������ׂ���B
���炪���˂����Ђ����|���ׂ��B
���y���݂��A���ɂ��܂ꂸ�A�������炸�A
�����݂��A�V��ɂ̂ڂ��l���܂��Ȃ��A�l�S�ЂƂւɂ��납�Ȃ�B
�J�J��肱�̂��������̐l�Ȃ��A�������܂��Ƃ����������B
���͂��́A�����Ȃ邩���A�����Ȃ邩���Ƃ��炴��ɂ��B
�O�˂̖{���ɂ��炫�ɂ��āA�����̂��Ƃ��Ȃ�B
���͂��܍˂̐�����������B
���̋��͊�O�̐��F�ɂ��炫�ɂ��ĂȂ�B
���炫���Ƃ͌o�������炴��ɂ��ĂȂ�A�o���Ɏt�Ȃ��ɂ��ĂȂ�B
���̎t�Ȃ��Ƃ��ӂ́A���̌o���A�����\���Ƃ��ӂ��Ƃ����炸�A
���̌o�A�����S��A���������Ƃ��炸�A
�������̐������݂̂�ށA�����\��A���������Ƃ��ӂ��Ƃ����炴��Ȃ�B
���łɌÌo������A�Ï�����ނ����Ƃ��́A���Ȃ͂���Â̈ӎ|����Ȃ�B
��Â̂����날��A�Ìo�����茻�O����Ȃ�B
�����c�A�����鰑��c�A�����V�ۂ̘���������߁A
�n�`�̌������ւ���҂Ȃ�B
�����̂��Ƃ��̌o�T�A������ނ�Ƃ��A���������O�˂�����߂�����Ȃ�B
���܂������̂��Ƃ��̐��N�̉��ɂ��͂���S���̂Ƃ�����́A
�����Ȃ�����N�ƂȂ�ЁA�����Ȃ�����e�ƂȂ�ӂƂ��炴��A
�N�q�Ƃ��Ă����͂�ނׂ����̂Ȃ�A�e���Ƃ��Ă����͂�ނׂ��Ȃ�B
�b�ƂȂ����A�q�ƂȂ����A�����������Â�ɂ����ʁA
���A�������Â�ɂ����ʂ�Ȃ�B
�����̂��Ƃ��Ȃ�Ɩ�ɂ��܂�āA���y�̂������E�A
�Ȃق��Â���l�Ȃ��A���낫���ʂȂق����ށB
�ɂ����Ƃ��Ȃق�������A���߂��Ƃ��͌������܂�Ȃ��B
�����̂��Ƃ��̕Ӓn�A�����̂��Ƃ��̔��˂̐g���������Ȃ���A
�����܂Ŕ@���̐��@��������݂��ɁA
�����ł����̔��˂̐g���������ނ����날���B
������ł̂��ɁA�Ȃɂ��̂̂��߂ɂ����Ă�Ƃ���B
�����������������A�Ȃٖ@�̂��߂ɂ����ނׂ��炸�A
���͂����˂̐g������B
���ƂД��˂Ȃ�Ƃ��ӂƂ��A�ד��ז@�̂Ƃ���ɁA
�����܂����邱�Ƃ���A��V�����M�Ȃ�ׂ��A
�ˉ������M�Ȃ�ׂ��B
���ق悻�V�_�n�_�A�O�E�O�������M�Ȃ�ׂ��B
��������ɁA���c�͓�V�����������̑�O�c�q�Ȃ�B
���łɓV�����̒���Ȃ�A�c�q�Ȃ�B
���M�̂���܂ӂׂ��A�����Ӎ��ɂ́A
�����Â����Ă܂�ׂ��V���A���܂����炴��Ȃ�B
���Ȃ��Ȃ��A���낻���Ȃ�A�a����Ȃ��B
���͂��킪���ɂ͉����̐�݂Ȃ�A
�����ł��卑�̍c������܂ӋV�������B
���ƂЂȂ�ӂƂ��A�I�Ȃ��Ă킫�܂ӂׂ��炴��Ȃ�B
����ƒ�҂ƁA���̋V���ƂȂ�ׂ��A
���̗���y�d����ǂ��A�킫�܂ւ��炸�B
���Ȃ̋M�˂����炴��A���Ȃ�۔C�����B���Ȃ�۔C������A
���Ȃ̋M�ˁA���Ƃ�������ނׂ��Ȃ�B
���F
�����F�����������A�����炷�B
����F�@ �����̎�l�B�@
���F ��x�O����������t�Ȃ�
�B����t�ɑ��Ĕ��Q���������l�X���w���B�@
�āi���傤�j�F�Ă͒����̌Ñ�ɂ����閼�N�̖��B
�����ł͋Ă̂悤�ɂ����ꂽ�l���B�@
�����F�@���ߐ[�����B
�����F �@���ԓI�ȉ��`�B
������ԁF�@ ����ׂ�A��r����B
���y�F�@�����B
���F�����̕����B
�����F���l���������邱�ƁB
�F�@�@�V�ƒn�B
�O�ˁF�@ �V�E�n�E�l�̎O�������B�˂͂͂��炫�B
�{���F ���ƂƂ����B�n�ƏI�B
�܍ˁF �E�E�y�E���E���̌܂B�����A�܍s�̂��ƁB
���F�F �����łƂ炦������́B
�o���F�o�T�⏑�ЁB
�����F�@�@ ������Ă��邱�Ƃ̊O���I�ȈӖ��B
��ÁF�@ �Ðl��炤���ƁB
�����c�F ���̍��̑n�n�ҁB���M�B�@
鰑��c�F鰂̕���B�����B
�V�ۂ̘�F�������C��������Ă��鎍�B
�S���F�@�����̖��A�l���A�����B�@
���N�F �N�ɂ����邱�ƁB
�Ȃ�ӁF �������Ď����̐g�ɂ���B�܂ȂԁB�@
���e�F�@�e�ɂ����邱�ƁB
�N�q�F�@�@�N��B�@
�����F�@�@���a����ڂ�����悤�ȕ�ʁB
�Ɩ�F �@�ƕ��B�@
�݂��F�@�@�r���B
��V�F�@�@�V��A���A�V�̐_�B�@
�։��F �]�����B�@�@
�V�_�n�L�F�V�̐_�ƒn�̐_�B
��S���i�̌�����
���̂悤�ɁA�B���͗�����鰂֍s�������Ƃ͖��炩�ł���B
���R�ɍs���A���ю��Ɏ~�܂����B
�����ĕǂɌ����č��T�������A����͑T��̏K�B�ł͂Ȃ������B
�t�͈ꊪ�̌o�����������Ȃ��������A���@��`�����������ȋ���ł���B
�������A���j�Ƃ͂��̂��Ƃ𖾂炩�ɂ����A
�T����K�B����ҒB�̕��ނɕ��ނ����̂́A
�܂��Ƃɋ����ŁA�߂��ނׂ��ł���B
���̂悤�ɂ��Ďt�͐��R�ɍs�������A
���l�̌������V�q��Ꟃ�i�����悤�ɁA�t���掂���l�B�������B
����ނׂ��l���ł���A�܂��Ƃɋ����ł���B
�S����l�Ȃ�A�N�����̎t�̎������y�邾�낤���B
�S����l�Ȃ�A�N�����̎t�̉��ɕȂ��ł����悤���B
���Ԃ̉���Y��邱�ƂȂ��A��ɂ���l�͑����A�����l�ƌ����̂��B
�c�t�̑剶�́A����̉���������Ă���B
�c�t�̎����́A�e�q�ɂ���ׂ��Ȃ��B
���{�ɏZ�މ�X�����˂Ȃ��Ƃ́A�v�����낵���قǂ��B
�����̍��y���������Ƃ������A���Ƃ����������ɐ��܂ꂸ�A
���l��m�炸�A���҂������A�V��ɏ�����l�����������A
�l�̐S�͂܂����������ł���B
���y���J���ĈȌ�A���������������l�͂Ȃ��A
���������������Ƃ��Ȃ��B
����́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����ނ��ƂŁA
�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����邱�Ƃł��邩��m��Ȃ����炾�B
�V�q�ɂ�鐭����A
�V�ƒn�Ɛl�̖{���̓����ɈÂ����炱�̂悤�ɂȂ�̂ł���B
�܂��Ė������\������؉Γy�����ɂ�鐢�̐�����m��Ȃ��B
���̋��́A��O�̌���������̂ȂǁA�����̐^���ɈÂ����Ƃ������ł���B
�Â��̂́A�o����m��Ȃ�����ł���A�o���ɖ��邢�t�����Ȃ�����ł���B
���̂悤�Ȏt�����Ȃ���A���̌o���͊�\���Ƃ������Ƃ�m�炸�A
���̌o�͊��S��A���猾�ł���ƒm�炸�A�������͂̔瑊������ǂނ̂��B
�����Ɋ����A��������������Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��̂ł���B
���ɁA�Ìo��m��A�Ï���ǂ�ł���l�́A�Ðl��炤�u������B
�Ðl��炤�S������A�Ìo�͂���ė��ĖڑO�Ɍ����B
���̍��c��鰂̑��c�Ȃǂ́A�V���̐����𖾂炩�ɂ��A
�n�`�̐������t��`�����鉤�ł���B
���̂悤�Ȍo�T�𖾂炩�ɂ��鎞�A
�ق�̏����V�n�Ɛl�𖾂炩�ɏo����̂ł���B
�܂����̂悤�ȗD�ꂽ�N��̓����ɉ��Ȃ������̐l���́A
�ǂ����邱�Ƃ��N��Ɏd���邱�ƂŁA
�ǂ����邱�Ƃ��e�Ɏd���邱�Ƃł��邩��m��Ȃ��̂ŁA
�b���Ƃ��Ă�����ł���A�q�Ƃ��Ă�����ł���B
����ł͐b���ƂȂ��Ă��q�ƂȂ��Ă��A
�M�d�Ȉ�ڂ̕�ʂł������p�Ȃ��̂Ƃ��A
��ȏ����̎��Ԃ����ʂɉ߂����Ă��܂��B
���̂悤�ȉƖ�ɐ��܂������l�ɁA���̏d�E��������l�͂��Ȃ����A
�y�����ʂ����ɂ��ނ��낤�B
�������ꂽ���ł������ł���A���̐����ɂ́A
�߂����ɕ������Ƃ͖������낤�B
���̂悤�ȕӒn���{�ŁA���˂̐g�ł���Ȃ���A
�v������ �@���̐��@�����ɁA
�ǂ����Ă��̔��˂̐g��ɂ��ނ��Ƃ����낤���B
�ɂ���ɁA���̐g�����̂��߂Ɏ̂Ă�Ƃ����̂��낤���B
�g���̍������l�́A�@�̂��߂ɐg��ɂ���ł͂Ȃ�Ȃ��B
�܂��Ĕ��˂̐g�͏��X�̂��Ƃł���B
���Ƃ����˂̐g�ł����Ă��A���Ɩ@�̂��߂ɁA
�g��ɂ��܂��̂Ă�Ȃ�A�V��E�̐l�����M�����낤�B
���E�����߂�]���������M�����Ƃł��傤�B
���悻�V�n�̐_�����A���̐��E�̒N�����M�����Ƃ��낤�B
����ɁA���c �B���́A��C���h�� �������̑�O�c�q�ł���B
���ɃC���h�����̎q���ŁA�c�q�ł���B
���M�Ȑl���}����ɂ́A���h���ė��s�����ׂ������A
�����̕Ӎ��ɂ́A�o�q���ɂ��ĂȂ���@���A�܂��m���Ă��Ȃ������B
�����Ԃ��Ȃ��A�~�����e���ł���A�{�a���e���������B
�܂��ĉ䂪���{���́A�C���u�Ă������̒n�ł���A
�ǂ����đ卑�̉����h����@��m���Ă��邾�낤���B
���Ƃ��w��ł��A�܂����ĕ���Ȃ����낤�B
����ƒ鉤�Ƃł́A���̗�@�͈قȂ�A
�y�d�����邪�A������킫�܂��Ȃ��B
���Ȃ̋M�˂�m��Ȃ���A���Ȃ�ۂ��Ƃ͏o���Ȃ��B
���Ȃ�ۂ��Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�A
�܂����Ȃ̋M�˂�悸���炩�ɂ���ׂ��ł���B
�B����t�͐��R�ɍs�������A�t���掂����Q���邷��l�B�������B
�B���͒P�Ȃ�K�T�̓k�ł͂Ȃ��A���@��`�����������ȋ��傾�������A
���j�Ƃ͂��̂��Ƃ𖾂炩�ɂ����A
�T����K�B����ҒB�̕��ނɕ��ނ����̂́A
�܂��Ƃɋ����ŁA�߂��ނׂ����B
�B����t�̉��́A����̉���������A���̎����́A�e�q�ɂ���ׂ��Ȃ��ƁA�B����t�������]�����Ă���B
�܂������́A���ؕ����ɔ�ׁA�A���{�Ɠ��{�l�̌������ȉ��̂悤�ɒႭ�]�����Q���Ă���̂����ڂ����B
���{�l�����˂Ȃ��Ƃ́A�v�����낵���B
�����̍��y���������Ƃ������A���Ƃ����������ɐ��܂ꂸ�A
���l��m�炸�A���҂������A�V��ɏ�����l�����������B
�l�̐S�͂܂����������ł���
���y���J���ĈȌ�A���������������l�͂Ȃ��A��������A�����������Ƃ��Ȃ��B
����́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����ނ��ƂŁA
�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����邱�Ƃł��邩��m��Ȃ����炾�ƒQ���Ă���B
�V�q�ɂ�鐭����A�V�ƒn�Ɛl�̖{���̓����ɈÂ����炱�̂悤�ɂȂ�B
�܂��Ė������\�������܍s�i�؉Γy�����j�ɂ�鐢�̐�����m��Ȃ��B
�ƒ����̌Ñ�v�z�ł���A�z�܍s�v�z�����̐�����m�邽�߂̐�i�I�w��⓹���Ƃ��ĕ]�����Ă���̂����ڂ����B
���̂悤�ɓ����͓��{�l�͕����̍������ؕ������������l�ɔ��
���˂ŕ�����m�炸
�l�S�͂܂����������ł���Əq�ׂĂ���B
����͓������������P�R���I�̓��{�Ɠ��{�l�ɂ��Ă����s�I�]���ƈӌ��ƌ����邾�낤�B
�������A���ꂩ��W�O�O�N���炢�o�����Q�P���I�ł͂��̕]���͋t�]���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
�܂��ɐ��̖���Ɛ����̌������ɋ��������B
���̋������́A��O�̌������閜���̐^���ɈÂ����Ƃ������ł���B
�Â��̂́A�o����m�炸�A�o���ɖ��邢�t�����Ȃ�����ł���B
���̂悤�Ȏt�����Ȃ���A���̌o���͊�\���Ƃ������Ƃ�m�炸�A
���̌o�͊��S��A���猾�ł���ƒm�炸�A�������͂̔瑊������ǂނ̂��B
�����Ɋ����A��������������Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��B
���ɁA�Ìo��m��A�Ï���ǂ�ł���l�́A�Ðl��炤�u������B
�Ðl��炤�S������A�Ìo�͂���ė��ĖڑO�Ɍ����B
���̍��c��鰂̑��c�Ȃǂ́A�V���̐����𖾂炩�ɂ��A
�n�`�̐������t��`�����鉤�ł���B
���̂悤�Ȍo�T�𖾂炩�ɂ��鎞�A�ق�̏����V�n�Ɛl�𖾂炩�ɏo����
�̂ł���ƌo�T�⏑���̑��������Ă���B
�܂��D�ꂽ�N��̓����ɉ��Ȃ������̐l���́A
�ǂ����邱�Ƃ��N��Ɏd���A�e�Ɏd���邱�Ƃ���m��Ȃ��̂ŁA
�b���Ƃ��āA�q�Ƃ��Ă�����ł���Əq�ׂĂ���B
����ł͐b����q�ƂȂ��Ă��A
�M�d�Ȉ�ڂ̕�ʂł������p�Ȃ��̂Ƃ��A
��ȏ����̎��Ԃ����ʂɉ߂����Ă��܂��B
���̂悤�ȉƖ�ɐ��܂������l�ɁA
���̏d�E��������l�͂��Ȃ����A�y�����ʂ����ɂ��ނ��낤�B
�������ꂽ���ł������ł���A
���̐����ɂ́A�߂����ɕ������Ƃ͖������낤�B
����ɁA���c �B���́A��C���h�� �������̑�O�c�q�ł���B
���ɃC���h�����̎q���ŁA�c�q�Ƃ������M�Ȑl�ł���B
���M�Ȑl���}����ɂ́A���h���ė��s�����ׂ������A
�����̕Ӎ��ɂ́A�o�q���ɂ��ĂȂ���@���A�܂��m���Ă��Ȃ������B
�����Ԃ��Ȃ��A�~�����e���ł���A�{�a���e���������B
�܂��ĉ䂪���{���́A�C���u�Ă������̒n�ł���A
�ǂ����đ卑�̉����h����@��m���Ă��邾�낤���B
���Ƃ��w��ł��A�܂����ĕ���Ȃ����낤�B
����ƒ鉤�Ƃł́A���̗�@�͈قȂ�A�y�d�����邪�A������킫�܂��Ȃ��B
�u���Ȃ̋M���v��m��Ȃ���A���Ȃ�ۂ��Ƃ͏o���Ȃ��B
���Ȃ�ۂ��Ƃ��o���ȂȂ��Ȃ�A
�܂����Ȃ̋M�˂�悸���炩�ɂ���ׂ��ł���B
������
�u���Ȃ̋M���v��m�薾�炩�ɂ��ׂ����Əq�ׂĂ���B
�M�˂Ƃ� �M�����ƂƁA�ڂ������ƁA
�܂��A�g���̍����l�ƒႢ�l�Ƃ����Ӗ��ł���B
�������A����̓��{�ɂ͋M�����x�̂悤�Ȑg�����x�͂Ȃ��B
�m���Ɛ����l���ׂĂ��A
�u�E�ƂɋM�˂Ȃ��v�Ƃ�����悤�ɗ��҂͕����ł���B
���̂悤�ȏ�Ԃ���A�u���Ȃ̋M���v��m��
���炩����Ƃ����Ӗ����������Ƃ��낪����B
�����ł͋M�˂Ƃ͐S���M�����ƂƁA
�ڂ������Ƃ��ƍl���邵���Ȃ����낤�B
����́A
�Q�T�C�s�ɂ���Ĕڂ����S�̂悤�����M�ȐS�ɓ]�������悤�ɐ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
5�����T
�@���c�́A�ߑ����\�����̕t�@�Ȃ�A
���ɂ���Ă�肱�̂����A���悢�您�����B
�����̂��Ƃ��Ȃ�吹�����A�Ȃَt���ɂ��Đg���������܂���́A
�`�@�̂��߂Ȃ�A�~���̂��߂Ȃ�B
�^�O���ɂ͂��܂����c������肳���ɁA�����P�`�̕��q���݂��A
�����ʎ��̑c�ʂ�ʎ������A�������܂������肫�B
�̂��ɂ����c�̉����̂ق��A����ɐ���������Ȃ�B
�܉Ԃ̈ꌻ�́A�₷����ׂ��A�N�����܂��ĎZ�����ׂ��A
���c�̐����́A�ӂ����т���ׂ��炴��Ȃ�B
��������ɑc�t�̉����Ə̂���Ƃ�������A
�^���̎����ɂ�ӂċʐ��܂��킫�܂ւ��A
�o�t�_�t���Č����ׂ��Ƃ����ւ�B
���������ɂ��Ă�������Ȃ�B
�h�B�ʎ�̐���Ȃ��₩��́A�c���̉����ƂȂ炸�A
�����Â�ɖ����̎טH�Ƀ��C�w�C������̂��͂�ނׂ��B
���̕��ʂ��̂��A�Ȃِ��V�ɂ䂭���̂���A
����Ȃɂ̂��߂��A�����̂͂Ȃ͂������Ȃ�B
���Ƃ̂Ђ��ɂ��đ����Ƀ��C�w�C����Ȃ�B
�����ɗU�@�̎טH�ɂ����ނ��A�����ɐe���̉Ƌ������B
�Ȃ����V�ɂ�����ĂȂ�̏���������A�����R���ɐh�ꂷ��݂̂Ȃ�B
���V�̓�������@�|���w�����A���@�̓��Q��������߂���ɂ��āA
�����Â�ɐ��V�ɖ��H����Ȃ�B
���@�����Ƃނ閼�̂���Ƃ��ւǂ��A���@�����Ƃނ铹�O�Ȃ��ɂ��āA
���V�ɂ��Ă����t�ɂ��͂��A�����Â�ɘ_�t�o�t�ɂ݂̂��ւ�B
���̂��́A���t�͐��V�ɂ����݂���ǂ��A
���@�����Ƃނ鐳�S�Ȃ��ɂ��āA���@�Ȃ�����ɂ��炴��Ȃ�B
���V�ɂ�����Đ��t���݂���Ƃ��ӂ��ꂩ�A
���̐l���܂�����������Ȃ�B
�������t�ɂ��͂A���������̖��̂������̂���A
�Ȃ��ɂ��Ď��̂��܂����炸�B
���F
�@�t�@�F���@�̌��̐^����t�^���ꂽ�l�B�@
�t���F �t���̖��߁B�@
�~���F �O�����~�ς��邱�ƁB�@
�����F�@���ɉ���ƁB
�܉ԁF�@ �F�D�܉B�C���h�ɂ�����z����̐A���B
3000�N�Ɉ�x�Ԃ��炭�Ƃ����A���̎��ɓ]�����������ɏo������Ƃ����B
�^���̎����F�����ɂ����đ^��
�Ăꂽ���͑召���Ӎ��قǑ��݂��邪�A
�����ɂ����^�������̒��̂ǂ�ɊY�����邩�͂͂����肵�Ȃ��B
�^���̎����Ƃ́A�B����t�̗�������ޑm���ł���Ȃ���A
���T�𒆐S�Ƃ����������o�T��_���𒆐S�Ƃ����������A
���ɂɂ����Ă͑��Ⴊ�Ȃ����Ƃ��咣�����m�����w���Ă���B
���������F���������Ȃ��A�������ł��邱�ƁB�@
�h�B�ʎ�F�@ �@���N�ɂ킽���Đ������q�d�B���邱�ƁB
����F�@�@�������f���B�@
���C�w�C�F�@ ���܂悢�������ƁB
���̕��ʁF �B����t�������ɓn���������̔N���i520�N �` 527�N�j�B
�Ƌ��F�ӂ邳�ƁA�̋��B
�����i�Ƃ������j�F �@�����čs�����ƁB�@
�Ȃ��F���O�����B
�h��F�@ �Ђǂ��ꂵ�ނ��ƁB�@
���O�F�^���悤�Ƃ���O��B
���������F �ǂ�Ȃɂ�������B
���́F���R�ɖ��O�������ė��邱�ƁB
��T���i�̌�����
���c�́A�ߑ�������\����̖@�̑����҂ł���B
�����ɓ����Ă���́A���悢��d�v�Ȑl�ɂȂ����B
���̂悤�ȑ����吹�l�i�B���j���A�X�Ɏt�̂��܂��߂ɏ]���āA
�g����ɂ��܂������֓n�����̂́A�@��`���A�l�X���~�����߂������B
�����ɂ́A���c�B�����C���h���痈��ȑO�ɁA
�ߑ�����A�ȂƑ��`���ꂽ�@��`���镧��q�͂��Ȃ������B
���̂��߁A��X�@�𑊓`�����t���璼�ږ@����ʎ��͂Ȃ������B
�܂������������Ƃ��Ȃ��B
���̌���A���c�̉����ȊO�́A�C���h���琼�������l�͒N�����Ȃ��̂ł���B
�O��N�Ɉ�x�炭�Ƃ����D�܉̉Ԃ������̂́A������Ƃł͂Ȃ��B
����͔N���𐔂��đ҂Ă悢���炾�B
�������A���c���C���h�������ė��������́A������x�ƂȂ��̂��B
����Ȃ̂ɁA�c�t �B���̉����Ɩ����҂������A
�^���̋�l���ʂƐ̈Ⴂ�𐳂����m��Ȃ������悤�ɁA
�o�T��_�����u����t�����c�Ɠ�����������ׂ�l�ł��낤�ƍl���Ă���B
����͕��@�����Ə��Ȃ�����������ł���B
�ߋ����ɁA���������̒q�d�̎��A���Ȃ������҂������A
�c�t�̓��̖@���ƂȂ炸�ɁA�k�ɋ�����F������
��������ɂ������҂ƂȂ邱�Ƃ́A����Ȃ��Ƃł���B
�B�����������̕��ʔ��N�i527�N�j�ȍ~�ɂ��A
�ˑR�Ƃ��Đ����C���h�֕��@���w�тɍs���҂������B
����͉��̂��߂��낤���B
�r���������B
���̎ғ��͌Ȃ̈��ƂɈ�����āA�������������Ă���̂ł���B
���̎҂́A�������A���@��掂�ד��Ɍ������A
�������A���e�̉Ƌ����瓦���Ă���̂��B
���O�B�̓C���h�ɍs���āA�������鏊�����������B
�����R����n�闷�ɋ�J�����������B
�B����t���A�����̒����֗����^�ӂ��w�Ȃ���A
���@�̓��Q��������Ȃ��̂ŁA�k�ɃC���h�ŕ��@�ɖ����̂��B
���@�����߂�Ƃ������ڂ������Ă��A���@�����߂铹�S���Ȃ��̂ŁA
�C���h�ɍs���Ă����t�ɉ�킸�A�k�ɘ_�t��o�t�����ɉ�̂��B
���̗��R�́A���t�̓C���h�ɂ����邯��ǁA
���S���Ȃ��̂ŁA���@�͂��O�B�̎�ɓ���Ȃ��̂��B
���̏؋��ɁA�C���h�ɍs���Đ��t�ɉ�����Ƃ����l������Ƃ́A
�܂����������Ƃ��Ȃ��B �������t�ɉ�����Ȃ�A���������̖����������낤�B
�������A�N������Ă��Ȃ����猾��Ȃ��̂��B
���̑�T���i�ł��B����t�̍s�Ղɂ��ďq�ׂĂ���B
���͂���e�ɓ���ȂƂ���͂Ȃ��B
�����T�̏��c�B���́A�ߑ�������\����̖@�̑����҂ł���B
�B�����A�ʎᑽ�����҂̖��߂ɏ]���āA�����֓n�����̂́A�`�@�Ɛl�X���~�����߂������Ƃ��Ă���B
�����ɂ́A���c�B�����C���h���痈��ȑO�ɁA
�ߑ�����A�ȂƑ��`���ꂽ�@�i�T�j��`���镧��q�͂��Ȃ������B
���̂��߁A��X�@�𑊓`�����t���璼�ږ@��������ʎ��͂Ȃ������B
�܂����������l�����Ȃ��B
���̌���A�C���h���琼�������l�ɂ͒N�����������l�����Ȃ��B
�O��N�Ɉ�x�炭�Ƃ����D�܉̉Ԃ������̂́A������Ƃł͂Ȃ��B
����͔N���𐔂��đ҂Ă悢���炾�B
�������A���c���C���h�������ė��������Ƃ������Ղ́A������x�ƂȂ��̂��B
����Ȃ̂ɁA�c�t �B���̉����Ɩ����҂������A
�^���̋�l���ʂƐ̈Ⴂ��������Ȃ������悤�ɁA
�o�T��_�����u����t�����c�Ɠ����悤�Ȑl�ł��낤�ƍl���Ă���B
����͕��@�ɑ��闝���������炾�B
�ߋ����ɁA�������ʎ�̒q�d�̎��A���Ȃ������҂������A
�c�t�̓��ɓ��炸�A�k�ɋ�����F�����閼���̎ד��ɖ����̂́A���ꂾ�B
�c�t�����̗��̕��ʔ��N�i�T�Q�V�N�j�ȍ~�ɂ��A
�ˑR�Ƃ��Đ����C���h�֕��@���w�тɍs���ҒB�������B
����͉��̂��߂��낤���B�r���������B
���̎ҒB���Ȃ̈����Ɉ�����āA�������������Ă���B
�Əq�ׂĂ���B
���̎ҒB�́A�������A���@��掂�ד��Ɍ������A
�������A���e�̉Ƌ����瓦���Ă���悤�Ȃ��̂��B
�ޓ��̓C���h�ɍs���Ă��A�������邱�ƂȂ��A
�����R����n�闷�ɐh�ꂷ�邾�����B
�B����t�����������@�𒆍��ɓ`�����̂ŁA�����A�C���h�֕��@���w���ɍs���K�v�������Ȃ����̂ł���B
����炸�ɈˑR�Ƃ���
�A�����C���h�֕��@���w�тɍs���̂����Ӗ��ŁA�r�������ȍs�ׂł���
�Əq�ׂĂ���B
�B����t���A�����̒����֗��ē`�@�����^�ӂ��w���A
���@�̓��Q�𗝉����Ă��Ȃ��̂ŁA
�C���h�ɍs���Ă��k���C���h�ŕ��@�ɖ������ƂɂȂ�B
���@�����߂��Ƃ������_�����邾���ŁA
�^�̕��@�����߂��^�̓��S�������̂ŁA�C���h�ɍs���Ă����t�ɉ�킸�A�k�ɘ_�t��o�t�����ɉ���ƂɂȂ�B
���̗��R�́A���t�̓C���h�ɂ����邪�A�^�̓��S���Ȃ��̂ŁA���@�����ł��Ȃ��̂��B
���̏؋��ɁA�C���h�ɍs�������t�ɉ�����Ƃ����l������Ƃ́A�܂����������Ƃ��Ȃ�
�����t�ɉ���Đ^�̕��@�ł���T���w�Ԃ��Ƃ̏d�v�����������Ă���B
�������t�ɉ�����Ȃ�A���������̖����������낤�B
�������A�N������Ă��Ȃ����猾��Ȃ��̂��B
�����ł́A�B����t�����@�𒆍��ɓ`�����ȏ�A
�����C���h�֕��@���w�тɍs���Ă����t�ɉ��Ȃ�����
�C���h�ŕ��@���w�Ԃ��Ƃ͂ł��Ȃ��Əq�ׂĂ���B
���ۃC���h�ɍs���Đ��t�ɉ�����Ƃ����l���Ȃ��Əq�ׂĂ���B
���̓����̍l�����ɗ��ĂA�����i�U�O�Q�`�U�U�S�j��
�U�Q�X�N���H�œ�����C���h�Ɍ������A�����o�_�̌������s���U�S�T�N�ɋA�҂����B
�������A�ނ͂U�T�V���̌o�T�╧���Ȃǂ������ċA�����������m��Ȃ����A
�C���h�ɍs���Ă����t�ɉ�킸�A���������@�����ł����A
�����R����n�����ɋ�J���������Ƃ����]���ɂȂ邾�낤�B
�C���h���畧�����`�����Ĉȍ~�A�����ł͐M�҂����債�čs���B
����Ƌ��ɁA���@�����߁A�C���h�֗��������m���B�������B
�����ł́A���̑�\�I�ȑm�������O�l�̃C���h���s�Ɛl�������Ă݂悤�B
�@��
�@���i337���`422���j�́A���W�̑m���ł���B
���̐l�ƂȂ�́u�u�s���q�A�V�O���l�Ȃ�Ƃ���ꂽ�B
�����̊w����i�߂�ɂ��������A�o�T�̊����o�ɂ���ׂ�
���������������E�ɂ����Ċ������Ă��炸�A
�o���Ƃ��ɍ���⌇��������̂ɋC�t���Q���Ă����B
399�N�ɒ������o�����A�����̌��T��T�����ɂł��B
�s���͗��H�Ő����ʂ�A�U�N�������āA
���C���h�i���V���j�ɒB���A���ɏ�Ȃǂ̕��Ղ��߂������B
�w���d�m�_���x�A�w�G�����ܐS�_�x�ȂǂāA
����ɃX�������J�ɂ킽��A�w�ܕ����x�A�w�����܌o�x�Ȃǂ����Ƃ߂��B
�����̉��̓`�����h���O�v�^2���i�݈ʁF�R�V�U���`�S�P�T���j�ŁA
�����ł͒������ƏЉ��Ă���B
�@���̓C���h�ŗl�X�ȕ����o�T����ɓ����ƁA
�A��̓X�������J����C�H�Œ����ɖ߂����B
���N�ŕ�����ɗ��ɏo��A
�@���������A�����w��ʟ��όo�x������o����A���Ϗ@�����̊�ƂȂ����B
�w���d�m�_���x40�����ꂽ�B�@���͌t�B�]�˂̐h���Ŗv�����B
���N86�B�v��A�w�ܕ����x�����ɏY�����B
�A����A�@���́w�����L�x�Ƃ����C���h�̗��s�L�����B
�w�����L�x�́A�����j�͂������A
�C���h�j�E�����A�W�A�j�E��m�����j�Ȃǂ̌����ɂƂ��Ă��A
�ɂ߂��M�d�Ȏj������Ă���B
����
�����i602�`664�j�͓���̑m���ł���B
629�N�ɍ��ւ̍��O���s�����s���A���H�Ő���o�R�ŃC���h�ɕ������B
�����̃C���h�̓n���V��=���@���_�i�i�݈ʁF606�`647�j
�̓������郔�@���_�i���ł������B
�n���V�����͒����ł͉������ƌĂ��B
������5���I�ɃO�v�^�����������������w�@�̃i�[�����_�[�m�@�ŌܔN��
�����Ɏt�����ėB���w���w�сA�܂��e�n�̕��Ղ����q�����B
�@ ���̌�C���h�e�n�Ōo�T�E�����Ȃǂ����W���A645�N�ɗ��H�ŋA�������B
�A����A���@�̑��߂ƂȂ��č����ɎQ������悤���߂�ꂽ���A
�ނ͍��O���玝���A����657���̌o�T�̖|�����̎g����
�l���Ă������ߑ��@�̗v����f��A���@������𗹏������B
�A�����������́A�����A�����c��Ȍo�T�̖|��ɗ]���̑S�Ă�������B
���@�̒����ɂ��A�����͒��19�N�i645�N�j
����O�����̖|�o�@�Ŗ|�Ƃ��J�n�����B
�A���T�̊���ɓw�߂������́A�@���@���J�����B
�܂��A����̗��s�L���w�哂����L�x�ɂ܂Ƃ߂��B
���ꂪ��ɓ`����w���V�L�x�̊�Ƃ��Ȃ����B
���͖̂@�t�A�O���ȂǁB�������Y�Ƌ��������A
���邢�͐^���ƕs��������܂߂��l���o���Ƃ��Ă��B
�����͌�̖���ɐ��������w���V�L�x�̎O���@�t�̃��f���ł���B
�`��
�`��i635�`713�j�͓��̑m���ł���B
671�N�ɍL�B����C�H�ŃC���h�ɕ������B
����͌����Ƃ͈Ⴄ���[�g�ł���B
�c�����ďo�Ƃ��A15�̎��i649�N�i���23�N�j�j�ɂ͐���s���u���A
�@���⌺���̍s�Ղ��v�炵�Ă����Ƃ����B
�����Ɠ������A�i�[�����_�[�m�@�Ŋw�сA
400���A50����̃T���X�N���b�g�̌o���_�A���T�����W�����B
�A���͊C�H�ŁA��C�������o�R���ē���A�W�A�̃V�����[���B�W����������
�؍݂������ƁA695�N�ɊC�H�ŋA�����A56��230���ɂ̂ڂ镧�T�̊�����ʂ������B
�`��́w��C��A���@�`�x�Ƃ������s�L���V�����[���B�W���������؍ݒ��ɒ������B
�w��C��A���@�`�x��
�����̃C���h���瓌��A�W�A�n��̗l�q��`�����d�v�Ȏ���
�@ �Ƃ��č����]������Ă���B
�R�����g
�@ �����T�t�̍l�����ɗ��ĂA
�ȏ�Љ���@���A�����A�`��̂R����
�C���h�ɍs���Ă����t�ɉ�킸�A���������@�����ł��Ă��Ȃ��B
�]���āA
�ޓ��͂���������R����n�闷�ɋ�J���������ɂ����Ȃ�
�Ƃ����]���ɂȂ邩���m��Ȃ��B
�������A����3���̍s�Ղ�㐢�ɗ^�����e�����������A
�����T�t�̍l�����͐^�ʖڂł����Ă��A�������삪�����A
�O���͂��̂悤�Ȋϕ��Ɏ��܂�Ȃ��悤�Ɏv����B
���������l�����Ǝ�����L���đ��l�Ȑ�������F�߂Ă��ǂ��悤�Ɏv����B
�����U
�@�܂��^�O���ɂ��A�c�t�������̂��A
�o�_�ɘ߉����Đ��@���ƂԂ�͂���m�����ق��B
����o�_���{���Ƃ��ւǂ��A�o�_�̎|��ɂ��炵�B
���̍��Ƃ͍����̋Ɨ݂͂̂ɂ��炸�A�h���̈��Ɨ͂Ȃ�B
�����Ђɔ@���̐^�����������A�@���̐��@���݂��A
�@���̖ʎ��ɂĂ炳�ꂸ�A�@���̕��S���g�p�����A
�����̉ƕ�����������A���Ȃ��ނׂ��ꐶ�Ȃ��B
�@�E���E�v�̏���A�����̂��Ƃ��̂����Ђ��ق��B
�����h�B�ʎ�̎�q����l�́A�s���ɓ��傹����A
����͎Z���̋Ƃ���E���āA�c�t�̉����ƂȂ�肵�́A
�Ƃ��ɗ����̋@�Ȃ�A���̋@�Ȃ�A���l�̐���Ȃ�B
��ւ̂₩��A�Ђ������o�_�̐_���Ɏ~�h����݂̂Ȃ�B
��������ɁA�����̂��Ƃ��̛ӓ�邳���Ђ��������Ƃ��͂��A
���c�������錺���A���܂Ȃق��ӂ��Ƃ���ɁA
���炪�L��܂�������ŁA�ЂɂȂɂɂ�����B
���F
�k�U���F �����ُ̈́B
�߉��i�����j�F �����ɂ���邱�ƁB
��{�F �Ђ炢�ēǂނ��ƁB
���ƁF��܂����s�ׁB
�Ɨ́F �s�ׂ��琶�܂ꂽ�e���́B
�h���F ���N�̐��U�B
�^���F �^�̉��`�B
��ցi�������j�F���납�Ŗ��q�Ȑl�X�B
�ӓ�i����Ȃ�j�F ���킵����V�Ȃ��ƁB
��U���i�̌�����
�܂��c�t�B�����C���h���琳�@��`������ł��A
�����ɂ��A���@���o�T��_�������菊�ɉ��߂��āA
�c�t�̐��@��q�˂Ȃ��m�����吨�����B
�����̐l�X�́A�o�T �_�����J���ēǂ�ł��A
�o�T �_���̐^�ӂɈÂ��悭�m��Ȃ��B
���̂悤�ɁA�c�t�̐��@���w�Ԃ��Ƃ̏o���Ȃ����Ƃ́A
���݂̋Ƃ����łȂ��A�ߋ��̈��Ƃ̕ł���B
�����ɁA�@���̏C�s�̔錍�����A�@���̐��@�������A
�@�����ʎ������@�ɏƂ炳�ꂸ�A�@���̕��S��p�����A
�����̉ƕ����Ȃ����Ƃ́A�߂��ނׂ��ꐶ�ł���B
���A���A�v�̎���ɂ��A���̂悤�Ȑl�����͑��������B
�Ђ�����ߋ����Ɍ��̒q�d�̎�q��A�����l�X�́A���܂��ܕ����ɓ��債�Ă��A
����҂͐�����Ȃ��Ƃ���E���āA�c�t �B���̖@���ƂȂ邱�Ƃ��o�����B
����́A�F�D�ꂽ�����̎�����ł���������ł���A
�ŏ�̋@�����������l����������ł���A
�����Ȑl�ԂƂ��Đ��@���p���l����������ł���B
�����Ȑl�X�́A�����ԁA�o�T �_���̋����̒��Ɏ~�܂��Ă��邾�����B
����Ȃ̂ɁA���̂悤�Ȍ���������ȍ��ɁA���܂��A���킸�A
�n���ė������c�̉��[���@�����A���A�h���w�Ԃ̂ɁA
�䂪�g�����X�ɂ���łǂ�����̂��B
�c�t�B�����C���h���璆���ɐ��@��`������ł��A
���@���o�T��_�������菊�ɉ��߂��āA
�c�t�̐��@��q�˂Ȃ��m���₻�̐^�ӕ���Ȃ��ҒB���吨�����B
�B���̐��@���w�Ԃ��Ƃ̏o���Ȃ��̂́A���݂̋Ƃ����łȂ��A
�ߋ������Ƃ̕��ł���ƁA�B���̐��@��������Ȃ��̂����Ƃ̕��ł���B
�ƍl���Ă���B
���A���A�v�̎���ɂ��A���̂悤�Ȑl�����͑��������B
���A���A�v�̎���ɂ����@���o�T��_�������菊�ɉ��߂��āA
�c�t�B���̐��@��m�炸�q�˂Ȃ��m�����吨�����B
�c�t�B���̐��@���w�Ԃ��Ƃ̏o���Ȃ��̂́A
���݂̋Ƃ����łȂ��A
�ߋ��̈��Ƃ̕��ł���ƁA�`���I�����ʉ�����Ő������Ă���̂���ۓI�ł���B
�Ђ�����ߋ����Ɍ��̒q�d�̎�q��A�����l�X�́A
���܂��ܕ����ɓ��債�Ă��A������Ȃ��Ƃ���E���āA
�c�t �B���̖@���ƂȂ邱�Ƃ��o�����B
����́A�D�ꂽ�����ƍŏ�̋@���̎�����ł���A
�����Ȑl�ԂƂ��Đ��@���p���l����������ł���B
�����Ȑl�X�́A�����ԁA�o�T �_���̋����̒��Ɏ~�܂��Ă��邾�����B
����Ȃ̂ɁA���̂悤�Ȍ���������ȍ��ɓn���ė���
���c�B���̉��[���@�����w�Ԃ̂ɁA
�䂪�g��ɂ�����ǂ�����̂��ƁA�B�����`�������@��^���Ɋw�Ԃׂ����Ƌ������Ă���
�̂���ۓI�ł���B
�����V
�����T�t���͂��A
�S�v������אg�ׂɂ��A
�m�炸�A�g�͐���˒��̐o�Ȃ邱�Ƃ��A
�������Ɣ���@�����Ɍ��ꖳ�����A
����͐��ꉩ��`��̐l�B
��������͂��Ȃ͂��A�����ނɂ��ƂЕS�v��������Ă��Ƃ��ӂƂ��A
�Ђɂ���˒���̂̐o�Ɖ�������̂Ȃ�B
���͂�₢���Â�ɏ����̉����ɂ��͂�āA
�����ɒy�����邠�Ђ��A��h����A�������̐g�S�������邵�ނ�B
�`�ɂ��Ă͐g�������낭���A�}���̗�킷�ꂴ�邪���Ƃ��B
���ɂ��͂��O�r�A�����Ó��̉_���Ȃ�B
���b�ɂ��͂�A���Ԃɐg����������́A�ނ�����肨�ق��B
�����ނׂ��l�g�Ȃ�A����ƂȂ�ʂׂ����ɁB
���ܐ��@�ɂ��ӁA�S��P���̐g�������ĂĂ��A���@���Q�w���ׂ��B
�����Â�Ȃ鏬�l�ƁA�L��[���̕��@�ƁA
���Â�̂��߂ɂ��g�������ׂ��B
���s�тƂ��ɐi�ނɂ�Â�ӂׂ��炴����̂Ȃ�B
���Â��ɂ����ӂׂ��A
���@��ɗ��z�������Ƃ��́A
�g���𐳖@�̂��߂ɝe�̂��Ƃ��˂��ӂƂ����ӂׂ��炸�A
���@�ɂ��Ӎ����̂�����˂��ӂׂ��B
���@�ɂ��ӂĐg�������Ă�������Q������B
�͂Âׂ����̓������͂Âׂ��Ȃ�B
��������A�c�t�̑剶���ӂ��Ƃ́A����̍s���Ȃ�B
���Ȃ̐g�������ւ�݂邱�ƂȂ���B
�b�������납�Ȃ鉶���A������ł��Ă��邱�ƂȂ���B
���ƂЈ��ɂ��Ƃ��A���N�̂Ƃ��Ȃ�ׂ��炸�B
�������̂��Ƃ��Ȃ�Ɩ�A���݂̂ĂƂǂ܂邱�ƂȂ���A
���ƂЂƂǂ܂�Ƃ��A�Ђ̗H���ɂ��炸�B
�ނ������c�̂��������肵�A
�݂Ȏ����q���Ȃ����āA�ʓa��O�����݂₩�ɂ��B
�����̂��Ƃ��݂�B���y�̂��Ƃ��݂�B
�����݂Ȍ×��̕��c�́A�×��̕��c���ӂ��������m���̋V�Ȃ�B
�a���Ȃى��������ꂸ�A�O�{�̊悭��ӂ���B
���T�Ȃى����킷�ꂸ�A�]�s�̈�悭��ӂ���B
���Ȃ��ނׂ��A�l�ʂȂ���{�ނ������Ȃ�Ƃ́B
���܂̌������@�́A���c�ʖʂ̍s����肫����鎜���Ȃ�B
���c�����P�`�����A�����ɂ��Ă������ɂ������B
���̉��A�Ȃٕ�ӂ��ׂ��A��@�̉��A�Ȃٕ�ӂ��ׂ��B
���͂��@�ᑠ�����@�̑剶�A������ӂ�������B
����ɖ��ʍP�͍��̐g�����ĂƂ˂��ӂׂ��B
�@�̂��߂ɂ��Ă˂́A�����̂���A���ւ�ė�q���{���ׂ��B
���V���_�A�Ƃ��ɋ��h���d�����]�V����Ƃ���Ȃ�A
��������K�R�Ȃ邪���ɁB
���V�����ɂ́A�鐂������鐂����Ӕk����̖@�A�Ђ�������������B
���ꕷ�@�̐l�̎��[�`�[�̌����A���ق����Ƃd����Ȃ�B
���ܓ��̂��߂ɐg�������Ă���A���@�̌��������炸�B
�g�������ւ�݂����@���邪���Ƃ��́A
���̕��@���n����Ȃ�A�����鐂͑��d���ׂ��Ȃ�B
���܂���A���̂��߂ɂ��Ă�����鐂́A
�Ǔ��ɂ��炳��Ė�O�ɂ��Ă��Ƃ��A���ꂩ������q����A
���ꂩ���������B�����̐����A���ւ�Ă���ނׂ��B
�S�̐捜�������肫�A�V�̐捜��点������B
�����Â�ɐo�y�ɉ�����Ƃ��������Ђ��A
���܂̈��ɂȂ��A�̂��̂��͂�݂���B
����ق����Ƃ���́A�݂�l�̂Ȃ݂��̂��Ƃ��Ȃ�ׂ��B
�����Â�ɐo�y�ɉ����āA��ɂ��Ƃ͂���鐂����āA
�悭�����͂Ђɕ����@���s�����ׂ��B
���̂��ɁA��������Â�Ȃ���A
���ꂢ�܂��l����Ԃ炸�A���ꂢ�܂�������Ԃ炸�B
�����s�C�����Âׂ��A�s�C����l����Ԃ蓹����Ԃ�B
�s�C�悭�l����Ԃ蓹����Ԃ�B
���M�����Â邱�ƂȂ���A
���M���܂��l����Ԃ炸�A���M���܂�������Ԃ炸�B
�s�C�悭�l����Ԃ蓹����Ԃ�B
���������n���Ƃ�́A�����̏��J�Ȃ�B
�������Ƃߓ������Ƃ߂āA�S�{�ɂȂ�͂���ׂ��B
�����܂��ɍs���Ȃ����͏����̍s���Ȃ�B
���F
�����T�t�F�@�����q�ՑT�t�i�H�`�W�X�W�j�B�C�R��S�T���̖@�k�B
�S�v�F�@ �����̌v��B
����F �����̕���B�@�@
�����F�@���炪�A���炪�̐l�B�@
����F ���҂̍s�����A���y�B
�����F�@�ω�����B
�`�F�@ ���������A���`�B
�}���F �N��E�e���̎����Ƃ�ǂ��āA
�b���E�e���Ȃǂ����E���邱�ƁB�@�@
���ӁF�@�p��������A�͂��炩����A�g������B�@�@
�Ó��̉_���F �����łȂ�����
����ɉ_�▶���������Ă���悤�ȏ�ԁB
����F�@�@�^���̂���B
�P���F �P�͍��̂��ƁB�P�͂̓K���W�X�́B
�P�͍��Ƃ̓K���W�X�͂̍��̈ӂŁA�ɂ߂đ傫�Ȑ����g�I�ɕ\�킷�B
�e�́i�ق�����j�F �����̂Ă邱�ƁB�@
�������F�@�����Ď̂Ă�ꂽ���́A���݁A����A�����B�@
�ʓa�ԘO�F �M���ŏ���ꂽ�������œh�肽�Ă�ꂽ���a�B
�����i�Ă����j�F�@�Ȃ݂�����B
�a���F�@ �����~�L�Ɍ�������b�B
�k��Ƃ����҂���̎��A���������F���������������A
���ꂪ������̎g���ł����āA�k��Ɏl�̔�����^���A
��ɗk����O���̈ʂɂ������Ƃ����B
�O�{�̊F �O�{�͎O���̕{�B
�������k��ɔ�����^���āA�k����O���̈ʂɂ��������Ƃ��w���B�@
��ӁF�@���ӁB�@
���T�F�W����`�Ɍ�������b�B
�E���Ƃ������̂��A���鎞�T�����������A��ɗ]�s���̒����ƂȂ����B
�����Ē����Ƃ��Ă̈�������A���̈�ɒ������T�̒�����
���ď������T�̎p�Ɠ����ł������Ƃ��납��A
�]�s���̒����ƂȂ蓾���̂́A�������T�̕ɂ����̂ł��邱�Ƃ�
�m�����Ƃ����̎��B�@
�]�s�̈�F�@�E�����������]�s���̒����̈�������B
���͏h��A�h�w�̈ӁB�@�@
�l�ʁF �l�̊�A�l�̎p�B
���ˁF�@���l�̂��炾�A���[�B
�����F �^���A�^���Ɋւ��闝�_�B
�K�R�F �K�������Ȃ�A�����Ƃ����Ȃ�̈ӁB�@
�鐁F�@�����Ƃ�Ĕ����Ȃ��������B���ꂱ���ׁB
�t�@���o�Ɍ�������b�B�́A�k���傪���Đl�Ԃ̓������Ă������A
���̐j���œ����̎��̏����h���A
�ђʂ�����̂͐��O�A���@���������Ƃ��č����������Ƃ����B�@
�S�̐捜��������F ���牤��g�o�Ɍ�������b�B
���l���H�T�Ɏ��[�����������A�����V�g����q���Ă���̂ŁA
���̂��Ƃ����˂���A
���̎��[�͎����̂��Ă̐g�̂ŁA
���̐g�̂ɂ���đP�s���������߂ɁA
�V��E�ɐ��܂�邱�Ƃ��ł����ƌ�����B
�܂�������֍s���Ƃ���ǂ͋S����̎��[��ł��Ă������A
���̂��Ƃ����˂��Ƃ���A�����͂��̐g�̂ɂ����
���낢��̈��s���s�Ȃ������߂ɁA�S�̎p�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA
�����̎��[��ł��Ă���̂��ƌ�����Ƃ����B
���͂�݁F�@�ӂт�ɂ��������ƁB
����ق��F �����Ȃ��A�������B
��Ԃ�F�@�j��B
�s�C�F ���H���Ȃ����ƁB
���ÁF�@ �������B�@
���������F�@���{�N�o�A���H�n���i�Ɍ����Ă���̎��B
�����B�Ƃ����k����̉����A�ߑ��Ȃ�тɌܕS�̑m�������҂��Ă���Ȃ���A
���̎��ɐS��D���ĐH���������グ�邱�Ƃ�Y�ꂽ���߁A
�ߑ��Ȃ�тɌܕS�̑m���͔n�̔���H�p�ɂ��ꂽ�B�@�@
�n���Ƃ�F �@�j�L��`��ɂ���̎��B
���̕������u�������߁A�u�̈�b�ł��锌�Əf�ĂƂ́A
��z�R�ɓ����Ęn��H�ׁA���̈���H�ׂȂ������Ƃ����B
��V���i�̌�����
�����q�ՑT�t�͌������A
�u���X�̑����̂͂��育�Ƃ́A�����䂪�g�̂��߂ɂ��Ă����B
���̐g�͕��̓y�ƂȂ邱�Ƃ�m��Ȃ��B
�@�����͌��Ȃ��ƌ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@����͖��y����̌��t��`����l�ł����B�v
����������A�䂪�g�������邱�ƂɁA
���Ƃ������s�����Ă��A�I�ɂ͕��̓y�ƂȂ�B
�܂��āA���̐g��k�ɏ����̉��Ɏd���閯�Ƃ��Ďg���āA
�����ɋ삯���Ԃ̑����̋�J�́A�ǂ�قǐg�S���ꂵ�߂邱�Ƃ��B
���b�̋`���ɂ���Ď����̐g�����y�����A�}���̗�𐋂���҂�����B
���`�Ɏg����҂̑O�r�́A
�܂�ňÂ��_���̂悤�Ɉꐡ���������Ȃ��B
���̂悤�ɏ����̐b�Ƃ��Ďg���A
���Ԃɐg�����̂Ă�҂́A�̂��瑽���B
�����ނׂ��l�g�ł���B
�����̊�ƂȂ���̂�����ł���B
������A�� ���@�ɉ�����Ȃ�A
����Ȃ����̐g�����̂ĂĂ��A���̐��@���w�Ԃׂ��ł���B
�܂�Ȃ����l�ƁA�L��[���ȕ��@�Ƃ��ׁA
�ǂ���ׂ̈ɐg�����̂Ă�ׂ����́A
�����l�������Ȑl���A���ɐg�̏������ɔY�܂Ȃ��B
�Â��ɍl���Ă݂Ȃ����B
���@�����Ԃɗ��z���Ă��Ȃ����ɂ́A
�g���𐳖@�ׂ̈ɓ����̂Ă悤�Ɗ���Ă��A���@�ɂ͉�Ȃ��B
������A���@�ɉ�����̉䓙�����ӂ��Ȃ����B
�����Đ��@�ɉ���Đg�����̂ĂȂ��䓙��[���p���悤�B
�p����̂Ȃ�A���̓�����p����ׂ����B
�ł�����A�c�t �B���̑剶�ɕ邱�Ƃ́A��������̍s���ɂȂ�̂��B
���̍s���Ɏ��Ȃ̐g�����ڂ݂Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@ �b���������ȉ������A�ɂ���Ŏ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���Ƃ������ɂ���ł��A����͒��N�̗F�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�����̂悤�ȉƖ�𗊂�ɂ��āA���܂��Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���Ƃ����܂��Ă��A�����͏I���̏Z�ݏ��ł͂Ȃ��̂��B
�̂̕��c�͌����������B
�F�A����̒���⑽���̎q�𓊂��̂āA
�������{�a �O�t�𑁁X�Ɏ̂Ăďo�Ƃ����̂��B
������܂���̂悤�Ɍ��A�������y�̂悤�Ɍ����̂ł���B
�����͊F�A�×��̕��c�����c�ɕ��ӂ��A
����m�艶�ɕ���@�ł���B
�k��ɏ�����ꂽ��������Y�ꂸ�ɁA
���̎q�����O�{�ɓo�点�ĉ��ɕ��b������B
�܂��A�������T���l�x������Ɍ����ċ���A���ɕ��Ƃ����b������B
�߂��ނׂ��́A�l�̊�����Ă��Ȃ���{�ނ������ł���B
��X�����A���Ɍ����Ė@�����Ƃ��o����̂́A
���c�̏C�s�ɂ���āA�@���`�����Ă������A�ł���B
���c�������A�e�����@��`���Ȃ���A
�ǂ����č����܂œ`��������낤���B
���c���`�������̉��ɂ����ӂ��ׂ����B
��@�̉��ɂ����ӂ��ׂ����B
������A���@�ᑠ����̑�@��`���Ă��ꂽ
�剶�Ɋ��ӂ����ɂ����悤���B
�@�ׂ̈ɁA����Ɍ���Ȃ����̐g�����̂Ă悤�Ɗ肤�ׂ��ł���B
�@�ׂ̈Ɏ̂Ă��r�́A�㐢�̉�X���A��q�����{���邾�낤�B
���V�◴�_�������A���Ɍh�����d���Ď�삵�]�Q���邾�낤�B
����͕K�R�̓��������炾�B
�C���h�ł́A�鐂蔃������k����̖@������ƁA�\�ɕ����Ă���B
����͖@�����l���鐂�g�̂́A�������傫���Ƒ��d����Ă��邩�炾�B
���A���ׂ̈ɐg�����̂ĂȂ���A���̕��@�̌����͂���ė��Ȃ��B
�g�����ڂ݂��ɕ��@����A���̕��@�͐��n����̂��B
���̐l���鐂͑��d���ׂ����B
����X�́A���ׂ̈ɐg�����̂ĂȂ������鐂́A
�����N����Ė�O�Ɏ̂Ă��Ă��A�N��������q���邾�낤���B
�N�������鐂����邾�낤���B
���̎��ɂ́A
�����̕s�b��Ȃ������̐�����U��Ԃ��č��ނ��ƂɂȂ邾�낤�B
�S�����O�̈��s�ŋS�̎p���������Ƃ������āA
�������̍���ł��Đӂ߂����Ƃ��������B
�V�l�����O�̑P�s�œV�ɐ��܂ꂽ���ƂɊ��ӂ��āA
�������̍����q�������Ƃ��������B
���̐g������̓y�ɂȂ鎞�̂��Ƃ��v���A
���̈��ɂ̐S�͖����Ȃ�A
����œy�Ɋ҂鎩��������Ɏv������ł���B
�Â����̂́A���������l�̗܂̂悤�Ȏv���ł���B
�ł�����A����̓y�ɂȂ��āA
�l�Ɍ������鐂ƂȂ邱�̐g�ŁA
�K���ɂ�����Ƃ��o�������̐��@���s�����ׂ��ł���B
����́A�~�̊��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���ꂪ�l�����������Ƃ͂Ȃ����A���ꂪ�������������Ƃ��Ȃ��B
�����C�s���Ȃ����Ƃ������ׂ��ł���B
�C�s���Ȃ����Ƃ��l�������A����������B
�Ă̏���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�������l�����������Ƃ͂Ȃ����A�������������������Ƃ��Ȃ��B
�C�s���Ȃ����Ƃ��l�������A����������̂ł���B
�ߑ��ƒ�q�������A�H�ׂ镨�������Ĕ��̋��{�������Ƃ�A
���i�͂����j�Əf�āi���キ�����j���`���d�āA
�n��H�ׂĉB�ِ����������Ƃ́A�o�ƂƑ��l�̏��ꂽ���Ղł���B
�������ߓ������߂āA�S��{���̐^�������Ă͂����Ȃ��B
�Ђ�����ȍs���̈���́A�����̍s�Ȃ��ł���B
�`���ł͍����q�ՑT�t�̌��t�����p����
�䂪�g�������爤���A�����s�����Ă��A�I�ɂ͉䂪�g�͕��̓y�ƂȂ�B
�����̊�ƂȂ�l�g��ɂ��݁A
���@�ɉ�������A�g�����̂ĂĂ��A���̐��@���w�Ԃׂ��ł���
�ƌ����Ă���B
���̂�����͓����̐^�ʖڂ��Ƌ����S�����ꂽ�悤�ȕ��͂ł���B
���@�����Ԃɗ��z���Ă��Ȃ����ɂ́A
�g���𐳖@�ׂ̈ɓ����̂Ă悤�Ɗ���Ă��A���@�ɂ͉�Ȃ��B
������A���@�ɉ���Ƃ��ł��鍡���̉䓙�����ӂ��ׂ����B
�����Đ��@�ɉ���Ă��g�����̂ĂȂ��䓙��[���p����ׂ����ƌ����B
���@�������炵���A�c�t �B���̑剶�ɕ邽�߂ɂ́A
����������C�s�ɗ�݁A���Ȃ��g�����ڂ݂Ă͂Ȃ�Ȃ��Əq�ׂĂ���B
�b���������ȉ����₲���̂悤�ȉƖ�Ɏ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����ȕ��c�͎���̒���⑽���̎q�𓊂��̂āA
�������{�a �O�t�𑁁X�Ɏ̂Ăďo�Ƃ����̂��B
������܂���̂悤�Ɍ��A�������y�̂悤�Ɍ����̂ł���B
�B����t���A���@�ᑠ����̑�@��`���Ă��ꂽ�剶�Ɋ��ӂ����ɂ����Ȃ��B
�@�ׂ̈ɁA����Ɍ���Ȃ����̐g�����̂Ă悤�Ɗ肤�ׂ��ł���B
�@�ׂ̈Ɏ̂Ă��r�́A�㐢�̐l�X���A��q�����{���邾�낤�B
����̓y�ɂȂ��āA�l�Ɍ������鐂ƂȂ邱�̐g�ŁA
�K���ɂ�����Ƃ��o�������̐��@���s�����ׂ��ł���B
����́A�~�̊��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���ꂪ�l�����������Ƃ��A�������������Ƃ��Ȃ��B
�����C�s���Ȃ����Ƃ������ׂ��ł���B
�C�s���Ȃ����Ƃ��l�������A����������̂��B
�Ă̏���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�������l�����������Ƃ͂Ȃ����A�������������Ƃ��Ȃ��B
�C�s���Ȃ����Ƃ��l�������A����������̂��B
�����œ�����
�u�Ă̏���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�������l�����������Ƃ͂Ȃ����A�������������Ƃ��Ȃ��B
�@�C�s���Ȃ����Ƃ��l�������A����������̂ł����B�v
�Əq�ׂĂ���B
����ł͉Ă̏���������������M���ǂ̌����ɂȂ莀�ʂ��Ƃ��������Ă���B
�������l�������l�����Ɏ��点�邱�Ƃ������̂��͂����肵�Ă���̂ł���B
�����T�t�̎���ɂ���w�������B�����������������댯�����������Ă��Ȃ������̂��낤���B
�����̎���͎��R���L���ŁA���ʂ��̗ǂ��e���ȏZ��ɏZ��ł�������
�M���ǂɂ���Ď��ʂ��Ƃ͏��Ȃ����������m��Ȃ��B
�������A�ߑ�̕����Љ�ł͏��������������
�M���ǂ̌����ɂȂ莀�ʂ��Ƃ�����̂Œ��ӂ��ׂ��ł���B
�Ђ�����ȍs���̈���́A�����̍s�Ȃ��ł���B
���̕��i�ŁA������
�u���ׂ̈ɐg�����̂ĕ��@���ׂ����A
�Ƃ��A���@�ׂ̈ɐg�����̂Ă悤�Ɗ肤�ׂ��ł����v
�Ƃ������Ă���B
�����d���錻��l�ɂƂ���
���@�̂��߂��g�����̂Ă��Ƃ��������T�t�̍l�����͎�����Ȃ�
�ƍl����l�������Ǝv����B
���̂悤�ȍl������
���������^�ʖڂȐ��i�����@�����`�Ɋ�Â����l�������Ǝ~�߂�ق��Ȃ����낤�B
�����W
�@�^�O���c��c���@���o��t�́A�_�S�Ƃ��ɚ��炷�A
�������Ȃ������d���������̎t�Ȃ�A�D�B�̎m�Ȃ�B
�ɗ��ɋv�����ČQ�������A
���ɂ̂܂�Ȃ�Ƃ���Ƃ���A�l�̂��Ђ������Ȃ�B
�@�����d�̂��ɁA�_���Ō����āA�c�ɂ�����Ă��ӁA
�u���Ɏ�ʂ�~�͂A�������ɑ���A
�哹�����ɔق��A�𑴂��ւ䂭�ׂ��v�B
��������A�ɂ͂��ɓ��ɂ��邱�Ǝh�������Ƃ��B
���t�A���z���十�R���T�t�A�����������Ƃ���Ƃ��ɁA
�ɐ��L��ĞH���A
�u����T���������ӂ�Ȃ�A��̒ɂɔ��v�B
�c�A���Ɍ��_�̎����ȂāA�t�ɔ����B
�t�A���̒����i������ɁA�����ܕ�̏G�o���邪�@���B
�T���H���A
�u�������A�g�˂Ȃ�A���ɏ��ؗL��ׂ��B
�_�̓� ��ւ䂯�Ƃ��ӂ��A
�z�ꑥ�����ю��̒B����m�A�K�������t�Ȃ��B�v
���F
��c���@���o��t�F�@��c�d�i�S�W�V�`�W�X�W�j�B
�B����t�̖@�k�B�����T�̑��c�B�T�X�R�N�P�O�V�˂Ŏ����B
���@���o��t�Ƃ����薼���ꂽ�B
�_�S�F�@�@�_���S���B�@
����i���傤�ځj�F�@�S����A�������B
�D�B�i�������j�F�S���L�X�Ƃ��ĕ����ɂ������Ȃ����ƁB
�S�̂܂܂Ɏ��K���ĕ����ɍS������Ȃ����ƁB
�ɗ��F�ɐ��Ɨ����ƁB�ɐ��͉͓�Ȃ𗬂���̖��B
�����͟����Ȃɔ����͓�Ȃ𗬂���̖��B
�Q���F�@�������̏����B
�����F�@�L�͈͂ɓǂނ��ƁB
�@�����d�F�@�@�������Ă��镧�@�������̍����A
���̐g�ɂ������s�����h�ɒl���邱�ƁB �@
�_���F�@��l�B
�Ō��i���キ����j�F�ɂ킩�Ɍ����邱�ƁB
���z�F�@�@�����̖k�Ɉʂ��A������������c�n�B
�����������ɓs���A
�㊿�E���K�E��鰁E�@�E�ܑ�Ȃǂ��A�������������s�Ƃ����B�@
����F�@���z�̓�ɂ���R�̖��B
���R���T�t�F��c�d��t�̍ŏ��̎t���B
���_�F�@�����ł͐_����������Ƃ��w���B�@
�����F�@�@�\���Ɠ����B
�����F�@�@���̂Ă���̍��B
�G�o�F���т��o��B
�g�ˁF�@�߂ł������邵�B
��W���i�̌�����
�����T�̑��c�A���c���@���o��t�A�_���d�i�������� �j�́A
�_��S�ɕ���A�o�Ǝ҂ƍ݉Ǝ҂��瑸�d���ꂽ�����̑c�t�ŁA
�S�̍L���l���������B
�ɗ��ɋv�����Z��ŁA���܂��܂ȏ������w�B
���̍��ł���ȗD�ꂽ�l���ŁA���l�������B
���@�ɗD��l���ɗD�ꂽ�l�ŁA
����� �_���ɂ킩�Ɍ���A�d�Ɍ������A
�u���@�̌������߂����Ȃ�A�ǂ����Ă����ɋ���̂��B
�哹�͉����ɂ͂Ȃ��B���͓�֍s���ׂ����B�v
�d�͎��̓��A�ˑR�h���悤�ȓ��ɂ��������B
�t�̗��z����̍��R��ÑT�t���A�������Ƃ���ƁA���琺�������B
�u����͍��������Ă���̂��B���ʂ̒ɂ݂ł͂Ȃ��B�v
�����Ōd�́A�O�� �_�ɉ�������Ƃ��t�ɘb�����B
�t�����̓��̍�������ƁA�܂̕G�łĂ���悤�������B
�����Ŏt�͌������A
�u���O�ɂ͋g�˂̑�������Ă���B�����ƌ�鏊�����낤�B
�_�����O�ɓ�֍s���ƌ������̂́A���ю��̒B����t���A
�����Ƃ��O�̎t�Ƃ������Ƃ��낤�B�v
���̋������āA�d�͏�����̒B����t�̏��֍s�����B
���̎��̐_�́A�d�̉i���̏C���̎��_�������B
��W���i�͒����T�̑��c�_���d�̍s���ɂ��ďq�ׂĂ���B
�����T�̑��c�A���c���@���o��t�A�_���d�́A
�_��S�ɕ���A�o�Ǝ҂ƍ݉Ǝ҂��瑸�d���ꂽ�����̑c�t�ŁA
�S�̍L���l���������B
�d�͂��܂��܂ȏ������w�сA�����ł���ȗD�ꂽ�A���l�������B
���@�ɂ��D��l���ɗD�ꂽ�l�ŁA
����� �_���ɂ킩�Ɍ���A�d�Ɍ������A
�u���@�̌������߂����Ȃ�A�ǂ����Ă����ɋ���̂��B
�哹�͉����ɂ͂Ȃ��B���͓�֍s���ׂ����B�v
�d�͎��̓��A�ˑR�h���悤�ȓ��ɂ��������B
�t�̍��R��ÑT�t���A�������Ƃ���ƁA���琺�������B
�u����͍��������Ă���̂��B���ʂ̒ɂ݂ł͂Ȃ��B�v
�����Ōd�́A�O�� �_�ɉ�������Ƃ��t�ɘb�����B
�t�����̓��̍�������ƁA�܂̕G�łĂ���悤�������B
�����Ŏt�͌������A
�u���O�ɂ͋g�˂̑�������Ă���B�����ƌ�鏊�����낤�B
�_�����O�ɓ�֍s���ƌ������̂��A
���ю��̒B����t���A�����Ƃ��O�̎t�Ƃ������Ƃ��낤�B�v
���̋������āA�d�͏�����̒B����t�̏��֍s�����B
���̎��̐_�́A�d�́A�i���̏C���̎��_�������B
������d�ɉi���̏C���̎��_������A
�u���@�̌������߂����Ȃ�A�ǂ����Ă����ɋ���̂��B
�哹�͉����ɂ͂Ȃ��B���͓�֍s���ׂ����B�v
�ƌd�ɍ�����B
���̓��A�d�͓ˑR�h���悤�ȓ��ɂ��������̂�
�t�̍��R��ÑT�t�̏��ɍs�����B
��ÑT�t���A���ɂ��������Ƃ���ƁA����
�u����͍��������Ă���̂��B���ʂ̒ɂ݂ł͂Ȃ��B�v
�Ƃ������������B
�����Ōd�́A�O�� �_�ɉ�������Ƃ��t�ɘb�����B
��ÑT�t�����̓��̍�������ƁA�܂̕G�łĂ���悤�������B
�����Ŏt�͌������A
�u���O�ɂ͋g�˂̑�������Ă���B�����ƌ�鏊�����낤�B
�_�����O�ɓ�֍s���ƌ������̂��A
���ю��̒B����t���A�����Ƃ��O�̎t�Ƃ������Ƃ��낤�B�v
���̋������āA�d�͏�����̒B����t�̏��֍s�����B
���ꂪ��c�d���B����t�̏��֍s�����������Əq�ׂĂ���B
��ÑT�t���A���ɂ��������Ƃ���ƁA����
�u����͍��������Ă���̂��B���ʂ̒ɂ݂ł͂Ȃ��B�v
�Ƃ������������b�B
��ÑT�t���d�̓��̍�������ƁA
�܂̕G�łĂ���悤�Ɍ������b�ȂǁA
�����ɏo�ė���b�͂ǂ���_������������I�ŕs�v�c�Șb����ł���B
�����T�t�ɂ͐\����Ȃ���
�M�҂͂����̒��팻�ۂ̂悤�Ȗ��d�s�v�c�Șb��M���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�����T�t�͂����̘b��
�^�����ƂȂ��A�f���ɐM�����̂ō̗p�����̂��Ǝv����B
�M�҂�
�u�_���ɂ킩�Ɍ���A�d�Ɍ��������Ƃ���琺�����āE�E�E�E�A
�i���̏C���̎��_�A
������ꊷ���Čd�̓��̍����A�܂̕G�łĂ���悤�Ɍ������b�v
�Ȃǂ�M���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�����������T�t�ɂ�
���̂悤������I�����d�s�v�c�Șb���D���őf���ɐM���鐫����������B
�i �s���P�̑�P�P���i���Q���j�B
�����X
�@���̋��������āA�c���Ȃ͂�������ɎQ���B
�_�́A�݂Â���̋v���C���̎瓹�_�Ȃ�B
���̂Ƃ����d���V�Ȃ�A�\�����Ƃ��ӁB
�V��J��Ȃ炸�Ƃ��A�[�R����̓~��́A
�����Ђ��ɁA�l���̑��O�ɗ��n���ׂ��ɂ��炸�B
�|�߂Ȃٔj���A������ׂ�����Ȃ�B
��������ɑ��x�n�A���R�v��Ȃ�B
�j�Ⴕ�ē������ƂށA�������̛ӓ�Ȃ�Ƃ�����B
�Ђɑc���ɂƂÂ��Ƃ��ւǂ��A������邳�ꂸ�A
��ᾂ����邪���Ƃ��B
���̖�˂Ԃ炸�A�������A�₷�ނ��ƂȂ��B
�����s���ɂ��āA��������܂ɁA���Ȃ����Ȃ������Ƃ��B
������č������Âނ��Ђ��A����Ȃ݂��H�H���ق�B
�Ȃ݂����݂�ɁA�Ȃ݂��������ʁA�g�����ւ�݂Đg�����ւ�݂�B
���҂��炭�A�@
�u�̂̐l�A�������ނ���A
����Ȃ��Đ������A�����h�����_������ς��B
����z���ēD�ЁA�R�ɓ����ČՂɎ����B
�Â֏� ���̎Ⴕ�A�䖔�A���l���B�v
�����̂��Ƃ������ӂɁA�u�C���悢���u����B
���܂��Ӂu�Ï��፟�A�䖔���l�v���A
�Ӑi���킷�ꂴ��ׂ��Ȃ�B
���炭������킷���Ƃ��A�i���̒��M����Ȃ�B
�����̂��Ƃ����҂��āA�@�����Ƃߓ������Ƃނ�u�C�݂̂����Ȃ�B
�U����U���U�Ƃ�����ɂ��āA�������肯��Ȃ�ׂ��B
�x���̂��̏����A�͂����Ƃ���Ɋ̒_���������ʂ邪���Ƃ��B
�����g�т̊���������݂̂Ȃ�B
���c���͂�݂Ė��U�ɂƂӁA
�u���A�v�����ᒆ�ɗ����āA���ɉ����������ނ��B�v
�����̂��Ƃ������ɁA
��c�A�ߗ܂܂��܂����Ƃ��Ă��͂��A
�u�Ҋ�킭�͘a���A���߂����ĊØI����J���A�L���Q�i��x���ׂ��B�v
�����̂��Ƃ��܂����ɁA���c�H���A
�u��������̖����́A�D���ɐ����āA��s�\�s���A��E�ɂ��ĔE�Ȃ��B
每������q�A�y�S���S���ȂāA�^���b�͂�Ƃ���A�k�J�ɋ�Ȃ���B�v
���̂Ƃ��A��c�����Ă��悢���q�シ�B
�Ђ����ɗ������Ƃ�āA�݂Â��獶�]��f���Ēu���t�O����ɁA
���c���Ȃ݂ɁA��c����@��Ȃ�Ƃ���ʁB
�T���H���A
�u�����A�ŏ��ɓ������ނ�ɁA�@�ׂ̈Ɍ`��Y���B
�����A�]����O�ɒf�A���ނ邱�Ɩ��Ȃ邱�ƍ݂��B�v
���F
���F�@���P�B
�c�F�@�����T�̓�c�_���d�i�S�W�V�`�T�X�R�j�B
������F�@鰂̐��R�̎O�\�Z��̈�B
���R�̓��ɂ���̂�厺��Ƃ����A���ɂ���̂�������Ƃ����B
���ю��̏��ݒn�B
�_�F�@�@�@�_��B
�v���C���F�@�@�@�ɂ߂Ē��N���ɂ킽���ĕ����C�s�����ė������ƁB
�瓹�_�F�@���@��ێ����ė������Ƃ��琶�܂ꂽ�����B
���d�i���イ�낤�j�F�@���͂����܂����̈ӁB
�d���d���A�A��\�B�@
���V�F�@�@���ނ���A�����V��̓��B
�����F�@���{�A����̖�B�@
�J��F�@�J�͐�₠��ꂪ�ӂ�̈ӁB�J��͐Ⴊ�ӂ�B
���O�F�@���̊O�B
�x�n�F�@��n�S�́B
�j��F�@�ᓹ���J���Đi�ނ��ƁB
��ᾁi���߂�j�F�ӂ肩�����Ă݂邱�ƁB�@
�����F�@�@�����Ɨ����Ă��邱�ƁB�@
���F�@����@����ɁB
���ҁF�@�݂�����l���邱�ƁB�҂͂������A������B
����Ȃ��Đ������F�@��ʎ�o�̏�e�i�ɂ�����b�B
��e��F���@�O��F�̏��֍s���āA��ʎ�̋��������Ƃ������A
�������{������̂��Ȃ������̂ŁA�킪�g��A
�����������Đ������o���āA��������{�����Ƃ����b�B
�����h�����_������ς��F�@���������o�̎��͉��i�ɂ�����b�B
��@�����Ƃ���腕���̍������A�Q�����S���~�����߂�
�킪�g���h���Č��t���S�ɗ^�����Ƃ����b�B�@�@
����z���ēD���F�@�@���όo�Ɍ�������b�B
�ߑ��̑O���ɂ����ĕ������邠�܂�A�ʂ���݂Ɏ����̔��̖т�z���āA
�R�������킽�点���Ƃ����̎��B�@
�R�ɓ����ČՂɎ��ӁF�@�@�������ŏ����o�̎̐g�i�ɂ�����b�B
�������D�����̑�O�c�q�ł�������F���A
���C�̎q��{���Ă���Ղ��Q���Ď��ɂ�����
�Ȃ��Ă���̂��݂āA�킪�g��^�����Ƃ����̎��B
�@�䖔���l�i���܂��ȂɂтƂ��j�F
�����͈�̉��҂Ȃ̂��B
�k��ɐg����ɂ���ʼn��ɂȂ낤���B
�U��i�������j�F�@�U������A����߂�B
�U��͏C�s���Đg�S����߂邱�ƁB�@
�U���U�Ƃ����F�@�C�s���C�s�ȂǂƂ��ӎ����Ȃ����ƁB
�x���F�@�閾���܂��ƁB
�̒_�F�@�@�@�̑��ƒ_�X�B�S�̉���B�^���̐S�B�@
�����i����́j�F�����ꂨ�̂̂����ƁB
���U�i�܂�����j�F���������A�������B�@
�ØI��F�@�@�ØI�͏��_����p��������ŁA
��������ނƕs�V�s���ɂȂ�Ƃ����B
�ØI��͎ߑ��̐����ꂽ�@��A�����̂��ƁB
�Q�i�F�@�O���B
�D���i���������j�F�@�������ԁB
�����ɒ����̂��i���Ƃ����A�ߋ��ɒ����̂�D���Ƃ����B�@
�y�S�F�@�@����͂��݂ȐS�B
���S�F�@�����肽���Ԃ�S�A���ʂڂ�B
�^��F�@�^�̏敨�B�ߑ��̋����B
�q��i�����ꂢ�j�F�@�q�i�������j���āA�u���͂��܂��B�@
�@��@�F�@���@���p�������ʁB
�`��Y���F�@�O�`��Y���A���̂�����B�@
��X���i�̌�����
���̋������āA�d�͏�����̒B����t�̏��֍s�����B
���̎��̐_�́A�d���g�́A�i���̏C�s�̎��_�������B
�d���B����t��K�˂������́A�N�̐��̊����G�߁A
�\���{ ����̖�ł������ƌ����Ă���B
��Ⴊ�~��Ȃ��Ă��A�[�R����̓~�̖�́A
�z������ɁA�ƂĂ��l�Ԃ����̊O�ɗ����Ă���ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ��B
�����Œ|�̐߂��������Ƃ������낵���������B
���������̓��͑�Ⴊ�n�ɖ����āA�R�ߕ�߂Ă����B
������������Đi��ōs���̂́A��ςȓ�V�������B
�d�́A���ɒB���̕����ɍs�����������A
�t�͕����ɓ��邱�Ƃ������Ȃ������B
�d��U��������Ƃ������Ȃ������B
�d�͂��̖�A���炸�A���炸�A�x�܂Ȃ������B
�����Ɨ����Ė閾����҂d�ɁA��̐�͗e�͂Ȃ��~��ς������B
�Ⴊ����ς����č��߁A������܂̈�H��H�͓���A
���̗܂����Ă܂��܂��d�˂��B
�d�͉��x���䂪�g���Ȃ݂āA�l�����A
�u�̂̐l�́A�������߂�̂Ɏ����̍����������Đ������o�������A
�Q�����҂��~���̂Ɏ����̐g���h���Č���^�����B
�����́A���ׂ̈Ɏ����̔���D�̏�ɕ~�������A
�����́A�@�ׂ̈ɊR����g�𓊂��ċQ�����Ղɗ^�����肵���B
�̂̐l�ł����A���̂悤�ɂ����̂ł����B
�Ȃ�Ύ��͈�̉��҂Ȃ̂��B�v
���̂悤�ɍl���āA�d�͋����̎u�����悢���܂����B
�������Ƃ���́A
�u�̂̐l�ł����A���̂悤�ɂ����̂ł����B
�Ȃ�Ύ��͈�̉��҂Ȃ̂��B�v
�Ƃ������t���A�ӊw��i�̐l���Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����ł������Y���A�i���ɋ�E�ɒ��ނ��낤�B
�d�͂��̂悤�Ɏ���l���āA�@�����߁A�������߂�u������ςݏd�˂��B
��𗁂тĐS�̐������������邱�Ƃ͓��R���ƍl�����̂ŁA�����Ȃ����̂��낤�B
�閾���̒x�����~�̖�̊����́A�z����₷�銦�����������낤�B
�v���ΐg�̖т��悾���肾�B
���c �B���́A�d������Ɏv����
�������ɐq�˂��A
�u���܂��͒����� ��̒��ɗ����āA��̉������߂Ă���̂��B�v
���̂悤�ɐq�˂�ƁA��c �d�͔߂��݂̗܂��܂��܂����Ƃ��ē������A
�u�ǂ������肢�ł��A�a���l�B
�����߂������ĊØI�̖@����J���A�L���l�X���~���ĉ������B�v
���̂悤�ɓ�����ƁA���c�͌������A
�u�����̖���̖����́A�i���ɐ��i�����A
�s������Ƃ��悭�s���A�E�ѓ���Ƃ�E�˂Ȃ�Ȃ��B
����q�d�̏��Ȃ��҂����S�����A
�^�̕��@�����߂Ă��A���ʂɋ�J���邾�����B�v
���̎��A��c�͂��̌��t���āA���悢�掩����܂����B
�����āA�����ɉs����������Ď��獶�]��f���A������t�̑O�ɒu�����B
���c�́A����ɂ���ē�c���@�킾�ƒm��A
�����Ō������A
�u�������ŏ��ɓ������߂����ɂ́A�@�ׂ̈Ɏ����̐g�̂�Y�ꂽ�ƌ����B
���܂������A���̑O���]��f���ē������߂Ă��邱�Ƃ��A
�܂��悵�Ƃ��ׂ��ł��낤�B�v
���̕��i�ł͌d������̂Ȃ��A�B���̂��Ƃ�K��
�]��f���ċ����S���������ƂŒB���ɓ�����������܂ł�
�o��̕��ꂪ�����Ă���B
���e�����ɓ���Ƃ���͂Ȃ��B
���̕���͗ǂ��m���A��������̐�M�ɂ��u�d�f�]�}�v�ɂ��`����Ă���B

�}14.1 ��M�M�u�d�f�]�}�v�@�@
���̐}�̍������ɂ͌d���]��f���ċ��������S��������ʂ��`����Ă���B
�u�d�f�]�̕���v��ǂ�Ŏv���̂́A�͂����āA
�u�B���͌d���]��f���ċ��������S�������܂œ���������Ȃ��������낤���H�v
�Ƃ����^��ł���B
���]�������邭�炢�ł͖��Ȃ����낤���A
�{�����]��f���炢�[����������o�������Ő����܂Ŏ���ꂩ�˂Ȃ�����ł���B
�u�d�f�]����v�ɂ��Ă͍]�˂̔��B�T�t�ɂ��u�d�f�]�}�v���m���Ă���B
�}14.�Q�ɔ��B�T�t�ɂ��u�d�f�]�}�v�������B

�}14.2 ���B�T�t�M�u�d�f�]�}�v�@�@
�E��̉~�̒��ɂ͒B�����`����Ă���B
�}�̍������ɂ͌d��������O�b�ƐL�����ɂ������̘r��낤�Ƃ��Ă���B
�}�̏㕔�ɂ�
�u�����̎��f���ĐS����J���ȂǁA���Ɩ��ʂȍs�ׂ��v
�Ƃ̔��B�̉�^������B
���̉�^���A���B�T�t�͓��傷��̂Ɏ������]��藎�Ƃ��K�v�͂Ȃ��ƍl���Ă��邱�Ƃ�������B
���̉�^�ɂ́u�d�f�]����v�ɂ��Ă̔��B�T�t�Ǝ��̉��߂��q�ׂ��Ă��ċ����[���B
�u�d�f�]�̕����v�͘b��ʔ����h���}�`�b�N�ɂ��邽�߂��n�삳�ꂽ����̉\���������B
�����P�O
�����蓰���ɂ���B
�������N�A�ΘJ�疜�A�܂��Ƃɂ���l�V�̑�˜��Ȃ�Ȃ�A
�l�V�̑哱�t�Ȃ�Ȃ�B
�����̂��Ƃ��̋ΘJ�͐��V�ɂ��������A���n�͂��߂Ă���B
�j��͌Â������A�����͑c�Ɋw���B
���Â��Ɋϑz���炭�́A���c�����疜�̐�������Ƃ��A
��c�����s�������A�����̖O�w�[�傠��ׂ��炸�B
��������A���@���������邽���ЂƂȂ��A
�c�̉����Ȃ炸��ӂ��ׂ��B
���̕�ӂ͗]�O�̖@�͂�����ׂ��炸�A
�g�����s���Ȃ�ׂ��A������������ɂ��炸�B
����͑��l�ɂ����͂�A�e�q�ɂ���Â�B
�g���͖���ɂ��܂����A��N�ɂ��܂����A�ד��ɂ��܂����B
��������A����������ĕ�ӂɋ[����ɁA�s���Ȃ�ׂ��B
�����܂��ɓ����̍s���A���̕�ӂ̐����Ȃ�ׂ��B
���͂��̓����́A�����̐����Ղɂ����A
�킽�����ɂЂ₳�����ƁA�s������Ȃ�B
���̂��͂�����B
���̐����́A�O���̍s���̗]�c�Ȃ�A
�s���̑剶�Ȃ�A��������ӂ��ׂ��B
���Ȃ��ނׂ��A�͂Âׂ��B
���c�s���̌�������萶������`�[���A
�����Â�Ȃ�Ȏq�̂Ԃ˂ƂȂ��A�Ȏq�̂��������тɂ܂����āA
�j���������܂���Ƃ́B
���ɂ��Đg���𖼗��̗����ɂ܂����B
�����͈ꓪ�̑呯�Ȃ�B���������������A���������͂�ނׂ��B
���������͂�ނƂ��ӂ́A
���c�ƂȂ�ʂׂ��g�����A�����ɂ܂����Ă�Ԃ炵�߂���Ȃ�B
�Ȏq�e�����͂�܂Ƃ��A�܂������̂��Ƃ����ׂ��B
�����͖�����Ȃ�Ɗw���邱�ƂȂ���A�O���̂��Ƃ��w���ׂ��B
���������͂�܂��A�ߕ�����炵�ނ邱�ƂȂ���B
�Q�w�̐��Ⴀ�܂˂��������݂ƁA�����̂��Ƃ��Ȃ�ׂ��B
���l�̂Ȃ�������A���Ⓙ�߂̖b�A�Ȃٕ�ӂ��B
�D��D���̂悵�݁A�����날��݂͂ȕ�ӂ̂Ȃ������͂��ށB
�@������̐��@����������剶�A����̐l�ʂ��킷���Ƃ������B
������킷�ꂴ���A�ꐶ�̒���Ȃ�B
���̍s����s�ޓ]�Ȃ��`�[�鐂́A
���������A���Ȃ������ɂ����߁A��ؐl�V�A�F�����{�̌����Ȃ�B
�����̂��Ƃ��剶����Ƃ���ȂA
���Ȃ炸���I�̖��������Â�ɗ뗎�����߂��A
�@�R�̓����˂�ɕׂ��B
���ꂷ�Ȃ͂��s���Ȃ�B
���̍s���̌��́A�c���Ƃ��čs�������ꂠ�肵�Ȃ�B
���ق悻���c�E��c�A���Đ����𑐑n�����A�㑐�̔ɖ��Ȃ��B
����юO�c�E�l�c���܂������̂��Ƃ��B
�ܑc�E�Z�c�̎��@�����������A���E��Ԃ��܂������̂��Ƃ��B
���F
�����F�@�w��̉��`�B
�����F ���҂Ƃ��Ă̋߂��s�Ȃ����ƁB
�ΘJ�F�@�Ζ��̋�J�B
�疜�F�@�����E���ʂ��ے��I�ɕ\�킷�B
�˜��i�����j�F�@����ɂȂ���́B
�c�F ��c�d��t�B
�u���܂��͎��̐����v�F�B�����l�l�̒�q�i�d�A����A���A�����j�ɑT�@��`��������
�u��������v�̈�b�����̂悤�ɓ`�����Ă���B
�B����t�́A������ˑR�A�����̒�q�B�ɖ₤���A
�u���͍Ō�̎��������悤���B
���N�A���̂��̎��瓾�����̌��t���q�ׂĂ݂��B�v
�@���̎��A�����i�ǂ��Ӂj�Ƃ�����q��
�u�����ɕ߂��ꂸ�A�܂������𗣂ꂸ�ɁA�Ջ@���ςɌ��̓������ׂ����Ƃ��ł��܂��B�v
�ƌ������B
�@�B����t��
�u���܂��́A������B�v
�ƌ������B
�@���ɓ��i�ɂ������j�͌������A
�u�h�邬�Ȃ����E�����āA�Ăь������Ǝ������Ȃ����Ƃł��B�v
�@�B����t��
�u���܂��͓������B�v
�ƌ������B
�@�����ɓ���i�ǂ������j�͌������A
�u�����I���ۂ͖{����ł���A���������̂��Ȃ��A���Ƃ͂�����A�S�̓����������Ă��܂��B�v
�@�B����t�͌������A
�u���܂��͂킪�����̍������B�v
�Ō�ɁA�d�͂����O�ɐi�݁A��q�����A���ɖ߂����B
�@�B����t�͌������A
�u���܂��͎��̐����B�v
�ƌ������B
���ʓI�Ɂu���v���Ə̂���ꂽ�d���B���̌�p�ҁi��c�j�ƂȂ�̂ŁA
�u��v�A�u���v�A�u���v�A�u���v�̏��ł��[���������ƍl������B
�ϑz�F�@�ϏƂ��l���邱�ƁB
�O�w�F�@�O����قǏ[���Ɋw�Ԃ��ƁB
�[��i�������j�F �厖��[�u���邱�ƁB
����F�@�@�����B�@
�s���F�@���ɂ��炸�̈ӁB�������Ȃ����ƁB
���ՁF�@�����Ɉӂ𗯂߂��Ȃ�����Ȃ��ƁB
���邪�܂܂ɂ܂����邱�ƁB�@
�킽�����F�@ ���Ȃ̗~�]�A�������~�B
�]�c�F�@�c����l�̑P�s�ɂ���Ďq��������K�^�̂��ƁB
�������B�@
�������F�@�@�w�͂̐��ʁB
�Ԃ�F�@�����ׁA������A���j�A�����B
�j���F�@ �@�j�����B
�����F�@�������̗��B���S�Œʗ͂悭�l�𖣂��A
�܂��l��H���Ƃ����B�@
�ꓪ�F�@�@�ꓙ�A��ԁB
���F�@���ҁA�G�B�@
���͂�ށF �������ށA�߂ł�B
��F�@�@���̂̂Ȃ�����̌��ہB
���߁F�@���炵���ߘM���B
�b�F�@�b�݂������ނ炷�B)
�D��F�悢���t�A���h�Ȍ��t�B
�D���F�@�@�悢���A�����B
�悵�݁F�@�e���������A�e���݁A���b�B
�Ȃ����F�@�����݁A�v�����A�l��B�@
���I�F ���̗t�̏�ɏh�����I�̂悤�ɂ͂��Ȃ����́B
�뗎�F�@�@���ڂꗎ���邱�ƁA���ʂ��ƁB�@
���F�@�@���p�A���ʁB
�c���F�@�@�@�c�t�╧�B
�����F�@���ɉ����̗��B���@�̂��ƁB�@
���n�F�@�@�@�͂��߂đ��邱�ƁB
�㑐�i�������j�F�@�@���������čr�n���J�����ƁB
��P�O���i�̌�����
�d�́A���̎�����t�̓����ɓ������B
�����Ďt�Ɏd���邱�Ɣ��N�A������C�s�ɗ͂�s�������B
�܂��Ƃɂ��̐l�́A�l�ԊE�V��E�̑傫�ȐS�̋��菊�ł���A
�l�ԊE�V��E�̑哱�t�������B
���̂悤�ɋ����ɗ͂�s�������l�́A
�C���h�ł��������A���n�����ł����߂Ă̂��Ƃ������B
�́A��h�R�̖@��ŁA�ߑ����Ԃ���ɁA�u������ƁA
���d�ޗt�������������B
�����Ŏߑ��͉ޗt�ɐ��@��`�����ƌ�����B
�܂��A���c�B�����S�l�̒�q�ɏC�s�œ������̂����X�ɐq�˂����A
�Ō�Ɍd�͏��c�̑O�ŗ�q���Č��̈ʒu�ɋA���ė������B
���̎����c��
�u���܂��͎��̐����B�v
�ƌ������Ƃ����b�́A���̑c�t����w�Ԏ����o����B
�Â��ɍl���Ă݂�A���c�����疜��A�C���h���痈���Ƃ��Ă��A
��c�d�����c�̖@��`���Ȃ���A
�����̉�X�͕��@���\���Ɋw�Ԃ��Ƃ��o���Ȃ������B
�c�t�d�̂����ŁA�����̉�X�͐��@���������钇�ԂƂȂ����B
������A���̑c�t�̉��ɂ͕K�����ӂ��ׂ����B
���ӂ���ɂ́A���̕��@�͓K���ł͂Ȃ��B
���̐g���ŕ悤�Ƃ��Ă��s���ŁA�������[���ł͂Ȃ��B
�����͑��l�ɂ��D���A�e��q�ɂ�������̂��B
���̐g���͐��̖���ɂ��C���A
��N�ɂ��C���A�ד��ɂ��C������̂ł���B
������A����őc�t�ɕ��ӂ���Ƃ͌���Ȃ��̂��B
�������X�̍s�����A���ӂ̐����ł���B
���̓����́A���X�̐��������������ɉ߂������A
���I�Ȃ��̂ɔ�₳�Ȃ��悤�ɏC�s���邱�Ƃł���B
���̂Ȃ�A���̍s�����鐶���́A
�̂̕��c�ɂ��s���̗]�c�ŁA�s���̑剶�ɂ����̂����炾�B
������A�}���ł��̑剶�ɕ�ӂ��ׂ��ł���B
�߂��ݒp���ׂ����Ƃ́A
���c�̍s���̌������琶�܂ꂽ�g�̂��A
�܂�ʍȎq�̂����ׂƂ��A�Ȏq�̐����̂��߂Ɏg���A
�����Ԃ�邱�Ƃ�ɂ����Ǝv��Ȃ����Ƃł���B
�˂��������Đg���𖼗��̈��S�ɔC���A
�����͑��̑呯�ƂȂ邾�낤�B
�������d��Ȃ�A���������Ƃ����ނׂ����B
���������Ƃ����ނƂ́A���c�ƂȂ�ׂ��g�����A
�����ɔC���ď����Ȃ����Ƃ��B
�Ȏq��e�������Ƃ����ނ��Ƃ��A�܂����̂悤�ɂ��ׂ��ł���B
�����͖��⌶�̋��Ԃł���Ɗw�Ԃׂ��ł͂Ȃ��B
�l�X�̎v���悤�Ɋw�Ԃׂ����B
���������Ƃ����܂��ɁA�߂̕�ςݏd�˂Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�������w�Ԑ�������́A�S�Ă̂��̂��A���̂悤�Ɍ���ׂ��ł���B
���̒��ł���̂���l�́A
����Ⓙ��������Ⴆ�Ί��ӂ��悤�Ƃ���B
�܂��A�D�܂������t��̐e���ɂ́A
�S����l�͊F ���ӂ̏��s�������Ƃ���̂��B
�܂��āA�@���̖���̐��@���������邱�Ƃ�
�o����悤�ɂ����c�t�̑剶���A
�l�ԂȂ�ΒN���Y�����̂��낤���B
�����Y��Ȃ����Ƃ��ꐶ�̕ł���B
���̍s����ӂ�Ȃ��g�̂��鐂́A���̎������̎����A
����̓��ɔ[�߂��āA������l�V�ɋ��{�����
�Ƃ�������������̂��B
�A�c�t�ɂ͂��̂悤�ȑ剶�����邱�Ƃ�m��A
�����đ��I�̂悤�ɂ͂��Ȃ����ʂɂ����A
�R�̂悤�ȉ����ɁA�e���������Ă����ׂ����B
���ꂪ�s���ł���B
���̍s���̌����́A�c���Ƃ��čs������
�䂪����Ƃ������Ƃł���B
���悻���c���c�́A���@��n�������A
��������y�n���J���ɖ��͂Ȃ������B
�����ĎO�c�i�Ӓq�m�T���j��l�c�i��㓹�M�j�������������B
�ܑc�i�喞�O�E�j��Z�c�i��ӌd�\�j��
���玛�@��n�������킯�ł͂Ȃ����A
���i�s�v�j���ԁi�����j�������������̂ł���B
���̕��i�ł��Q�c�d�̍s�����Љ�Ă���B
�Q�c�d�͎t�B���̓����ɓ������B
�����Ďt�Ɏd���邱�Ɣ��N�A������C�s�ɗ͂�s�������B
��c�d���B���̖@�𐳂����`���Ă��ꂽ���߁A
�u�b�_�ȗ��̐��@���p�������X�ɓ`����ꂽ�̂��B
�Q�c�d�͐l�ԊE�V��E���傫�ȐS�̋��菊�ł���A�l�ԊE�V��E���哱�t�������Ɛ�^���Ă���B
�@���̖���̐��@�������o����悤�ɂ���
�c�t�d�̑剶��Y�ꂸ��ӂ��ׂ����ƌ����Ă���B
���ڂ����̂́A
���c�̍s���̌������琶�܂ꂽ������g�̂������̐����Ɏg�����Ƃ�ے肵�Ă������Ƃł���B
�����̐��������Ȃ���C�s���鋏�m�T�͑ʖڂ��Ƃ���ƁA
�`���I���o�Ǝ����`�ɂȂ邵���Ȃ����낤�B
��������
��ؐ��O�́u���@�����@�v�̂悤�Ȑ����m��̗D�ꂽ�T�v�z�͐��܂�Ȃ����낤�B
�i ��ؐ��O�́u���@�����@�v�̎v�z���Q���j�B
�����P�P
�Γ���t�́A���r���ɂނ��тāA�Ώ�ɍ��T���B
����ɂ˂Ԃ炸�A��������Ƃ��Ȃ��B
�O�����k荂����Ƃ��ւǂ��A�\�̍��T�A���Ȃ炸�Ƃ߂������B
���ܐ��̈�h�́A�V���ɗ��ʂ��邱�ƁA�l�V�𗘏������ނ邱�Ƃ́A
�Γ���͂́A�s�����ł̂������炵�ނ�Ȃ�B
���܂̉_��E�@��́A������ނ�Ƃ��날��A
�݂ȐΓ���t�̖@���Ȃ�B
���F
�Γ���t�F�@�Γ���J�i�i�����Ƃ� ������A700 �` 790�j�B�@
���s�v�T�t�̖@�k�B�n�ߘZ�c�d�\�T�t�ɏA���ďo�Ƃ������A
�Z�c�̎���A�▽�ɂ���čs�v�T�t�Ɏt�������B
�@ �t�R�̓쎛�ɍs���A�Α��Ɉ�������ō��T�����̂ŁA
���̐l���Γ��a���ƌĂB
����Z�N�����A�N��\��B���ۑ�t�Ƃ����薼���ꂽ�B
�����ɐΓ������̂���юQ���_������B
�i �Q���_���Q���j�B
�O���F�@�����̖��߁B
�����F�@�@���v��^�����������ƁB
�_��F�@�@�_�啶��i�������Ԃ�A�W�U�S�`�X�S�X�j�T�t�B�@
�@��F�@�@�ᕶ�v�T�t�i�W�W�T�`�X�T�W�j�B
�@���F�@�@�T�̎q��W�ɂ�����q���B
��P�P���i�̌�����
�Γ���J�T�t�́A�������̏�ɑ���A�̏�ō��T�����B
����ɖ��炸���T���Ă��Ȃ����͂Ȃ������B
���X�̖��߂������������Ƃ͂Ȃ��A����̍��T�͕K���w�߂��̂ł���B
�����A���i�s�v�j�̈�h���V���ɍL�܂��Đl�X�𗘉v���Ă��邱�Ƃ́A
�Γ��̑�͗ʂɂ�錘�łȍs���̂����ł���B
�����̉_��@��@��@�ŁA�@�̊�𖾂炩�ɂ����l�����́A
�F�A�Γ���t�̖@���ł���B
�Γ���J�T�t�́A�������̏�ɑ���A�̏�ō��T�����B
����ɖ��炸���T���Ă��Ȃ����͂Ȃ������B
�_��@��@��@�ŁA�@�̊�𖾂炩�ɂ����l�����́A
�F�A�Γ���t�̖@���ł�����Γ��̑�͗ʂɂ�錘�łȍs�����̎^���Ă���B
�}�P�T�ɐΓ���J���W����@�n�}�������B
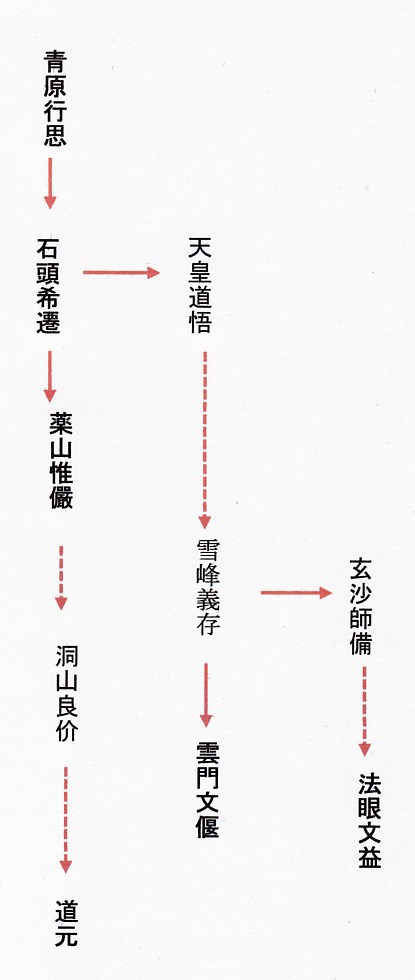
�}�P�T ����J���W����@�n�}�@
�}�P�T�Ɏ������悤�ɁA
�Γ���J�̖@�n�������@�݂̂Ȃ炸�_��@��@��@�ɋy�������̏@�h�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ��������Ă���B
�����P�Q
�@��O�\��c���T�t�́A�\�l�̂��̂��݁A
�O�c��t���݂����A���J��ڂȂ�B
���łɕ��c�̑c�����k��������A
�ېS�����ɂ��ċ��s���ȂȂ邱�ƁA�͘Z�\�N�Ȃ�B
���A���e�ɂ����Ԃ炵�߁A���A�l�V�ɂ��܂˂��B
�^�O�̎l�c�Ȃ�B
���F
��O�\��c�F�@�����T��l�c��㓹�M�T�t���w���B
�@ �ߑ��̒��ڂ̌�p�҂Ƃ���門���ޗt���҂��琔����ƒB���͑�Q�W�c�A
�d�͑�Q�X�c�A�O�c�i�Ӓq�m?�j�͑�R�O�c�A
�l�c�i��㓹�M�j�́A��R�P��ڂ̋��c�w���҂ɓ�����B
���T�t�F�@ �����T�̑�l�c��㓹�M�T�t�i�T�W�O�`�U�T�P�j�B
�����T�̑�O�c�Ӓq�m�T���T�t�̌�p�ҁB
��q�ܑ̌c�O�E�Ƌ��Ɂu���R�@��v�ƌĂ���吨�͂�z���A
��̑T�@�̕�ق��`������B
���͎i�n���A�U�T�P�N�����A�N�V�Q�B�@
���̂��݁F�@�@���̐́B�@
�O�c��t�F�@�����T�̑�O�c�Ӓq�m�T���T�t�i500�N���`606�N�j�B
�����T�̑�O�c�B��c�d��t�̌�p�ҁB
���A�������s���B����ɐM�S��������B �i�M�S�����Q�Ɓj
�i�M�S�����Q���j�B
���J�F�@�J���ɕ����邱�ƁB
��ځF�@��N�B�@
�ېS�F�@�@�S�������߂ĎU�炳�Ȃ����ƁB
�����i�ނсj�F�@�@���͂˂�A�˂ނ�B�����͂˂ނ�Ȃ����ƁB
�e�F�@�e���B�@�@
�ȁF�@�ނ���A��ނ���B
�́F�@�قƂ�ǁB�@
���F�@�@�����B�@�@
���e�F�@�����Ɛe���ƁB
���F�@���]�B
��P�Q���i�̌�����
�@���͉ޗt���҂��琔���đ�O�\���̑c�t ���T�t�i���M�j�́A
�\�l�̍��ɎO�c��t�i�m�T���j�Əo����Ă���A�t�ɋ�N�ԏ]�����B
���c�̉ƕ����p���ł���́A
�S�𐮂��Ė��邱�ƂȂ��A�g�����������ɁA�قژZ�\�N�߂������B
���̋����́A���݂̂���l�ɂ��e�����l�ɂ��������y��ŁA
�����͐l�ԊE�ƓV��E�ɍs���n�����B
���ꂪ�����̑�l�c�ł���B
�ߑ������O�\���̑c�t ���T�t�i���M�j�́A
�\�l�̍��ɎO�c��t�i�m�T���j�Əo��A�t�ɋ�N�ԏ]�����B
���c�̉ƕ����p���ł���́A
�S�𐮂��Ė��邱�ƂȂ��A�g�����������ɁA�قژZ�\�N�߂������B
���̋����́A�����ɂ��e���ɂ��������y�сA
�����͐l�ԊE�V��E�ɍs���n�����B
���ꂪ�����T��l��ڂ̎w���҂ł����
�l�c���M�T�t���s���s�x�̍s�����Љ�̎^���Ă���B
�@���M�T�t�͎O�c�i�m�T���j�̖@���p�����Ă���قژZ�\�N
�S�𐮂������邱�ƂȂ��A�g�����������ɁA
�߂������Ƃ����ď̎^���Ă���B
���������ŋC�ɂȂ�͓̂����T�t�́u���ɁA�s���s�x�̍s�����D���Ȃ��Ɓv�ł���B
�����ɂ킽�鐇���s���͌��N�ɏd��Ȉ��e�����y�ڂ��\����
���邱�Ƃ������w�ŕ������Ă���B
�����s���͓��̓I�ɂ����_�I�ɂ����N�ɗl�X�Ȉ��e���������N�����A
�������������\�������閝���I�Ǐ�̃��X�N�ɂ��炳���B
�����I�Ȑ����s���͓����̖��C���ӗ~�ቺ�E�L���͌����Ȃ�
���_�@�\�̒ቺ�������N�����B
���ꂾ���ł͂Ȃ��A�̓����z����������⎩���_�o�@�\�ɂ�
�傫�ȉe�����y�ڂ����Ƃ��m���Ă���B
���邱�ƂȂ��A�g�����������ɁA�C�s�ɐ�O����̂́A
1.
�����̖��C��ӗ~�ቺ�E�L���͌��ނȂǐ��_�@�\�̒ቺ�������炷�B
2.
�z����������⎩���_�o�@�\�ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��B
���̌��ʁA�������A���A�a�A�����d���A�F�m�ǂȂǂ��a�C�ɂȂ�\���������̂Ŏ~�߂������ǂ��Ǝv����B
�̂͐����s���ƕa�C�̊W���������Ă��Ȃ������̂ŁA
�e���҂��S�c�̂悤�ɕs���s�x�̏C�s�҂����h����Ă����B
�i�s���P�A��S���i���Q���j�B
�������A�����s���ƕa�C�̊W���������Ă������݁A�Q�Ȃ��ŏC�s����̂����d�ȏC�s�ł���ƌ����ėǂ��B
���̂悤�ȏC�s�͔����Ñ�I��s�ł���A����̏C�s�@�Ƃ��ẮA�~�߂�����ǂ��Ǝv����B
�����P�R
���ᡉK�̍A���@�A�t�̓����сA
���ʂ��ۂ�Ɨ~���āA�������ق��B
�t�A��\���ӂ��邱�ƑO��O�ԂȂ�B��Ɏ����ȂĎ����B
��l�x�A�g�ɖ����ĞH���A
�u�@���ʂ��ĕ�������A���������藈���B�v
�g�A�R�Ɏ����Ď|��@���B
�t�A�T����������Đn�ɏA���A�_�F�V�R����B
�g�A�V���قƂ��A���ď���Ȃĕ����B
��A����V�炷�B
�������A�����āA�Ȃđ��̎u�𐋂��B
���F
��ψ��K�F�U�S�R�N�B
��B�]�V���i���傤���イ���イ����A�V�V�W�`�W�X�V�j�T�t�B
���T�t�̖@�k�B�W�X�V�N�����A���N�P�Q�O�B��^�O��������B
���@�F�@�r�͌����ׂ������������
���@�F�@���̑��@�B
�������̑�i�U�Q�U�`�U�S�X�j�B�������B�@
�_�F�@�ނ����A�S�����B
�����F�@�^���̖����A���B�������n�B�@
�X�F�@�݂�B
���ʁF�@���тɓ����B�l�̂悤���A�������B�l�i�A�l���B�@
��\�F�@���ʂ����Ă܂邱�ƁB
���ӁF�������Ď��ނ��邱�ƁB�@
���F�@��܂��A�a�C�B
���F�@��������A�̂��A�Ђ��ʂ��B�@
�_�F�F�@�@���_�Ɗ�F�B�悤���A�ԓx�B
�V�R�i����j�F�@�Ќ��̂��邳�܁A���������ɂ����������܁B�@
�فF�@�����ށA�^���A�s�v�c�Ɏv���B�@
��F�@����A�����B
���F�@�t������A�\���グ��B�@
�V��i����ځj�F�]�V���A���������ƁB
�����i�����j�F�@�@�M�d�Ȍ��D���B
��P�R���i�̌�����
�Z�l�O�N�ɁA���̑��@�͑�㓹�M�T�t�̓����ɋ����������A
���̐l�������悤�Ƃ��āA�s�ɗ���悤���߂����B
���������T�t�͏��ʂ����Ă܂茪���ɎO��f�����B
�����čŌ�ɂ͕a�C�𗝗R�Ɏ��ނ����B
��l��ڂ̏����ɓ����čc��́A�g�҂ɖ����Ă������A
�u�����ǂ����Ă����Ȃ��ƌ����Ȃ�A���̎��͎������ė����B�v�@
�g�҂͑��T�t���Z��ł����R�ɍs���A
�c��̎�|������������A
���T�t�͑����Ɏ�������ׂ̂ē��̑O�ɍ������B
���̑ԓx�͋C���������������B
�g�҂͂����s�v�c�Ɏv���A���ʂɂ���đt�サ���B
�����ōc��́A�܂��܂��]�V�ԕ炵�A
�M�d�Ȍ��D����T�t�ɉ������A���̎u�𐋂����B
���M�T�t�̓����ɋ��������������̑��@�́A
�U�S�R�N�A�s�ɗ���悤���߂����B
���������T�t�͏��ʂŌ����ɎO��f�����B
�����čŌ�ɂ͕a�C�𗝗R�Ɏ��ނ����B
�@ ��l��ڂ̏����ɓ����čc��́A
���Ƃ��Ă�����ƁA�g�҂ɖ����Ă������A
�u�����ǂ����Ă����Ȃ��ƌ����Ȃ�A���̎��͎������ė����B�v
�g�҂͑��T�t�̂��Ƃɍs���A�c��̎�|������������A
���T�t�͑����Ɏ�������ׂ̂ē��̑O�ɍ������B
���̑ԓx�͋C���������������B
�g�҂͂����s�v�c�Ɏv���A���ʂɂ���đt�サ���B
�����ōc��́A�܂��܂��]�V�ԕ炵�A
�M�d�Ȍ��D����T�t�ɉ������A���̎u�𐋂����B
�����ł͑�P�Q���i�ɑ����A
�S�c���T�t�i���M�j���Љ�A
�S�c���M�T�t�����͎҂ɋ߂Â��Ȃ��M�O�ƍs�����Љ�A�̎^���Ă���B
�����P�S
�@����������Ȃ킿�A�l�c�T�t�́A�g����g���Ƃ����A
���b�ɐe�߂������ƍs������s���A�����̈���Ȃ�B
���@�͗L�`�̍���Ȃ�B
�����́A���̂�����ׂ��ɂ��炴��ǂ��A
�����̂��Ƃ���B�̍s���͂��肯��ƎQ�w���ׂ��Ȃ�B
�l��Ƃ��Ă͈����A�����āA
�g���������܂���l�������A�Ȃٕ~����Ȃ�B
���ꂢ���Â�Ȃ�ɂ��炸�A
���A�������݁A�s������ɂ���Ȃ�B
��\�O�ԁA���̗�Ȃ�B
���ܔ��G�ɂ́A���Ƃ߂Ē�҂ɂ܂݂���Ƃ˂��ӂ���B
���@�i�J�h��Ή[�㌎�l���A�����ɖ�l�ɐ��r���ĞH���A
�u��؏��@�́A�����F ��E�Ȃ��B
�� �e�� ��O���āA�����ɗ������ׂ��v�B
�����^��Ĉ������Đ����B
�����\�L��A�{�R�ɓ������B
���N�l�������A���̌ˁA�̖������Ď���J���A
�V�������邪�@���A����A��l ���ĕ� �����B
���F
�l�c�T�t�F�@�����T�̑�S�c��㓹�M�T�t�B�@
�L�`�F�@�`�������̈ӁB�����������Ȃ����l�����Ӗ�����B�@
�C�G�i���傤���j�F�l����������̗��ꂽ���̐��B
�������������y���ɂȂ�������B�����B
��ҁF�@�鉤�A�c��B
���@�F�@���̑�O��c��i�݈ʁF�U�S�X�`�U�W�R�j�A�����B
�i�J�h��F�@�@�U�T�P�N�B
�[�F�@���A��ł͈�N�����̍�]�ɍ��킹�Ė�R�U�O��
�ƒ�߂Ă��邩��A
�ܔN�ɓ�x�̊��ň�N���\�O�J���Ƃ��A���̔N�ɂ͂��錎���x�J��Ԃ����B
���̌����[���Ƃ����A�[���̂���N���[�N�Ƃ������B�@
���r�i���������j�F�@��������邱�ƁB�r�͋��ɓ����B
��l�F�@�剺���B
��O�F�@�S�Ɏ����Â��邱�ƁB
���F�@�@��������B
���F�y�������ς�ň⍜�𑠂߂邱�ƁB
�V���F�V�͂������A�悤���B���͗e�e�A�݂߂������B
��P�S���i�̌�����
���̂悤�Ɏl�c ���T�t���A�g�������̂Ƃ������A
���� ��b�ɐe�߂��Ȃ��悤�ɐg���������s���́A
��N�Ɉ�x���������Ȃ��D�ꂽ�s���ł���B
���@�͓��`��������傾����A
����Ƃɂ��������������킯�ł͂Ȃ����A
��X�́A���̂悤�ɐ�B���������s�����w�Ԃׂ��ł���B
�l�X�̎�l�ł��鑾�@�Ƃ��ẮA�g����ɂ��܂��ɁA
���̑O�Ɏ��L���l�����A�܂����V���h�炵���̂ł���B
���̑T�t�͖��p�Ȏ��������킯�ł͂Ȃ��A
���A��ɂ���ŏC�s����ɂ����̂ł���B
���ʂ��O�x������āA�Q�������ނ����̂́A���ɂ��H�Ȏ��ł���B
�����̂悤�ȓ��� �l��̂����ꂽ���ɂ́A
���狁�߂Ē鉤�ɉ�����Ɗ肤�҂�����قǂ��B
���̍��@�̑�A�U�T�P�N�X���S���A
�l�c�́A�ˑR ��l�����ɋ����Č������A
�u�S�Ă̂��̂́A���Ƃ��Ƃ��F ��E���Ă����B
���O�����́A���̂��ƂɋC�t��
������Ɍ��A�����ɋ������L�߂Ȃ����B�v
���������I���ƁA�������ĖS���Ȃ����B
���͎��\��B�{�R�i�j���R�j�ɕ擃�����Ă�ꂽ�B
������N�̎l�������A���̔������R���Ȃ����R�ɊJ���ƁA
���̎p�͐����Ă���悤�������B
���̌��l�����́A���Ĕ�����悤�Ƃ��Ȃ������B
��13���i�ł݂��悤�ɁA�S�c���M�T�t�͎��̍c��ɌĂ�Ă��A
�g�������̂Ƃ������A���� ��b�ɐe�߂��Ȃ��悤�ɐg���������B
���̍s���́A��N�Ɉ�x���������Ȃ��D�ꂽ�s���ł���B
���@�͓��`��������傾����A����Ƃɂ��������������킯�ł͂Ȃ����A
��X�́A���̂悤�ȍs�����w�Ԃׂ��ł���B
�T�t�͖��p�Ȏ��������킯�ł͂Ȃ��A
���A��ɂ���ŏC�s����ɂ����B
���ʂ��O�x������āA�Q�������ނ����̂́A���ɂ��H�Ȏ��ł���B
�����̂悤�ȓ��� �l��̂����ꂽ���ɂ́A
���狁�߂Ē鉤�ɉ�����Ɗ肤�҂�����قǂ��B
���@�i�J�h��Ή[�㌎�l���i�U�T�P�N�X���S���j�A
�l�c�́A�ˑR ��l�����ɋ����Č������A
�u�S�Ă̂��̂́A���Ƃ��Ƃ��F ��E���Ă����B
���O�����́A���̂��ƂɋC�t���A������Ɍ���A
�����ɋ������L�߂Ȃ����B�v
���������I���ƁA�������ĖS���Ȃ����B
���͎��\��B�{�R�i�j���R�j�ɕ擃�����Ă�ꂽ�B
������N�̎l�������A���̔������R���Ȃ����R�ɊJ���ƁA
���̎p�͐����Ă���悤�������B
���̌��l�����́A���Ĕ�����悤�Ƃ��Ȃ������B
�����ł���P�Q�A�P�R���i�ɑ����A
�S�c���T�t�i���M�j���Љ���̗D�ꂽ�s�����̎^���Ă���B
�����ł����M�T�t�̕擃�̔������R���Ȃ����R�ɊJ���ƁA
���̎p�͐����Ă���悤�������ƒ���I�Ŗ��d�s�v�c�ȏo�������Љ�Ă���B
�����ł���W���i�Ō���ꂽ�����T�t��
����I�����d�s�v�c�Ȃ��Ƃ��D���������T�t�̐��i������Ă���B
�i�s�����A��W���i�̉��߂ƃR�����g���Q���j�B
�S�c���M�T�t�̈⌾��
�u��؏��@���F��E�B�e����O�A���������v
�ł���B
�����
�u�S�Ă̂��̂́A���Ƃ��Ƃ��F ��E���Ă����B
���O�����́A���̂��ƂɋC�t���A������Ɍ��A�����ɋ������L�߂Ȃ����B�v
�Ɩ��B
�⌾�̊j�S������
�u��؏��@���F��E�v
�Ƃ��������ł���B
���̎咣�͑�柸�όo��
�u��؏O�����L�����v
�Ǝ��Ă���B
�u��؏O�����L�����v�ɂ����āA
��؏O�����@��؏��@�A���L�������@���F��E
�ɒu���������
�u��؏��@���F��E�v
�ɂȂ邩��ł���B
�Ƃ��낪�w�ǂ̐l�́u��؏��@���F��E�v
�̎����ɋC�t���Ȃ��B
���M�T�t�͍��T�C�s�ɂ����
�u��؏��@���F��E�v�̎������C�t���A������Ɍ��A�����ɂ��̋������������z���Ȃ���
�ƌ����Ă���̂ł���B
��������̐}�P�U�ɂ���Đ�������B
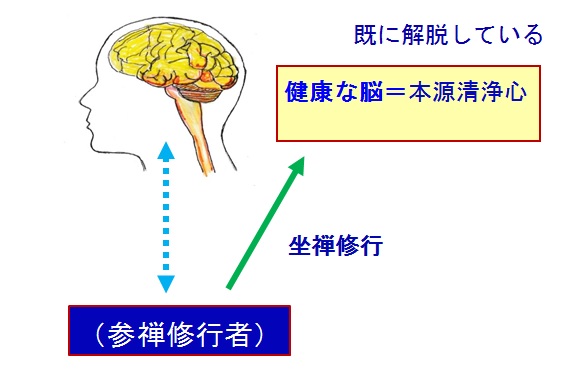
�}�P�U �s�f�̍��T�C�s�ɂ���č��T�C�s�҂̔]��
���N�Ȕ]�i�{������S�j�ɂȂ�ƁA���̐l�͊��ɉ�E���Ă��邱�ƂɋC�t���B
�}�P�U�Ɏ������悤�ɁA�s�f�̍��T�C�s�ɂ����
�Q�T�C�s�҂̔]�����N�Ȕ]�i�{������S�j�ɂȂ�ƁA
���̐l�͊��ɉ�E���Ă��邱�ƂɋC�t���B
���M�T�t��
�u��؏��@�͂��Ƃ��Ƃ��F ��E���Ă���̂��B
���O�����́A���̂��ƂɋC�t���A���̋C�t�����Ɍ���A
�����ɂ��̋������������z���Ȃ����B�v
�ƌ����Ă���̂ł���B
�u�e����O�v�Ɓu��O�v�Ƃ������t������̂�
�u��؏��@���F��E�v�̎����ɋC�t�������łȂ���Ɉӎ����A���T�C�s�ɂ���āA
���̋C�t����[�߁A
�u��؏��@���F��E�v���u��O�v���邱�Ƃ̑���������Ă��邱�Ƃ�������B
���̂S�c���M�T�t�̈⌾��
�s����̑�P�S���i�œ������q�ׂĂ��邱�ƂƓ����ł���B
�i�s���P�A��P�S���i���Q���j�B
���̍l�����͓V��{�o�v�z�Ǝ��Ă���B
�{�o�i�ق��j�Ƃ́A�{���̊o���i�������傤�j�Ƃ������ƂŁA
��̏O���ɖ{���I�ɋ�L����Ă�����i���o�j�̒q�d���Ӗ�����B
�@�����╧�������Ƃ�̖ʂ��猾�������̂ƍl������B
������Ղ������A�O���͒N�ł����ɂȂ��Ƃ������ƁA
���邢�͌���������Ă���i����Ă���j���Ƃ������B
��ɓV��@�𒆐S�Ƃ��ĕ����E�S�̂ɍL�܂����v�z�ƍl�����A
�����ł͖{�o�v�z�A���邢�͓V��{�o�v�z�Ƃ��̂���Ă���B
�S�c���M�T�t�̈⌾�̊j�S������
�u��؏��@���F��E
�i�S�Ă̂��̂́A���Ƃ��Ƃ��F ��E���Ă���B�j�v
�ł���B
�����
�u�O���͒N�ł����ɂȂ��Ƃ��������A
���邢�͕������{����������Ă����i����Ă���j�v
�Ǝ咣����{�o�v�z�Ƃ悭���Ă���B
���q���㏉���ɐ��܂�A���{�����@�̊J�c�ɂȂ��������i1200-53�j�́A
�Ő����J�����V��@�̔�b�R��K�ˁA14�ŏo�Ƃ����B
�����́A�V��O�啔�ɏ�����Ă���Ƃ���
�u�{���{�@���A�V�R�����S
�i�l�͐��܂�Ȃ���ɂ��Đ���ŁA���Ƃ��ƌ��Ă���j�v
�Ƃ����l���ɋ^���������B
������
�u�����A�l�͐��܂�Ȃ��畧��������A���Ă���Ȃ��A
�Ȃ��O���̏����͔��S���ďC�s�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H�v
�Ƃ����^����������̂ł���B
���̋^����b�R�ŐF�X�ȍ��m�ɓ������ĕ��������A
���̋^��ɖ��m�ɓ����邱�Ƃ��ł���l��
��b�R�ł݂͂���Ȃ������Ɠ`�����Ă���B
����͓����̔�b�R�̕����̃��x������������
�������̂ł͂Ȃ��������Ƃ������Ă���B
�l�͏C�s�ɂ���āA
�u�{���{�@���A�V�R�����S�v
�i�l�͐��܂�Ȃ���ɂ��Đ���ŁA���Ƃ��ƌ��Ă���j
�Ƃ������ƂɋC�t���̂ł���B
�����C�s�́u�{���{�@���A�V�R�����S�v
�i�l�͐��܂�Ȃ���ɂ��Đ���ŁA���Ƃ��ƌ��Ă���j�v
�Ƃ��������ɋC�t�����߂ɍs���̂��Ƃ������Ƃ�������Ȃ������Ƃ͂������ق��Ȃ��B
�����̔�b�R�̒�x���Ƒ��Ԃ�������Ă���B
�u�{���{�@���A�V�R�����S�v�i�l�͖{����������L���A���Ƃ��ƌ���Ă���j�Ƃ��������ɋC�t���̂���������ł���B
���̎����ɋC�t�����߂̏C�s�@�Ƃ��āA���T�C�s���ŒZ�̓��ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ����낤�B
�Q�l�����ȂǁF
�P�D�������@������q�Z���A��g���X�A��g���ɁA�u���@�ᑠ�i��j�v�P�X�X�Q�N
�Q�D���J���_���A�t�H�ЁA���@�ᑠ�Q���@�����@�P�X�V�Q�N
�R�D�����a�v�A�����ЁA�����@�ᑠ�@�����@��l��