
�u����ցF���̂Q�v�ł͐����b�M�A��g���Ɂu����ցv���傽��e�L�X�g�ɂ���
�����I�Ȋw�I���ꂩ��u����ցv�̂Q�T���`�S�W������Ղ�����������B
��g����ւ��D�P�O�U�`�P�O�W
�{���F
�R(���傤����)�a���A���ɖ���(�݂낭)�̏��ɉ�(��)���āA��O���Ɉ������B
�ꑸ�җL��A����(�тႭ��)���ĉ]���A�u������O���̐��@�ɓ������v�B
�R�T���N(��)���āA���Ƃ��ĉ]���A�u���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�B
����(�������傤)�A�����v�B
�]���F
��(����)����(��)���A������@���邩�A���@�����邩�B�����J���Α��������A
�����������r���B�J������������A�\������B
��F
�����V�A�����ɖ�������B
�s��(�˂�����)�s���A��O���@�s(����)�R���B
���F
�R(���傤����)�a���F�R�d��i���傤�����Ⴍ�j�i�W�O�V�`�W�W�R�j�B
�C�R��S�i�V�V�P�`�W�W�R�j�̖@�k�ŃC�@�i�����傤���イ�j�̑c�B
�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@���S����C���C�R��S���R�d��
���ӁF����}�C�g���[���̉��ʁB���ӕ�F�̂��ƁB
�\�Z�����疜�N��Ɋ����V(�Ƃ��Ă�)���炱�̐��ɉ������ďO�����~�ς���Ƃ�����F�B
���Ɓi�тႭ���j����F���ӂ����N���邽�ߒƂ�ł��炷�B
���d���i�܂�����j�̖@�F���d��(�܂�����)�Ƃ͞���}�n�[���[�i�̉��ʂŁA�傫�ȏ�蕨�̂��ƂŁA
�@���ƈӖĂ���B���d��(�܂�����)�̖@�Ƃ͑��̖@�Ƃ����Ӗ��B
�l��𗣂�S���₷�F������_�����Ă���B�l��ƕS��ɂ��Ă͌�q����B
�s���i�˂������j�F���̉��Ɏ��t���ꂽ�悤�ɉ������Ȃ��ƁB
�\������F�\�����痢�B�\�����痢����������Ă��邱�ƁB
�s(����)�R���F�x���B
�{���F
�R(���傤����)�a���́A���̒��Ŋ����V(�Ƃ��Ă�)�ɏ���
����(�݂낭)��F�̏��ɍs���āA��O���ɒ������B
����ƈ�l�̍��m���o�Ă��āA�Ƃ�ł��炵�āA
�u�F����A�����͑�O�������@���܂����v�ƌ������B
��������R�͋N(��)���オ���ĉ��d�ɍs���A�Ƃ�ł��ĉ]�����A
�u���̕��@�͎l��A�S��Ȃǂ�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����v�B
�]���F
���āA�R�a���͈�̐��@�����̂��A���@���Ȃ������̂��B
�����J���ΊԈႢ�ɂȂ邵�A
�ق��Ă���ΐ��@�ɂȂ�Ȃ��B������Ƃ����Č����J���������Ƃ������Ƃł��A
���@�������Ȃ���������Ă��܂��B
��F
�����V�̖��邢���ɁA�������Ė��̒��ŕ��@��������B
�R�a���̂���Ȗ�����͐r�����������̂��B
����ȉ������b���x����Ă͂��߂���B
�{���ɉ����ċR�́u���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�v
�ƌ����Ă���B
���̌��Ă𗝉����邽�߂ɂ́A���̎l���S��A�S��Ƃ͉����̒m�����K�v�ł���B
�ȉ��ɂ���ɂ��ĉ�����悤�B
�P�`�Q���I�C���h�����̊w�҂��i�[�K���W���i�i�����j������B
�ނ͑�敧������̗��_�̊m�����ŁA���@�̑c�Ƃ��Ă�Ă����w�҂ł���
( ��ɂ��Ắu���ϕ����v���Q�� )�B
���l��_�����̓i�[�K���W���i�i�����j���n�n�����_���Ƃ���Ă���B
�i�[�K���W���i�̎l��_���͑T�╧���̘_���Ƃ��Ă��悭�����B
�i�[�K���W���i���l��_���Ƃ͂����鑶�݂������̎l�l���ɕ��ނ���B
�P�F�L�i���݁j�B
�Q�F���i�݁j�B
�R�F�L�i���݁j�ł���ƂƂ��ɖ��i�݁j�ł���B
�S�F�L�i���݁j�ł����i�݁j�ł��Ȃ��B
�̎l�ł���B
���̓��R�́u�L�i���݁j�ł����薳�i�݁j�ł�����v�͑o��(�����₭)�ƌĂ�A
�S�͑o��(������)�ƌĂ��B
�R�̑o��(�����₭)�̘_���̓A���X�g�e���X�̘_���w�ɂ͂Ȃ��B
�A���X�g�e���X�̘_���w�ɂ́u�L�i���݁j�ł��邩���i�݁j�ł��邩�ł��̒��Ԃ͂Ȃ��v
�Ƃ����r����������B
�R�̘_���͂����r�����ɔ�����_���ł���B
�܂��A���X�g�e���X�̘_���w�ł́u�L�i���݁j�ł��邩���i�݁j�̂ǂ��炩���咣����i�������j�B
�������A�S�́u�L�i���݁j�ł����i�݁j�ł��Ȃ��v���咣���Ă���̂ł����������ɔ�����B
�A���X�g�e���X�̘_���w�͉��Ă̘_���w�̊�b�ɂȂ��Ă���B
���̊ϓ_����i�[�K���W���i���l��_���͉��Ă̘_���w�ƈقȂ�_�����܂�ł���B
����ւQ�T���ɂłė���l��Ƃ͂��̘_�����w���Ă���B
�S�����l�����玟���̂悤�ɂ��ē������_���ł���B
�l��͕v�X�Ɏl����܂ނ̂ŏ\�Z��ɂȂ�B
���̏\�Z��͉ߋ��A���݁A�����̎O���ɂ킽��ƍl����ƁA�P�U���R���S�W�ɂȂ�B
����𖢋N�o�����N�����Ă��Ȃ��ꍇ�p�ƁA�ߋN�i���łɋN�������ꍇ�j�ɕ������
�X�U�i�S�W���Q�j��ɂȂ�B����Ɍ��X�̎l���������ƕS��ɂȂ�B
���̕S���ے肵�����̂��S��ł���B
�l��ƕS�傪��敧���̂��ׂĂ̘_���ƂȂ�B
������A�u���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�v
�Ƃ����R�̌��t��
�u���̕��@�͈�̘_�����Ă����v�ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B
�o��(�����₭)�Ƒo��(������)�̘_���͓��{�����̗����ɂ��������Ȃ��B
�ȉ��ɂ��̗�����悤�B
���m�̘_���ł͐_�ƕ��͑S���ʂł���B
���������{�ɓ����ė������r���h�̕������͐푈�܂ł��āA�����h�̑h�䎁�Ƒ������B
����͌�X�܂Ŋ���I�Ȃ�������c�����ƍl������B
�������A���Ƌ��ɓ��{�ł͐_���K���̍l�������W��
�C���h����n�����������Ɠ��{�ŗL�̓y���@���ł���_�������ǂ���������悤�ɂȂ����B
���̂悤�Ȑ_�������_���K���͐��m�ł͍l�����Ȃ��B
���[���b�p�ł̓Q���}���l�̌ŗL�@���̓L���X�g���ɂ���Ĕr�˂��ꖕ�E���ꂽ�B
�C�X�����Љ�ł��y���̖����@���͖��E����Ă���B
�A�t�J�j�X�^���̃o�[�~�����̋���Ε��͐��E���̔��̐��ɂ��S��炸
�Q�O�O�P�N�R�� ���j�j�ꂽ�̂����̗�ƌ�����B
�C�X�������͋������q���֎~�ے肷��B
�����𐒔q���镧���̓C�X���������猩��������q�̎��ł���B
�o�[�~�����̋���Ε���������1�ɉ߂��Ȃ�����j�ꂽ�ƍl������B
�@
�} ���S�ɔ��j�E�j�ꂽ�o�[�~�����̍����R�W���̑�Ε�
�@�Ƃ��낪���{�ł͖�������܂ŕ����Ɛ_�������ǂ��������ė����B
�u�_������v��_���K���́u�o���̘_���v�ōl���邱�Ƃ��ł���B
�����u�o���̘_���v�ł́A�u�_�ł����蕧�ł������B�v
���邢�́u���ł�����_�ł������B�v�ƍl����B
��敧�����������{�ɂ͂��́u�o���̘_���v������B
�]���ē��{�ł͌����͐_�O�ł��āA�����͕����ł��邱�Ƃ͉���s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�ޗǂ̋������ł͎��̑m���B�����N�P���Q���ɏt����ЂɎQ�w����B
�m���B�͏t����Ћ{�i��_���̕��X�ƈꏏ�ɎQ�w���Г��ɂ����ĕ����o�T��njo����̂ł���B
�i�����i�����@�j�̖�O���i�Q���̒��j�ɂ͔��R�_�Ђ�����B
���N�t�O���̔ފ݉���ɂ́A���̔N�ɏ�R�����i�����̉_�������R�_�Ёi����j�ɎQ�w����B
�����Ė𗾘V�t�̓��t�̂��Ɛ_�O�njo������B
���̂悤�Ȑ_�O�njo�͉��Ă̐l�ɂ͊�قŗ����ł��Ȃ����Ƃ����m��Ȃ��B
�L���X�g����ŃR�[������ǂނ悤�Ȃ��Ƃł��邩��ł���B
�������A���{�ł͐_�O�njo�͉���s�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
���{�Œ����������_���K���̓`���͂P�W�U�W�N�i�������N�j�������{�̐_�������߂ɂ���ċ֎~���ꂽ�B
�p���ʎ߂Ȃ����_�������߂͈��̕����j��ł���A
�Ǝ��̓`���Ƒ����̕��������������͎̂c�O�Ȃ��Ƃł���B
�������͌��݂ł�����������Ȗ��ł���B
�C�X���G���́u�p���X�`�i�͉�X�C�X���G���̂��̂ł����v�Ǝ咣����B
�p���X�`�i�l�́u�p���X�`�i�͉�X�p���X�`�i�l�̂��̂ł����v�Ǝ咣����B
�����Ă��ꂼ�ꂪ���̍����̐��������咣����B
�������A�����̂Ԃ��荇���Ƙ_���ł͉�������Ȃ��Ƃ���ɔߌ�������B
����ɑo���̘_����K�p����Ƃǂ����낤���H
�o���̘_���ł́u�p���X�`�i�̓C�X���G���̂��̂ł���Ɠ����Ƀp���X�`�i�̂��̂ł����B�v�ƂȂ�B
����͐��m�̓_���ł͗�������Ȃ��_���ł���B
�������A���̘_��������邱�Ƃ��ł���p���X�`�i���͉������邾�낤�B
�u�p���X�`�i�̓C�X���G���̂��̂ł���Ɠ����Ƀp���X�`�i�̂��̂ł����B�v
���̘_��������A���ǂ����������A�������p����Ηǂ��B
���̂悤�ɗ�������Αo���̘_���́u�����E�����v�̘_���ƂȂ邾�낤�B
���_���l�����Q�̖��Ƃ��Đ��E�����܂���Ă�����
�p���X�`�i�l���Z�ݒ����ė���Ԃ��Ă���Ă����ƍl����A
�p���X�`�i�n�����ꏏ�ɋ����J�������ǂ����������A�������p����������Ηǂ�
�Ǝv���̂͑o���̘_���Ɋ��ꂽ�y�ϓI�ȓ��{�l������ł��낤���B
�~�h�����V
�ŋߘb��ɂȂ��Ă���~�h�����V���o��(�����₭)�̘_���Ő����ł��邾�낤�B
�~�h�����V�͉h�{�L�x�Ȃ��߁A�H�ƂƂȂ�B
�܂��W�F�b�b�g�G���W���̔R����,�q��R���Ƃ��Ȃ�̂Œ��ڂ���Ă���B
�~�h�����V�͖{�������ł��邪�A�̓��ɗt�Α̂������������s���A���ł�����B
�����A�����ł���ƂƂ��ɐA���ł�����B
����͑o���̘_���Ő����ł��邾�낤�B
��
������̗�͌��ł���B
���̓}�b�N�X�E�F���d���C���_�ł͓d���g�ł��邩��A�g�̐����������Ă���B
�������A�Q�O���I�����ɐ��������ʎq�͊w�ł́A���͗��q�̐����������q�ł���B
�������͔g�ł���ƂƂ��ɗ��q�Ƃ��Ă̐����������Ă���B
������o���̘_���Ő����ł��邾�낤�B
���̗�ł�������悤�ɁA�o���̘_���͗ʎq�͊w�̘_���Ƃ�������B
�ʎq�͊w�̘_���͗ʎq�R���s���[�^�̊�b�Ƃ�������_���ƂȂ��Ă���B
���̂��Ƃ��l����ƁA�T�̘_���Ƃ��ėp������l��_����
�ӊO�ɍŐV�Ȋw�̘_���Ƃ�������s�v�c�Ș_���ƌ����邾�낤�B
�P.���C�̓K���F
�u�M�����Ȃ��A�������Ȃ��v�Ƃ����\��������B�������M�����̓_���ł͓K����\�����邱�Ƃ͓���B
�߂����Ղ��K�x�ȉ��x��\�����鎞�ɂ͑o��̘_�����g����B
�Q.�����s�F
�_��������s���i�u�������s�������v�j�Ƃ������t������B
���ʂ̓_���ł͉ł��邩�s�ł��邩�ł���B
�����s���i�u�������s�������v�j�͂��̂ǂ���ł��Ȃ��ƌ����킯������o��̘_���Ƃ�����B
���̌��t�͓��ɗD��Ă���킯�ł��Ȃ������ɂЂǂ��킯�ł��Ȃ��A
�u�܂��܂��ł����v�Ƃ����ꍇ�ɂ悭�g����B
����͗ǂ�����͂��߂Ƃ͂����茈�߂��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���B
�R.�e�a�̔�m�F
�e�a�i������A1173�|1262)�͏�y�^�@�̊J�c�Ƃ��Ēm����B
�͉��i�͂�˂�j�E�^��(���������)�E�P�M�Ƃ��̂��A��Â𐩂Ƃ���B
�@�R��l�̒�q��1�l�ł���B
���i2(1207)�N�A�������Ȃǂ̍��i�ɂ���āA�@�R��l�ȉ��̗��߂ɍۂ��A
�e�a���z�㍑�ɗ��߂ƂȂ��ė����ꂽ�B
���̊ԂɁu��m�v�̋�Ðe�a�Ə̂��A
�Ȃ̌b�M��(1183�|1268)�Ɛ��������ɂ��Ă���B
���̑m���ł��Ȃ��A���l�ł��Ȃ��i�m�ɔ��ɔj�Ƃ��������u��m���v�ł���B
�O���͓Ó��őm���̎p�����Ă��Ă����ʂ͋����ȑ��l�ł��邱�Ƃ�����
�u�Áv�̂����Ɂu���v�����āA��ÂƖ�������ƍl������B
�e�a�͉z�㗬�߂��_�@�Ƃ��āA��m���̗����\�������ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�]���̕����͍��ƕ����̐��x�̉��ɂ���A�m���ɂȂ�ɂ͍��Ƃ̏��F���K�v�ł������B
�����̑m���́A���͂ɂ���ĕی삳������ɒ����M���̂��߂ɋF��������A
�ʂ�^����ꂽ�肵�č��Ƃ̒�߂������ɑg�ݍ��܂�Ă����B
���������Ĕ�m�Ƃ́A���̂悤�ȑm���ł��Ȃ��A����Ƃđ��l�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł����āA
�m���̂킭�g�݂𗣂ꂽ�V��������������Ă���B
���̂��Ƃ͕����k�Ƃ��Ă܂��������R�ȗ���ɂ��������Ƃ��Ӗ����A�e�a�͂��ꂱ���O���҂̎p�ł���Ǝ������ƍl������B
����ƂƂ�����m���́A�O���̋������o�ƒ��S�̕����ł��Ȃ��A
�܂������̌��͂̂��߂̕����ł��Ȃ��A���ׂĂ̐l�ɂЂƂ����J���ꂽ�����ł���A
�Ƃ����e�a�̐��_��\�킵�Ă���B
��m���̐��E�͎��̐}�ɂ���Đ����ł��邾�낤�B
�@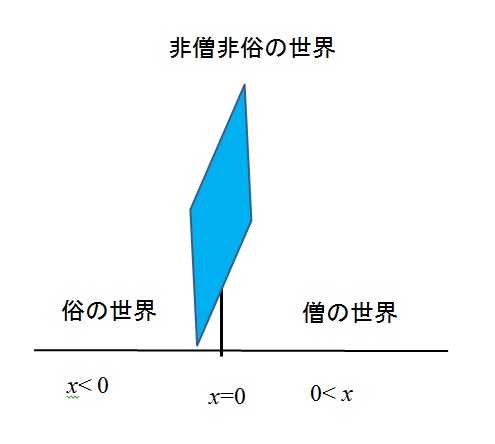
�} ��m�̐����}
�@�}�ɂ����āA����0��m�̐��E�A����0�̐��E�ƍl����B
��m�̐��E�͂���0�@�ł��Ȃ����A����0�ł��Ȃ��B�]���āA�����O�ɂȂ邵���Ȃ��B
������ł����O�͕��������Ȃ��B
�]���ē_�̐��E�ł��邘���ɐ����ȕʂ̐��E���l���邵���Ȃ��B
���̐��E�́@�����ɐ����ȐF�̐��E�ŕ\�����Ƃ��ł���Ǝv����B
�@���ʂ̘_���ł́A�m�łȂ���Α��ł���B�m�ł���Α��ł͂Ȃ��B
�����̘_���ł͔�m�̐��E�͒��r���[��
�����܂��Ș_���Ɋ�Â��Ă���ƍl�����邾�낤�B
��m�͎l��_���ł́u�o��̘_���v�ɊY������l�����ɂȂ邾�낤�B
�S. ���{�̞B���ȍٔ��F
���{�̍ٔ��́u�o���̌������A�܂��Ƃɂ����Ƃ��ł���v�ƌ�����
�B���ȍٔ����ǂ��ٔ����ƍl�����Ă���B
�u�O���ꗼ���v��u���ܗ����s�v�I�ȍق����������̂�����s�Ƃ����B
���Ă̍ٔ��ł́A���������邩�̂ǂ��炩�ŞB�������Ȃ��B
���{�̍ٔ����͍������͂����茈���悤�Ƃ��Ȃ��B
���فA�ɂݕ����A���������Ȃǂ̌��_�����{�l�̍D�݂ł���B
���̂悤�����{�l�̞B�����͎l��_���ƊW������̂����m��Ȃ��B
���̌��Ă���������ɂȂ��Ă���_�Ń��j�[�N�ł���B
�R�͖��̒��Ŗ��ӕ�F�̑O�Ő��@����B
�R�͑吨�̕�F�̑O�Łu��敧���̋��ɂ͈�̘_���ƕ\�����Ă����v
�Ɛ��@����B
����́u�T�͂�����_���Ǝv�z�����w�s�������̐��E�ł����x�ƌ����Ă���B
�T�̐��E�ł���]�F���͕��w�m���팾��n��_���ł͐����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�T�̐��E�ł���]�F�����Ȋw�I����Ƙ_���Ő������邵���Ȃ��̂œ��R�ł��낤�B
�{���̃e�[�}�ł���T�Ɩ��ɂ��čl���悤�B
���͕��ʐ������Ɍ���B�����͑̂�]�̔�J���������邽�߂ɕK�v�s���ł���B
���͐����ł��郌�������iRapid Eye Movement Sleep,�ዅ�������Ă��鐇���j���ɗǂ�����悤�ł���B
���ڂ낰�ł͂��Ȃ��l�q���u���A���̔@���v�ƌ����B
���́A���킢���Ȃ��͂����肵�Ȃ��B
���̒��ł͂͂�����Ɛ[���������l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�������A���͑T�̌��Ƌ��ʂ�����̂�����B
����͋��ɔ]�����ۂł���_�ł���B
�����ɂ��̌��Ă𗝉����錮������Ǝv����B
�ȏ�̉���ŁA�u���̕��@�͎l��A�S��Ȃǂ�����_�����Ă��܂��v
�Ƃ����R�̌��t�̈Ӗ��͕��������Ǝv���B
����ł͂��̑�25���̌��Ăł͉������������̂��낤���H
�M�҂́u�T�̍��{�����v�̑���ł��遃��p�������̓T�^�Ⴞ�ƍl���Ă���
�i�u�T�̍��{�����Ɖ��p�v�̑�����Q���j�B
�R�̐��@�͓���ɂ����@�ƌ��t�ɂ����@�̓�̐��@���琬��ƍl���邱�Ƃ��ł���B
1.���t�ɂ����@�F
�R�̌��t�ɂ����@�Ƃ́w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��x�ƌ������t�ɂ����@�ł���B
�Q.����ɂ����@
�R�̓���ɂ����@�Ƃ́w��l�̍��m���o�Ă��āA�Ƃ�ł��炵�ċR���ĂԂ�
�R�͋N(��)���オ���ĉ��d�ɍs���A�Ƃ�łA�x�ƌ�������ɂ���Đ��@���������Ƃł���B
�ʏ�̐��@�͌��t�ɂ����@�Ȃ̂Ŗ��Ȃ�������ɂ���Đ��@�Ƃ͉����Ӗ�����̂������������m��Ȃ��B
�ȉ��Ő�������悤�ɓ���ɂ����@���T�̐��E�ł͗��h�Ȑ��@�ƂȂ�̂ł���B
�R�̌��t�ɂ����@���u���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��v�ƍl���邱�Ƃɂ͂Ȃɂ����Ȃ����낤�B
���̎��A�{���ň�ԏd�v�ȕ����͋R�̓���ɂ����@�ƌ��t�ɂ����@�̗������܂�
�R�͋N���オ���ĉ��d�ɍs���A�Ƃ�ł��ĉ]�����A�w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����x
�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�R�̐��@��
���d�ɍs���A���@�Ƃ�łA���w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����x
�Ɖ]������ɂ����@�ƌ��t�ɂ����@���琬�藧���Ă���B
�����A���d�ɍs���A�@�Ƃ�łƂ����u����ɂ����@�v
��
���t�ɂ����@�w���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����x
�Ɖ]��2�̐��@���琬��ƍl���邱�Ƃ��ł���B
����ɂ���āA�����̖{�̂Ƃ��Ă̕����i���]�j���n�^���L�i��p�j���F�Ɏ������̂ł���B
�]�i�����j�̓����i�s���A�łA�b���̂R�s�ׁj�ŋR�̐��@�͗��h�Ɋ������Ă���
�ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
���炽�߂āA����p�������̌��������̐}�P�O�Ŏ����B
�@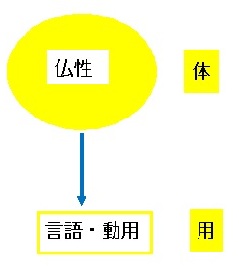
�}�P�O�D����p�������̌����}
�@�����A�R�͉��d�ɍs���A�Ƃ�ł��āA
�u���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��B�悭�����Ȃ����v
�Ɖ]�����ƂŁA����p�������̌����𗧔h�Ɏ������Ɖ��߂ł���B
�����Œ��ӂ��ׂ��́u���̕��@�͂�����_�����Ă��܂��v
�Ƃ����R�̌��t�ł���B
��̐}�P�O�ɂ����āA���������T�C�s�ɂ���Č��N�ɂȂ����]���ƍl����A
����p�������̌����͌���̔]�Ȋw�ɂ���Ė����ɐ����ł���B
�]���ċR���������u������_���v�Ƃ�
�Ȋw���������w����팾��̘_���ł����ƌ�����B
�����̓���͂܂��Ñ�ł���A����̐i�]�Ȋw�͂Ȃ���������ł���B
�}�P�P�ɐ}�P�O���X�ɕ�����Ղ��`�����������̂������B
�@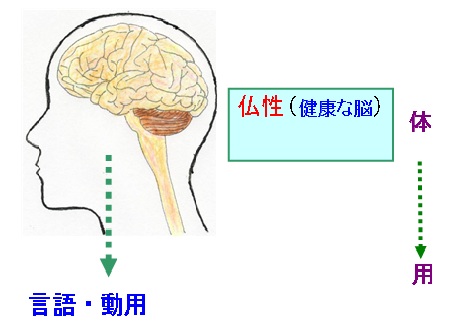
�}�P�P�D����p�������̐����}
�@�R�́u���@�̋��ɂ̂Ƃ���͕��w����팾��̂�����_�����Ă��܂��v
�ƌ����Ă���B
�R�������������̓���͖����Ñ�ł���B
����̂悤�Ȑi�]�Ȋw�͖��������̂ł������������Ȃ������̂ł���B
����́u�]���v�ɉ����āu�����J���ΊԈႢ�ɂȂ邵�A�ق��Ă���ΐ��@�ɂȂ�Ȃ��B
������Ƃ����Č����J���������Ƃ������Ƃł��A���@�������Ȃ���������Ă��܂��v
�ƌ����Ă���B
�����ŕ�����ɂ����̂́u�����J���������Ƃ������Ƃł��A���@�������Ȃ���������Ă��܂��v
�Ƃ������Łu�����J���������v�Ƃ������ł���B
���͊J�������邩�̂P�Łu�����J���������v�Ƃ������Ƃ͕s�\�ł���B
����͂��̂悤�ɕs�\�Ȃ��Ƃ������ĉ�X�����炩���Ă���̂ł���B
��g����ւ��D�P�O�X�`�P�P�P
�{���F
����(���傤��傤)��@��A��(����)�݂ɑm�A�֑O(��������)�ɏ�Q���B��A����Ȃ��ė����w���B
���ɓ�m�L��A�����������ė��������B��H���A�u�꓾�A�ꎸ�v�B
�]���F
��(����)����(��)���A����N�����A�N�����A�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����Ĉ�NJ�(������������)��(��)�����A
�ւ�����(���傤��傤)���t�s�(�͂�����)�̏���m���B
�����̔@���Ȃ��嫑R(�@���@���@��)���A�Ɋ��ޓ�����(�Ƃ�����)�Ɍ����ď��ʂ��邱�Ƃ��B
��F
���N(����)����Ζ����Ƃ��đ��(��������)�ɓO���A���P��������@�ɍ�(����)�킸�B
��(����)�ł���(��)�������s(����)�ĕ���(�ق���)���āA�ȖȖ����A����ʂ������ɂ́B
���F
����(���傤��傤)��@��F�@�ᕶ�v�i�W�W�T�`�X�T�W�j�B����(���傤��傤)���v�Ƃ���m���哱�t�Ƃ������B
����̑T�ҁB�@��@�̎n�c�B�����j�`��(��������)�i�炩������A�W�U�V�`�X�Q�W�j�̖@�k�B
�@�n�F���R��Ӂ�����`���������t���������j�`�����@�ᕶ�v�@
�֑O�i��������j�F�ւ͒��H�̂��ƁB���H�O�B
��NJ�i������������j�F����Ƃ͕ʂ̐S��B��O�̊�B
�s荁i�͂����j�̏��F���s�������B�����Ƃ������B
���ʂ���F���k����B���c����B���k�ɂ����āA��������Ă��݂�����������悤�ɂ���B
�{���F
��������H�̑O�ɁA����(���傤��傤)�@�̑�@��a���̏��ɓ�l�̑m������ɗ����B
�a���͖ق��ė����w�������B
��m�͑����ė��̏��ɍs���ė��������グ���B
����ƁA�a���͌������A�u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�B
�]���F
�����A�N���悭�āA�N�͑ʖڂȂ̂��낤���B�������̏������������������Ă���A
����(���傤��傤)���t���ʖڂ��������������邾�낤�B
�������A�����ł����Ă��A�ǂ��炪�悭�āA�ǂ���͑ʖڂ��Ȃǂƍl�����肵����ʖڂ����B
��F
���������グ��Ζ��邢�������B����͑T�̌��̋��n�Ɏ��Ă���Ƃ��낪���邪�A
���̋��n�͂�����Ă���B
����Ȍ��̋��n�����������̂Ăāi���z���āj�A
����ʂ��Ȃ��قǐ^�̎��Ȃɖ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
������̒��H�O�ɓ�l�̑m���@��T�t�̂Ƃ���Ɏ���ɗ����B
���x���̎��A�����̗������ꂽ�܂܂Ŏ����͈Â������ƌ�����B
���̎��A�@��T�t�͖ق��ė����w�������B �@
��l�̑m�̓n�n�A����͗��������グ�Ȃ����ƌ������Ƃ��ȂƎ@�m���A���̏��ɍs���Ċ����グ���B
�l�Ԃ͋@�]�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
��������Ɩ@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�ƌ������B
���̌��Ă̓��e�͂��������ꂾ���ł���B
���̌��Ă͑T�C�s�̐S��������������グ��Ƃ������s�ׂ�ʂ��Ď����Ă���Ƃ���Ă���B
���_�͖@��T�t�͖ق��ė����w�������̂����āA��l�̑m�͗��̏��ɍs���Ċ����グ���B
�@��T�t���ق��ė����w���������A�n�n�A����͗��������グ�Ȃ����ƌ������Ƃ��ȂƎ@�m���A
���������グ���B
���̂悤�ɁA�l�Ԃ͋@�]�������@�q�ɍs�����Ȃ��Ƃ��߂��Ƌ����Ă���B
���_�͖@��T�t�͓�l�̑m�͗��̏��ɍs���Ċ����グ�����A
�@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�ƌ������Ƃ���ł���B
�@��T�t�́u�`�͂���ł悢���A�a�͑ʖڂ��v�Ɠ�l�̑m�̖��O�������Ă͂��Ȃ�
�Ƃ���ɒ��ڂ��ׂ��ł���B
�m�̖��O������Ȃ���A��l�̑m�͎����͖J�߂�ꂽ�̂�����ꂽ�̂�������Ȃ��B
���M�̂Ȃ��҂͂܂������A���M�̂���҂͂܂����Ȃ��B
�����̂������ƂɊm�M�����҂͖J�߂��Ă������Ă��בR����Ƃ��ĉ��Ƃ��v��Ȃ����낤�B
�@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v�Ɩ��O������Ȃ����ƂŁA
��m�̐S���䂳�Ԃ��Ă���Ƃ��낪����B
��O�_�͖@��T�t�́u��l�͂���ł悢���A��l�͑ʖڂ��v
�Ƃ������t�ŗǂ������i�ʖڂ��j�������Ă���悤�Ɍ�����B
�������A�P������E����ʂ�����ɍS�邱�Ƃ�,�T�́u�����ʒq�v���猩��Ηǂ��Ȃ��B
�P������E����ʂ�����ɍS�邱�Ƃ̓X�g���X�ƔϔY�ނ���ł���B
�u�����ʒq�v�͂��̂悤�ȕ��ʒq����Ƃ���ɂ���B
����͕]���Łu�Ɋ��ޓ������Ɍ����ď��ʂ��邱�Ƃ��v�ƌ����Ă���B
����͑��E�v�A����E���������u�����ʒq�i���w�]���S�̖{���̎��ȁj�v
�ɖڊo�߂�悤�ɑ����Ă���̂ł���B
��ɂ����āu����s(����)�ĕ���(�ق���)���āA�ȖȖ����A����ʂ������ɂ́v
������������ɂ����B
����͗����グ��Α������B
�Q�T�C�s�ɂ���Ă��̑��ɂ��������̋��n�邱�Ƃ��ł���B
�������A����Ȍ��̋��n�����������Ă��܂��ׂ����B
����ɐi��Ŗ��E��̕����ʂ錄�Ԃ��Ȃ��قǂ҂�����Ɩ�������悤�ɁA
�^�̎����i���w�]���S�̖{���̎��ȁj�ɖ������āA�^�̎��Ȃɖڊo�߂邱�Ƃ��厖���ƌ����Ă���̂ł���B
���_�A�^�̎��ȁi���w�]���S�̖{���̎��ȁj�ɖ�������
�^�̎��Ȃɖڊo�߂�ɂ́A���T���ō��̎�i�ł������Ƃ͌����܂ł��Ȃ����낤�B
��g����ւ��D�P�P�Q�`�P�P�S
�{���F
���a���A���݂ɑm�₤�ĉ]���A�u��(����)���Đl�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�L����H�v�B
��]���A�u�L���v�B
�m�]���A�u�@���Ȃ邩����l�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�H�v�B
��]���A�u�s���S(�ӂ�����)�A�s����(�ӂ��Ԃ�)�A�s����(�ӂ�����)�A�v�B
�]���F
���A���̈����(������)���āA���ɓ�����Ǝ�(����)�𝅐s(������)���A�Y��(�낤�Ƃ�)���Ȃ��炴�邱�Ƃ��B
��F
���J�͌N����(����)���A�����^(�܂���)�Ɍ��L��B
�C�](����)����C�͕ς�����A�I(��)�ɌN���ׂɒʂ����B
���F
���a���F���i�Ȃ�ӂ���A�V�S�W�`�W�R�S�j�B����̑T�ҁB�n�c����i�V�O�X�`�V�W�W�j�̖@�k�B
�S����C�A�����q���ƂƂ��ɔn�c�剺�̎O��t�̈�l�B
�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��
�l�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�L���H�F�N�������Ȃ������@������܂����H
�s���S(�ӂ�����)�A�s����(�ӂ��Ԃ�)�A�s����(�ӂ�����)�F
�@���̌��t�́u�،��o�v�ɏo��u�w�S�A���A�O���x�̎O�ɍ��ʂȂ��v�ƌ����L���ȕ���ƊW���Ă���ƍl�����Ă���B
�u�s�����v�̕��͂��̂Ȃ��̏O���i������O���j���w���Ă���ƍl�����Ă���B
��X�̖{���Ƃ��Ắu�{���̖ʖځi���w�]���S�̔]�j�v�͐S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A���̂ł��Ȃ��A
���Ƃ������悤�̂Ȃ����̂��ƌ����Ă���ƍl������B
���̐��������̎���ɂ́A�S�̖{���Ɠ����͔]�ɂ��邱�Ƃ��������Ă��Ȃ������B
���̂��߁A���̂悤�ȕ\���ɂȂ����ƍl������B
�Ǝ��i�����j�F�Ƃ̍��Y�B
���s�i������j�F���Ă����ѐs�������ƁB�ʁi�͂��j��s�������ƁB
�Y���i�낤�Ƃ��j�F��ꂭ���т��l�q�B
��C�͕ς���F�u��C�ς��ČK�c�Ɛ���v�̗��B
��C���ς��ČK�c�Ɛ���A���̒��̕ω����������Ƃ����Ӗ��B
�{���F
�@���a���ɂ���m���q�˂��A�u�����N�������Ȃ������@���L��܂����H�v�B
���͉]�����A�u�L���v�B
�m�͉]�����A�u�����N�������Ȃ������@�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v�B
���͉]�����A�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A�O���ł��Ȃ����̂��v�B
�]���F
���́A����Ȉ��𗁂т����āA�Ƃ̍��Y��S�ĕ���o���āA�ւƂւƂɔ��Ă��܂����킢�B
��F
���͂��܂蒚�J�ɐ����������ߎ����̓��܂ő��Ȃ����B�ނ���ق��Ă��������ǂ������B
���Ƃ���C�����n�ɕω����Ă��A���̖���Ȃ�ΌN�B�ɂ͐����Ă��Ȃ���B
�{���͑m�Ɠ��̖ⓚ�ł���B
�m���u�����N�������Ȃ������@���L��܂����H�v�Ǝ��₵���̂ɑ�
�A���́A�u�����������ɁA�������Ă���̂́A�S�ł��Ȃ��A���ł��O���ł��Ȃ��B
�Ƃ����āA�S�ƕʂ̂��̂ł��Ȃ����A����O���ƕʂł��Ȃ��B����͈�̉����낤���H�v�ƌ����Ă���B
����̂悤�Ɍ����Ė₢�����Ă���̂�
�T�̒��S�e�[�}�ł���u�^�̎����v�ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�u�^�̎����v�͌��t�ŕ\���ł��Ȃ��Ƃ��āA
�u�^�̎����i�����Ȗ{���̖ʖځj�v����邱�Ƃ���X�ɑ����Ă���̂ł���B�@
���́u�s���S�A�s�����A�s�����v�Ƃ������t�͓�ԉ����́u�����ꕨ���s���v�Ɏ����Ƃ��낪����
�i�u�����ꕨ���s���v���Q���j�B
����Ɠ������Ă͕Ɋޘ^�Q�W���u���s���v�ɂ���B
�Ɋޘ^�Q�W���ł͓��ƕS�䟸�Ϙa���̖ⓚ�ɂȂ��Ă���B
�i�u�Ɋޘ^�Q�W���v���Q���j�B
�S�䟸�Ϙa�������ɁA�u��(����)���Đl�̗^(��)�߂ɐ��������̖@�L����H�v�Ɛq�˂��̂ɑ��A
���́u�s���S�A�s�����A�s�����A�^(����)�b(����)�͂�������(�����)�v�Ɠ����Ă���B
���́u�����������ɁA�������Ă���̂́A�S�ł��Ȃ��A���ł��O���ł��Ȃ��B
�������̗l�ɍ݂邪�܂܂Ɂi�@���Ɂj���邾�����v�ƌ����Ă���̂��B
����͕]���ɉ����ā@
�u���́A����Ȉ��𗁂т����āA�Ƃ̍��Y��S�ĕ���o���āA�ւƂւƂɔ��Ă��܂����킢�v
�ƌ����Ă���B
��������Ȉӗg(����悤)�̕\���i���t���Ȃ��ĐS�ŖJ�߂�\���@�j�ł���B
��X�����̂悤�Ȗ��ɐ^���Ɏ��g��ō��܂Œ��߂��m��ϑz�Ȃǂ̑S�Ă��������
�{�����ꕨ�́u�^�̎����v�ɖڊo�߂�悤�����Ă���̂��B
��ł́u���͂��܂蒚�J�ɐ����߂������ߓ�g�̓��Ȃ����B
�u�ނ���ق��Ă��������ǂ������i�������Ƃ��ł��Ȃ�����j�B
���Ƃ���C�����n�ɕω�����悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��A���̖���Ȃ�ΌN�B�ɂ͐����Ă��Ȃ����v
�Ɣ���I�ɉr���Ă���B
�����
�{���̖ʖڂ͐����������Ƃ͂ł��Ȃ����A���̂悤�ɉB�����ƂȂ��ԗ��X�ɘI�o���Ă��邶��Ȃ����B�����C�t���Ȃ��̂�
�Ɖ�X�Ɏ��o�𑣂��Ă���̂ł���B
��g����ւ��D�P�P�T�`�P�Q�P
�{���F
���K�A���݂ɓ��R���v(����)���Ė�ɒ�(����)��B
�K�]���A�u��[(��)���ʁB�q�A�������苎�炴���v�B
�R�A���ɒ��d���ė����f���ďo���B
�O�ʂ̍��������ċp��(���傤��)���ĉ]���A�u�O�ʍ����v�B
�K�T(���Ȃ�)�����C(�����傭)��_���ēx(��)�^(��)���B
�R�A�ڂ���Ƌ[���B�K��(���Ȃ�)������(�����߂�)���B
�R�A���ɉ����č��R(���˂�)�Ƃ��ďȗL��B
��(���Ȃ�)�����(���炢)���B
�K�]���A�u�q�A�ӂ̐r��(�Ȃ�)�̓������������v�B
�R�]���A�u�^�b(���ꂪ��)�A������苎���ēV���̘V�a���̐㓪���^�킸�v�B
�����Ɏ����āA���K�A螓�(����ǂ�)���ĉ]���A
�u��(����)�ӂ̊��L��A��(��)�͌����̔@���A���͌��~(���ڂ�)�Ɏ����A
��_�ɑłĂǂ�������炳����A�����ٓ��A�Ǖ�(���ق�)����Ɍ����ČN�����𗧂���݂���v�B
�R�A���ɑa��(�����傤)������āA�@��(�͂��Ƃ�)�̑O�ɉ����āA
���x(��)��(��)����(����)�Ē�N���ĉ]���A
�u��(�������)�̌���(����ׂ�)�����ނ���A
��|(����)��(��������)�ɒv(��)������(����)���A
���̐��@���(��)������H������(������)�ɓ�����Ɏ������v�B
�a��(�����傤)����(����)�ĕ�(���Ȃ�)���Ă��B���ɉ����ė玫(�ꂢ��)���B
�]���F
���R�����ւ��o�ł��鎞�A�S����(�ӂ�Ղ�)�A���q�q(�Ђ�)����B
�����Ƃ��ē���ɗ������ċ��O�ʓ`�̎|��ŋp����Ɨv���B
?(�ꂢ)�B�̘H��ɓ���ɋy��Ŕk�q(��)�ɖ₤�ē_�S(�Ă�)���Ƃ��B
�k�]���A�u�哿�̎Ԏq�̓��͐���r���̕������H�v
�R�]���A�u�����o�̑a��(�����傤)�v�B�@
�k�]���A�u�����o���ɓ������@����A�ߋ��S�s���A���ݐS�s���A�����S�s�����B
�哿�A�߉ӂ̐S�����_����Ɨv���H�v�B
���R�A�҂̈������Ē��ɓ�������w����(�ւ�)�Ɏ����邱�Ƃ��B
���̔@���Ȃ���(����)�R(��)���A�����m�Ĕk�q(��)�̋剺�Ɍ����Ď��p�����B
���ɔk�q(��)�ɖ₤�A�u�ߏ��ɐr��(�Ȃ�)�̏@�t���L���H�v
�k�]���A�u�ܗ��̊O�ɗ��K�a���L���v�B
���K�ɓ���ɋy��Ŕs�(�͂�����)��[(��)��s�����B
���ׂ�����O�����ɉ������ƁB
���K�傢�Ɏ�������ŏX�����Ƃ��o������Ɏ�����B
���̍��q(���Ⴕ)�̉Ύ�L������ĘY�Z(�낤�ڂ�)���Ĉ���(������)����(��)����
�}��(�܂��Ƃ�)�Ɉ��C(���傤)���C�E(���傤����)���B
��n�Ɋŗ���A���̍D�Ȃ�B
��F
��������͖ʂ�����ɔ@�����A�ʂ�������͖�����ɔ@�����B
�@�E(��)���~����������(����)�R(��)���A����(������)����A
��[�C���Ћp(�������Ⴍ)���邱�Ƃ��B
���F
���K�i��イ����j�F���K���M�i��イ��������A���v�N�s�ځj�B
����̑T�ҁB���s�v�̖@�n���A�V�c����i�V�S�W�`�W�O�V�j�̖@�k�B
�@�n�F�Z�c�d�\�����s�v���Γ���J���V�c���偨���K���M�����R���
���v�i�����j�F�L�v�ȋ����𐿂����ƁB
�����F���⓹���̈Ӗ��ł͂Ȃ��A��̓I�Ȗ���o����������
螓��i����ǂ��j�F�㓰�B
���d�i���傤�j�F���ނ��鎞�̈��A�̌��t�B���悤�Ȃ�A���厖�ɁB
���فi����ׂ�j�F�����̖{���ɂ��ċc�_�������́B
���̐��@�F�n���p�B
�S�����i�ӂ�Ղ�j�A���q�q�i�ЂЁj����F�S�����S���Č��t�ɂȂ�Ȃ����܁B
���q�q�i�����ЂЁj�F�S�̒��ɗ��܂������̂�f���o�����Ƃ��ďo���Ȃ����܁B
���فi���傪���j�F�傫�ȒJ�B
�_�S�i�Ă�j�F�H���ȊO�ɐۂ�y���H�ו��B�X�i�b�N�A�َq�B
���w�����i�ւ�j�Ɏ�����F�w����(�ւ�)�͓V���_�̂��ƁB
�����������Ȃ��Č���^�ꕶ���ɕ��Ă���̂Ɏ��Ă���B
���ׂ�����O�����ɉ������F�̋��őT��ŋp���Ă���
�匾�s�ꂵ���ɂ�������炸���K�a���Ƃ̖@��Ɍ����ɔs�ꂽ�B
�̋��ł̑匾�s��Ɨ��K�a���̂Ƃ���̌������ׂ��
�O�オ�҂������v���Ă��Ȃ��ƌ��������Ȃ��B
���q�i���Ⴕ�j�́F�����́B
�Y�Z�i�낤�ڂ��j���āF����Ăӂ��߂��āB
�@�E�i�т����j�F�{���̖ʖځB
��[�C�F���ݐ������B
�{���F
���K�a���̂Ƃ���ɁA���鎞���R����������ɂ���ė����B
�c�_�͔��M���A���̂�����ɂȂ����B���K�́A
�u��������ԍX���Ă������炻�낻��R�����肽�����悢�̂ł͂Ȃ��낤���v�ƌ������B
���R�́A�d���Ȃ��ʂ�������āA�����グ�ĊO�ɏo�悤�Ƃ����B
�Ƃ��낪�O���^���ÂȂ̂ň����Ԃ��ė��āu�����O�͐^���Âł��v�ƌ������B
���K�a���͒ɓ������ēn���Ă�����B
���R������낤�Ƃ������A���K�̓v�b�Ɠ��𐁂������Ă��܂����B
���R�́A���̎��A���R(���˂�)�Ƃ��Č��A���K�a���ɐ[�X�Ɠ����������B
���K�́u���O�����̂ǂ��������v�ƌ������B
���R�́A�u�������玄�͐��̘V�t�B�������邱�Ƃ��^���܂����v�ƌ������B
�����ɂȂ��āA���K�͐��@�̍��ɏ���āA
�u�����A���̒��Ɍ����̂����~�̂悤�Ȍ��ƌ����̂悤�Ȏ��������A
�_�őł���Ă��т��Ƃ����Ȃ��悤�Ȓj������Ȃ��A
���̒j�͂��̓����A�N��l���t���Ȃ����݂ɓƎ��̕��@��ł����Ă邾�낤�v�Ɖ]�����B
���R�͐��Ɂ@�A�@��(�͂��Ƃ�)�̑O�ɍs���Ď����ė��������o�̒��ߏ������グ�A
��{���x��(����)�����ƁA
�u�ǂ�Ȃɕ����̋��`����(����)�߂Ă��A��{�̔��̖т���ɓ������悤�Ȃ����A
�܂��ǂ�Ȃɓn���p�����߂Ă���̐��H��傫�ȒJ�ɓ�����悤�Ȃ��̂��v
�Ɖ]���Ă����̒��ߏ����ċp���Ă��܂����B
�����ė���q�ׂ�Ƃ������ƎR������čs�����B
�]���F
���R�͌̋��ɂ������́A�S�Ɏv�����Ƃ���t��������
��������t�Ɍ����\�����Ƃ��ł��Ȃ������B
�������A�䂱���́u���O�ʓ`�v�̕������ƌ����Đ����𑝂��Ă���T�@��
���Ƃ��Ƃ��_�j���Ėŋp���Ă�낤�Ɠ���ɂ���ė����B
���C�B�i�ꂢ���イ�j�܂ł���ė��ĕ������̂ŘH�[�̒��X�ɗ������
���X�̔k����ɓ_�S�i�y�H�j�𒍕������B
�Ƃ��낪���̔k����͂����҂ł͂Ȃ��B
�k����͓��R�ɁA�u���V�l�̎Ԃɐς�ł��鏑���͈�̉��̖{�ł����H�v�Ɛq�˂ė����B
���R�́A�u����͎��������������o�̒��ߏ��ł����v�ƌ������B�@
����Ɣk����́A
�u�����o�ɂ́A�ߋ��S�s���A���ݐS�s���A
�����S�s���Ə����Ă���͂��ł��B
���Ȃ��͍��_�S�𒍕�����܂������A��̂ǂ̐S�Œ������ꂽ�̂ł����H�v�ƕ����ė����B
���R�́A���̈��ɂ����Ƃ܂��Č����ꕶ���ɕ����܂܂ɂȂ����B
�����Ȕނ͂��̎���ɂ����ɓ����邱�Ƃ��ł��Ȃ���������ł���B
���ɓ��R�́A�k����ɁA�u���̋߂��ɑT�̏@���������܂����H�v�ƕ������B
�k����́A�u��������S�L�����藣�ꂽ���ɗ��K�a���������܂��v�Ɖ]�����B
�����ŗ��K�R�ɍs���A���K�a���ɉ���Ė@����킹����
����Ƃ����قǂ̔s�k���i���Ă��܂����B
����ł͌̋��ł̑匾�s��Ɨ��K�ł̌����������ς荇���Ă��Ȃ��ƌ��������Ȃ��B
���K�a���͂��̎ᑢ�i���R�j���C�ɓ����Ă��܂�������ɁA
���̂��e�����ɋC�t���Ȃ������悤���B
���R�ɏ�������˔\������ƌ��āA�Q�ĂēD���𗁂т������A
�܊p�̌��̉Ύ�������Ă��܂����킢�B
��Âɗ��K�̂���������ƑS�����̂���������B
��F
�����Ŗ��O�����ꌩ���������ǂ��B
���ۂɉ���Č�����i���R�́j���O�������ĉ��Ȃ��ł��������ǂ������B
���Ƃ��@���~�����Ƃ����Ă��A�̐S�̖ڋʂ��Ԃ�Ă��Ă͂��߂��B
�{���ł͏\�O���ŏo�Ă������R��ӑT�t���T�ɓ��債
���K���M�̉��Ō��������镨�ꂪ���ł���B
���R��ӂ͐�冂ɂ����ċ����ʎ�o�𗝘_�I�Ɍ������A�u�������v
�Ƃ����ٖ��������ČĂ��قǂ̗L���ȕ����w�҂ł������B
�ނ͋����o�̒��ߏ��������قǂŎ���������o�̌����ł͑��l�҂ł���ƍl���A
�l�ɂ��F�߂��Ă����B
���R�̎���͑T�������암�ŋ������g�債�Ă������A�u���O�ʓ`�v�A�u�s�������v�ȂǁA
�`���I�Ȍo�T�Ɋ�Â��`���I�����Ƃ͈قȂ鋳��������̂�
�����s�����Ă��Ȃ������̂ł���B
���R�͍ŋ߁u���O�ʓ`�v�A�u���S�����v�ȂǂƁA
���o�ɂ͐�����Ă��Ȃ����Ƃ������Đ����𑝂��Ă����T�@�ɑ��ẮA
�����������A����͐����������ł͂Ȃ��A�����ƍl���Ă����B
���̂悤�Ȏ������Ƃ��Ƃ��_�j���Ėŋp���Ă�낤�Ɠ���ɂ���ė����B
�Ƃ��낪�A���X�̔k����ɁA
�u�����o�ɂ́A�ߋ��S�s���A���ݐS�s���A
�����S�s���Ə����Ă���͂��ŁA���Ȃ��͍��_�S�𒍕�����܂������A
��̂ǂ̐S�Œ������ꂽ�̂ł����H�v
�Ǝ��₳��Ă��A�����Ƃ܂��ē����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
������@���ɗ��K�a���ɉ���Ė@����킹�����A���K�a���Ƃ̖@��ɂ��s�k���i���Ă��܂����B
���K�a���Ƃ̖@��ɖ����ɂȂ������ߋC�t���ƊO�͊��ɈÂ��Ȃ��Ă����B
�����œ��R�͒���ĎR������悤�Ƃ����B
���������R����낤�Ƃ������A���K�a���̓v�b�Ɠ��𐁂������Ă��܂����B
���̎��A���R�́A
�������Ă����u�{���̖ʖ��i���^�̎��ȁ��]�j�v�����R(���˂�)�Ƃ��Č�����B
�����ŗ��K�a���ɐ[�X�Ɠ����������B
���K�͓��R�̌�������������������B
�������K�a���͐��@�̍��ɏ�������A���R�̌��ɂ��āA
�u���̒j�͂��̓����A�N��l���t���Ȃ����݂ɓƎ��̕��@��ł����Ă邾�낤�v
�Ƒ傢�ɖJ�ߏグ�ďЉ���B
���R�͎����ė��������o�̒��ߏ���S�ďċp���ĎR������čs�����B
�ȏオ�{���Ŏ��グ�����R�̌�������ł���B
����͔n�c��Սς��u�����ڑO�ɗp�����͑c���ƕʂȂ炸�v�ƌ�����
��X�̌���E���p���{�̂ł���c���i�������j�̓����ł���Ƃ��遃��p�������̍l���ɂ���Đ����ł���i�}�P�O�C�P�P���Q�Ɓj�B
��X�̌��铭���i���o�j���{�̂ł���c���i�������j�̓����ł���ƍl���Ă��邱�Ƃ�������
�i�u�T�̍��{�����v�̑�����Q���j�B
���K�a���Ƀv�b�ƒ̓��������ꂽ���A
���R�͍��������Ă������̂��u�ԓI�Ɍ����Ȃ��Ȃ����B
���̎��ނ͌��铭���i���o�j�̖{�̂ł���c���i�������j�̓������n�b�Ǝ��o���A
���ꂪ�{�̂ł���c���i�������j���ƌ�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�]�Ȋw�I�Ɍ����Ό��铭���i���o�j�̖{�̂ł���c���i�������j�Ƃ͔]�̂��Ƃł���B
����ł͖����S�̍��͐S���ł���ƍl�����A���̂��Ƃɂ��Ă͂����肵�Ă��Ȃ��������E�E�E�B
�u��v�ɂ�����
�u�����Ŗ��O�����ꌩ���������ǂ��B����Č����薼�O���Ă��������ǂ������v�Ƃ�
��O�͓��R�́u�������v�ƌĂ�鍂���Ȑl�ł�����������Č���ƒP�Ȃ镧���v�z�̊w�҂ŁA
���̖ڂ������l�ł��邱�Ƃ��͂����肵���B
����ł͉��薼�O�������Ă��������ǂ������Ɣ�����Ă���B
�u���Ƃ��@���~�����Ƃ����Ă��A�̐S�̖ڋʂ��Ԃ�Ă��Ă͂��߂��v
�Ƃ͓��R�̌��͖������r���[�̓���i�K�ɉ߂��Ȃ��B
���ꂭ�炢�̌��͖����A�̐S�̖ڋʂ��Ԃ�Ă���悤�Ȃ��̂��Ɖr���Ă���B
���ꂭ�炢�̌����ɖ������Ă͑ʖڂŁA�X�Ɍ���[�߂čs���K�v�������Ɖ�X�C�s�҂ɒ��ӂ𑣂��Ă���̂ł���B
��g����ւ��D�P�Q�Q�`�P�Q�S
�{���F
�Z�c�A���݂ɕ�����(�����ς�)���A(��)���B��m�L��A�Θ_���B
��͉]���A�u�������v�B
��͉]���A�u�������v�B
�������đ](����)�Ė������Ɍ_(����)�킸�B
�c�]���A
�u���ꕗ�̓����ɂ��炸�A���ꔦ�̓����ɂ��炸�A�m��(�ɂ�)���S�����̂��v�B
��m���R(���傤����)����B
�]���F
���ꕗ�̓����ɂ��炸�A���ꔦ�̓����ɂ��炸�A����S�̓����ɂ��炸�B
�r(����)��̏��ɂ��c�t������B
�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����Č������Đe�Ȃ�A���ɓ�m�A�S���ċ����m��B
�c�t�E�r�s��(�ɂ��ӂ���)�ɂ��āA���̘R��(�낤�Ƃ�)�Ȃ�B
��F
�����S���A���ɗ̉�(��傤��)���B
�@���������J�����Ƃ�m���āA�b��(�킾)���邱�Ƃ��o�����B
���F
�Z�c�F�@��ӌd�\(�������̂�)�i�Z�c�d�\�A�U�R�W�`�V�P�R�j�B
�ܑc�O�E(���ɂ�)�i�U�O�Q�`�U�V�T�j�̖@���k���Œ����T��Z��̑c�t�ƂȂ�B
�C���h�ȗ��̓`���I�T���`��ے肵�A�ʎ�̒q�d����Ƃ���ڌ�T��n�������B
������@�T�̊m���n���҂Ƃ����B
�����̘b�F���̌��Ă̘b�͘Z�c�d�\���ܑc�O�E�̖@���k���œ���̌̋��ɋA��A
�ܔN�Ԑg���B���ďZ��Ō��̏C�s�o���ْ��{�p�����Ă���
�L�B�@�����ł̏o�������Ƃ���Ă���B�@�@
�m�ҁi�ɂ�j�F���l�̂̌h�́B
���R�i���傤����j�F���ꂠ��Ă�邳�܁B�u���ё쌘(���������������)�v�Ɠ����B
�E�r�s�ցi�ɂ��ӂ���j�F��m�炸�������炷���ƁB���R�ƏΊ�ɂȂ邱�ƁB
�R���i�낤�Ƃ��j�F�j�]�B�{�����o�����ƁB
���ɗ̉�(��傤��)���B�F�P�̖@���̗ߏ�œ��߂��Ƃ��ĊF���S������B
�b�i�킾�j���F�����̏q�ׂ����t���̂��j�]��I�悵�Ă���B
�{���F
���鎞�@����m�点�鎛�̔������Ƀp�^�p�^�h�ꓮ���Ă����B
��������ē�m���c�_���킹�Ă����B
��l�̑m�́u���������Ă���̂��v�Ɖ]���ƁA
�@������l�̑m�́u���╗�������Ă���̂��v
�Ɖ]���Ă��݂��̗��������Ȃ��̂Ō����������Ȃ������B
�����ɋ��R�Z�c���o���킵���B���̋c�_�����Z�c��
�u����͕��������Ă���̂ł��Ȃ��A�܂����������̂ł��Ȃ��A
���Ȃ����̐S�������Ă��邾�����v�Ɖ]�����B
���������m�̓]�b�Ƃ��Ē������������B
�]���F
���������̂ł��A���������ɂ̂ł��Ȃ��B�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��B
����ł͑c�t�������������͈�̉����ɂ���̂��낤���B
�Ⴕ�A��������������ƌ������Ȃ�A���̓�m���͂��ߓS�����Ƃ����̂ɁA
�v��������������ɓ��ꂽ���Ƃ������邾�낤�B
����ɂ��Ă��Z�c�͗D�����������߂ɂƂ{�����������ꖋ�ł������B
��F
�����S���������ǂ����ő呛�������āA�F���߂ōS�����ꂽ�B
�Z�c���v�킸�����J�������߁A
�����̌��t���{�����o���Ă���̂ɋC�t���Ȃ��Ƃ͏�Ȃ��B
�ܑc�O�E�̖@���k���Œ����T��Z��̑c�t�ƂȂ����d�\��
�k�@�̏؋��Ƃ��ĒB���̈ߔ��������ē���ɍs�����i���ꂽ�H�j�Ɠ`�����Ă���B
���̎��ܑc�O�E�̒�q���S�l���B���̈ߔ���D�����ߌd�\�̌��ǂ����Ƃ����B
��Q�R���u�s�v�P���v�̘b��
�僆��(������ꂢ)�Œǂ������d���i������j�ƌd�\�̖ⓚ���Ƃ���Ă���B
�i��Q�R���u�s�v�P���v���Q���j�B
���̌���d�\�͐��ɏo�邱�Ƃ͂Ȃ�
�P�T�N�ԗt�i���邢�͏��v�j�̊ԂʼnB�ِ����𑗂����Ɠ`�����Ă���B
���鎞�d�\����B���k�̖@�����Ɏ������B�{���͂��̎��̖ⓚ�ŁA
������_�@�Ɍd�\�͏o�����A���@���J�n�����Ɠ`������B
���̈Ӗ��Ŗ{���͓�@�T�̗����錾�ɓ�����L�O��I�ⓚ�Ƃ�������B
�������Ƀp�^�p�^�h�ꓮ���̂����ē�m�����@�Ɋւ���c�_���킹�Ă����B
��l�́u���������Ă���̂��v�Ɖ]���ƁA
�@ ������l�́u���╗�������Ă���̂��v�Ɖ]���Ă��݂��̗��������Ȃ��̂Ō����������Ȃ��B
���̋c�_�����Z�c��
�u����͕��������Ă���̂ł��Ȃ��A�܂����������̂ł��Ȃ��A
���Ȃ����̐S�������Ă��邾�����v�Ɖ]�����B
�d�\�͓�l�̑m���O�E�ɒ��ӂ������ċc�_�����Ă���̂����āA
�u���@�̖{���͊O���o�O�E�p�̕��┦�ɂ���̂ł͂Ȃ��A
���Ȃ̐S�ɒ��ӂ������Ă�����������邱�Ɓi���Ȏ������j�ɂ���̂��v
�ƌ������������̂��Ǝv����B
��Q�R���u�s�v�P���v�ł��Z�c�́A������ɁA
�u�P�����l���镪�ʈӎ��𗣂ꂽ���A������A���Ȃ��̖{���̖ʖڂ͈�̉����ɂ���̂��H�v
�Ɛq�˂Ă���B
�i��Q�R���u�s�v�P���v���Q���j�B
���̂��Ƃ��d�\�͕��@�̖{���i�T�̖{���j�͊O���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ȃ̐S���������邱��
�i���Ȏ������j�ɂ���ƍl���Ă��邱�Ƃ�������B
�u�Ɋޘ^�v��X���̕]���ɂ����āA���Қ��华�́u���悻�Q�T�⓹�͎��Ȃ����v
�ƌ����Ă���B
�����
���@�̖{���i�T�̖{���j�͊O���ɂ���̂ł͂Ȃ����Ȃ̐S���������邱�Ɓi�Ȏ������j�ɂ���
�ƍl���Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�Ƃ��낪�u�]���v�ł͖����
�u���������̂ł��A���������ɂ̂ł��Ȃ��B�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��B
����ł͑c�t�������������͈�̉����ɂ���̂��낤���B
�Ⴕ�A��������������ƌ������Ȃ���A
���̓�m���͂��ߓS�����Ƃ����̂ɁA�v��������������ɓ��ꂽ���Ƃ������邾�낤�B�v�ƌ����āA
�u���A���A�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��v�Ɣے肵�Ă���B
����͌d�\�̎��ォ��S�O�O�`�T�O�O�N�o�����ω���\�킵�Ă���B
���傪�u���A���A�܂��Ă͐S�������̂ł��Ȃ��v
�Ɣے肵�Ă���͉̂�X�����@���c�_���鎞�u���A���A�S�v�̑S�Ă��T�O�����ċc�_����B
�T�O�Ƃ��Ắu���A���A�S�v�͒P�Ȃ钊�ۊT�O�i�ϔO�j�ɉ߂��Ȃ��B
��X�����t���g���Ă�����c�_���Ă����@�̖{����͂ނ��Ƃ��ł��Ȃ��ƌ����Ă���̂ł���B
�T�O�V�Y�i�c�_�j�ȂǂŃG�l���M�[�����Ղ�����A���T�ɏW�����āu�^�̎��ȁv��̌��I�ɋ������ׂ���
�ƌ����Ă���ƍl������B
�d�\���{���Ɍ����������͂����ɂ���ƍl������B
�u���v�ł͈ꌩ�Z�c���������낵�Ă���悤����
������T���L�����Ȉӗg�i����悤�j�̕\�����Ǝv����B
30��g����ւ��D�P�Q�T�`�P�Q�V
�{���F
�n�c�A���݂ɑ�~�₤�A�u�@���Ȃ邩���ꕧ�H�v�B
�c�]���A�u���S�����v�B
�]���F
�Ⴕ�A�\������(������)�ɗ̗�(��傤��Ⴍ)��������A���߂�(��)���A���т��i���A
���b������A���s���s����A�������ꕧ�Ȃ�B
���̔@���Ȃ�ƑR(�@�����@)�(��)���A��~�A�����̐l�������āA
�����Ē�Ր�(���傤�傤)��F�߂��ށB
���ł��m��(�@��)���ӂ̕��̎�������ΎO���Ԍ���������Ƃ��B�Ⴕ����ӂ̊��Ȃ�A
���S�����Ɛ��������āA������(����)���ĕւ������B
��F
�V�����A�Ɋ��ސq�K(����݂Ⴍ)���邱�Ƃ�
�X�ɉ��@�Ɩ₦�A��(����)������ċ��Ƌ��ԁB
���F
�n�c�F�n�c����i�V�O�X�`�V�W�W�j�B����̑T�ҁB��ԉ����i�U�V�V�`�V�S�S�j�̖@�k�ō^�B�@�̑c�B�@�@
�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����~�@��
��Ր��i���傤�傤�j�F�V���̞��̋N�_�ɂ��鐯�`�̈�̂��ƁB���̌y�d�ɊW�̂Ȃ����ʖځB
��Ր���F�߂��ށF������K�v�̂Ȃ����̂Ɏ���������B
�u���S�����v�Ƃ������t�����������ׂɕ��̐^��������点���B
�فi�����j�F���i
���F����̐g�Ɋo���̂Ȃ����Ƃ�������B�܂����̂悤�Ȗڂɉ���ƁB
�ق�����ċ��Ƌ��ԁB�F���i������Ɏ����āA�u�����͓���ł��Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��B
�{���F
�n�c�a���͂��鎞�A��~����u���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����H�v�Ǝ��₳�ꂽ�B
�n�c�́A�u�S�����������̂��̂��v�Ɠ������B
�]���F
�����A�n�c�̌������Ƃ������ɕ�����A���߂�(��)���A���т��i���A���b������A
���s���s�����Ƃ��ł���B���ꂪ�������ł���B
���̂悤�ł����Ă��A��~�a������҂��A�����̐l����������ŁA�Ӗ��̂Ȃ����Ƃ����������̂���B
����Ȑl�ɁA�ǂ����ĕ��Ƃ����������ɂ��������ŎO���Ԍ�����߂��Ƃ����b
�������邾�낤���B
���@�̂悭�������Ă���l�Ȃ�A�u���S�����v�ȂǂƐ����̂��A
�����ǂ��ő��苎�邾�낤��B
��F
�u�S�����������̂��̂��v�Ƃ����^���͐V�����̂悤�ɖ��炩�ł���B
������v�z�I�ɍl���Ēǂ����߂Ă͂��߂��B
���̏�X�Ɂu���Ƃ͉����v�Ǝ��₷��͓̂��i����Ɏ����āA
�u�����͓���ł��Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��B
�{���̖ⓚ�͔n�c����́����S�������̑T�v�z��\�킵�Ă���B
�i���`���^�ɘZ�ɂ́A�n�c�A����O�Ɉ����ĞH���A
�u���l�A�e�X���S���ꕧ�Ȃ邱�Ƃ�M����B���̐S�����ꕧ�S�Ȃ��B�v�Ƃ���B
�����聃���S�������Ƃ�
�S���������S
�ł��邱�Ƃ������Ă���B
�n�c�́A���T�T�C�s�ɂ���ĔϔY�𗣂ꂽ�S�����������ƌ����Ă���B
���̐S�͉�X���ʐl�̗~�ƔϔY�ɂ܂݂ꂽ�S�i��]�V�玿�̕��ʈӎ����S�̐S�j
���w���Ă���̂ł͂Ȃ��B
��X���ʐl�͕��Ƃ����ƕ����ȂǗ�q�̑ΏۂɂȂ��Ă��钴�z�҂Ƃ��Ă̕����l����B
�n�c�͂��̂悤�ȐM�̑Ώۂ̕��ł͂Ȃ��A
�u���T�C�s�ɂ���ĉ��w�]���猒�N�ɂȂ������̐S�������ł����ƌ����Ă���̂ł���B
������A�n�c�̌��������S��������
�S���������S�����T�C�s�ɂ���Č��N�ɂȂ����S�]���琶�܂��S
�Ƃ��������ɂ���Ď������Ƃ��ł��邾�낤
�i��V�́u���Ƃ͉����H�v���Q���j�B
���̐}�R�O�ɑ̗p�v�z�ɂ���Đ������������S�������̍l�����������B
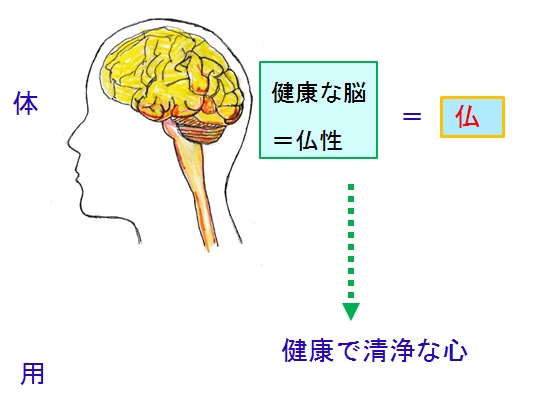
�}�R�O�@�̗p�v�z�ɂ�遃���S�������̐���
���̐}��
���T�C�s�ɂ���Č��N�Ő���ɂȂ����S�������ł���
���Ƃ������Ă���B
�u�Z�c�h�o�v�ɂ́����S�������̎v�z�����ɏo�Ă���B
�u�Z�c�h�o�v�ɂ����āA
�d�\�͒�q�@�C�������S�������Ƃ͉����Ǝ��₵���̂ɑ��A
�u�O�O�ł�,��O�����̎��A�S�͕s���s�ł̖��O�̏�ԂɂȂ��B
���̖��O�̔O���������S�������ł����B�v�ƌ����B
�X�Ɂu�T����C�s����ΐS������ɂȂ��B
���́u�S�����v�����łł����B
��d��o�C����Ζ{�����ꕨ�������S�������̓��̂�������v
�ƕ�����Ղ������Ă���B
����͑T��C�s�ɂ���ĉ��w�]���猒�N�ɂȂ����]���琶�܂�鐴��Ȗ��O�����̐S��
�łł���ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�ނ͑O�O���ł��Ă��鎞�͕s���ł���,��O�����̎��͕s�łł���ƕs���s�ł̖��O���������B
���ۂɕs���s�ł̖��O��ԂɂȂ�̂͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A���Ȃ�̏C�s���K�v���Ǝv����B
�������d�\�������Ă��邱�Ƃ͎��ɘ_���I�Ŗ����ł���B
���ʁA�����S�������Ƃ������t�͑���q�ł���n�c����̎v�z�Ƃ��ėL���ł���B
�������A�u�Z�c�h�o�v�ɂ͘Z�c�d�\�̎v�z�Ƃ��ďq�ׂĂ���̂͒��ڂ����B
�d�\�́u�O�O�ł�,��O�����̎��A�S�͕s���s�ł̖��O�̏�ԂɂȂ��B
���̖��O�̔O���������S�������ł����B�v�ƌ����B
�X�Ɂu�T����C�s����ΐS������ɂȂ�B���́u�S����v�������ł����B
�����T��ɂ���ĒB������鐴��Ȗ��O�����̐S�����ł����v�Ɛ����Ă���B
�Սς��ՍϘ^�œ��l�Ȃ��Ƃ����ׂĂ���B
�i�ՍϘ^���O�T�|�P���Q���j�B
�]�Ȋw�I�ɂ͔]���Ƒ�]�Ӊ��n�͖��ӎ��̔]�ł���B
���T�C�s�ɂ���āA�[���T��ɓ���A���w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�����ӎ��]�j�������������ƁA����Ȗ��O�����̐S�ɂȂ�B
�]���āA
��������Ȗ��O�����̏�ԂɂȂ������w�]���S�̔]�����ł���
�ƒ�`�ł��邾�낤�B
�]���ɂ��āF
����́u���@�̂悭�������Ă���l�Ȃ�A�����S�������ȂǂƐ����̂��A
�����ǂ��ő��苎�邾�낤��v
�ƌ����Ă���B
������T�ғ��L�̔���I�\���i���Ȉӗg(����悤)�̕\�����Ǝv����B
����́u���S�����v�ȂǂƊT�O�����Ďv�z�ő����Ă͂��߂��ƌ����Ă���̂ł���B
�����܂ł��A���T�C�s�ɂ���Ċ�������������Ȗ��O�����̏�ԂɂȂ������w�]���S�̔]
�����̌����āA�n�߂āu���S�����v��������ƌ����Ă���B
���̎��A���߂�(��)���A���т��i���A���b������A���s���s�����Ƃ��ł���B
���ꂪ�������ł���B
��ɂ��āF
�u�w�S�����������̂��̂��x�Ƃ����^���͐V�����̂悤�ɖ��炩�ł���B
������v�z�I�ɍl���Ēǂ����߂Ă͂��߂��B�v
�Ɖr���Ă���͍̂��T�C�s�ɂ���Ċ��������ꐴ��Ȗ��O�����̏�ԂɂȂ���
���w�]���S�̔]�����̌��������A
�u�S�����������̂��̂��v
�Ƃ����^���͐V�����̂悤�ɖ��炩�ɂȂ�ƌ����Ă���B
�u���̏�X�Ɂu���Ƃ͉����v�Ǝ��₷��͓̂��i����Ɏ����āA
�u�����͓���ł��Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��v�Ɖr���Ă���B
����́u�w���Ƃ͉����x�Ǝ��₷��͕̂�������L���Ă���̂ɁA
�u�����ɂ͕����͂Ȃ��v�Ƌ��Ԃ悤�Ȃ��̂��v�ƌ����Ă���̂ł���B
�}�P�Q�ɔn�c�T�́����S�������̐�����}������B
�@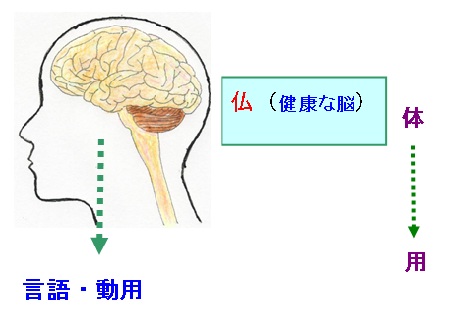
�}�P�Q�D�n�c�T�́����S�������̐���
���̐}�Ŏ������悤�ɁA����E���p�̖{�̂ł���]������i���N�j�ɂȂ��������A���ł���ƍl����B
�W���I�ȍ��T�C�s�ɂ���āA�{�̂ł����S�](����w�]�{���w�]�j������i���N�j�ɂȂ������A
�u�{������S�v�ƌĂ��悤�����N�Ȕ]�̓����i���Ƃ��Ă̓����j�����R�ɏo�Ă���B
������m��I�ɍl����̂��n�c�T�́����S�������̎v�z���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�i��V�́u���Ƃ͉����H�v���Q���j�B
�����S�������Ɋւ��āA�C�G�Y�X��m�I���K���`�[�m�Ɠ�T���̈V�̖@�_���`�����Ă���B
����͗��j�I�Ɍ��Ă��A�L���X�g���ƑT�̍ŏ��̏o����Ǝv����B
��ϋ����[���̂ňȉ��ɏЉ��B
�C�^���A�̃C�G�Y�X��m�I���K���`�[�m�i�P�T�R�R�`�P�U�O�X�j�͂P�T�V�O�N�ɗ������A
�D�c�M���̌������u��؎��v�����Ă��B
�ނ͓n���ȗ��������������A���̑�ӂɒʂ��Ă����Ɠ`�����Ă���B
�������A�L���X�g�������{�ɍL�܂�ɂ�
���{�ݗ��̏@���i�_���A�����A�j�Ƃ̃g���u�����p�������B
�L���X�g���̊ϓ_���猩��Γ��{�ݗ��̏@���i�_���A�����A�j�͋������q�̎��ɉ߂��Ȃ��B
�L���X�g�����L�܂����n���ł̓L���X�g���k�ɂ��_�Е��t�╧���̔j��
���p�������Ɠ`�����Ă���B
���̂��ߐV���̃L���X�g���̎א��𖾂炩�ɂ��邽�߈��y����ŏ@�_�����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�V���ܔN�i�P�T�V�V�N�j�̂��Ƃ��Ƃ����B
�L���X�g�����͓�؎��̊w�m�t���R���i���C�X�E�t���C�X�H�j�A���̑��̃o�e�����A�C���}���B�ł���B
�������͓�T���̈V�i�Q�U�W���A�~�t�H�j�̑��A
��؉@�̗����a���A�i�ϓ��̐[�C���t�Ȃǂ̊w�m�B���o�Ȃ����B
���@�̑m���������Ԃƃt���R����_�t�Ƃ��ē�؎��̊w�k�B���Ȃɏo�Ă����B
��؎���\�t���R����再g�т̈߂𒅂��A
��ڗ]��̒�����ттāA�m���Ɍ����Đi�B
�m���̕������T���̈V������ɑ��@�_���n�܂����B
�ŏ��Ƀt���R�����V�Ɏ��₵���A
�u���@�Ƃ͉��ł��邩�H�v
�V�͓����Č������A
�u���S�����v�B
�t���R���͂܂��q�˂��A�u���S�����̉��`�͉��ł��邩�H�v�B�@
�V�͏d�˂ĉ]�����A�u���S�����v�B
���̎��A�t���R���͍��𗧂��āA���V�ɋ߂Â��ċ������B
�ނ͐��Ɍ����ċ��ɓ˂����Ĕ������A
�u���S�����̉��`�Ƃ͉��ł��邩�H�v�B
�������A�V�͕��R�Ɗ����ĖّR�Ƃ��Ă����B
�V�͊����ĖّR�Ƃ������Ƃ̓t���R���̎���ɑ��铚�����ƍl������B
����͔n�c�T�́���p�������̎v�z�Ő����ł��邾�낤�B
���S�����̉��`�Ȃǂ͌��t�ŕ\�킷�����ł��Ȃ�����ّR�Ƃ����̂ł��낤�B
�V�͊����ĖّR�Ƃ��邱�ƂŖ��S�̋��n���������Ƃ��l������B
�����͕s�������̃M���M���̂Ƃ�����������Ƃ����߂ł��邾�낤�B
���̎��A���ɂ�����؉@�i���s�A��y�@�̎��j�̗����a���i�����a���H�j�́A
���V�������ĖّR�Ƃ��Ă����̂����āA�V�̕������ƌ�������B
�����Ŏ��������낤�Ƃ����B
�������A�V�̒�q�B�͏������������A�܂����̗����͌����Ȃ��B
�����������҂��������Ɨ����a���������~�߂��B
���̎��A�V�͍�������J���āu�J�A�[�b�I�v�Ƒ吺�ꊅ�����B
�t���R���͊���ӂ����ł��܂炸���|�i�C��j���Ă��܂����B
���̈��y��ł̖@�_�́u��؎����p�L�v�ɋL�q����Ă���B
�n�c�T�̎v�z���猩��ƁA�ق��Ă��邱�Ƃ��ꊅ���邱�Ƃ�
�S�̖{�̂Ƃ��Ă̕����i���]�A�{���̖ʖځj�̊���p�ł���B
�V�͊��Ƃ������{���̖ʖڂ̊���p����ʂ��āA���h���u���S�����v�̉��`��\�������ƌ����邾�낤�B
�������A�t���R���ɂ͂���Ȃ��Ƃ͒ʂ���͂��͂Ȃ��B
�t���R���͍��𗧂��āA���V�̋������݁A
�����ċ��ɓ˂����Ă����܂Ō��t�ɂ��𔗂����̂ł��낤�B
�ՍϑT�ł͊��ɂ͎l��ނ���Ƃ����B
�P�D�������̔@�����A�Q�D���n���т̎��q�̊��A
�R�D�T�Ɖe���̊��A�S�D�����p�̊�
�̎l�ł���B
���̎��̈V�̈ꊅ�́u���n���т̎��q�̊��v
���邢�́u�������̔@�����v�Ƃł������邾�낤���B
�t���R���͂��܂炸���|�i�C��j���Ă��܂����Ƃ�������]�قNj���Ȋ��������Ǝv����B
�S�b�̉��ł�����т̎��q���l���ɔ�т����鐨��
���������ꊅ�������̂ł͂Ȃ����낤���B
���邢�͕��̖{�̂Ƃ��Ă̕����i���]�A�{���̖ʖځj�̍�p�͂��̂悤�ɗ͋����������B
�u���ꂪ���S�����̉��`���v�Ǝ������������̂��낤���B
�ܘ_�t���R�����n�߃L���X�g���k���ɂ�
���̂悤�ȑT�̉��`�̕\���@�͑S���ʂ��Ȃ������ł��낤�B
�V�̋���Ȉꊅ�ɖZ�R�������A�̂�D���邵���Ȃ������Ǝv����B
�ŏ��Ƀt���R���̍ŏ��̎���A�u���@�Ƃ͉��ł��邩�H�v
�ɑ���V�̓����u���S�����v��
���@�̖ړI�͎��ȋ����ɂ��邱�Ƃ�T�I�Ɏ��������̂ƌ����邾�낤�B
�������A�L���X�g���k�ł���t���R���ɂ͂���͑S�������ł��Ȃ��������낤�B
�����k�ɂƂ����_�ɂ����������݂̕����S���Ƃ͂��킲�Ƃ��Ǝ��ꂽ�����m��Ȃ��B
�L���X�g���͌���i���m���j��_�����g���Ă����ɐ_�Ə@����\�����邩�ɑS�͂��g��
���ʒq�i�m���j�̏@���ł���B�@
�L���X�g���͌���i���m���j��_�����g���Đ_�̋�����\���ł���ƍl����B
����ɑ��T�͋��ɂ̐^���͌��t�ł́A�\���ł��Ȃ��Ƃ���i�s�������j�B
���w�]���d�����閳���ʒq�Ɓ����A�����̗���ɗ����Ă���B
�B��_�̊T�O�������B
�T�ƃL���X�g���̗���͑S���Ƃ����قLjقȂ闧��ɗ����Ă���B
���҂��݂��ɗ����ł���悤�ɂȂ閘�ɂ͂����Ǝ��Ԃ������邾�낤�B
�Q�l�����F�C�V��L����A���}�ЁA���m���ɂP�S�u��؎����p�L�v���D�S�Q�`�S�S�D
��g����ւ��D�P�Q�P�`�P�R�P
�{���F
��B�A���݂ɑm�k�q(��)�ɖ₤�A
�u��R(��������)�̘H�A�r(����)��̏��Ɍ����Ă������H�v�B
�k�]���A�u�}����(�܂�������)�v�B
�m�A�킸���ɍs�����ƎO�ܕ��B
�k�]���A�u�D�ӂ̎t�m�A������(�����)�ɂ������v�B
��ɑm�L���ďB�ɋ���(����)���B
�B�]���A�u�䂪�����ē����^(��)�߂ɔ�(��)�̔k�q(��)�����߂����҂��v
�B�����ւ������Ė�������@���₤�B�k����������@�������B
�B�A���ďO�Ɉ����ĞH���A
�u��R(��������)�̔k�q(��)�A�������^(��)�߂Ɋ��j(�����)����(����)����v�B
�]���F
�k�q(��)������(��)�Ȃ���ɛ��(������)�ɂ͂��邱�Ƃ������āA
�v(�悤)��(��)���ɒ������Ƃ�m�炸�B
��B�V�l�́A�P���c���(�ʂ�)�ݍ�(����)����(���т�)�����̋@��p�����A
��������l�̑������B
���_������������A��(�ӂ�)���(�Ƃ�)�ɉߗL��B
���������A�ߗ���������B�A�k�q(��)�����j(�����)���鏈�B
��F
����Ɉ�ʂȂ�A������������������B
�ї�(�͂��)�ɍ��L��A�D��(�ł����イ)�Ɏh(�Ƃ�)�L��B
���F
��B�F��B�]�V��(���傤���イ���イ����)�i778�`897�j�B����̑�T�ҁB
���i�V�S�W�`�W�R�S�j�̖@�k�B��B�ω��@�ɏZ�̂���B�a���ƌĂ��B
�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��
�k�q�i���j�F�V�k�B�ܑ�R(��������)�֓o��H�T�̒��X�ł����̐ڑ�
�ł����Ă����V�k���ƍl������B
���̘V�k�͑����T�̌��̊�������Ă����悤�ł���B
�{���͂��̘V�k�����ē�������e�����ł���B
��R�i��������j�F�ܑ�R(��������)�̂��ƁB
�R���Ȃɂ��镶���F�M�̗��B�����R�Ƃ������B
�u�،��o�v�̕�F�Z���i�Ɂu���k���ɕ�F�̏Z������A�����R�Ɩ��t���v�Ƃ���B
���̎R�ŕ����F�����@���Ă���Ƃ����l���Ɋ�Â��āA
�ܑ�R(��������)��̓���Ƃ���M���N�������Ƃ����B
�����i�����j���B�F��������B
���߁i���j�F����ׂ邱�ƁB
�u�䂪�����ē����^(��)�߂ɔ�(��)�̔k�q(��)�����߂����҂āv�F
�u�ЂƂ����s���Ă��̔k����̐��̂��������Ă�낤�v�B
�k�q(��)������(��)�Ȃ���ɛ��(������)�ɂ͂��邱�Ƃ��������A
�v(�悤)��(��)���ɒ������Ƃ�m�炸�B�F
�V�k�͎����̐w���ɍ�(��)�Ȃ���헪����邱�Ƃ�m���Ă���炵�����A
�v�ǂ����ɂ���Ă��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��B
�c���(�ʂ�)�ݍ�(����)����(���т�)�����̋@�F�{�c�ɐ���������v�ǂ�N������n�^���L�B
�ї�(�͂��)�ɍ��L��A�D��(�ł����イ)�Ɏh(�Ƃ�)�L��F�v��ʂƂ���ɍ���h������A�������B
�{���F
���鎞�m���A���X�̘V�k�ɕ������A
�u�ܑ�R(��������)�ւ̓��́A�ǂ��s���̂ł����H�v�B
�V�k�͌������A
�u�^�������ɍs���Ȃ����v�B
�m���A���̌��t�ʂ�ɎO�ܕ��s���ƘV�k�͌������A
�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v�B
��őm�����̘b����B�ɘb�����B
��B�͌������A
�u�ЂƂ킵���s���Ă��̔k����̐��̂����͂��Ă�낤�v
��������ɂȂ�ƁA��B�͏o�����čs���ē����悤�ɓ���q�˂��B
�V�k���܂������悤�ɓ������B
��B�͋A���ė���Ɩ剺�̏C�s�m�Ɍ������A
�u�킵�͂��O�����̂��߂ɂ��ܑ̌�R(��������)�̔k��������j���Ă��܂������v�B
�]���F
�V�k�͎����̐w���ɍ�(��)�Ȃ���헪����邱�Ƃ�m���Ă���炵�����A
�v�ǂ����ɂ���Ă��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��B
��B�͖{�c�ɐ������A�v�ǂ�N������n�^���L�����������A
�i��������s���Ƃ́j�叫�R�̂悤�ɂ͌����Ȃ��B
�悭�_������Γ�l�Ƃ��ɗ����x������B
�Ƃ������B�a���͈�̘V�k�̉��������j�����̂ł��낤���A�����Ă݂Ȃ����B
��F
�����������₪�����Ȃ�A���������Ă���͓̂��R�̂��Ƃ��B
�������A�V�k�̓������ꏏ���ƌ����Ă����т̒��ɍ����������Ă�����A
�D�̒��Ɏh���B��Ă��邱�Ƃ�����B
�{���͘V�k����B�a������l���ł���B
���̘V�k�ܑ͌�R�֓o��H�T�̒��X�ł����̐ڑ҂ł����Ă����ƍl������B
���̘V�k�͑����̑T�̌��̊�������Ă����悤�ł���B
�ܑ�R�֓o��m���A�u�ܑ�R(��������)�ւ̓��́A�ǂ��s���̂ł����H�v
�Ɛq�˂�ƁA�V�k�͂����A
�u�@�}�����i�^�������ɍs���Ȃ����j�v
�Ɠ������t�œ����Ă����B
�m���A���̌��t�ʂ�ɐ^�������ɎO�ܕ��s���ƘV�k�́A
�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v
�Ɣ���������̂���ł������B
�{���ܑ͌�R(��������)�֓o��H�T�ňӖ����肰�ɓ��ē�����V�k
�̂��Ƃ�����B�a�������ۂɏo�����Ĕޏ���_�����A
�u�@�}�����i�^�������ɍs���Ȃ����j�v�Ƃ͉��������j����̂����Ƃ����邾�낤�B
�ܑ�R�͕���M�̎R�ł���B
�����F�͉�X�̐S�ɋ���u�ʎ�̒q�d�v���ے����Ă���B
�u�ʎ�̒q�d�v�͖����ʒq�i�����q�j�ł���B
�u�ʎ�̒q�d�v�͑T�̋��ɂ̖ړI�ł���B
�u�ܑ�R�ւ̓���q�˂�m�ɁA�V�k�͂����A�u�}�����@�i�@�^�������ɍs���Ȃ����j�v�Ɠ�����B
�������A���́u�}�����@�i�@�^�������ɍs���Ȃ����j�v
�Ƃ������t�͒P�Ȃ�n���I���ē��̌��t�ł͂Ȃ��B
�u�ʎ�̒q�d�v�i�����ʒq�����̒q�d�j�ɓ��B���邽�߂̓��ē��̌��t�ł���B
�����A�V�k�́u�C�s�ɐ�S�W�������A�^�������Ɏ��Ȃ��u�ʎ�̒q�d�v�ɍs���Ȃ����i�}�����j�v
�ƌ����Ă���̂ł���B
���̌��t��P�Ȃ�n���I���ē��̌��t���ƌ�����āA
�^�����������čs���m�ɑ��ĘV�k��
�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������i���̐^�ӂ�������Ȃ��Łj�A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v
�Ɣ���������Ă���̂ł���B
�u�]���v�ɉ����Ė���́u�悭�_������Γ�l�Ƃ��ɗ����x�������v�ƌ����Ă���B
��l�̗����x�Ƃ��Ď����̂悤�Ȃ��Ƃ��l������B
�V�k�̗����x�F
�V�k�ܑ͌�R�֓o�铹��q�˂�m�ɁA
�u�}�����@�i�@�^�������ɍs���Ȃ����j�v�Ɠ�����B
���̌��t��P�Ȃ�n���I���ē��̌��t�Ǝ���Đ^�����������čs���m��
�u�Ȃ��Ȃ��̖V����Ɍ��������i���̐^�ӂ�������Ȃ��Łj�A��͂蓯���悤�ɍs���Ȃ����v
�Ɣ���������Ă���B
����͒P�Ȃ����Ƃ�����莩���̋��n���ւ�A
�m���������Ě}���Ă���悤�ȋ���������B
�V�k�́u�C�s���S�W�����Ȃ����v�B
�V�k�́u�ܑ�R�Ƃ����O�E�̎R�Ȃɂɒ��ӂ������Ă͂����Ȃ��B
���Ȃ̐S�����߁A�^�������ɁA���Ȃɋ����u�ʎ�̒q�d�v�ɍs���Ȃ����i�}�����j�v
�Ƃ͂�����Ǝ���m�Ɍ����Ă��Ȃ��B
���̂��߁A�m�͒n���I���ē��̌��t�Ǝ���Đ^�����������čs���̂ł���B
�V�k�͎��������������^�ӂɋC�t�������ɁA����������āA
���Ȃ��ւ��Ă���͎̂��ߐS�������Ă����ƌ��킴��Ȃ����낤�B
����͕��@�̏C�s�҂Ƃ��Ă̗����x�ƌ����邾�낤�B
��B�̗����x�F
��B�ܑ͌�R�֓o��H�T�̒��X�̘V�k�́u�^�������ɍs���Ȃ����i�}�����j�v�ƌ������́A
�P�Ȃ�n���I���ē��̌��t�ł͂Ȃ�
�����Ђ�����ɁA���Ȏ������̏C�s�ɐ�S�W�����āu�ʎ�̒q�d�i�����ʒq�j�ɍs���Ȃ����i�}�����j�v
�ƏC�s�ԓx�ɂ��Č����Ă���̂��Ɗ��j�����B
�������A����͘V�k�̐^�ӂ����j�����ɉ߂��Ȃ��B
��B�قǂ̗͗ʂ���T�҂Ȃ�A
�P.�V�k�Ɂu�}�����v�ƌ����Ĕ���邾���ł͕s�[���ł���ƘV�k��@���B
�Q.�w�l�̖ϑz��D���A�^�ܑ̌�R�͊O�ɂ���̂ł͂Ȃ��A
�r���i���Ȃ̐S���j�ܑ̌�R�ɓo��A
�u�^�̎��ȁv�ɖڊo�߂邱�Ƃ��^�̖ړI�ł��邱�Ƃ�������B
�R.���̂��߂̊���i�Ȃǂɂ��ĘV�k�ɏ������邱�ƂȂǂ��K�v�ł͂Ȃ����낤���B
�u��v�ł�
�V�k�̓������u�}�����v�ƌ��������������ƁA
���f���Ă���Ƃ��т̒��ɍ����������Ă�������H�ׂ�ƃK�W���ƍ�������A
�D�̒��ɉB��Ă���h���h����悤�Ȗڂɂ������ƂɂȂ�B
�C�s���ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂Ŗ��f������
���Ӑ[���C�s���Ȃ�������Ȃ��Ɖr���Ă���B
�{���ŕ����F�M�̗�R�ł���ܑ�R���o�Ă��Ă���B
�ՍϘ^�̎��O�ɂ����āA�ܑ�R�ƕ���ɂ��ėՍϋ`���́A
�u�ܑ�R�ɂ͕���͂��Ȃ��B����͂��O�B���g�A���ꂱ��������������Ȃ̂��v
�ƌ����āA�O�E�i�ܑ�R�j�ɕ�������߂Ă͑ʖڂ��ƌ����Ă���B
���̗Սς̐��@���{���̎Q�l�ɂȂ�B
�i�ՍϘ^���O�V�|�Q���Q���j�B
��g����ւ��D�T�O�`�T�Q
�{���F
�����A���݂ɊO��(���ǂ�)�₤�A
�u�L��(������)���킸�A����(�ނ���)���킸�H�v�B
��������(����)���B
�O���^�Q���ĉ]���A
�u�����̑厜���(������������)�A
�䂪���_���J���ĉ�����ē���(�Ƃ��ɂイ)�����߂������v�B
�T(���Ȃ�)����(�ꂢ)����(��)���ċ���B
����A�q���ŕ��ɖ₤�A�u�O���͉��̏��ؗL���Ă��^�Q���ċ����H�v�B
�����]���A�u���̗ǔn�̕ډe�����čs�����@���v�B
�]���F
�@����͔T(���Ȃ�)������q�A��(����)�����O���̌���(����)�ɔ@�����B
��(����)�炭��(��)���A�O���ƕ���q�Ƒ������邱�Ƒ������B
��F
���n(����ɂ�)��ɍs���A�X��(�Ђ傤��傤)��ɑ���B
�K��(�����Ă�)�ɏ�(�킽)�炸�A���R(����)�Ɏ���T(����)���B
���F
�����F���̏\���i�\�̕ʖ��j�̈�B�����Ƃ͞���̃o�K�o�b�g�i����������ҁj�̊���B
�O��(���ǂ�)�F�C���h�ɂ����ĕ����ȊO�̑��̏@���̋����B�܂����̐M��ҁB
�Z�t�O���A��\��̊O���Ȃǂ��m���Ă���B
����(����)�F������ƍ��蒼�����ƁB�ق��Ĉ֎q�ɍ��邱�ƁB
����F�u�b�_�̏\���q�̈�l�ő������Ə̂��ꂽ�A�[�i���_�̂��ƁB��22���Ɋ��o�B
���̗ǔn�̕ډe�����čs�����@���F�G���܌o��
�u���Ɏl��̗ǔn�L��B�ǔn�L���ĉ핽����ȂāA���̕ډe���ڂ݂Ēy�E�E�B�v�Ƃ���̂���B
���n(����ɂ�)��F�u���n��̎��v�Ƃ͔����g�̌��ɒ��ʂ������Ԃ̂��ƁB
�K��i�����Ă��j�ɏi�킽�j�炸�F�\�n�̕�F�̂悤��
�Q���ɒi�K��ŕ��ʂɓ���Q�C�ł͂Ȃ�
�꒴�ɕ��ʂɎ���ڌ�ɂ��Č����Ă���B
���R�i�����j�Ɏ���T�i�����j���F
�f�R��ǂł��܂��Ă������p�b�Ɨ������ƁB�厀��Ԃ���B
�{���F
�u�b�_�ɂ���O�����������A
�u�L�Ƃ����Ă��A���ƌ����Ă��\�킷���Ƃ��ł��Ȃ����͉̂��ł����H�v�B
�u�b�_�͂��炭�ق��č����Ă����B
����������O���͎^�Q���āA
�u�����̑傫�Ȏ��߂ɂ���āA���̖����̉_������A��点�Ē����܂����v
�Ɨ�����ċ����čs�����B
����ƈ���̓u�b�_�ɕ������A
�u�O���͈�̉���������ƌ����āA���̂悤�Ɏ^�Q���ċ����čs�����̂ł����H�v�B
�u�b�_�͉]�����A
�u�ǔn���ڂ̉e�������r�[�ɑ����čs���悤�Ȃ��̂����v�B
�]���F
����̓u�b�_�̒���q�ł��邪�A�O���̌����ɋy�Ȃ��B
����ł͂��̊O���ƕ���q�Ƃ��ׂĂǂ�ʂ̍������邩�����Ă݂�B
��F
�s�����̐n�̏���s������A������邩������Ȃ��X�̏�𑖂�悤�Ȃ��̂��B
�T�̓��ł͊K���Ō�邱�Ƃ͂Ȃ��A
�f�R��ǂł��܂��Ă������p�b�Ɨ����悤�Ƀp�b�ƌ��̂��B
�{���ł́A����O�����u�L�ł��A���ł��Ȃ����͉̂��ł����H�v�Ƃ������������B
���̎���̓A���X�g�e���X�̘_���w�ł͂��肦�Ȃ��B�@
���̂Ȃ�A�A���X�g�e���X�̘_���w�ł́u�L�ł��邩�A���ł��邩�̂ǂ��炩�ł���A���̒��Ԃ͂Ȃ��i�r�����j�v
�Ƃ��邩��ł���B
�{���́A�Q�T���ɉ����ċR���������u���̕��@�͎l��A�S��Ȃǂ�����_�����Ă��܂��j�B
�悭�����Ȃ����i���d��(�܂�����)�̖@�͎l��𗣂�S��𗣂�S���₷�j�B�v
�Ɠ����^�C�v�̖��ł���B
�i��Q�T���u�O�����@�v���Q���j�B
�Q�T���ŋR�́u���@�̋��ɂ͎l��A�S��A�S��Ȃǂ����錾��\�����Ă����v�ƌ����Ă���B
�{���͈�̌���E���삷�ׂĂ������̑S�̍�p�ł���ƍl����n�c�T�i�^�B�@�j�́���p�������̎v�z�Ő����ł���B
����p�������̎v�z��
���ɑ�Q�T���i�O�����@�j�̐}�P�P�ɂ���Đ����������A�O�̂��߈ȉ��ɍĂю����B
�@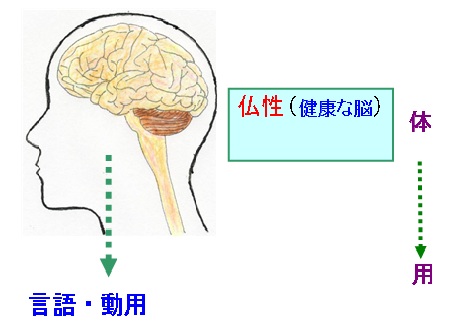
�}�P�P�D����p�������̐����}
�@�}�P�P�Ɏ����悤�ɁA�T�ł���̌���E����͖{�̂ł���]�i�������j�̍�p�ł���
�ƍl����i����͉Ȋw�I�ɂ��������j�B
�u�b�_�i�����j�͂��炭�ق��č����Ă��邱�Ɓi�����������j�ł�����������ƌ�����B
�ق��Ă��邱�Ƃ́u���i�����j�������������Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����H�v
�Ƃ����^�₪�N���邩���m��Ȃ��B
�u�L�i�L��(������)�j�͂ǂ��ɂ��邩�H�v�Ƃ����^�₪�N���邩���m��Ȃ��B
���̋^��ɑ��Ă͎����̂悤�ɓ����邱�Ƃ��ł���B
�ق��Ă���ƌ����Ă��]�͏�ɓ����Ă���B
�ċz�����Ă���Ή����̌ċz�����͓����Ă���B
�]�͏�ɓ����Ă���B���̑��ʂ͗L�i�L���j���ƌ�����B
�܂��A�]�ɂ͔����d����������Ă��Ȃ��̂Ŗ����A���`�ŁA���̑��ʂ����B
�����l����Ɣ]���L�ł���Ɠ����ɖ��ł����Ƃ������ʂ������Ă���B
����͗L�łȂ����A���ł��Ȃ��Ɓw�o��̘_���x�Ő������邱�Ƃ��ł���B
�{���͌��̖{�̂ł���]�̃n�^���L���u�b�_�̋����Ŏ����A
�O���͂�����u���ɗ����������Ăƌ����邾�낤�B
�������A���̂悤�ȑT�I�ⓚ���u�b�_�ݐ�����ɂ������Ƃ͍l���ɂ����B
���n�����̌o�T��ǂތ���A�u�b�_�̐��@�͘_���I�ŕ�����Ղ��B
�}�P�P�Ŏ���������p�������̎v�z�͒�������̔n�c����̑T�ɂ����ďo�Ă����v�z�ł���A
�u�b�_�̌��n�����ɂ������Ƃ͍l�����Ȃ��B
���̈Ӗ��Ŗ{���āi�R�Q���j�͒����ł̑T�@�̌��Еt���̂��߁A�����T�ɂ����ĐV�����n�삳�ꂽ�ⓚ�ƌ����邾�낤�B
�u���v�ɂ����āA
�u���n��ɍs���A�X�ŏ�ɑ����v�Ɖr���Ă���B
����͌��̐n�̏��X�ŏ�ł͂����������Ă���Ƒ�������芊�藎����B
���ʈӎ������āA�����������Ă����Ȃ����ƌx�����Ă���̂ł���B
�u���v�̑���ł́A
�u�T�̓��ł͂��������\�n�̊K���Ō��悤�ȑQ�C�̓����Ƃ�Ȃ��B
�f�R��ǂł��܂��Ă������p�b�Ɨ����悤�Ƀp�b�ƌ��̂��B�v�Əq�ׂāA
���ڌ�T�i��@�T�j�̗�����r���Ă���B
��g����ւ��D�P�R�T�`�P�R�U
�{���F
�n�c�A���݂ɑm�₤�A�u�@���Ȃ邩���ꕧ�H�v�B
�c�H���A�u��S���v�B
�]���F
�@�Ⴕ�A�җ��Ɍ����Č������A�Q�w�̎�(��)�L(����)��ʁB
��F
�H�Ɍ��q�Ɉ���A�{�炭�悷�ׂ��B���l�ɑ��킸��Ό����邱�Ɣ���B
�l�Ɉ����ẮA��(����)���O��������A�����S����Ђ��{���ׂ��炸�B
���F
��S�F�u��S�v�ƌ������t�́u�n�c��^�v�Ɍ�����B
�w���S�����x���S�����ł���Ƃ���A�u��S�v�́u�S�͕��łȂ��v�ƂȂ邪�A
�`���I�ȉ��߂ł́w���S�����i�S�����j�x�ɑ��鎷�����������߁A
�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v�Ƃ���Ă���B
�җ��i�����j�F�����B�{���̖ʖځi���^�̎��ȁj�������B
�l�Ɉ����ẮA��(����)���O��������A�����S����Ђ��{���ׂ��炸�F
�u�������Q�v�ɓ�ɁA
�u�l�Ɉ����ẮA��(����)���O���̘b������A�����S����АS��e�ׂ��炸�v�ƌ�����B
���F�Ƃ����ǂ��{�S�����炯�o���Ęb���Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��B
�{���F
���鎞�A�n�c�a���ɑm���������A�u���Ƃ͂ǂ��������̂ł����H�v�B
�n�c�͉]�����A�A�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v�B
�]���F
�������̏����������邱�Ƃ��ł���A�T�̏C�s�͊������B
��F
�H�Ō��q�Ɉ��������ɂ́A�����o���ׂ������A���l�łȂ���Ύ����o���K�v�͂Ȃ��B
�l�ɂ́A�O��������Ă��ǂ����A�S�Ă��{���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�R�O���́u���S�����v�̑����b���n�c��^�ɏo�Ă���B
����m���X�ɔn�c�ɖ₤���A�u�a���͉��́A���S�����Ɛ����̂ł����H�v
�n�c�͌������A�u�q���������̂��~�߂邽�߂��B�v
�m�H���A�u�����~���͂ǂ�����̂ł����H�v
�n�c�͌������A�u��S���B�v
���̂悤�ɁA����S�����ƌ������t�́����S�������ɂ��Ă̖ⓚ�ŏo�Ă��Ă���B
����S�����ƌ������t�́����S�������̔ے�\���ł��邩��
�R�O���́u���S�����v�̌��ĂƊW������B
�i��R�O���u���S�����v���Q�� �@�j�B
���A�����S��������
�S���� �E�E�E�E �i�P�j
�̓����ŕ\�킷�Ƃ��̔ے�\����
�S�@���@���@�@ �E�E�E�E �i�Q�j
�i�S�͑������ł͂Ȃ��j�ƂȂ�B
�i�Q�j���́u�S�͑������ł͂Ȃ��v�́u�T�O�����ꂽ�S�͕��ł͂Ȃ��v
�ƌ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�n�c�́����S�������Ƃ������t��
�i�P�j���̂悤�Ɂi�S�����j�ƊT�O���i�v�z���j����镾�Q���������B
�`���I�ȉ��߂ł́u��S���v�ƌ������t�́A
�T�O���i�v�z���j���ꂽ�����S�������i�S�����j�ɑ��鎷�����������߁A
�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v�Ƃ���Ă���B
����̉Ȋw�I�ϓ_�ɗ��ƁA�u�{���̖ʖځv�̖{�̂́w�]���𒆐S�Ƃ������w�]���S�̔]�x�ƌ������Ƃ��ł���B
�i��S�́u���̑̌��Ƃ��̕��́F���̂Q�v���Q���j�B
�]���āA�u�S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��v���̂Ƃ�
�w�@�]���𒆐S�Ƃ������w�]���S�̔]�i���{���̖ʖځj�x���S�ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A���Ƃ��\��������̂��B
�ƌ����Ă���ƍl������B
��ԉ����́u�����ꕨ���s���v�Ƃ������t�Ɏ����Ƃ��낪����B
�i�����ꕨ���s�����Q�� �@�j�B
�u�]���v�Ŗ��傪�u�������̏����������邱�Ƃ��ł���A�T�̏C�s�͊������v�ƌ����Ă���̂�
������̓��ł���ΑT�̖ړI�͒B���ł��������R���ƌ����Ă���̂��Ǝv����B
���w�]�͑�ꑥ�̎��ł������̖{�̂ł���A
���ꂪ������ΑT�̖ړI�͒B���ł��������R������ł���B
�n�c�́����S�������̋����ŊJ�債������̑�~�@��T�t�i752�`839�j��
�J��̌�A�V��R�̑�~�R�̈��ɋ����ĎR���o�邱�ƂȂ��C�s���d�˂Ă����B
����m����~�@��T�t�Ɂu���̍��A�n�c�́���S�����ƌ����Ă���悤�ł���v�ƍ������B
��~�@��T�t�́u�n�c�́���S�����ł悢�̂��B���͂��������S���������B�v�Ɠ������B
�n�c�͂��̘b���āu�~�q�n�����B�v�ƌ����đ�~�@��T�t��J�߂��Ɠ`������B
�@����S�����͂悭�S�ł��Ȃ����ł��Ȃ��Ɛ��������B
�O�c�m�T���́u�M�S���v�ɁA
�u��S�s���Ȃ�Ζ��@�閳���B��Ȃ���Ζ@�����A��������ΐS�ɂ��炸�v
�Ƃ������t������B
����͈�S�s���̖{�̂������{���̖ʖځi�^�̎��ȁj�ł��邱�Ƃ��q�ׂ��ӏ��ł���B
��S�s���̖{�͉̂��w�]�i���]���{��]�Ӊ��n�j�ł��邱�Ƃ��������Ă���B
(�M�S�����Q���j�B
���̂Ȃ牺�w�]�͖��O���z�̖��ӎ��]�ł��邩��S�i���ӎ��j�������邱�Ƃ��Ȃ�����ł���B
�ӎ��������邱�Ƃ��Ȃ���ΐS�ł͂Ȃ��B
���̂悤�Ȃ��̂͐S�ł��Ȃ��A�܂����ƌĂԂ��Ƃ��ł��Ȃ��B
���������S�����ƌ������ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�@�����S�������́����S����(�������Ԃ�)���Ƃ������邪���҂͓������Ƃł���B
�u���v�ɉ����āA
�u�H�Ō��q�Ɉ��������ɂ́A�����o���ׂ������A���l�łȂ���Ύ����o���K�v�͂Ȃ��v
�Ɖr���Ă���B
����͑���̒��x�ɉ����āi���āj�Ή����ׂ����Ƃ������Ă���̂ł���B
�H��œ����̕�����Ȃ��l�ɁA�����o���Ă����������悤�ɁA
���l�łȂ��l�Ɏ���������K�v�͂Ȃ��Ɖr���Ă���̂ł���B
�u�l�ɂ́A�O��������Ă��ǂ����A�S�Ă��{���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ́A
�l�ɑS�Ă�������Ƃ��̐l���Q������Ƃ��낪�Ȃ��Ȃ�̂łR�O�����炢�Ŏ~�߂Ȃ����Ɖr���Ă���B
����͔n�c�a���͂���Ȃɐe�ɋ����Ă���Ă���̂ɖ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ͏�Ȃ�
�Ƌt�ɉ�X�ɔ����Ă���̂ł���B
��g����ւ��D�P�R�V�`�P�R�W
�{���F
���]���A�u�S�͐��ꕧ�ɂ��炸�A�q�͐��ꓹ�ɂ��炸�v�B
�]���F
����(����)�ׂ��A�V���ā@�(�͂�)����(��)�炸�ƁB
�킸���ɏL��(���イ��)���J���A�ƏX(�����イ)�O(�ق�)�ɗg(��)����B
�����̔@���Ȃ�ƑR(����)�(��)���A����m��҂͏��Ȃ��B�@
��F
�@�V����ē���(�ɂ��Ƃ�)�o(��)�ŁA�J�����Ēn�㎼(���邨)���B
���s�����ēs(����)�Đ�����(����)��A��������M�s�y(����ӂ��イ)�Ȃ邱�Ƃ��B
���F
���a���F���i�Ȃ�ӂ���A�V�S�W�`�W�R�S�j�B
����̑T�ҁB�n�c����i�V�O�X�`�V�W�W�j�̖@�k�B
�S����C�A�����q���ƂƂ��ɔn�c�剺�̎O��t�̈�l�B
�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��
�q�F�m���B
����(�ɂ��Ƃ�)�F���z�B
�M�s�y�i����ӂ��イ�j�F�M���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƁB
�ƏX�O�i�����イ�ق��j�ɗg�i���j����B�F�ƒ���̒p���O���ɂ��炯�����B�T�̖��ӂ��O�ɋ�����B
�{���F
���a���͉]�����A�u�S�͕��ł͂Ȃ��A�q���͕����ł͂Ȃ��v�B
�]���F
���Ƃ����낤�l���A�Ƃ��Ēp�Ƃ������̂�������Ȃ��Ȃ����̂��낤���B
�@�L�������J���ĉ�������ׂ����Ǝv������A�Ƃ̒p���O�ɂ��炵����B
���Ƃ��������Ƃ��Ă��A���a���̑剶��m��҂����Ȃ��̂͒Q���킵�����Ƃ��B�@
��F
�����̑��ɂ͑��z���P���A�J���~��Α�n�͎�(���邨)���B
�v���̂�����s�����āA�S�Đ���������Ă��A
�M���邱�Ƃ��ł��Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��B
�n�c���������u���S�����v��u����S�����v�̑T��
�����I�ŕ��ՂȂ��ߍL�������ꔚ���I�ȗ��s���݂��悤�ł���B
�������A�L���ɂȂ�Ƌ��ɕ��Q���o�Ă����B
����́u���S�����v��u����S�����v���T�O�����Ďv�z�Ƃ��đ����邱�Ƃł���B
�����Ȃ�Ɣn�c�̐^�ӂƈقȂ�B
�{���͂�������邽�ߔn�c�̒���q�ł��������������t�����ƂȂ��Ă���B
�Q�T�C�s�҂́A�u���S�����v�ƕ��������̐S�����̂܂ܕ����Ɠ��ɊG��`���悤�ɂȂ�B
�܂��u����S�����v�ƕ����Ƃ��̗~�ʼn��ꂽ�}�S�����̂܂ܓ����Ǝv���B
���͂��̂悤�Ȉ��ՂȑT��ے肷�邽�߁A
�u�S�͐��ꕧ�ɂ��炸�A�q�͐��ꓹ�ɂ��炸�v�ƌ����Ă���̂ł���B
����͈ꌩ�A�u���S�����v��u����S�����v��ے肵�Ă���悤�ł��邪�A
�t���I�Ɍ����Ă��邾���ŁA�u���S�����v��u����S�����v�̐^�ӂ�`���邽�߂Ɍ������ɉ߂��Ȃ��B
�u�q�͐��ꓹ�ɂ��炸�v�Ƃ�
�{�Ȃǂ�ǂ�œ����m���╪�ʈӎ��Ɋ�Â����ʒq�i���m�j�͓��ł͂Ȃ��A
���T�C�s��ʂ��āA���w�]����̂ɂ����]���琶�܂�閳���ʒq�����ł����ƌ����Ă���B
����
���t��v�z�Ɋ�Â����m�̒q�d�ł͂Ȃ��A���T�C�s�ɐ�O���ĉ��w�]����̂ɂ����u�����ʒq�v��̌����J������
�ƌ����Ă���ƍl������B
�u�]���v�ł͓��͂��������V�l�������������Ēp�����炵����A
�܂�Ƃ������ĕ��Ƃ̒p�����炵�Ă���Ƃ������낵�Ă���B
�������ɂ���Č��Ȉӗg�̕\���ł���B
���̌��t�K�ɂ��ĉ��悤�Ȃ��Ƃ͂����A
���̐^�ӂ����ݎ��Ɖ�X�ɒ��ӂ�^���Ă���̂ł���B
�u���v�ɂ�����
�u�����̑��ɂ͑��z���P���A�J���~��Α�n�͎�(���邨)���v�Ɖr���Ă���B
���@�̐^���͂��̂悤�ɊȒP���ĂȂ��̂������Ă���B
�������A�v���̂�����s�����đS�Đ���������Ă��A
�u�^�̎����v�ւ̐M��O�ꂵ�������哹���Ȃ�����ǂ����悤���Ȃ��ƌ����Ă���B
��g����ւ��D�P�R�X�`�P�S�P
�{���F
�ܑc�A�m�ɖ₤�ĉ]���A�u�菗����(��������肱��)�A�߉�(�Ȃ�)������^��(����Ă�)�H�v
�]���F
�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����Đ^�����蓾�A
��(���Ȃ�)���m���k(����)���o�Ċk�ɓ��邱�ƁA���ɂɏh���邪�@���Ȃ���B
���ꈽ���͖����R(����)�炸��A�ɗ������邱�Ɣ�(�Ȃ�)��B
�}�R�Ƃ��Ēn���Ε���U���A���ɗ���{�E�I�̎��蔪�r�Ȃ邪�@���Ȃ��B
�ߎ��������Ɣ���A���킸�ƁB
��F
�@�_�����ꓯ���A�k�R(��������)�e�X�قȂ�B
����(�܂�Ղ�)�����A����ꐥ��B
���F
�ܑc�F�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�B�k�v�̑T�ҁB
�ՍϏ@�k��h�A���_��[�i�P�O�Q�T�`�P�O�V�Q�j�̖@�k�B
�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E���Α��^�~���k�������_��[���ܑc�@���@
�菗�����i��������肱��j�̘b�F
�u�菗�����v�̕���͓���̓`����w�����L�x�ɏo�Ă���B
�����͓��̎���A�t�z�ɒ��ӂƂ����l�������B
���ӂ̈�l���菗�́A�Ȃ��Ȃ��̔��l�ŁA�����Ƃ������j�q�Ɨ����������B
�菗�Ɖ��������������@���ӂ͓�l�����������ďグ�悤�ƌ����Ă����B
��l�͊��ŁA���̋C�ɂȂ��Ă����B
�Ƃ��낪��l���傫���Ȃ�ƁA���e�̒��ӂ́A�ޏ���ʂ̒j�ƌ��������悤�Ƃ����B
���̂��߂ɘ菗�͟T�a�ɂȂ����B
�����͒��ӂ̂�����������œs�ɍs�����ƌ��ӂ��āA�̋�����ɂ����B
���炭�s���ƁA�菗���ǂ������ė��āA
�u���Ȃ��Ƃ�������łȂ�����v �ƌ������B
�����͂��̐S�������ꂵ���v���A��l�͎�Ɏ�����������ĉ���冂̍��ɋ삯���������B
�ܔN�̍Ό�������āA�q������l�ł����B
�₪�āA�菗�͖]���̔O��݂������A������������Č̋��̍t�z�ɋA�邱�ƂɂȂ����B
�����͂܂���l�Œ��Ӂi�菗�̕��j�̉Ƃɍs���A�s�F��l�сA�͂�������B
�Ƃ��낪�A���ӂ̓P�Q���Ȋ���ŁA
�u���O�͘菗��A��삯���������ƌ������A
�菗�͂��O���Əo���Ĉȗ��Y�[�b�ƕa�C�ŁA���܂��܂��ׂ̕����ɐQ�Ă�����v
�ƌ����B
�@����������Ɖ�������������炳���ς�킩��Ȃ��Ȃ����B
�Ƃɂ����M����Ɏc���Ă����菗��A��Ă���ɂ�����Ƃ��A
�}���ň����Ԃ��A�菗��A��ė����B
�@����ƁA���܂̂��܂܂ŕa�炵�Ă����菗���C�\�C�\�ƁA
�ׂ̕�������o�Ă��āA
�Z��̘菗�݂͌��ɕ��݂�������Ǝv���ƃA�b�Ƃ����Ԃɍ��̂��Ĉ�l�ɂȂ����B
�{���͂��̕�������ɂ��Čܑc�@�������Ă�n�������̂ƍl������B
�ܑc�@������ܑ�ڂ̖@���ł��閳��d�J�ɂ��̌��Ă��`�����Ă����ƍl������B
�߉Ӂi�Ȃ��j������^��i����Ă��j�H�F�ǂ��炪�{�����H
�@�߉ӂƂ́A����A����A�̂��ƁB�܂��A��ȏ�̎����ɑ��āA
���̂��Âꂩ�����I�ڂ��Ƃ���Ƃ��ɗp����^��㖼���B
�ǂ�A�ǂ���̂��́B�^��͐S�̉���A�S��̂��ƁB
�n���Ε��F�Ñ�C���h�l���M�������E�����̎l���f�B
�n���Ε���U�F�l�啪���Ƃ������B�l�Ԃ����ʂ��ƁB
�{�E�I�F�I
���ɗ���{�E�I�̎��蔪�r�Ȃ邪�@���A�F
���ɗ������I���葫���o�^�o�^�����������ꂵ�ނ悤�ɁA
�����i��Ղ��j�F���ׂĂ߂ł����Ƃ����A���A�̌��t�B
�{���F
�ܑc�@���T�t�͑m�Ɏ��₵���A
�u�菗�̓��̂��獰�������������Ƃ������ꂪ���邪�A��̂ǂ��炪�{���̘菗�ł��낤���H�v
�]���F
�����A���̘b�̊����𑨂��A�{���̘菗�͂��ꂾ�ƌ��A
����ō����g�̂��痣��A�܂��g�̂ɓ���Ƃ������Ƃ́A
�����������ɏo�ďh����h�ɔ��܂�悤�Ȃ��̂��ƕ�����B
�������A��������Ă��Ȃ��Ȃ�A�ނ�݂ɐl���𑗂邱�Ƃ����Ă͂����Ȃ��B
�ˑR���ʂ悤�Ȃ��ƂɂȂ������A�Q�Ăӂ��߂��āA
�܂�œ��ɗ������I����r���o�^�o�^�����������ꂵ�ނ悤�Ȃ��ƂɂȂ邾�낤�B
����Ȏ�������Ă��n�܂�Ȃ��B
��F
�@�_�ƌ��͓����悤�Ȃ��̂����A�k�R�͂��ꂼ�����Ă���B
�@���ꂪ�킩��߂ł������肾�B��ł������ł�����B�@
�u�菗�����v�̌��Ă͕�����ɂ����B
�u�菗�����v�̕���͓���̓`����w�����L�x�ɏo�Ă���B
���̘b�̐����͏ȗ����ꂢ���Ȃ�{���̎��₪�o�Ă��邩��ł���B
���̘b��m��Ȃ��Ɓu�u�菗�����v�̘菗�ɂ��āA
�u��̂ǂ��炪�{���̘菗�ł��邩�H�v
�ƕ�����Ă��������₳��Ă���̂���������Ȃ��B
�@���鎞�ܑc�@���T�t�͒�q�B�Ɂu�菗�����v�̘b��������A
�u�w�菗�����x�̘b�œ�l�̘菗�̂ǂ��炪�{�����낤���H�v�Ƃ�������������B
���ꂪ���̌��Ă̌��ɂȂ��Ă���̂ł���B
�������A�u�菗�����v�̏ڂ����b�͏ȗ�����Ă��邽�ߖ{���͕�����ɂ����B
�u���@�ɕs�v�c�Ȃ��v�Ƃ����āA
�T�ł͖��d�s�v�c�Ȃ��Ƃ������B���̌��Ă͂��̐���S��b�ł͂Ȃ��B
�łܑ͌c�@���T�t�͂Ȃ�ł���Ȋ�Șb�����グ���̂��낤���B
�l�Ԃ͐S���������߂Ă����Ȃ��ƁA�菗�̂悤�ɐS�Ƒ̂����Ă��܂��A
����������ɋC�t���Ȃ��ł���ꍇ���A���Ȃ��Ȃ��B
���̂悤�ȏꍇ�ǂ̂悤�ɍl���Ώ�������悢���l�������邽�߂��ƍl������B
���̖����l���邽�߁A���a�ɜ���ĉƂŐQ����ł��܂����菗��菗�@�Ƃ��A
������冂̍��ɋ삯���������菗��菗�A�Ƃ��悤�B
�菗�@�Ƙ菗�A�͎��̕\�U�̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��悤�B
�@�\�U�@�菗�@�Ƙ菗�A�̕��ށ@
| �菗�̕��� | �菗�̏�� | �菗�̐S����� |
|---|---|---|
| �菗�@ | ���a�ɂȂ��Ď��ƂŐQ���� | �F�Ƌ`���̘_���ɏ]���� |
| �菗�A | ������冂̍��ɋ삯�������� | �F�Ƌ`������������� |
�u�菗�@�Ƙ菗�A�̂ǂ��炪�{�����H�v�Ǝ��₳�ꂽ���A
���ʂ̐l�͘菗�@���菗�A���{���ł���͂����ƍl����B
�������A���̂悤�ȓ�ґ���I�l�����ł͐l�Ԃ̖{���ɔ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�菗�@���{�����Ƃ��Ă��菗�A���{�����ƍl���Ă���ʊςɉ߂��Ȃ��B
�{���̘菗�͘菗�@�ł���ƂƂ��ɘ菗�A�ł���i��̉��������́j
�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�菗�@�Ƙ菗�A�̂ǂ�����{�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B
���ɏq�ׂ��o���̘_���ł���B
�i��Q�T���̎l��_�����Q���j�B
�l�Ԃ͂��鎞�͇@�̏�Ԃł���A���鎞�͇A�̏�ԂɂȂ肤��B
�菗�@�Ƙ菗�A�̊Ԃ�h�ꓮ���Ă���ƍl����̂ł���B
�@���ۘ菗��冂̍��ŗ��l������5�N�Ԑ���������A�����Ă���B
����͍F�Ƌ`���̘_���ɏ]���菗�A����菗�@�ɂȂ����ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�l�Ԃ͈�ʊςł������ƌ��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����ʐ��������Ă���B
�l�Ԃ͉E�������A�P�������A���������邩�A�g�̂��S���A
�ƒ납�d�����A�������_�����X�A��ɓI���ʈӎ��ɐU���Ă���B
���̌��Ă͂��̂悤�ȑ��ΓI���ʂ��̑I��������ΓI���E�A
���Ȃ킿�A�g�S�������Η����Ȃ���q��@�̐��E�ɖڊo�߂��������߂̌��Ă��ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�u�]���v�ɉ����Ė���͂����A���̌��Ă̐^�ӂ�������A�������͕Ђ����A
�u����ō����g�̂��痣��A�܂��g�̂ɓ���Ƃ������Ƃ��A
�����������ɏo�ďh����h�ɔ��܂�悤�Ȃ��̂��ƕ������E�E�E�v�ƌ����Ă���B
����͌Ñ�C���h�̗։��]�����Ɋ�Â��Č����Ă���B
�C���h�̗։��]�����̓`���[���h�[�M���E�E�p�j�V���b�h��
�u�܉ΐ��v�ɋN�������P�Ȃ�z�����ł���B
�։��]�����͉Ȋw�I�]���⌟�ɑς��鍪���������Ă��Ȃ��B
���̓_�u�]���v�ɉ����Ė��傪�����Ă��邱�Ƃ͊�������čl����K�v������B
�i�u�։��]���Ɠ܉ΐ��v���Q���j�B
�u��v�ł́u�_�ƌ��͓����悤�Ȃ��̂����A�k�R�͂��ꂼ�����Ă���v�Ɖ̂��Ă���B
�_�ƌ��͕v�X�菗�@�Ƙ菗�A��栂��Ă���B
�菗�@�Ƙ菗�A�͓����菗����o���p�Ȃ̂œ����悤�Ȃ��̂����A
�J�ƎR���ʕ��ł���悤�Ɉ���Ă���Ɖ̂��Ă���B
�菗�@�Ƙ菗�A�͓����菗�̕ʂ̖ʂ�\�킵�Ă���B
����Ɠ����悤�ɓ���̐l�Ԃ��菗���菗�@�Ƙ菗�A�ɂȂ����悤��
���̎���������ɏ]���ĕω�����ʂ������Ă����B
������u��ł������ł������v�Ɖ̂��āA
���Ƃ�����̐l�Ԃł����Ă��A���ʓI���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă���̂ł���B
�u��v�ł́A
����l�ԁi���j����ʐ��i���ʐ������j�������Ă��邱�Ƃ�������u�߂ł������肾�v�Ɖr���Ă���B
�]�Ȋw�I�Ɍ����Ɛl�Ԃ͎�̂Ƃ��Ĕ]�i���j�������Ă��邪�A
�������ł��邽�ߏ����ɏ]���āA�]�i���j�͑��l�Ȏp�ɕω�����B
�����Ȏp�ɂȂ�������Ƃ����āA�����ʕ��ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�،��v�z�ł͂�����ꑦ���A�������ƕ\������B
���邢�́A�����i���ƍ��ʁi���Ƃ������t��p���āA
���������������A�����ʑ��������Ƃ������B
���̂悤�Ș_���I�ɖ��������\���͑T�╧���ł悭�p������B
��g����ւ��D�P�S�Q�`�P�S�R
�{���F
�ܑc�H���A�u�H�ɒB��(���ǂ�)�̐l�Ɉ���A��ق���(����)�đ������B
���������A�r��(�Ȃ�)����(����)�Ă������H�v
�]���F
�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ����đΓ�(�����Ƃ�)���Đe�Ȃ�A
�W�����c��(��������)�Ȃ邱�Ƃ��B
���ꈽ���͖����R�炸��A�炽�{�炭��؏��Ɋ���ׂ�
��F
�H�ɒB���̐l�Ɉ���A��ق���(����)�đ�����B
�����G(���)����(�ւ��߂�)�Ɍ����A�����ɉ�Εւ����B
���F
�ܑc�F�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�B�k�v�̑T�ҁB�ՍϏ@�k��h�A���_��[�i�P�O�Q�T�`�P�O�V�Q�j�̖@�k�B
�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E���Α��^�~���k�������_��[���ܑc�@���@
�B���i���ǂ��j�̐l�F���O�ꂵ���l�B
�җ��i�����j�F�����ł́u��قɍS�D���Ȃ����n�v�������B
�W�����F�͂Ȃ͂��A�����ւ�A�̈Ӗ��B
�W�����c���Ȃ邱�Ƃ��B�F�������̏�Ȃ����Ƃł��낤�B
����F�悭�C�����Č���B
�����G���ʁi����ւ��߂�j�Ɍ����F�{��͂�Ő^�������牣�肩���邱�ƁB
����(�ւ��߂�)�Ƃ͔߂��݂̂��܂蓁�Ŋ�����ƁB
�{���F
�ܑc�@���T�t�͉]�����A�u�H��ő��O�ꂵ���l�ɏo��������ɂ��A
���t�ő��Ă����قő��Ă������Ȃ��B
���āA�������Ƃ���A�ǂ��̂悤�ɉ�����Ηǂ��̂��낤���H�v
�]���F
�@������قɍS�D���Ȃ����n�Ƀs�^���Ƒ��邱�Ƃ��ł���A
�������̏�Ȃ����Ƃł��낤�B
�������A�������̂悤�ȋ��n��������Ȃ��Ȃ�A
�s�Z����̈�؎����ɏ�ɒ��ӂ��ďC�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��F
�H�ő��O�ꂵ���l�ɏo��������ɂ́A���t�ő��Ă����قő��Ă������Ȃ��B
����ł�����������Ȃ��Ȃ�A�{��j��������قǂԂ�B
��������A�ɂ��ɉ��Y��Ė{���̖ʖڂɂ����C�t�����낤�B
�{���́u�T�C�s�҂��H��ő��O�ꂵ���l�ɏo��������ɂ͂ǂ�������ǂ����H�v
�Ƃ������Ăł���B
�T�̊�{�I���_�Ǝp�����Ă���ƌ���Ηǂ����낤�B
�T�̊�{�I���_�ƌ��́u�����ʒq�v�ł���B
(�����ʒq�ɂ��Ă͕��̒q�d�������ʒq�A�����ʒq���Q���j�B
�u�����ʒq�v�Ƃ͖��䖳�S�̑f���ȐS�ƌ����Ă��ǂ��B
���̐S�͏����ɉ����đf���ɑf�����Ή����ē����S�ł�����B
�����ʎ�o�Ő���
�u�������Z�������S(�����ނ��傶�イ�ɂ��傤������)�i�܂��ɏZ���邱�ƂȂ����̐S���ׂ��j�v
�̐S�ƌ����Ă��悢���낤�B
�]���āA�u����ςȂǂ��������ɑf���ȐS�ōs���v�����̓����ƌ����Ă��ǂ����낤�B
�u�]���v�ł́A������قɍS�D���Ȃ��Ŗ����Ƀs�^���Ɛe���K�ɑΉ����邱�Ƃ��ł���A
���̐l�̓��퐶���͂��̏�Ȃ������K���Ȃ��̂ɂȂ�ł��낤�B
�������A�����@���̂悤�ȋ��n��������Ȃ��Ȃ�A
�s�Z����̈�؎����ɂ����Ē��Ӑ[�����f�Ȃ��C�s��ӂ�Ȃ��悤�ɂ��ׂ����ƌ����Ă���B
�u��v�ł́A�u�H�ɒB���̐l�Ɉ���A��ق���(����)�đ������v
�Ɩ{���̌��t�����̂܂ܗp���Ă���B
���̐��_�͊��ɘ_�����悤�Ɂu���N�Ɉ����Ă��A����������ꍇ�ɂ��A�f���Ȗ��S�̐S�ōs���v
�Ƃ������Ƃɐs����B
�Ȃ��̂Ăđ���Ƃ҂�����ƈ�ɂȂ邱�ƁA
�d���̎��ɂ͎d���ɏW�������䖳�S�Ɏd�������邱�Ƃł���B
�����A����ł�����������Ȃ��Ȃ�A�{��j��������قǂԂ�B
��������A�ɂ��ɉ��Y��āu�{���̖ʖ��v�ɂ����C�t�����낤�Ɖr���Ă���B
��g����ւ��D�P�S�S�`�P�S�T
�{���F
��B�A���݂ɑm�₤�A�u�@���Ȃ邩����c�t����(�����炢)�̈Ӂ@�H�v
�B�]���A�u��O�̔����q(�͂����サ)�v�B
�]���F
�@�Ⴕ��B�̓���(��������)�Ɍ������Č���(����Ƃ�)���Đe�Ȃ�A
�O�Ɏ߉ޖ�����(���肦)�ɖ���(�݂낭)�����B
��F
���A����W�Ԃ邱�Ɩ����A��A�@�ɓ������B
������(��)������̂͑r(����)���A��ɑ�(�Ƃǂ���)����͖̂����B
���F
��B�F��B�]�V��(���傤���イ���イ����)�i778�`897�j�B����̑�T�ҁB
���i�V�S�W�`�W�R�S�j�̖@�k�B��B�ω��@�ɏZ�̂���B�a���ƌĂ��B
�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c����@����聨��B�]�V��
�c�t�����i���������炢�j�̈ӁF
�u�c�t�B�����C���h����͂��n�������i����(�����炢)�j���̈Ӗ��͂ǂ��ɂ���̂��H�v
�Ƃ��������ʂ��đT�̖{����₤�퓅�I�Ȍ��t�B
���j�I�Ȃ��Ƃ����₵�Ă���̂ł͂Ȃ��B
�����q�i�͂����サ�j�F�q�͏����B
��B�]�V���T�t��������B�ω��@�ɂ͔��̖i�����q(�͂����サ)�j�����������ƌ����B
�������A���̔��͕��ʂ̔��ł͂Ȃ������i�тႭ����j�������B
�����̓q�m�L�ȃr���N�V�����̍��B�����Ɏ�����Ύ��ŁA���͕O�Ɏ��ĐԂ��c���܂��������B
�}�P�R�ɔ����̎ʐ^�������B
�@
�}�P�R�D����
�@����W�Ԃ�F���������S�ɕ\������B
�@�ɓ������F���c�̐S�@�Ɍ_(����)��Ȃ��B
��A�@�ɓ������F���t�͕��c�̐^�̓����Ɍ_�����Ȃ��B
�{���F
��B�a���ɂ���m���q�˂��A�u�B����t���͂��C���h�������ė����Ӑ}�͉��ł����@�H�v
�������B�͒���w�����ĉ]�����A�u���̔��̎������v�B
�@
�����q
�]���F
������B�̓����������͂�����ƌ��������Ƃ��ł���A
�߉ޖ�����ӕ�F�������ɓ������ƌ�����B
��F
���̎�����͌��t�Ő����ł��Ȃ����A�j�S�ɐG��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
���t�������������A�S���������������B
�{���̖ⓚ�ɏo�Ă��锐�̎��Ƃ͂��̗t�𔐖݂ɗp���锐�̖i�u�i�ȁj�ł͂Ȃ��B
�}�P�R�Ɏ���������(�тႭ����)�ƌ����q�m�L�Ȃ̐j�t���i���j�ł���B
��(���͖����ɕʂꂽ���}�̎��͂Ɏ����Ɏ����t���t���A�ɖΗ͂�������Ύ��ł���B�@
�@��������F�a���������ω��@�ɟT���Ɣɂ��Ă����ƌ����Ă���B
���ʂ̐l�͎��͎����i�S�j�ƕʂ��̂ŁA�����ƑΏۂł�����i���j��Η��I�Ɍ��Ă���B
�������A��B�ɂƂ��āA�����ƑΏۂł�����i���j��Η��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�ނ͐S�Ƌ��Ƃ���̂ɂȂ����u�S����@�E��������v�̑T�̋��n�ɗ����Č��Ă��邩��ł���B
��B�͂��̐S����@�̋��n���u���̔��̎�����i��O�̔����q�j�v�Ƃ������t�œ������̂ł���B
���̖ⓚ�̌��T�u��B�^�v�ɂ��Ǝ��₵���m����B�̓����ɖ��������A
�u�a���A���������Đl�Ɏ����Ȃ����v�ƌ������Ɠ`������B�@
���₵���m����B�Ɂu�a���A�O�E�̕��i�O���j�ȂŎ����Ă�������܂����B
�����Ɛ��_�I�ȓ��e�������t�Ő������Ă���Ȃ��ƕ�����܂�����v
�ƌ�������B�ɍR�c�����B
�������A����m�̍R�c�I�Ȏ�����Ă��A��B�́u���̔��̎�����i��O�̔����q�j�v
�Ƃ����������t�œ������Ƃ����B
����m�m�ɂ���B�̓����̐^�Ӂi�S����@�E������́j���`���Ȃ������̂ł���B
���̌��Ă�3���́u���w�v�̌��ĂƓ��ނł���B
�i�����3���u���w�v���Q���j�B
�w�S����@�̋��n�x�Ƃ��ϑz���ʂ�O��I�ɒD���s�������Ƃœ����鏃���ӎ��ł���
�ƍl�����Ă���B
���̌��Ăɂ��Ė��S���J�R�̊֎R���t�́u�����q�̘b�ɑ��@�����B�v
�Ƃ����L���Ȍ��t���c���Ă���B
���@�Ƃ́u�ϑz���ʂ�D�������v�Ƃ����Ӗ��ł��邩��A
�֎R���t��
�u�����q�̌��Ă͖ϑz���ʂ�O��I�ɒD���s�������Ƃŏ��߂Ă��̐^�ӂ��������B�v
�ƌ����Ă���̂ł���
�i��6�̖͂�����̂̋��n���Q���j�B
��g����ւ��D�P�S�U�`�P�S�W
�{���F
�ܑc�H���A�u栂��ΐ��R���i���������イ�j�̑��Q(�����ꂢ)���߂��邪�@���@�A
���p(������)�l��(������)�s(��)�ׂĉ߂���(����)��Ɂ@�A
�r��(�Ȃ�)�Ɉ����Ă����b(�т�)�߂��邱�Ƃ���@�H�v
�]���F
�@�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ������ē^�|(�Ă�ǂ�)���āA
��NJ�(������������)�����A��]����������A
�Ȃ��ď�l���ɕA���O�L����(����)���ׂ��B
���ꈽ���͖����R�炸��A
�X�ɐ{�炭���b(�т�)���ƌ�(���傤��)���Ďn�߂ē��ׂ��B
��F
�߂�����A�B��(��������)�ɑ��A��藈��p���ĉ�(���)���B
�ҍ�(���Ⴕ��)�̔��b�q(�т͂�)�A���ɐ���r������Ȃ�B
���F
�ܑc�F�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�B�k�v�̑T�ҁB
�ՍϏ@�k��h�A���_��[�i�P�O�Q�T�`�P�O�V�Q�j�̖@�k�B
�Ζk�Ȍܑc�R�ɏs�Z�̂Ōܑc�ƌĂԁB
�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E���Α��^�~���k�������_��[���ܑc�@���@
���R���i���������イ�j�F�Ă̐����B
���Q�i�����ꂢ�j�F���̊i�q�i�Q�j�B�Q�i�ꂢ�j�͑��̊i�q�̂��ƁB
���b�i�т́j�F�K��(������)�B
�^�|�i�Ă�ǂ��j���āF�t�l(��������)�ɂȂ��āB
�l���F�P�D����̉��A�Q�D�O���̉��A�R�D�����̉��A�S�D�O��i���A�@�A�m�j�̉��@
�̎l�̉��̂��ƁB
����ł��R�D�͍��Ƃ̉��b�A�S�D�͏@����Ȋw�Z�p�̉��b
�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B
�O�L�F�O��̑��ݗ̈�A�����~�E�A�F�E�A���F�E�̎O�E�̂��ƁB
�������J��Ԃ������̐��E�̂��ƁB
�i�O���琢�E�ƎO�E���Q���j�B
�u�{�炭�E�E�E���Ďn�߂ē��ׂ��v�F�u�E�E�E����B��������E�E�E�ł��悤�v�Ƃ����Ӗ��̏�p��B
�B�́F���B
�ҍ��i���Ⴕ��j�F�����́B���͕�����\�킷����B
���ɐ���F�܂����������āB���ӂ̏����B
�{���F
�ܑc�@���͉]�����A�u栂��ΐ������ʂ�߂���̂𑋉z���Ɍ��Ă�����A
���A�p�A�l�̋r�S�Ă��ʂ�߂��Ă��܂��Ă���̂��A
�ǂ������킯�ŐK�������͒ʂ�߂��Ȃ��̂��낤���@�H�v
�]���F
�@�@�Ⴕ���̎��Ԃɑ��ċt�̕�����A
�^������������ŁA�j�S��˂����t��f�����Ƃ��ł���A
��͎l���ɕA���͖����̏O�����~�����Ƃ��ł��邾�낤�B
�������������܂ł͓����Ă��Ȃ��Ȃ�A
����Ƃ����̐����̐K�������͂��Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�B
��F
��������ʂ�߂���A���ɗ����A��蓹�����Ă�����ɂ����B
���̐K���Ƃ������̂́A���Ƃ����(��������)���ƌ��������Ȃ���B
�{���͔��B�T�t�̔���̌��Ă̂P�Ƃ�����ł���B
�{���Ōܑc�@���T�t�͐��R���i���������イ�j��栂��őT�̋��ɂ̏����������Ƃ����B�@
���R���i���������イ�j�Ƃ͖Ă̐����̂��Ƃ����A
����́u�^�̎����v��栂��Ƃ���Ă���B�@
���Q(�����ꂢ)�͑��i�q�Ƃ����Ӗ��ł���B
�����ł͖����̐��E��栂��Ƃ��ėp�����Ă���B
���������\���I������y�Q�T�҂Ȃǂɉ�����Ė��Ȃ�����
���̌��Ă����������Ă��邩������Ȃ��B
�����܂��Ȍ��Ăƌ�����B�@
�����̑̑S�́i���p�l��(������������)�j�͋������̓�����ʂ��Ă��܂����̂ɁA
�����ȐK�����ǂ����Ă��ʂ�Ȃ��Ƃ͈�̉����Ӗ����Ă���̂��ƎQ������̂�
�{���̂˂炢���Ƃ���Ă���B
�����̓��p�l��(������������)�Ƃ�
��X�̓��̒��ɂ����V�I�Ȓm���E�o���E�v�z�Ȃǂ̖ϑz��\�킵�Ă���B
�����̌�V�I�Ȗϑz��S�đ|�����ăN���A���Ă��܂����Ƃ�
�u�^�̎����v�ɋA���i�����j���Ƃ��ł���ƍl�����Ă���B�@
���ꂪ���p�l��(������������)���������̓�����ʂ�߂����i�K�ł���B
�܂������Ȃ��Ă��疢���c���Ă���K�����Q������i�K�ɂȂ�B�@
���p�l��(������������)���ʂ�߂����i�K�����ł�
�����^�́u�^�̎����v�Ƃ͌����Ȃ��B
�@�c���Ă���K�����ʂ�߂��Ă���A�n�߂āu�^�̎����v�ɂȂ�̂ł���B
�u�]���v�ł́A�������̌��ĂɌ����āA�t�ɂЂ�����Ԃ��āA
���[���o�ɖϑz�̎c�Ԃӂ��Ă��܂��ƌ��̊�i��NJ�j���J���āA
���̋��n�𗧔h�Ɍ����\�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B
�����Ȃ�ƁA��͎l���ɕA���͖����̏O�����~�����Ƃ��ł���B
�������������܂ł͓����Ă��Ȃ��Ȃ�A
����Ƃ����̐����̐K�������͂���ׂ����ƌ����Ă���B
�u��v�ł́A���̐��E�͕ʖ��u��E�̐[�B(���傤)�v�Ƃ��Ă��B
�����Ɏ~�܂�l�́u����̎����v�Ƃ�������A�����^�ɖ𗧂������Ȃ��B
�Ɋy���E�Œ��Q���Ă���悤�Ȃ��̂ł���B
������ƌ����Ė}�v�̐��E�Ɍ�ނ���������ĂԂ��ł���B
���̕ς��Ă��邪�̑�ȐK����{���ɒ͂܂��邱�Ƃ��ł���A
�^�̎��Ȋm�����ł���Ƌ��ɁA
�����̐��E�ɂ���O����{���ɋ~�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ɖr���Ă���̂ł���B
��g����ւ��D�P�S�U�`�P�T�P
�{���F
�_��A���݂ɑm�₤�A
�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�B
��喢���₹����ɁA��ɂ킩�ɞH���A
�u�(��)�ɐ��꒣��(���傤����)�G��(���イ����)�̌�ɂ��炸���H�v�B
�m�]���A�u��(��)�v�B
��H���A�u�b�����v�B
�㗈�A���S�_(�˂�)���ĉ]���A
�u��(����)����(��)���A�ߗ�(�Ȃ�)�������(��)�̑m���b�̏��H�v
�]���F
�@�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ������ĉ_��̗p���ϊ�(�䂤���傱��)�A
��(��)�̑m�r(�Ȃ�)�Ɉ����Ă��b���ƌ���(����Ƃ�)���A
�l�V(�ɂ�ł�)�̗^(����)�Ɏt�ƈׂ�Ɋ�(��)����B
���(����)�������߂���A���~�s��(�����ӂ�傤)�v
��F
�}���ɒ�(��)�𐂂�A�a��n(�ނ���)��҂͒�(��)���B
���D(�����ڂ�)�킸���ɊJ���A����(���傤�݂傤)�r�p(�������Ⴍ)����B
���F
�_��F�@�_�啶��i�������Ԃ�A�W�U�S�`�X�S�P�j�B����̑T�ҁB
���`���i�W�Q�Q�`�X�O�W�j�̖@�k�ʼn_��@�̎n�c�B
�@�n�F���s�v���Γ���J�����V�c���偨���K���M�����R��Ӂ@������`�����@�_�啶��
���ُG��(���傤�����イ����)�@�F���v�N�s���B�ܑ�v���i�P�O�`�P�P���I�j�̋��m�B
�G�˂͉ȋ��i�����o�p�����j�ɉ������l�̌ď́B
���ق͐Γ����l���̐Α��c��(����������������)�i�W�O�V�`�W�W�W�j�ɎQ�����̖@���k�����B
���ق��Α��̎w�����ŊJ�債������������u�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�@�}���ܗ실�Ɉ�Ɖ]�X�v�ł���B
���̖`���Ɂu������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�̋傪����B
���ُG�˂̖@�n�F���s�v���Γ���J����R�ҙV������~�q���Α��c�������ُG��
���S�F�������S�T�t�i�P�O�S�R�`�P�P�P�S�j�B�A���c�S�i�P�O�Q�T�`�P�P�O�O�j�̖@�k�B
�傢�ɗՍϏ@�����h�̏@�������߂��l�Ƃ��Ēm����B
�������S�̖@�n�F�Սϋ`�����o�Z�`�p�������d�쁨�A���c�S���������S�@
�b���F�������q�ׂ����t���̂��j�]��I�悷�邱�ƁB�{�����o���B���悾�B
�㗈�F��ɁB
�p���i�䂤����j�F���̒q�d����o�铭���B
�ϊ�i�����j�F�ǐ�덂�̗��B���t����B
�l�V�i�ɂ�ł�j�F�l�ԂƓV�l�B
�ߗ��i�Ȃ�j�F�����B
���~�s���i�����ӂ�傤�j�F���������~���Ȃ��A�����C�s�̎��i�ҁB
���D�i�����ق��j�F�O�B�D�͗ځA�����܂̈Ӗ��B
�{���F
�_��T�t�ɂ���m���q�˂��A
�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�B
�S���̎��傪�I���Ă��Ȃ��̂ɁA�_��͉]�����A
�u������A����͒��ُG�˂̎��̋傶��Ȃ��̂��H�v�B
�m�͉]�����A
�u�͂��A�����ł��v�B
�_��͉]�����A
�u���悾�I�v�B
����A�������S�T�t�͂��̖ⓚ�ɂ��āA
�u�����ɂ��̑m���b�i����j�����������邩�A�����邩���H�v�Ɖ]�����B
�]���F
�@�������̖ⓚ�ɉ����āA�_��̊��t����n�^���L�A
����ɂ��̑m�͂ǂ��Ń{�����o��������������A
�l�V(�ɂ�ł�)�̎t�ƂȂ�ɂ��Ƃ��ł��邾�낤�B
�����A����ł�����������Ȃ��Ȃ�A�����������~���Ȃ����낤�B
��F
�}���Ɍ����Ēނ莅�𐂂��A�������������a�ɔ�т��B
���̋��Ɠ����悤�ɁA�����J���Ĕ�т������ނ�グ���Ė����������낤�B
�@�{���̂˂炢�����邽�߂ɖⓚ�̗����������x�݂悤�B
����m���_��T�t�ɐq�˂��A
�u������ƕՉ͍�(�����݂傤���Ⴍ���傤�ւ���)�v�B
���̎���m�͂��̎��̑S���������Ă��玿��ɓ��낤�Ƃ����炵���B
�@�������A�_��͓r���ŎՂ��āA
�u������A����͒��ُG�˂̎��̋傶��Ȃ��̂��H�v�ƌ������B
�m�͉_��̌��t�ɒނ荞�܂��
�u�͂��A�����ł��v�Ƒf���ɓ������B
����Ɖ_��͉]�����A�u���悾�I�v�B
����A�������S�T�t�͂��̖ⓚ�ɂ��āA
�u�����ɂ��̑m���b�i����j�����������邩�A�����邩���H�v�Ɖ]�����B �@
�ȏオ���̖ⓚ�̂���܂��ł���B
���ꂩ�番����悤�� ���S�T�t�́u�����ɂ��̑m���b�i����j�����������邩�H�v
�̎���ɓ����A������͂����肳����Ƃ���ɂ˂炢������B
���̑m�͉_��̎���ɑ��Ă������ɓ����Ă���A�����Ԉ���Ă��Ȃ��B
����Ȃ̂ɉ_���
�u���悾�I�v
�ƌ����Ă��̑m�ɗ���̔�����������B
���̑m�́u�{���̖ʖ��v��̌��������������̂ƍl������B
�ނ͂��̌o���𑼐l�̌��t����ĕ\�����悤�Ƃ����B
�������A������f���炵���ƌ����Ă����l�̌��t�ł���A
�����̑T�̌�������̌��t�ŕ\�����Ă��Ȃ��B
���̑m�ɂ͎�̐����������Ȃ��B
�܂��A���l�̌��t����ĕ\�����悤�Ƃ����_�A
���l�̌��t�����̂܂�ĕ\�����悤�Ƃ����_�A
���̃p�N����͕�ɉ߂����A�m���g�̎�̐���Ƒn�����S�������Ƃ�����B
�Ƒn���������_�͉Ȋw�I�ɂ��S���]���ł��Ȃ��B�Ȋw�ł͓Ƒn�����d�����邩��ł���B
���ُG�˂̎�����肽�̂͑��l����ő��o���Ƃ�悤�Ȃ��̂ł���B
�������_��͂����������������āA
�u���O����͂悻�����肵�āA���l����ő��o�����悤�Ȃ��Ƃ����Ă��邩�痎�悾�v
�Ɣ��肵���̂ł���B
�u�]���v�ł́A
�@�������̖ⓚ�ɉ����āA
�_��̑f���炵���n�^���L�Ƃ��̑m�͂ǂ��Ń{�����o�����悵������������A���̊Ⴊ�J�����ƌ�����B
�����Ȃ�A�l�V�̎t�ƂȂ�ɂ��Ƃ��ł��邪�A
����{���Ɍ��Ȃ�����A�����������~���Ȃ����ƌ����Ă���B
�u���v�ł́A
�_�傪����m�̌��t���I��Ȃ����Ɂu����͒��ُG�˂̎��̋傶��Ȃ����v
�ƂЂ��������̂͂��������}���Ɍ����Ēނ莅�𐂂ꂽ�悤�Ȃ��̂ŁA
�����ނ�j�������Ȃ��B
����ŁA�������������a�ɔ�т��B����m�͂��̋��̂悤�Ȃ��̂ŁA
�����J���Ĕ�т������߁A�_��ɍ����ނ�グ���āA�����������Ƒm������栂��ĉr���Ă���B
��g����ւ��D�P�T�Q�`�P�T�T
�{���F
�@�C�R(������)�a���A�n�ߕS��̉(�����イ)�ɍ݂��ēT��(�Ă�)�ɏ[(��)����B
�S��A��(�܂�)�ɑ�C(������)�̎�l��I��Ƃ��B
�T(���Ȃ�)�������Ď��(���セ)�Ɠ������O�ɑ��ĉ���(������)�����߁A
�o�i�̎҉�(��)���ׂ��ƁB
�S��A���ɏ�r��_���A�n��ɒu���Ė₢��݂��ĉ]���A
�u����ŏ�r�ƍ삷���Ƃ��B������Őr���Ƃ��삳���H�v�B
���(���セ)�T(���Ȃ�)���]���A
�u����Ŗg�c�ƍ삷�ׂ��炸�v�B
�S��A�p���ĎR�ɖ₤�B�R�T(���Ȃ�)����r���e�L�|���ċ���B
�S����ĉ]���A
�u�����A�R�q�ɗA�p������v�B
�����āA�V�ɖ����ĊJ�R�ƈׂ��B�@
�]���F
�C�R(������)����̗E�A����(������)����S��̌��L��o�ł��邱�Ƃ��B
���_����������A�d���ɕւ肵�Čy���ɕւ肹���B
�����̂��B�j�C�i�ɂ��j�B�Փ���E�����āA�S�g��S�N���B
��F
╃��i������j���тɖ؎ۂ����E�����āA���z�̈�ˎ��Ղ�₷�B
�S��̏d�ւ���������Z(�Ƃ�)�߂��A�r��(���Ⴍ����)�e�L�o(�Ă������)���ĕ����̔@���B
���F
�C�R�a���F�@�C�R��S�i������ꂢ�䂤�A�V�V�P�`�W�T�R�j�B
����̑T�ҕS����C�i�V�S�X�`�W�P�S�j�̖@�k�B�C�@�̎n�c�B
�@�n�F�Z�c�d�\����ԉ������n�c���ꁨ�S����C���C�R��S���R�d��
�T���i�Ăj�F�@��O�i�C�s�m�j�̐H���̐��b�������E�B
��r�F��������Ă����Ď�������肷��̂ɗp����r�B
�b���F�������q�ׂ����t���̂��j�]��I�悷�邱�ƁB
�{�����o���B���悾�B
�g�c�i�ڂ��Ƃj�F�؍Y�B
�A�p�����F�����B������B
�j�C�i�ɂ��j�F��̌�̗]���B
�������w���������Ƃɂ���ċl�₵���蒍�ӂ𑣂����肷��ԓ����B�\�����邪�悢
�Փ��i�j�F�͂��܂��B
╁i�����j���F����B
���E���i�悤���j����F����o���B
���z�F�z�Ƃ͓���Ӗ�����B
�u���z�v�Ƃ͓�ɐ��ʂ��邱�Ƃł���B�����ł͐^���ʂ��Ӗ����Ă���B
���ՁF����̑������܁B
���z�̈�ˎ��Ղ�₷�B�F
���ʂ����r���R����ĕS��̂֗�����f�����Ă��܂����B
�r��i���Ⴍ����j�F���̒ܐ�B
�����̔@���F�����̕�����яo�����l(����)�͗��ꂽ���̂悤���B
�{���F
�C�R��S�T�t�́A�Ⴂ���A�S����C�T�t�̓���ő䏊�̐����W�߂Ă����B
���x���̍��S��a���͑�C�R����̏Z����l�I���悤�Ƃ��Ă����B
�����ŁA�S��͓���̖剺���i�C�s�m�j�B���W�߁A���Ȃ̌勫���q�ׂ����A
���͂̂���҂�I�����ďZ���ɐ��E���悤�Ƃ����B
�S��a���͂�ɂ�ɏ�r��n��ɒu���Ď��₵�ĉ]�����A
�u�������r�ƌĂ�ł͂Ȃ�Ȃ��B�����A���O�B�͂�������ƌĂԂ��H�v�B
���̖₢�Ɏ��(���セ)�́A�u�܂����ؕЂƌĂԂ킯�ɂ������܂����v�Ɠ������B
�S��́A���ɃC�R�Ɍ���������
�u���O�͂ǂ������H�v�ƕ������B
�C�R�͒����ɏ�r���R����Əo�čs�����B
���̎��S��a���͏��āA
�u����̓C�R�ɂ��Ă��ꂽ���v�Ɖ]�����B
�������ăC�R�͑�C�R�̊J�R�ƂȂ����̂ł���B
�]���F
�C�R��S�͂������Ĉ���̗E��U����ď�r���R�����C�R�̊J�R�ƂȂ����B
�������A����ŃC�R�͕S��̎d�|����㩂ɂ͂܂��Ă��܂�����B
�悭�悭����A�ނ͏d����ڂ�I��Ōy����ڂ�I�Ȃ������̂��B���̂��낤���H
���猩��A�ނ͓����甫������苎���Ă���A�S�̞g(����)��Ƃ߂�悤�Ȃ��ƂɂȂ����ł͂Ȃ����B�@
��F
�@�C�R���(����)�₵����������o���A���ʂ����r���R����ĕS��̂֗�����˔j�����B
���̎��݂̃n�^���L�ɂ͕S�䂪�݂����d�ւ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�������āA�C�R�̑��悩�疳���̊���������яo�����킢�B
�{���͕S��̓���Ő����W�߂Ă����C�R��S����C�R����̏Z���ɑI�������o�������Ăɂ������̂ł���B
�S��͓���̎��(���セ)�i�ԗјa���j�ƓT��(�Ă�)�i��S�j���Ăяo���A��O�i�C�s�m�j�̖ʑO�Ŗⓚ�������B�@
�S��a���͈�̏�r��u���āA
�u�������r�ƌĂ�ł͂Ȃ�Ȃ��B�����A���O�B�͂�������ƌĂԂ��H�v
�Ƃ��������l�ɏo�����B
���̖₢�Ɏ��(���セ)�i�ԗјa���j�́A�u�܂����ؕЂƌĂԂ킯�ɂ������܂����v
�Ɠ������B�����ŕ��}�ȓ����ł���B�@
����ɑ��A�T��(�Ă�)�i��S�j���������킸�ɏ�r���R����ƁA�������Əo�čs�����B
���̎��S��a���͂ɂ�������āA
�u����̓C�R�ɂ��Ă��ꂽ���v
�Ɖ]���ēT��(�Ă�)�i��S�j�́w�����ʒq�x�̃n�^���L��F�߂��̂ł���B�@
�������ăC�R�i��S�j�͑�C�R�̊J�R�ƂȂ����B
�u�]���v�ł́A
�C�R��S�͂������Ĉ���̗E���N���A
��r���R������͎̂��ɗ��h�ł��邪�A�S��̎d�|����㩂ɂ͂܂��č��i�Ƃ����i�D�ɂȂ����B
�������A�悭�l���Č���A
�ނ͋C�y�Ȗ�ڂ��~�߂Ĉ�R�̏Z���Ƃ����d���Ė��Ȗ�ڂ������錋�ʂɂȂ����̂��B���̂��낤���H
�ނ͓����甫������苎���Ă���A�S�̞g(����)��Ƃ߂�悤�Ȃ��ƂɂȂ����̂���
���O�ɃC�R��S�̐[�����S��J�ߏグ�Ă���B�@
�u��v�ł́A�(����)�₵������ȂǑ䏊��������o����
�ƌ����̂̓C�R���T��(�Ă�)�̖�E���~�߂����Ƃ��Ӗ����Ă���B
�C�R�͐����悭��r���R���������ǂ��A�N���C�R�a�����S�����邱�Ƃ��ł����C�R�̓ƒd�ꂾ�����B
�S��͏d�ցi���j��݂��Ĕނ��S�����悤�Ƃ����̂����C�R�͂���ɍS�����ꂸ�A
���̑��悩���������������ɔ�яo�����C�R�̎��݂ȃn�^���L��J�ߏグ�Ă����B
�C�R��S�͕S��T�t�̖����đ�C�R�ɑT������J�����B
�ނ͓�����J���Ă��Ă��~�����A�a�������Ă��A���N�Ԃ�����l�ō��T�ɑł����B
���ꂪ��ɂ��P�C�T�O�O�l���̏C�s�m��L����哹��ɔ��W�����Ɠ`������B
����͓������������l�Ԃ̒��g���厖���Ƃ������Ƃ������Ă���B
�S�O���͂P�A�R�A�P�S�A�R�V�A�S�R���Ɨގ����ʂ����u�����ʒq�v�Ɋւ�����Ăł���B�@
��g����ւ��D�P�T�U�`�P�T�W
�{���F
�B���ʕ�(�߂��)���B��c��ɗ��B�](�Ђ�)��f���ĉ]���A
�u��q�͐S���������炸�B��A�t���S�����߂��v�B
���]���A�u�S����(��)������A�����ׂɈ����v�B
�c�]���A�u�S���K(���Ƃ�)�ނ�ɗ�(��)�ɕs���Ȃ��v�B
���]���A�u�����ׂɈ��S���K(����)����v�B
�]���F
�P�b��(������)�̘V��(�낤��)�A�\�����̊C���q���ē���(�Ƃ��Ƃ�)�Ƃ��ė���B
��(����)�ׂ����ꕗ�����ɘQ(�Ȃ�)���N�����ƁB
����(�܂�)�Ɉ�ӂ̖�l��ړ�(���Ƃ�)���āA���p(����)���ĘZ���s��B
�C�C(����)�B�ӎO�Y(���Ⴓ�Ԃ낤)�l�������炸�B
��F
����(�����炢)�̒��w(������)�A���͏�(���傭)����Ɉ����ċN����B
�p�т��j���E��(�ɂ傤����)����́A����������B
���F
�B���F�@���B���BBohdi-dharma�̉��ʁB�Â��͒B���Ə����B
���v�N�ɂ��ẮH�`�S�X�T�A�H�`�S�R�U�A�H�`�T�Q�W�Ȃǂ̏���������x�[���ɕ�܂�Ă���B
�����T�̏��c�Ƃ����B
��c�F�@�d��c�T�t�i�S�W�V�`�T�X�R�j�B�@��̑T�ҁB
�B���T�̐^���đT�@���c�ƂȂ�B
�c���͐_���ŁA�l�\�˂̎��A���R�ɒB����K�ˁA
�{���ɐ����ꂽ�悤�Ȏ������������Ƃ���Ă��邪�A
����ɂ͗c���A���ɏP���č��]���ꂽ�Ƃ������Ă���B
�P�b���i�������j�̘V�ӁF�B���̂��ƁB
�B���͕�x�Ȃǂɑ��܂�A�����ΓŎE����悤�Ƃ����B
���̂��߁A���������������Ƃ����`��������A�u�P�b���̘V�Ӂv�ٖ̈������B
�����Ƃ��āF�킴�킴�B
�C�C�i�����j�F�l���������蒍�ӂ𑣂����ɔ�����吺�B�₢�I�B�܂������܁B
�ӎO�Y�l�������炸�F�����t���i�W�R�T�`�X�O�W�j�͑����ӎ��̎O�j��
�u�ӎO�Y�v�ƌĂꂽ�B
�B���͕������m�炸�K�̏�̎l�������ǂ߂Ȃ�����
�Ƃ����̎��Ɉ���ŒB�������Ȃ��J�߂Ă���B
�p�сi�������j�F�T�����߂Ďt�̉��ɏW�܂�C�s�ҒB�̋��������W�c�B
���i�ɂ傤���j����F�@��������B���f��������B�@
�{���F
�B�����ʕǂ��č��T���Ă����B
��c�d�͐�̒��ɗ����s�����]��藎�Ƃ��ĉ]�����A
�u���̐S�͖����s���ł��B�ǂ����t��A���S�����ĉ������v�B
�B���͉]�����A
�u�s���̐S�������Ɏ����ė��Ď����Ȃ����A���������炨�O�ׂ̈Ɉ��S�����Ă�낤�v�B
��c�d�͉]�����A
�u�s���̐S��T���܂������A�ǂ����Ă��͂ނ��Ƃ͂ł��܂���ł����v�B
�B���͉]�����A�u���O�ׂ̈ɂ������S�����I��������v�B
�]���F
�����������V�B���́A�\�����̊C���z���ăC���h����킴�킴����ė����B
����͂܂�ŕ��̖������ɔg���N�������悤�Ȃ��̂��B
���ʑO�ɂ悤�₭�k�@�̖�l�����A�ނ����Z���s��̒j�������B
�₢�A�ӎO�Y�I �������m��Ȃ��ꂳ���B
��F
�C���h����u���w�l�S�A���������v�̋�����
�`��������ɁA���f�������A���ł��T�т𑛂����Ă���B
������A�F�������ǂ���O����̂�������B
�@�{���͒����T�̏��c�B���Ɠ�c�d�̖ⓚ���ނɂ��Ă���B
�B���͓�C���h�̐l�łT�Q�O�N�ɒ����ɓn�����A�T�Q�W�N�Ɏ��₵���ƌ����邪�ڍוs���̐l���ł���B
�B���̑T�ɂ��Ắu����l�s�_�v���L���ł���B
(���B���Ɓu����l�s�_�v���Q�� �j�B�@
��c�d�i�S�W�V�`�T�X�R�j�͑�����_���ƌ����B
�_���͓�����̊O�召��̕������������߂��w�҂ŁA�B����t�ɎQ���Ă��̖@���k�����B
�B���̓C���h����n�����Đ��R�̏��ю��ɑ؍݂��āA
�����ʕǂ��ĂЂ����獿�T�����Ă����B�����_�����K�˂ė����B
�Ⴊ����ɍ~�銦�������������B���͐_���ɓ����������Ȃ������B
��̒��ɂ����Ɨ����Ă���_���ɁA�B����
�u�����͐��Ղ����u�ł͓�������̂ł͂Ȃ��B�����A���v�ƌ������B
�_���͎v���]���Đ��ɍ����]��f�����ĒB���ɍ����o���A
�Ȃ鋁���S�ƌ��ӂ��������B
����Ő_���͂悤�₭�B���̒�q�Ƃ��ē����������ꂽ�Ɠ`������B
����Ɠ����Ɍd�̖��O��^�����B���̎w���̉��ɏC�s����B
�������A�����獿�T�C�s�ɑł�����ł��A
���܂ł̊w����v�z���ז����ĂȂ��Ȃ����S�����̋��n�Ɏ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�S�͂�����^���Â̂܂܂ł������B
�v���]�����d�͒B���Ɂu���͖����ǂ����Ă����S�ł��܂����B
�ǂ�����������S�ł���悤�ɂ��w���������v�ƌ������B�@
�B���́A�u�������A����Ȃ�A���̕s���̐S�������ė����B
������������S�����Ă�낤���v�Ɠ������B
�d�͒B���́u�s���̐S�������ė����v
�Ƃ������t����|�����S�s�����A�u�s���̐S�v��T�����߂��B
�������A������l���Ă��T���Ă��u�s���̐S�v�͌�����Ȃ��B�@
�S����|����Ȃ��^���ÂȐ��_��ԂɂȂ����Ǝv����B
���Ƃ��������悤�ƁA���T�ɐ�O�A�W����������������A
���͂�A�u�s���̐S�v���ǂ��ɂ��������ƂɋC�t�����B
�{���������̂�L��̂��Ɩϑz���ď���ɋꂵ��ł����̂��Ɩڊo�߂��̂ł���B
���Ƃ��������悤�ƁA���T�ɐ�O�A�W�������������ʁA���̊Ԃɂ��A
�d���^���Èł̐S����w����S�Ƒ���y�̐^���Ԃ̐��E�x�i���{������S�����N�Ȕ]�F���j�x�ɖ��o�Ă����̂ł���B�@
�����Ōd�͒B����
�u�s���̐S��T���܂������@����Ȃ��͉̂����ɂ�����܂���ł������v
�Ɠ������B
�B���̓j�b�R�����āu�s���̐S���ǂ��ɂ��Ȃ����Ƃɂ���ƋC�t�������B
���ꂪ�{���̈��S����Ȃ����v�ƌ����d�̋��U���������B
�d�͍��T�C�s�ɐ�O�W���������ʁA
�d�͑�]�V�玿���琶�܂�镪�ʈӎ���X�g���X��Ős��
���w���ӎ��]�i�������ʒq�̖{�́j���S�́w����S�Ƒ���y�̐^���Ԃ̐��E�i���{������S�j�x�ɓ��B���Ă����̂ł���B�@
���ꂪ���炬�̐S�������I�ȐS�ł���ƋC�t���A���łɁA���S�����̋��n�ɓ��B���Ă����̂ł����B
(�T�ƑT��̔]�Ȋw���Q�� �j�B
���ꂪ�_���d�̌��i�������j�ł������ƍl������B
�u�]���v�ł́A
����͒B�����u�����������V���ڂ�e��v�Ɣl�|���Ă���悤����
���̒B����䅓�h�ꂵ�ĉ��H�C���h���痈�Ă��ꂽ���A��
���`�̑T��m�邱�Ƃ��ł����Ɛe���݂ƌh���̐S�����߂ČĂ�ł���̂ł���B
�ނ͕����������ɔg���N�����悤�ȗ]�v�Ȃ��Ƃ����Ă��ꂽ�ƌ����ĒB����t����Ă���B
�������A����͑T�@���L�́u���Ȉӗg�̕\���i���t���Ȃ��ĐS�ł͖J�߂�\���j�v�ł���B
�Ō�̏��Ŗ�l�d�Ė@��`���邱�Ƃ��ł������A
�ނ������������B�����l�Z�����s���S�ł������ƌ����Ă���B�@
�Ō�́u�ӎO�Y�l�������炸�v�ƒB���Ɠ�c��l�|���Ă���B
�������A����͔���I�\���ŁA
���ʒq��ے肵�T�́u�����ʒq�v�������グ�Ă���ƍl���邱�Ƃ��o���悤�B
�T�ł͊w����v�z��薳���ʒq���l��]������B
����͘V�q���������ׂ���̎v�z�̉e�����ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�u���v�ł͒B����t���C���h���璆���ɓn������
�u�s�������A���w�l�S�A���������v�Ƃ����ʓ|�ȋ�����`��������ɁA
�����e�n���T���ꂪ�ł��āA�����C�s�̂��߂̏W�c�����𑛂����Ă���B
��������𐳂��Γ�B�������{�l���ƒB����t���������낵�Ă��邪�A
������u���Ȉӗg�̕\���v�ł���B
��g����ւ��D�P�T�X�`�P�U�R
�{���F
�́A���݂ɕ���(����)�A�����̏W�܂鏈�Ɏ����ď����e�X�{��(�ق�)�Ɋ�(����)��ɒl���B
�҂���l�̏��l(�ɂ�ɂ�)�L���Ĕނ̕���(�Ԃ�)�ɋ߂Â��ĎO��(����܂�)�ɓ���B�@
����T�����ɔ������A�u�]�������l�͕����ɋ߂Â����Ƃĉ�͓������v�B�@
������ɍ����A�u��A(��)�����̏����o(����)���āA�O�����N�����߂āA��������V��₦�v�B
����A���l���߂��邱�ƎO�\�E(����)�A�w��炷���ƈꉺ(������)���āA
�T(���Ȃ�)����(����)���Ğ��V(�ڂ�Ă�)�ɑ��̐_��(����肫)��s�������o�����Ɣ\�킸�B�@
�����]���A�u���g(����)���S��̕�����������̏��l�����o�����Ƃ��B
�����\�͍�(������)�̍��y���߂���㦖���F(�����݂傤�ڂ���)�����B
�\�����̏��l�����o�����v�B
�{�k(�����)��㦖���m�A�n���N�o(�䂤�����)���Đ������q���B
�����A㦖��ɒ����B�p���ď��l�̑O�Ɏ����Ďw��炷���ƈꉺ���B
���l��(����)�ɉ����Ē���o���B�@
�]���F
�߉ޘV�q�A��(��)�̈��̎G��(��������)���(��)���B����(���傤���傤)��ʂ����B
��(����)����(��)���A����͐��ꎵ���̎t�A
�r(��)��Ɉ�(��)���Ă����l�����o�����Ƃ���B
㦖��͏��n(���傶)�̕�F�A�r(��)��Ƃ��Ă��p(����)���Ē���o��������B
�@�Ⴕ�җ�(�����)�Ɍ������Č���(����Ƃ�)���e�Ȃ�A
�Ǝ��Z�Z(���������ڂ��ڂ�)�Ƃ��ēމ����Ȃ��B�@
��F
�o��(������Ƃ�)������o�s���Ȃ���A��(����)�ƙN(���)�Ǝ��R����B
�_��(����)�Ȃ�тɋS�ʁA�s�(�͂�����)��(�܂�)�ɕ����B
���F
����:�@����t��(Manju-sri)��F���߉ޔ@���̍��ɍ����Ēq�d���i��ō��ʂ̕�F�B
�����ł͌��̒m�b�Ƃ��Ắu�����ʒq�v���w���Ă���B
�O�\�E�i�����j�F�C���h�̗�@�ŁA���҂�K�˂����A���̎�����E���ɂR���邱�ƁB
���V(�ڂ�Ă�)�F�Ñ�C���h�̐��E�ςɐ{��R���E��������B
�{��R���E���ł͐��E�̒��S�ɐ{��R�i������U�S�������j�Ƃ���������ȎR���ނ���B
���̎R�̒���������ɓV��E�����݂���Ƃ����B
�V��E�ɂ͉�����~�E�V�A�F�E�V�A���F�E�V�̎O�E�V������B
�F�E�V�͂P�W�V�ɕ�������B
�F�E�V�ɂ��鏉�T�V�ɂ͞��O�V�A����V�A�垐�V�̎O�V������Ƃ����B
���T�V�̑�O�V��垐�V�Ƃ����B�垐�V�̎傪�u���t�}���i���E�̑n���_�j�ł���B
�Ȃ��A�F�E�V�̍ŏ㕔�̐F����V�ɃV���@�_���Z�ނƂ����B
������ɂ���{��R���E���͌Ñ�C���h�̑z���I���E�ςł���B
�i�{��R���Ɋ�Â����E�̍\�����Q���j�B
�O���i����܂��j�F����samadhi�̉��ʁB�O���n�A�O���n�Ƃ������B
�T��ɂ����ĐS���W�����邱�ƁB
�͍��i������j�F�P�͍��i����������j�̗��B
�P�͂Ƃ̓K���W�X�͂̂��ƁB
�P�͍��Ƃ̓K���W�X�͂̍��̂��ƂŐ��̑������Ƃ�栂���B
�����ł̓K���W�X�͂̍��قǂ̐��ƌ����Ӗ��Ŗ�������\�킵�Ă���B
㦖��i�����݂傤�j��F�F�ʼn��ʂ̕�F�̑�\�B
㦂͖����Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ŁA㦖��Ƃ͖����Ɠ����Ӗ��ł���B
�����ł́A�ϔY�̌��ɂȂ镪�ʒq�i��w�]�����m�]�j���w���Ă���B
���n�i���傶�j�̕�F�F�F�،��o��ʎ�o�Ȃǂɉ����ĕ�F�̋��n�͏\�i�K�ɕ�������B
���̑��i�K�̕�F�̂��ƂŁA���藧�Ă̕�F�Ƃ����Ӗ��B
�����ł́A���ʒq�i��w�]�j���w���Ă���B
�Ǝ��Z�Z�i���������ڂ��ڂ��j�F�O���̋Ƃɂ���ė։��]���̐S�ӎ��ɋꂵ�ނ��ƁB
�P�b�މ��i�Ȃ��j���F�މ��͞����naga�̉��ʂŗ��̂��ƁB
�މ����́u�嗳�O���v�Ƃł����ō��̎O���̂��ƁB
�G���i���������j�F�v�E����̉����B�u��v�ɏo��_��(����)�ƋS�ʂ͎G���ɗp���鉼�ʁB
�s荁i�͂����j�F���s�B
�{���F
�́A����(����)��F�͏������u�b�_�̏��ɏW�܂�����A
�Ăт��ꂼ��̋��ꏊ�ɋA�҂��čs�����ɏo������B
�Ƃ��낪�A������l�̏������̓u�b�_����O�ŎO��(����܂�)�ɓ��葱���Ă����B
�����ŕs�v�c�Ɏv��������̓u�b�_�ɕ������A
�u�ǂ����Ă��̏��͂��Ȃ��̋��鏊�ɋ߂Â����Ƃ��ł��āA���͂ł��Ȃ��̂ł����H�v�B�@
�u�b�_�͕���Ɍ������A
�u�O�����̏����O�����o(����)���Ď����ł��̗��R���悢�v�B
�����ŕ���͏��̎�����O�x����āA�w���p�`���Ɩ炵�āA
���̏�����̏�̍ڂ��ēV��E�ɏ������B
�����Đ_�ʗ͂�s�����������̏����O������o�����Ƃ��ł��Ȃ������B�@
�u�b�_�͉]�����A
�u���Ƃ��P�O���l�̕��ꂪ�������Ă����̏����O�����o�����Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B
������艺�̕��\�͍��̖����̍��y���߂�������㦖���F�Ƃ�����F�������B
�ނȂ���̏������O�����o�����Ƃ��ł��邾�낤�v�B
�u�b�_�������I���₢�Ȃ�㦖���F���n�����N���o��悤�ɏo�����ău�b�_���q�����B
�u�b�_���������o���悤�ɖ������㦖���F�͏��̑O�ɍs���Ďw���p�`���Ɩ炵���B
����Ə��͂悤�₭�O�����o���̂ł���B
�]���F
�߉ޘV�q�A�܂����ƌ����c�Ɏŋ��������Ă����B
����͕��ݑ��̂��Ƃł͂Ȃ���B
����ł͉��������Č��Ȃ����A
�����̎t�ƌ����镶���F�͂ǂ����ď������o�����Ƃ��ł����A
�V�Ă�㦖�(�����݂傤)��F�̕����A�������ď������o�����Ƃ��ł����̂��낤���H�@
�Ⴕ���̏����͂�����ƌ��������Ƃ��ł���Ȃ�A
�ߋ��̈��Ƃɂ����������邱�ƂȂ��A
�嗳�O���̂悤�Ȑ[���O���ɓ��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
��F
���l��肩��o�����Ƃ��o����̂��o���Ȃ��̂��A����������h�ȃn�^���L���B
������_�̂��ʂƋS�̖ʂ��g�����G���̂悤�Ȃ��̂ŁA���s����قǖʔ���
�{���̓��e�͎����̂悤�ł���B
�́A�����F�͏��X�̕��B�������i�u�b�_�j�̏��ɏW�܂�����A
���U���Ă܂����ꂼ��̋����ɋA���čs���Ƃ���ɏo���킵���B
�Ƃ��낪������l�̏������������̍��̋߂��ł��̂܁T�O���ɓ��葱���Ă����B�@
�����ŕ���̓u�b�_�ɁA
�u�ǂ����Ă��̏��͂��Ȃ��̋��鏊�ɋ߂Â����Ƃ��ł����A
���͂ł��Ȃ��̂ł����H�v�ƕ������B
����ƃu�b�_�́A
�u���O�����̏����O������Ăъo�܂��āA�����ŕ����Ɨǂ��v�ƌ����B�@
�����ŕ���͏��̎�����O�x���A�p�`���Ǝw���C���Ė炵�A
���̏�����ɍڂ��ēV��E�ɏ���A
�_�ʗ͂����W�����낢��Ǝ��݂邪����肩��o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B
���̎��u�b�_�͌������A
�u���Ƃ��S��̕��ꂪ�͂����킹�Ă��A���̏���肩��o�����Ƃ͂ł��܂��B
������艺�̕��P�Q���P�͍��i�����j�̍��y���߂�����������㦖���F�ƌ�����F�������B
���̕�F�Ȃ�Ώ���肩��o�����Ƃ��ł���ł��낤�B�v�@
���̏u�ԁA㦖���F���n���N���o�āA�u�b�_�ɑ��Đ[�X�Ɨ�q�����B
�����Ńu�b�_��㦖���F�ɖ��߂���ƁA
㦖���F�͏��̑O�ɍs���ăp�`���Ǝw��炵���B
���̎����͂悤�₭����o���̂ł���B
���̌��Ă͔]�Ȋw�̎��_�ɗ��Ɩ����ɐ������邱�Ƃ��ł���B�@
�����F�͍ō��ʂ̕�F�Ő�Ε����́u�����ʒq�v���������Ă���B
(�����ʒq�ɂ��Ă͕��̒q�d�������ʒq�A�����ʒq���Q���j�B
����ɑ��A㦖���F�͍ʼn��ʂ̕�F�ł��邩�疢���u���ʒq�v���������Ȃ��B
���l�͕��ʂ̐l�Ԃł���A������u���ʒq�v���������Ȃ��B
�����A�����F�́u�����ʒq�v�̎�̂ł��鉺�w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j��\�킵�A
㦖���F�Ə��́u���ʒq�v�̎�̂ƂȂ��w�]�i��]�O���t����Ƃ������m�]�j
��\�킵�Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�@
�����F�́u�����ʒq�v���J�����������Ă�����F�ł��邩��
���ӎ��]�ł��鉺�w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�������ɓ����Ă���B
����ɑ��A���ʒq��̂�㦖���F�Ə��l��
���ʈӎ��]�ł�����w�]�i��]�O���t�j�������ɓ����Ă���B�@
�����Ŏ��̂悤�Ȃ��Ƃ��l����B
�C�D �����ʒq���番�ʒq�ւ̓��������͒ʂ��Ȃ��B
���D ���ʒq���番�ʒq�ւ̓��������͒ʂ���B
���ʒq�͐����E��\�킵�Ă���ƍl����Ε�����B
�C�D�̖����ʒq���番�ʒq�ւ̓��������͒ʂ��Ȃ����R�Ƃ��āA
�����ʒq�͈̑�Ȍ��̒q�d�ł��邪��͖̂��ӎ��]�ł��邩��
���ʒq��̂̑��l�ɂ͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ��i�ʂ��Ȃ��j�ƍl����Ηǂ��B
���̂��߁A�����F�͏��l�����o�����Ƃ��ł����A
���n��㦖���F�̕����������ď��l��肩��o�����Ƃ��ł����̂ł���B
����ł͕��ꂪ�u�b�_�Ɍ���������A
�u�ǂ����Ă��̏��͕����ɋ߂Â����Ƃ��ł��A���ɂ͂��ꂪ�ł��Ȃ��̂ł����H�v
�̉͂ǂ��l����Ηǂ����낤���H
������]�Ȋw�I�ɍl����Ύ��̂悤�ɂȂ�B
���l�i���l�j�͌��ݖ����ʒq���J�����������邽�߁A
�ꐶ�����C�s���ĕ����ɋ߂Â�����Ƃ���ł���B�@
����ɑ��A����͎����̎t�ƌ�����悤�ɖ����ʒq���J�����������Ă�����F�ł��邩��A�C�s�͊��Ɋ������Ă���B
���X�A�����ɋ߂Â��Ȃ��Ă��������̂��̂ƌ����ėǂ��B
���̂悤�ɍl����ƁA����͕����ɋ߂Â��Ȃ��ėǂ���
���l�i���l�j�͈ꐶ�����C�s���ĕ����ɋ߂Â��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă��邱�Ƃ�������B�@
�u��v�ł͖����ʒq�ƕ��ʒq���D�萬�����E���G���i�v�E����̉����j��栂��Ă���B
�G�������ɂ͐_�̖ʂ�S�̖ʂ�p����B
����Ɠ����悤�ɐl�͕��ʒq�△���ʒq��p���Đl������������B
���ʒq�Ɩ����ʒq�͈ꕧ���i�]�j�̗����ʂł���v�X�����h�ȓ����̏�������Ă���B
���̌��Ă̎G���ł͕��ꂪ㦖���F�ɕ������B
��l�i�����F�j���q���i㦖���F�j�Ƒ��o���Ƃ��āA��l���q���ɕ������悤�Ȃ��̂��B
������Ǝv��Ȃ��������ꂪ�\�z�ɔ����Ďq���̂悤��㦖���F�ɕ������̂�
���̎ŋ��͖ʔ����Ɖr���Ă���B
���̌��Ăɂ��čb��̓V�ޑc�őT�t�i�P�U�U�V�`�P�V�R�P�j�͎��̉̂��r���Ă�����Ƃ̂��ƁB�@
�߉ޔ@���A����㦖������A��Ă��ꂩ�炻��Ɛ[�R�̉�
���̉̂��߉ޔ@���͔]�S�́A����͉��w�]�A㦖��͏�w�]��v�X�\�킵�Ă���ƍl����ƁA
�u���w�]�Ə�w�]���琬��S�]�̃n�^���L�ɂ���āA���܂��炫�ւ�[�R�̉ԁX�̂悤�ȑf���炵�����E���W�J���Ă����v
��
���w�]�Ə�w�]�i���S�]�j�����N�ŃC�L�C�L�Ɠ������̐��E���r���Ă��邱�Ƃ�������B
���̌��Ă͌��̒q�d�ł��������ʒq�����łȂ��A���ʒq�̏d�v�����w�E���������ƌ�����B
�����ʒq�̎�̂ƂȂ鉺�w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j�����łȂ��A
���w�]�ɕ��ʒq�i���m���j�̎�̂ƂȂ��w�]�i�����m�]�j���������S�]�̓����̏d�v�����w�E���Ă���B
���̓_�A���ʒq�i�����m���j���y���������ȑT�@�ɂ����āA���قȌ��Ăƌ����邾�낤�B
��g����ւ��D�P�U�S�`�P�U�U
�{���F
��R�a���A�|��(������)��_���ďO�Ɏ����ĉ]���A
�u���l�A�Ⴕ��(��)��Œ|�͂ƍ�(��)���Α����G(��)���B
�@����Œ|�͂ƍ삳����Α����w(����)���B
�����l�A���������A����Őr��(�Ȃ�)�Ƃ��삳���H�v
�]���F
����Œ|�͂ƍ�(��)���Α����G(��)��B�@
����Œ|�͂ƍ삳����Α����w(����)���B
�L��Ȃ邱�Ƃ��A����Ȃ邱�Ƃ��B
�����ɓ�(��)���A�����ɓ�(��)���B
��F
�|�͂�_�N(�˂�)���āA�E(����)��(��������)�̗߂��s���B
�w�G��y(�͂����傭������)�A���c����(�߂�)����B
���F
��R�i���ゴ��j�a���F�@��R�ȔO�i�X�Q�U�`�X�X�R�j�B�k�v�̑T�ҁB
���������i�W�X�U�`�X�V�R�j�̖@�k�B�@�،o�ɐ��ʂ��u�O�@�v�ƌĂꂽ�B
�@�n�F�Սϋ`����������������@�d�M���E��������������R�ȔO
�|�́i�������j�F�@�t�Ƃ��C�s�m��ړ��E�w�����邽�߂̓���B
����|���|��ɋȂ��ق���������h���č��B�����͂U�O�����`�P���ł���B

�}�P�S�D�|��
�@��y�i�������j�F�x�n�Ȃǂ�����ŋ삯�����邱�ƁB
�w�G��y�i�͂����傭�������j�F�w�i�w�����Ɓj�ƐG�i�����邱�Ɓj�Ƃ����������ł��邱�ƁB
�{���F
��R�a���͒|(����)��(��)�����o���ďC�s�m�B�Ɏ����ĉ]�����A
�u���O�B�A���������|�͂Ɗ�(��)�ׂΖ��O�ɑ����邱�ƂɂȂ��B
�|�͂Ɗ��Ȃ���Ζ��O��ے肷�邱�ƂɂȂ��B
�����A���O�B�A��������Ɗ��Ԃ������Ă݂��v�B
�]���F
���������|�͂Ɗ�(��)�ׂΖ��O�ɑ����邱�ƂɂȂ�B
�|�͂Ɗ��Ȃ���Ζ��O��ے肷�邱�ƂɂȂ�B
����Ă������Ȃ����A�ق��Ă����߂��B�������������A���������B
��F
��R�a���͒|�͂����o���āA
���ʈӎ���|�����u�{���̎����v�������邽�߁A
����悤�Ȃ����߂��o�����B
�ے���m����ł��Ȃ�����O�ɂ��āA�������̕��c����������邾�낤�B
���̌��Ă͂Q�S���ƂR�U�A�S�O���ɗގ��������Ăł���B
�|�͂�|�͂ƌ���͈̂�ʂ̖}�v�̌����ŁA�}���ł���B
�������A��W���ł��q�ׂ��悤�ɑ�敧���̊�{�I�����͋�ςł���
(�u��Ƌ�ρv�ɂ��Ă͒��ϕ������Q��)�B
��ςł́A��̑��݁E���ۂ͈����i�����j�ɂ���Ă��̂悤�ɑ��݂��邾���ŁA
���̈����i�����j�����ŁE�ω�����ɂ���Ă��̑��݂����ŁE�ω�����B
������u���������̖@�͋�ł����v�ƌ����B�@
�]�����ۂ����̂悤�ȋ�I���ی�����B
�T�ł͖����ʒq�̎�̂ƂȂ鉺�w�]�i�]���{��]�Ӊ��n�j���Ε����̖��̐��E�ƌ����B
���w�]�i���]���{��]�Ӊ��n�j�͖��ӎ��]�Ȃ̂Ő�Ε����̖��̐��E���ƌ����Ă��ǂ����낤�B
����ɑ����ʈӎ��̎�̂ł����w�]�i��]�V�玿�A���m�]�j�͕��ʍ��ʂ̐��E�ł���B
�|�͂Ƃ������O��t�����̕��ƕ��ʍ��ʂ���̂�
���̏�w�]�i��]�V�玿�����m�]�j�̃n�^���L�ł���B�@
�{���ł͒|�͂ƌĂׂΕ��ʈӎ��i�}���j�ɑ����邱�ƂɂȂ�B
������ƌ����Ē|�͂łȂ��Ɣے肷��ΐ�Ζ��̒��ق̐��E�i���w�]�j�ɗ������ށB
�|�͂�|�͂Ƃ��闧��͑�R�V���́i��̗���j�ɑΉ����A
�|�͂�|�͂Ƃ��Ȃ�����͑�R�V���́i�ق̗���j�ɑΉ����Ă���B�@
���̓�̗���ȊO�ɂ���O�̗��ꂪ�l������B
�|�͂�|�͂Ƃ��闧��i��̗���j�ƒ|�͂�|�͂Ƃ��Ȃ�����i�ق̗���j
�̂ǂ���ɂ��S��Ȃ���O�̗���ł���B
���̎O�̗���������̕\�V�ɂ܂Ƃ߂�B�@
�\�V�|�͂ɑ���O�̗���̕���
| ���� | �|�͂Ɗ��Ԃ��ǂ��� | �ӎ��Ɣ] | �ꂩ�ق� | �L�ꂩ���ꂩ |
|---|---|---|---|---|
| �@ | �|�͂Ɗ��� | ���ʈӎ��i��w�]�j | �� | �L�� |
| �B | �@�ƇA�̗���ɑ����Ȃ� | |||
| �A | �|�͂Ɗ��Ȃ� | ���ӎ��i���w�]�j | �� | ���� |
����@�͒|�͂�|�͂Ƃ���u��̗���v�ɑΉ����}�v�̌����ł���B
����A�͒|�͂�|�͂Ƃ��Ȃ��u�ق̗���v�ɑΉ�����Ζ��ɗ������ށB�@
����A�͌��̐S�ɒʂ���ʂ����邪����Ɏ�������A
�n�^���L�̂Ȃ����ق̐�Ζ��ɗ������ށB
����͈��̑T�a�ł�����B
�{���Ŏ�R�a���͂����ǂ�����Ɖ�X�ɔ����Ă���B�@
��R�U���ɉ����Čܑc�@���́u��ق������đ�����v�ƌ����Ă���B
����͗���@�Ɨ���A�̂ǂ���ɂ��S�邱�ƂȂ����݂ɍs���Ƃ����Ӗ��ł���B�@
�\�V�ł͇B�̗���ɑ������鎩�R�ȗ��ꂾ�ƌ�����B�����}�P�S�Ő������悤�B
���ʂ̘_���ł͗���@�Ɨ���A�̂ǂ��炩�ł���B�`�ł��邩��`�ł��邩�̂ǂ���ł���B�@
�A���X�g�e���X�̘_���w�i���Ă̘_���j�͂��̓I�_���ł���B
����͐}�P�S�̂����̐��A���Ŏ����B�@
�@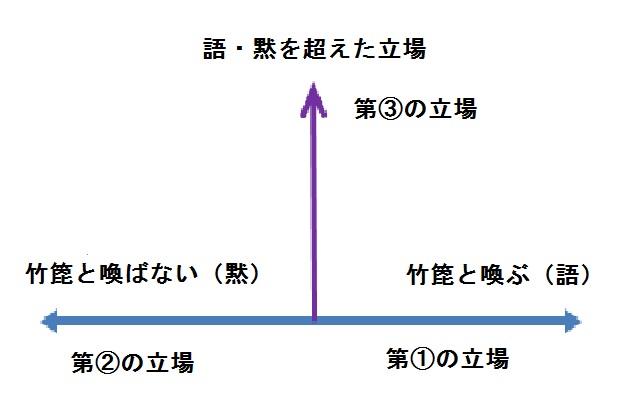
�}�P�S�D��E�قɍS��Ȃ���R�̗���@
��B�̗���͂`�ł��Ȃ���`�ł��Ȃ��o��̘_���i�l��_���A�Q�T���Q�Ɓj�ɗ����Ă���B�@
(�l��_���ɂ��Ắu�Q�T���Q�Ɓv���Q��)�B
���̗���̓A���X�g�e���X�̓I�_�������_���ŁA
�}�Ɏ������悤�ɁA�����ɐ����Ȏ��Ŏ������Ƃ��ł���B
���̗���͓I�_�������O���I�_���ƌ����邾�낤�B�@
���ꂪ�T�̖����ʒq�i���q�j�ƌ����Ă悢���낤�B�@
��S�O���ɂ����āA�S��a������r��n��ɒu���āA
�u�������r�ƌĂ�ł͂Ȃ�Ȃ��B�����A���O�B�͂�������ƌĂԂ��H�v
�Ǝ��₵�����A���(���セ)�́A
�u�܂����ؕЂƌĂԂ킯�ɂ������܂����v
�Ɠ������B�@
���ɕS�䂪�C�R(������)�Ɍ���������
�u���O�͂ǂ������v�ƕ��������A
�C�R�͒����ɏ�r���R����ďo�čs�����B�@
���̃C�R(������)��S�̓�������ق�����B�̗��ꂾ�ƌ����ėǂ����낤�B�@
���̌�ق��������ʒq����`���`�Ƃ������ʈӎ�����������ƍl����ƁA
��ق�����B�̗���́A�u�����v�����ꂾ�ƌ����ėǂ����낤�B
��g����ւ��D�P�U�V�`�P�U�W
�{���F
�m�Ԙa���A�O�Ɏ����ĉ]���A
�u���ɃV����q(���ザ�傤��)�L��Ή���ɃV����q��^�����B
���ɃV����q������A������V����q��D����v
�]���F
�}(����)���Ă͒f��(���傤)�̐����߂��A��(�Ƃ���)���Ă͖����̑��ɋA��B
�Ⴕ��(��)��ŃV����ƍ삳�A�n���ɓ��邱�Ɛ�(��)�̔@���Ȃ��B
�B�@
��F
�����̐[(����)�Ɛ�(����)�ƁA�s(����)�ď���(���傤����)�̒��ɍ݂�B
�V�����������тɒn���T�T(����)���āA�����ɏ@����U�邤�B
���F
�m�Ԙa���F�@�m�Ԍd���T�t�B�V���i���N�j�̐l�B����̑T�ҁB
�C�@�̑�O���쓃���N�i�W�T�O�`�X�R�W�j�̖@�k�B
���v�N�s���ł��邪�㐢�I�Ɋ����l���ƍl������B
�@�n�F�C�R��S���R�d��쓃���O���m�Ԍd��
�V����q�i���ザ�傤���j�F�@
�C���h�ɂ����ĘV�l��a�l���g�̂��x�����Ƃ��ėp�����B
�����ł́u�{���̖ʖځi�����A�^�̎��ȁj�v�Ƃ��Ă̔]��g���Ă���B
�{���F
�m�Ԙa���͏O�Ɏ����ĉ]�����A
�u���O�B�ɃV����q(���ザ�傤��)���L�����Ȃ�A���͂��O�ɃV����q��^���悤�B
���O�ɃV����q��������A���͂��O�̃V����q��D�����v
�]���F
���̖������n�鎞�ɂ͏����ƂȂ�A���̖����Ŗ�ɂ͑��ɋA�锺������B
�Ⴕ������V����Ɗ�(��)�ԂȂ�A��(��)�̂悤�ɒn���ɗ����邾�낤�B
�B�@
��F
�T�m�̋��n�̐[��͑S�ď�����������̎�ɂ���̂��B
�ނ̏�͓V�n���������āA�����ɂ��̎��͂�U����Ă���B
�V����q(���ザ�傤��)�Ƃ͑T�m����������ł��邪�A
�T�ł�����₻�̖{�̂ł��鉺�w�]���S���]�i�����A�^�̎��ȁj���ے��I�ɕ\���Ă��Ă���B�@
�����͔]��]�@�\���������Ă��Ȃ������̂ŁA�V����q�ł�����ے��I�ɕ\�킵���̂ł���B�@
�]���āA�{���̔m�Ԙa���̌��t�u���ɃV����q���L�����Ȃ�A���͂��O�ɃV����q��^���悤�B
���O�ɃV����q��������A���͂��O�̃V����q��D�����v����Ղ��A�@
�u�����A���O�B�����Ƃ����V����q�������Ă���Ƃ����ӎ����L��Ȃ���A
���͂��O��{���̃V����q�łԂ�Ȃ����Ă�낤�i�V����q��^���悤�j�v�B
�������O���w���̃V����q�������Ă��܂��Ƃ������悤���A
����ȉ���킵���ӎ��Ȃ����Ƃ����Ɏ̂ĂĂ������炩��i��j�ɂȂ��Ă��܂����x
�ƌ����Ȃ�A
�X�ɂ��̉��������Ƃ����̈ӎ������������O��I�ɒD���Ă��܂����v
�ƌ����Ă���̂ł���B�@
�u�]���v�ł́A
�u���̃V����q�i�]�j�����L��A����ɏ������ċ��̖������n�邱�Ƃ��ł����B
�܂����̃V����q�i�]�j�����L��A�^���ÂȈŖ�ł����A�Ŗ������ɋA���čs�����Ƃ��ł����B
�@��������i�]�j���V����q�Ɗ�(��)��Ŏ�������Ȃ�A��(��)�̂悤�ɒn���ɗ����邾�낤�v
�ƌ����Ă���B �@
�@�u���v�ł́A
���̃V����q�i���]�j�����L��A
�����̓���ɂ���t�Ƃ�T�m�̌��̋��n�̐[���S�ď����ɂ���悤��
�͂����茩�������Ƃ��ł���B
���̃V����q�i�������A���N�Ȕ]�j�͕��@�̓V�n���x���A
�����ɕ��c���`�̑T�������g�����̎��͂�U����Ă���ƁA
�V����q�i�������A���N�Ȕ]�j�̎��R���݂̃n�^���L���]�����Ă���B�@
�u�Ɋޘ^�v�̑�U�O���ɂ́u�_��V����q�v�ƌ�������ɗގ��������Ă�����B �@
��g����ւ��D�P�U�X�`�P�V�O
�{���F
���R���t�c(����)�H���A
�u�߉ޖ���(�݂낭)�͗P(�Ȃ�)������ނ̓z�B
���������A�ނ͐��ꈢ�N(����)���H�v
�]���F
���(����)�ނ�����(����Ƃ�)���ĕ���(�ӂ傤)�Ȃ�A
�(����)���Ώ\���X���ɐe��(�����)�ɓ���(�ǂ�����)���邪�@���ɑ������āA
�X�ɕʐl�ɖ₤�Đ�(��)�ƕs��(�ӂ�)�Ɠ�(��)�����Ƃ�{(����)�����B
�B�@
��F
���̋|��(��)�����Ɣ���A���̔n�R(��)�邱�Ɣ���B
���̔�ق��邱�Ɣ���A���̎��m�邱�Ɣ���B
���F
���R���t�c�F�@�ܑc�@���i�H�`�P�P�O�S�j�̂��ƁB�k�v�̑T�ҁB
�ՍϏ@�k��h�A���_��[�i�P�O�Q�T�`�P�O�V�Q�j�̖@�k�B��R�T�����Q�ƁB
�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E���Α��^�~���k�������_��[���ܑc�@���@
���N�i�����j�F�@���͐e���݂����߂��ړ���B�N�ɓ����B
�ނ͐��ꈢ�N���H�F�߉ނ���ӂ̖{�̂Ƃ��Ă̕����i�]�j�͈�̒N���낤���H�Ƃ����Ӗ��B
���Łi�ӂ傤�j�F�͂�����B
�ނ��������ĕ��łȂ�F�ށi�����j���͂����茩��Ȃ�B
�{���F
�ܑc�@���T�t�͉]�����A
�u�߉ނ����(�݂낭)�Ƃ����ǂ��P(�Ȃ�)�ނ̎g�p�l�i�z�j�ɉ߂��Ȃ��B
�ł͔ނƂ͈�̒N�̂��Ƃ��낤���H�v
�]���F
�����ނ��͂�����ƌ��������Ƃ��ł���Ȃ�A���Ƃ��A
���₩�ȊX�̎G�B�̒��Ŏ����̕��e�ɏo������悤�Ȃ��̂ŁA
���ꂪ�����̕��e�ł��邩�ǂ����𑼐l�ɕ����K�v�͖����B
��F
���l�̋|���(��)���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���l�̔n�ɋR(��)���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���l�̔�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���l�̎���m���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@ �ܑc�@���T�t�̎���u�߉ނ����(�݂낭)�Ƃ����ǂ��P(��)�ނ̎g�p�l�i�z�j�ɉ߂��Ȃ��B
�ł͔ނƂ͈�̒N�̂��Ƃ��낤���H�v�ɏo�Ă���ނƂ͒N�̂��Ƃ��낤���H
�����ŔނƂ͎߉ނ���ӂ̖{�̂Ƃ��Ă��������w���Ă���B�@
�ށi�����j�Ƃ͉�X�̈ӎ�����̖{�̂ł���^�̎��ȁi�����w�]�𒆐S�Ƃ����]�j�̂��Ƃł���B
�i��W�́u�T�̍��{�����v���Q���j�B�@
�O���{�����ł��邩��A��X�F�͌��̖{�̂ł���]�������Ă���B�@
����͎߉ޔ@������ӕ�F�Ƃ����ǂ��P(��)���g�p�l�i�z�j�̂悤�Ɏg�����Ƃ��ł����̑�Ȑ��ݓI�\���ł���B�@
���̎�����͂܂��^�̎��ȁi�����w�]�𒆐S�Ƃ����]�j�ɖڊo�߂�̂����ł��茩���ł���B
�@ �{���͎߉ނ���ӂ��g�p�l�i�z�j�̂悤�Ɏg�����̖{�̂ł���^�̎����i���]�j�ɋ^����W��������ɖڊo�߂邱��
�𑣂��Ă���B�@
�@ �u�]���v�ł�
�u�����ށi�]���^�̎��ȁj���͂�����ƒ͂܂����������Ƃ��ł���Ȃ�A
�@ ���Ƃ����₩�ȊX�̎G�B�̒��Ŏ����̕��e�ɏo������悤�Ȃ��̂ł���ƌ����Ă���B�@
�@ ���e�Ƃ͖ܘ_���ꖢ���ȑO�̌Â����j��L�����{���̖ʖځi���]�j
�@ �̂��Ƃł���B
�u���ꂪ�����̕��e�ł��邩�ǂ����𑼐l�ɕ����K�v�������v�ƌ����Ă���B�@
�u��v�ł́@
�@�@ ���l�̋|���(��)���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�@�@ ���l�̔n�ɋR(��)���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�@�@ ���l�̔�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�@ ���l�̎���m���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�Ƒ��l���S����o�Ă��Ă���B
���̑��l�͕��ʈӎ��ɑ�����ꂽ���ȂƑΗ����鑼�l�ł���B�@
���̂悤�ȑ��l�̂��ƂɊS�����ɂȂȂ��B
����Ȏ��Ԃ�����A
�����Əd�v���^�̎��Ȃ̋����i���T�C�s�j�ɓw�߂Ȃ����ƌ����Ă���̂ł���B
�܂��A�u��v�ł�
�����Η��̕��ʈӎ���ϑz���ʂɑ����āA�^�̎��Ȃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɖr���Ă����B�@
��g����ւ��D�P�V�P�`�P�V�R
�{���F
�Α�(��������)�a���]���A
�u�S�ڊƓ��A�@��������i�߂��v
�����]���A
�u�S�ڊƓ��ɍ������(�Ă�)�̐l�A����(�Ƃ��ɂイ)����嫑R(������)�������^�ƈׂ����B
�S�ڊƓ��A�{(���ׂ�)�炭����i�߂ď\�����E�ɑS�g�������ׂ��B�v
�]���F
����i�ߓ��A�g��|(�Ђ邪��)�����A�X�ɉ���̏��������đ�(����)�Ə̂�����B
���̔@���Ȃ��嫑R(������)���A���������A�S�ڊƓ��A�@��������i�߂�B�m(��)�B
��F
����(���傤����)�̊�(�܂Ȃ�)���Ћp(�������Ⴍ)���āA
��(�����)���Ē�Ր�(���傤�傤)��F�ށB
�g���̂Ĕ\�������̂āA��ӏO�ӂ������B
���F
�Α��i���������j�a���F�@�Α��^�~�i�Սω������A�X�W�V�`�P�O�S�V�j�B
����d�J�͐Α��^�~�̋��ڂ̖@���ɂ�����B
�@�n�F�@�Սϋ`���E�E�E�E��������������R�ȔO�����z�P���@���Α��^�~�@
�Ó��F�����i���̂��ƁB
�����i���͓��̖@�k�ŏs��ȋ@�N�Œm���A
�R���盨�咎�ƌĂꂽ�B
�S�ڊƓ��F�P�O�O�ځi�R�O���j�����钷���Ƃ����̐�B���B���ׂ��ɓ_�B
�\�����E�F������k�̎l���ƁA�l�ہi�l���̒��Ԉʁj�ɏ㉺�̏\���ƂȂ�B�@�S��ԁB
�m�i���j�F�V���b�A�Ƃ������B�����A�Ƃ������Q�̐��B
��Ր��i���傤�傤�j�F�V���̞��̋N�_�ɂ��鐯�`�̈�̂��ƁB
���̌y�d�ɊW�̂Ȃ����ʖځB
����i���傤����j�̊�i�܂Ȃ��j�F
���̒��ɂ���Ƃ�����O�̊�B����Ō����Ȃ����E�������Ƃ����B
��ӏO�ӂ������F�u��ʟ��όo�v��
�u��ӂ̐l�F�����邱�Ɣ\�킸�B�O�ӂȂ��Ƃ����ǂ��������邱�Ɣ\�킴�邪�@���v
�����p���Ă���B��ӂ��O�ӂ��悤�ɁA������O�����悤�Ȑl�ƂȂ邾�낤�Ƃ����Ӗ��B
�����ň�ӂ̐l�Ƃ͌��̔��E�L�݂Ȃǂ�����������̂āA
���̖{�̂ł��鉺�w�]�����R�ɂł��邽�{���̖Ӑl�i��債���l�j���w���A
�O�ӂƂ͐��̒��̖{���̖Ӑl�i������}�v�j�B���w���ƍl����ƕ�����Ղ��B
�{���F
�Α�(��������)�a�����]�����A
�u�S�ڂ̊Ɠ��ɍ݂鎞�A�ǂ̂悤�ɂ��čX�Ɉ����i�߂���悢���낤���H�v
���Ó��͉]�����A
�u�S�ڊƓ��ɍ��肱��ł���l�́A�ꉞ�����܂ł��s�����ɂ��Ă������^�̋��n�ł͂Ȃ��B
�S�ڊƓ����炳��Ɉ����i�߂ď\�����E�Ɏ��Ȃ̑S�g�����ׂ����B�v
�]���F
�S�ڊƓ���������i�߂ď\�����E�ɑS�g���ł����Ȃ�A
�����͏ꏊ���ǂ��Ȃ��Ƃ������Ȃ��ƌ����Č����悤�Ȃ��Ƃ����낤���B
���Ƃ������ł������ɂ��Ă��A
�S�ڊƓ�����ǂ̂�ɂ��Ĉ����i�߂���ǂ��������Č���B�����B
��F
����(���傤����)�̊�(�܂Ȃ�)�������Ζ��p�̂��̂ɊႪ����ށB
�g���𓊂��̂ĂĂ����A������O�����l�ƂȂ邾�낤�B
�{���̉��߂ɂ��āA�u�T�̐S�� ����ցv�̒��҈��J���_�V�t��
�T�C�s�ɂ����Čo�������ւ�
�u�S�ڊƓ��v�ƌ������t�ɂ���đT�C�s�҂ɓ`���悤�Ƃ��Ă���̂��Ɛ������Ă���B
���̐����͕�����₷���A�����͂�����悤�Ɏv����B
�T�C�s�̓�ւ�栂�����u�S�ڊƓ��v�ɂ͓��ނ���B
���ȑO�́u�S�ڊƓ��v�ƌ�����ȍ~�́u�S�ڊƓ��v�ł���B
���J���ɏ]���Ĉȉ��ɐ�������B�@
���O�́u�S�ڊƓ��v
�����Ȃ疳���̌��ĂɎQ�����T�C�s�҂��s���l�܂��Č��Ă���R�S�ǂɂԂ����������悤�Ɋ����Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ�����ԁF
�����O�́u�S�ڊƓ��v�ƌ����B
����͂��������u�S�ڊƓ��v�ɏ��l�߂��悤�Ȃ��̂ł���B�@
�����ɂ����݂��Ă����炢�܂Ōo���Ă����Ă͉������Ȃ��B
�����ŁA�v�����āu�S�ڊƓ��v���X�ɐi�݁A���g�̖��̊o��œ��̒��̖ϑz�G�O��|�����鎞���R�Ƃ��đ�傷��B
���ꂪ���O�́u�S�ڊƓ��v�ł���B�@
�������́u�S�ڊƓ��v
�u�S�ڊƓ��ɍ�������v�Ƃ͌��ɂ����ݕt�����Z���Ă����Ԃ������B�@
����������ԂɊׂ����T�C�s�҂͎��l���l�Ŗ��ɗ����Ȃ��B
��U������炻�̌��̔���L�݂���菜���A�X�Ɉ����������O�i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
�����Ɉ��Z���邱�ƂȂ��A���̐��E��[�ߑ��O�ꂷ��K�v������B�@
���̐��E��[�ߑ��O�ꂷ��T�C�s�҂̑O�ɏo������֖傪�������́u�S�ڊƓ��v�ł���B�@
�������́u�S�ڊƓ��v�͕��ʕ�����̌�����B
����ɑ��A���O�́u�S�ڊƓ��v�͈�x�ł���B
�{���̌Ó��]���A�u�S�ڊƓ��ɍ������(�Ă�)�̐l�E�E�E�E�v�̌Ó��͒����i�����w���Ă���B�@
�u�S�ڊƓ����炳��Ɉ����i�߂ď\�����E�Ɏ��Ȃ̑S�g�����ׂ����B�v
�Ƃ��������̌��t�͌������́u�u�S�ڊƓ��v�v�ɂ��Č����Ă���B�@
�܊p���ւ�ʂ��Č���Ă��u�S�ڊƓ��v�i���̋��n�j�ɖ��������Z���Ă�����A�����{���̌��ł͂Ȃ��B
��������X�ɕ���i�߂ď\�����E���S�@�S�\�������āA���߂đ��O���ł���̂ł���B
�䂪���̔��B�T�t�Ɠ��l�A�����i���́u���̏C�s�v���d�����Ă��邱�Ƃ�������B�@
�u�]���v�ł�
���ւ�ʂ�����A�u�S�ڊƓ��v�i���̋��n�j����X�ɕ���i�߂ē]�g���݂Ȃ�A
�s���Ƃ��ĉȂ炴��͂Ȃ��A
���Ƃ��Ēʂ�����͂Ȃ��Ƃ������V��V���B��Ƒ��̐l�ɂȂ�B
�������A����͌����͈Ղ������A���̋��n�ɓ��B����̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B
�����A�ǂ��i�߂邩�܂������Č��Ȃ����ƌ����Ă���B�@
�u���v�ł�
���Ƃ�����Ă����̌��Ɏ��������Z���Ă��Ă�
���̌Œ�ϔO�Ɋׂ��đ��O��͂ł��Ȃ��B
�����͖ܘ_�A���̔��E�L�݂���������̂ĂĖ{���̖Ӑl
�i���̖{�̂ł��鉺�w�]�����R�ɂł���l�j�ɂȂ��Ă����A
���̒��̖Ӑl�i������}�v�j�B�����Ƃ��ł���̂��Ɖr���Ă���B�@
��g����ւ��D�P�V�S�`�P�V�V
�{���F
�����x(�Ƃ�����)�a���A�O�ւ�݂��Ċw�҂ɖ₤�A
�u�����Q��(�͂���������)�͑���������}��B������l�̐��A�r��̏��ɂ��݂��H�v
�u����(�����傤)������(�����Ƃ�)����Ε�(�܂�)�ɐ���(���傤��)��E���B
���(����)���鎞�A�����(��������)���E�����H�v
�u������E������Εւ�������m��B�l�啪�����Đr(����)��̏��Ɍ����Ă������H�v
�]���F
�Ⴕ�\�����̎O�]����������A�ւ��Ȃ��Đ���(��������)�Ɏ�ƍ�(��)��A
���ɋ����đ����@�Ȃ�ׂ��B
���ꈽ���͖����R�炸��A�e(��)�T���͖O���Ղ��ך�(�������Ⴍ)�͋Q����B
��F
��O�����ς����ʍ��A���ʍ��̎������@���B
�@���ӂ̈�O���V���j����A�@���ς��̐l���V���j���B
���F
�����x�a���F�@�����]�x�i�Ƃ����イ���A�P�O�S�S�`�P�O�X�P�j�B�k�v�̑T�ҁB
����i�ق��ڂ������Ԃ�A�P�O�Q�T�`�P�P�O�Q�j�̖@�k
�@�n�F�Սϋ`�����i�ܓ`�p���Α��^�~�������d�쁨����������]�x
�����Q���i�͂���������j�F���̍����ď��������
����̎t�ɎQ���ď@�|�����߂邱�ƁB
�����F���Ȗ{���̍����I�S�i���{���̖ʖځj�����O���邱�ƁB
�u���w�l�S�A���������v�͍��T�C�s�̖ړI�ł���B
�����i�����傤�j�F���Ȃ̖{���i�^�̎��ȁj�B�u�Z�c�h�o�v�Ɍ����錾�t�B
��������������B�F��������B
����i�����j���鎞:�A���ʎ��B
�l�啪���F�l��͌Ñ�̉F���ςɂ����邠���鑶�݂��\������
�l�匳�f�ł���u�n���Ε��v���w���B�l�啪���͎����Ӗ�����B
�S�O���́u�]���v�ɂ������u�n���Ε� ��U�v�Ɠ����B
�O�]��F�O�ւɑΉ����A�j�S�����K�Ȍ��t�B
�����i��������j�Ɏ�ƍ�i�ȁj��F�u�ՍϘ^�v���O�Ɍ�����
�u����(��������)�Ɏ�ƍ�(��)��A�����F�Ȑ^�Ȃ��v�̌��t����B
�����Ȃ���ɉ����Ă���̐��������čs������ΐ^���ɓK���Ƃ����Ӗ��B
���ɋ����đ����@�Ȃ�ׂ��B�F�����ɋ����ďo�Ă��鎩�Ȃ̓��������ׂĕ��@�Ɍ_�����낤�B
�e�T���i������j�F�e���ȐH��
�e�T���͖O���Ղ��F�e���ȐH���͂����H���Ă�������t�ɂȂ邪�A�����Ђ������Ȃ�B
�ך��i�������Ⴍ�j�F�H�����悭����Ŗ�����ď������邱�ƁB
���i�����j�F���ɂ��Ă͎�X�̐�������B
�������ɂ��A�l�\���l���̋��ɕS�N���ɓV���������~��Ă��āA���̑��Ő��A
�₪�Đ��������薁�茸���Ė����Ȃ��������P���Ƃ���B
�����ɒ������B�������Ӗ����鐔�̒P�ʁB
�V���j(�����)���F���j��B
�{���F
�����]�x�a���͎O�֖̊��݂��ĎQ�T�C�s�҂ɖ₤���A
�u�������������̎t�ɎQ���ď@�|�����߂�ړI�͑��������ɂ��Č������邩�ɂ����B
�P.
�����������Ȃ��̎����͂ǂ��ɍ݂邩�H�v
�u�����𖾂炩�ɂ���A�����ɐ����E���邱�Ƃ��ł����B
�Q.
�ł͂��Ȃ��̊���������A���ʎ��A�ǂ̂悤�Ɏ���悢���낤���H�v
�u�����z�ł���Ύ���̍s������������B
�R.
�l�啪�����Ď������Ȃ��͉����Ɍ����ċ���̂��낤���H�v
�]���F
�Ⴕ�����̎O�̖₢�ɑ��Ċj�S�����K�Ȍ��t���������Ƃ��ł���A
�����ɋ��Ă���̐������Ċ��Ɏx�z�����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����낤�B
�����������̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�A
�����Ƃ���ĂĐH���Ē�����������Ƃ������H�ו����~�߂Ȃ����B
�ǂ����ĐH�ׂ�Q����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����낤�B �@
��F
��O�Ŗ���̎��Ԃ��ς���A����̎��Ԃ͍��ɂ���B
�����̈�O�����j��A�����̈�O���ςĂ���l�����j�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
���̌��Ắu�����̎O�ցv�ƌĂ�A�Սω��ł͟��ϓ����̑T�Ə̂��A
���ɗՂސl�̐S���ƌ�����B
���ւ͏C�s�҂��Q�T�ٓ�����ړI�͌����哹�ɂ����
�T�̖ړI���q�ׂĂ���B
�����ŁA���O����̖{���͂ǂ��ɂ��邩�A�ǂ�Ȃ��̂��A�����o���Č����Ȃ����Ƃ������ł���B
���ւ͌����哹���Đ����̖��Ɍ������t���A�������C�ɂ�����Ȃ��Ȃ�B
�����Ȃ�����A���ɗՂ�łǂ�Ȏ��ɕ������邩�Ƃ������ł���B�@
��O�ւ͌����哹���Đ����̖��Ɍ������t���A����ǂ��Ȃ邩��������͂����B
�����A����͂ǂ��Ȃ邩�͂����蓚���Ȃ����Ƃ������ł���B�@
�����̖��͎Q�T���āA�V�t�ɓƎQ�������A�����Ŏ�舵����B�@
���ւƑ�O�ւ͖���ւ̉�����ł́A�`���I�����̗։��]�����Ɋ�Â��ĉ������邱�Ƃ������悤���B
�`���I�����̗։��]�����͌Ñ�C���h�̗։��]�����Ɋ�Â��Ă���B�@
�Ñ�C���h�̗։��]�����̓`���[���h�[�M���E�E�p�j�V���b�h�́u�܉ΐ��v�ɋN�������P�Ȃ�z�����ł���B
�i�u�։��]���Ɠ܉ΐ��v���Q���j�B�@
�`���I�����̗։��]�����͉Ȋw�I�]���⌟�ɑς���q�ϓI�ȍ����������Ă��Ȃ��B
���݂ł��A�]������^�̎��ƍl���邩�ǂ����ȂǁA���̒�`�Ɋւ��ċc�_�͑����B
�����w�̒������i���ɂ���Ď����ς͌��݂Ɛ̂͂��Ȃ����ė��Ă���B�@
�����̖��ɂ��ẮA���̂悤�������Ȋw�̐i�����l���ɓ���čl����K�v�����낤�B�@
�u�]���v�ł́A
�����A���̎O�ւɑ��āA���ꂼ��K���Ȉ����������Ƃ��ł���A
�����Ɏ�l���Ƃ��Ď�̓I�ɐU�������Ƃ��ł��邾�낤�ƌ����Ă���B
���������ꂪ���@�ɓK�����U�镑���ɂȂ��Ă���̂��B
�����A���ꂪ�ł��Ȃ�����̌��Ăɐ^���ɎQ���Ă��̐��_���悭���݂��߁A�悭�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
�ۈ��݂���Έꎞ�I�ɕ����c��邩���m��Ȃ����A�����ɂȂ�B
�悭���Ė����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����Ă���B
�u���v�ł͖���̉ߋ��▢���͉�X�̓��őz�����邾���Ŏ��̂͂Ȃ��B
�������A���݂̈�O�ɂ͖���̉ߋ��Ɩ��������܂��Ă���B
����̉ߋ��▢���͈�O���W�ς��A��������o�Ă�����̂�����ł���B
�����̈�O�͂���������Ȃ��̂Ő�ΓI���l�������Ă���B
�����̈ꋓ�ꓮ�A��O��v���S���Ȃł���B�@
���̂悤�Ȉ�O�����j��A
�����̈�O���ςĂ���l�i���^�̎����j�����j�邱�Ƃ��ł��邾�낤�Ɖr���Ă���B�@
��g����ւ��D�P�V�W�`�P�W�P
�{���F
����(����ۂ�)�a���A���݂ɑm�₤�A
�u�\��������(����ڂ�)�A��H���ϖ�(������˂͂����)�B
���R(���Ԃ�)���H���r��(������)�̏��ɂ��݂��H�v�B
��A�V����(���ザ�傤)��_�N(�˂�)���A�c(����)��c���ĉ]���A
�u�җ��ɍ݂��v�B
��ɑm�A�_��ɐ��v���B
��A��q��_�N(�˂�)���ĉ]���A
�u��q�u��(�ڂ��傤)���ĎO�\�O�V�ɏ�����A
���(�������Ⴍ)�@�E(�т���)��z��(�������Ⴍ)���B
���C�̌(�肬��)�A�ł��ƈ�_����ΉJ�~���X���Ɏ������v�B
�]���F
��l�͐[�[����C��Ɍ����čs���āA���y(�Ђ�)�g�o(�悤����)���A
��l�͍�������R���ɗ����āA���Q��V(�͂��낤�Ƃ��Ă�)���B
�c����s�A�e��ǎ���o���ď@���}�G(�ӂ���)���B
�傢�ɗ��ӂ̒y�q(����)�A������������Ɏ�����B
���㉞�ɒ���(�����Ă�)�̐l������ׂ��B
����(���傤����)�Ɋϗ���Γ��V�A�y�ɖ����H�������炴���(��)��B
��F
����������(��)�����鎞�A�悸��(����)�ɓ���B
����������鎞�A�悸������(����)��B
���Ƃ�����(���Ⴍ���Ⴍ)�@��ɍ݂���A
�X�ɐ{�炭������(���傤)�L�邱�Ƃ�m��ׂ��B
���F
����i����ۂ��j�a���F�@�z�B����i�������イ����ۂ��A���v�N�s�ځj�B
�����̑T�ҁB�����@�̓��R�ǘ��i�W�O�V�`�W�U�X�j�̖@�k�B
�@�n�F�Z�c�d�\�����s�v���Γ���J����R�ҙV���_�ޓܝ���R�ǘ����z�B����
�������i����ڂ�j�F���̏\���i�\�̖��O�j�̂P�B
����bhagabat�̎�ibhagaban�̉��ʂŐ����Ɗ���B
�\���������Ƃ͏\���̏����Ƃ����Ӗ��ł���B
�u�\���������i�����ۂ�����ڂ�j�A��H���ϖ�i������˂͂����j�v�F
�u�\���������A��H���ϖ�v�Ƃ������t�͎��o�Ɍ܂�
�u�����B���͏\���̔������A��H���ς̖�Ȃ�v����̈��p�ł���B
�u�@�̌����i�����B���j�͏����i�\���̔������j�ɂƂ��āA���Ɏ����H�ł���
�i��H���ς̖�Ȃ�j�v�Ƃ����Ӗ��ł���B
���v(����)�F�����𐿂����ƁB
�O�\�O�V�F�Ñ�C���h�̐��E�ςɐ{��R��������B
�{��R���ł͐��E�̒��S�ɐ{��R�i������U�S�������j�Ƃ���������ȎR���ނ���B
���̎R�̒���������ɓV��E�����݂���Ƃ����B
�V��E�ɂ͉�����~�E�V�A�F�E�V�A���F�E�V�̎O�E�V������B
�~�E�V�ɂ͎l�V���i�����V�A�����V�A�L�ړV�A�����V�j���Z�ގl�V���V������B
�O�\�O�V�͎l�V���V�̂�����ɂ���V�ł���B
���̓V�ɂ͑P���邪�����ߓV�i�C���h���_�j���Z�ނƌ����B
�i�u�{��R���ƓV�̍\���v���Q���j�B
��߁F��ߓV�B�C���h���_�B
�C���h���_�̓C���h�ŌÂ̕����u���O�E�x�[�_�v�^��
�ɂ�����ō��̐_�ŗ��_�̐��i�������A�M���V���_�b�̃[�E�X�Ɏ����_�ł���B
�㐢�A�����Ɏ������ꕧ���̎��_��ߓV�ƂȂ����B
��ߓV�͎O�\�O�V�̎�ł���B
���y�g�o�i�Ђǂ悤����j�F�y�����ӂ邢���o���܂��グ�邱�ƁB
���Q��V�i�͂��낤�Ƃ��Ă�j�F�C�̐����V�ɓ͂��قLj���l�q�B
�����i���Ⴍ���Ⴍ�j�F��̈����B
��Ղɐ����낷���Ƃ��꒘�ƌ����B�������B
�y�q�i�����j�F�p�k�̂��ƁB
⁁i���傤�j�F�(���傤)�͌��̂��ƁB
�������o���肷�鏊�ŁA��ɉ����Ă͎�������v�ւ������B
�{���F
���鎞�A�m���z�B�����a���ɕ������A
�u�����o�ɂ́w�\���̏����́A��̘H��ʂ��Č��ɓ���ꂽ�x�Ƃ���܂��B
��̂��̘H�͉����ɂ���̂ł����H�v�B
�����a���́A�V����������グ�āA�Ɉ�����c���ĉ]�������A
�u�����ɍ݂邶��Ȃ����H�v�B
�������A�m�͂��̕ԓ��̈Ӗ���������Ȃ������B
�m�́A��ɂȂ��āA�_��T�t�̏��ɍs���ē�����������ċ���������B
�_��͐�q�������グ�ĉ]�����A
�u����͂���������q���O�\�O�V�ɒ��я�����A
��ߓV�̕@�ɓ������ē˂��グ��悤�Ȃ��̂��B
�܂��r�ʼnj���ł�����_�ň�ł�����A
���~���Ђ�����Ԃ����悤�ɐ�����юU��̂Ɏ��Ă�����v�B
�]���F
��l�͐[�[�Ƃ����C��ɓ����āA���o���グ�A
��l�͍����ނ���R���ɗ����āA�C�̐����V�ɓ͂��قLj�ꂳ���Ă���B
��l���������߂�ƁA������l�͊ɂ߂�B
�������Č݂��ɕЎ���o�������đT�@���x���Ă���킢�B
�܂�œ��p�k�����������킹�Ă���悤���B
���Ԃł͂���ɗ����������čs�������̗͂̂���l�͂��Ȃ��悤���B
�������A���̖��傪����(���傤����)�Ō���A
����Ɖ_��̓��V�́A�����{���́u���̈�ؘH�v��m��Ȃ��悤���B
��F
�����^�Ȃ��̂ɁA���������Ă���B
����������Ă��Ȃ��̂ɁA����������(����)���Ă���
���Ƃ������Ƌ@��𐧂��đł��Ă��A�X�ɍ����T�̋��n���L��̂��B
���鎞�A�m���A���o�̕���u�\���������A��H���ϖ��v�����p����
�u�w�\���̏����́A��̘H��ʂ��Č��ɓ���ꂽ�x�Ƃ���܂����A
��̂��̘H�͉����ɂ���̂ł����H�v�Ɖz�B�����a���Ɏ��₵���B�@
�����a���́A�V����(���ザ�傤)�������グ�ċɃO�[�ƈ꒼����`����
�u�����ɍ݂邶��Ȃ����v�Ǝ������B�@
����͔n�c�T�́���p�������̎v�z��
�V����������Ƃɂ���Ď������ƍl����Ηǂ�������i��Q�T���̐}�P�O�A�P�P���Q�Ɓj�B�@
�i��Q�T���̐}�P�O���Q���j�B�@
�V����������ē������Ă���͎̂�ł͂Ȃ��B
���̖{�̂Ƃ��Ă̖@�g���i���]�j����o�Ă���^���w�߂Ɋ�Â���
�V����������グ�ċɈ꒼����`���Ă������Ƃ��������̂ł���B�@
�������A�m�͊����a�������������Ă��ꂽ�̂��T�b�p��������Ȃ������B
�m�́A��ɂȂ��āA�_��T�t�̏��ɍs���ē�����������ċ���������B�@
�_��͐�q�������グ�āA
�u����͂���������q���O�\�O�V�ɒ��я�����A
��ߓV�̕@�Ƀs�V�����ƂԂ����������悤�Ȃ��̂����B
�܂��r�ʼnj���ł����ɂ��[���Ƌ߂Â��Ė_�ň�ł�����A
��̓o�V���[���ƒ��˂Ă�����͐����炯�ɂȂ��Ă��܂��̂Ɏ��Ă�����v�Ɠ������B�@
�_����]�_�o�n�̎��R�Ń_�C�i�~�b�N�ȓ�������̓�����栂����������ƍl����悭������B�@
�{���ł͊���Ɖ_��͌��̖{�̂ł����]�̓������꒼����`������栂��b�ŋ������Ă����B�@
�������A�����̓���ɂ͌���̂悤�Ȕ]�Ȋw���Ȃ������B
�����ł��̂悤�ɐe�ɋ�������Ă����̑m�ɂ̓T�b�p��������Ȃ��������̂Ǝv����B�@
�u���v�ł�
�u�����������ݏo���Ȃ��̂ɁA���蒅���v
�Ƒ������O�ɔ]���������Ƃŕ��s����Ƃ��������_�o�n�̓������r���Ă���B
�u����������Ă��Ȃ��̂ɁA����������(����)���Ă����v�Ƃ́A
��]�̃u���[�J��i�^�������ꒆ���j�̓����Őオ�������t������ׂ�
�Ƃ����������r���Ă���Ɖ��߂ł���B
�i��Q�O���F���t������ׂ�]�̎d�g�݂��Q���j�B�@
�u����������Ă��Ȃ��̂ɁA����������(����)���Ă����v�Ƃ����\����
�]�_�o�n�̓����������̎��ۂ̓����i���s��b�j�ɐ�s���Ă��������������Ă���̂ł���B�@
�{���͂Q�O���Ǝ������ĂŁA�]�Ȋw�I�ϓ_����悭�����ł���B
�i��Q�O�����Q���j�B�@
����ł́A�m���A���o�̕���u�\���������A��H���ϖ��v�����p����
�z�B�����a���ɐq�˂��u�w�\���̏����́A��̘H��ʂ��Č��ɓ���ꂽ�x�Ƃ���܂����A
��̂��̘H�͉����ɂ���̂ł����H�v�Ƃ�������
�ɑ���z�B�����a���̕ԓ��͉����Ӗ����Ă���̂��낤���H
�����a���́A�V����(���ザ�傤)�������グ�ċɃO�[�ƈ꒼����`�����Ƃɂ���āA
�u���̓���̖{���ł���]�������̌��ւ̒ʘH���̂��̂ł����A�����ɂ��邶��Ȃ����v
�Ƒm���������A�����̂ł���B�@
�u����ցv�̎Q�l����
�P�D�����b�M�A��g���ɁA�u����ցv�P�X�X�S�N�A
�Q�D���J���_���A�t�H�ЁA�T�̐_���@����ցA�P�X�U�T�N�D
�R�D���c���u���A�}�����[�A�T�̌�^�P�W�@����ցA�P�X�U�X�N�D
4.�ѓc�g�E�B���A�X�]���X�A������r���A�P�X�T�X�N�D
�g�b�v�y�[�W��
����ցF���̂P��
�y�[�W�̐擪�֖߂�