![�Ռ]�T�t��](images5/bannkei.jpeg)
�Ռ]�i��(���悤����)�T�t�i�P�U�Q�Q�|�P�U�X�R�j�͍]�ˎ��㏉���Ɋ����ՍϏ@�̑T�m�ł���B
����̏C�s���̑̌�����A�u�s���̕��S�v������Ǝ��́u�s���T�v��n�n�����B
![�Ռ]�T�t��](images5/bannkei.jpeg)
�Ռ]�͌��a���N�i�P�U�Q�Q�j�O�������ɔd�B�i���Ɍ��j�Ԋ��̕l�c�Ő��܂ꂽ�B
�ނ̎��Ƃ͑�X��҂������B
�Ռ]�͗c������C�F�l�ɗD�ꂽ���̂�����A�_�������ꂽ�B
�\��̎��A��҂ɂ��Ď̊�b�I�o�T�ł���l���̈�ł���w��w�x���w�B
���̎��A
�u��w�̓��͖����𖾂炩�ɂ���ɍ݂��v
�Ƃ����`���̈��ɏo���킵�����A
�u�����Ƃ͉����H�v
�Ƃ������Ƃ��ǂ����Ă�������Ȃ������B
�u���炩�ȓ��ł���Ƃ����Ȃ�A���̉��߂Ė��炩�ɂ���K�v������̂��A
�u�V���畊�^���ꂽ�얭�Ŗ��炩�Ȃ��̂��������Ƃ������A
�����̂ǂ��ɂ��̖���������̂��낤���H�v
�Ƃ����^��Ɏ����ꂽ�̂ł���B
�Ռ]�͂��̋^������ЂƂ����������Ǝv���A��҂ɐq�˂����A�ǂ̎�҂��m��Ȃ������B
�Ռ]�͈����҂ɐ����ɑł�������ƁA��҂�
�u���̂悤�ȓ�������A
�悭�T�m���m���Ă��邩��T�m�ɕ�������悢�B
����͎l���܌o�Ȃǂ̓����͂悭�����邪�����Ƃ������̂͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��͒m��Ȃ��v
�ƌ������B
�Ƃ͂����Ă��A�߂��ɂ͑T�����Ȃ������̂ŁA�����ȏ��ɏo�����Đ��@��u�߂������A
�Ȃ��Ȃ������͖����ɂȂ�Ȃ������B
���̂悤�ɂ��ĔՌ]�̋^��͂܂��܂����債
�w�Ƃ݂̂Ȃ炸��̎d������ɂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���̌��ʁA�Ռ]�͒��Z�̐��x�ɂ���ĕ������ꂽ���A
�����Ă����m�l�̂��A�ň������сA�C�s�𑱂����B
�\���̎��Ռ]�͐ԕ䐏�����̉_��S�ˁi����ہE���傤�A�P�T�U�W�`�P�U�T�R�j
�ɂ��ďo�Ɠ��x�����B
�_��͍b��b�ю��̉Β�ŗL���ȉ���ɎQ���A
���O�O�F���̓�i�Ɏk�@�����s���Ȗ{�i�I�T�m�ł������B
�_��̉��ŏC�s���Ă��u�����v�̖����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�Ռ]�͓�\�̎����̎t�̂��Ƃ������āA�������s�r���đP�m���i�P���w���ҁj��T�����߂����A
���ɖ��t�ɏo����Ƃ͂ł��Ȃ������B
�ނ͎������\��������H�ׂ��ɖ����������Ƃ��ڂ݂��Ɋ�̏�ɒ��i�����j�ɍ��T������A
���̌������ł̎l�N�Ԃ̌�H�A����̏�����Ђ̔q�a�ł̒���s��̒f�H�ېS�A
�L��啪�̎R���ł�ᚕa�̌�H�Ƃ̓����ȂǁA�������̋�C�𑱂������A
�u�����ɑ���^���v�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
��\�l�̎��Ռ]�͐������̖{�t�_��(�����)�a���̂��Ƃɖ߂�d�B�ԕ�̖쒆���Ɉ������Ă��B
�����Ō����̊o��ł��̓����������悤�ƓO�ꂵ��孋��������n�߂��B
�ނ͈��l���̏������Œ���Q���ɔO���ƍ��T�O���̐����ɓ������B
�������A���͉������邱�ƂȂ��A�S�J�̂��܂���ɑ�a�l�ɂȂ�A
ႂɂ͌����o��悤�ɂ܂łȂ����B
�����ԐH�����ʂ炸�����o�傷��܂łɂȂ����B
���x���̎��ςɊo���āAႂ�ǂɓf���������,
�^������"�ނ��낶"�̂悤�Ɍł܂���ႁv������肱���Ɨ����ė��āA
���̂������ǂ����S�n�悭�Ȃ����B
���̎��Ռ]�͂Ђ����
�u��̎��͕s���Œ����̂ł͂Ȃ����B�v
�ƋC�t�����B
�����C�t���ƍ��܂ł̏C�s�͖��ʂȍ��܂肾�����ƁA�����̔��m�����B
�����ŋ������������������o���Ċ������C�����ɂȂ����B
�����Ȃ�ƐH�~���u�R�ƗN���Ă��ĐH�����i�ݕa�C�������Ɍ��������B
���钩�Ռ]�͊O�ɏo�Ċ�����Ă����B
���̎���ォ�畗�ɏ���ĕY���ė����~����k�����r�[�A
�]���̋����̋^������Ə������艱��̒E����v���������B
���̎��ނ��s���ɂ��ė얾�Ȃ镧�S��������̂ł���B�Ռ]�Q�U�˂̎��ł������B
�Ռ]�͂��̎��̌o����
�É��̒�ʂ��ʂĂāA�O�E�Ɉ�~���̗ւ��������
�ƁA�̂Ɏc���Ă���B
���ɋ�ߏ\�l�N��̑��ł������B
����قǂ̋�s�����Č�����l�͌Ðl�ł��������ƌ�����B
���̈����O�܂ōs�����؎��Ȍo������A�Ռ]�͑m���̒�q�B�ɑ��ẮA
�ʒi�ɒ[�ȍ��܂�����Ȃ��Ă��u�s���̕��S�v���肳������Ηǂ��Ƃ���
�u�s���T�v������悤�ɂȂ�B�@
��債���Ռ]���������ɋA��A
�_��a���ɏ����i���傰�A��������n�ɂ������鎩���̌����j��悵���B
�_���
�u���O�͒B���̍����i�T�̐^���j��������B
�������A�����Ɉ��Z�����ɁA�����̖��m�ɎQ�₵�čX�Ɍ����ڎw���˂Ȃ���B�v
�ƌ����ė�܂��A
����q�̈�w�̑听�����҂����B
�Ռ]�̌��̏C�s�͂�������n�܂����B
�O�\�̎��Ռ]�́A�_��̖��ɂ��A������̓n���m�A
���Ғ����i�ǂ����Ⴟ�傤����A�P�U�O�Q�`�P�U�U�Q�j�ɎQ���邽�߂ɒ���܂ŏo�������B
���҂͔Ռ]�Ɍ������āA
�u���͌Ȏ��ɓ������Ƃ����ǂ��A�����@�����̎��𖾂�߂�
�i�M���͂��łɐS����J���Ă͂��邪�A�܂��X�Ȃ��̋��n���������Ă��Ȃ��j�v
�Əq�ׂ��B
�Ռ]�͓����͓��҂̂��̌��t�ɏ����ł��Ȃ��������A
���҂̗͗ʂ�F�߂āA���ƂȂ��Đ������ŏC�s�ɐ�S�����B
��O�ɍ������ďC�s���n�߂��Ռ]�́A�������̌o���̓ǂݕ��ȂǁA����̋K���ɏ]��Ȃ������B
���҂͂��̂悤�ȔՌ]���w�E���A�ӂ߂�ƁA
�Ռ]��
�u���͐��@���o�̑厖�̂��߂�ނɂ�܂ꂸ�A���ɂ����ɗ��Ă����B
�����̋K�����܂˂�K�v�͂Ȃ��A���{�̋K��ɏ]���v
�Ɠ������B
���̌�A���҂͂��̂��Ƃɂ��ĉ����ӂ߂Ȃ������ƌ�����B
�ނ̓��{�l�Ƃ��Ă̌ւ�Ǝ�̐�������Ȃ��ԓx�����Ď���B
�����ė��N�A��O�Ƌ��ɑT�����ō��T����歑R�i���˂�j�Ƒ�債���B
�����ɓ��҂̕���Ɏ���A
�ⓚ���ʂ̖��ɑ厖���L�i���@�̈�厖�ł���^�̋��n��̓��������Ɓj��F�߂�ꂽ�B
���҂ɂ��ؖ��̌���Ռ]�͓T���E�i�䏊���j�ƂȂ��ĐE���ɐ��サ�Ă����B
�߉ލ~�a���Ɏ����̑m���ꓯ���Ԍ䓰�̑O�ɏW�܂��Ă����B
���ґT�t�͏C�s�m�B�ɁA
�u�~�a�̕��͂ǂ����痈�邩�H�v
�Ɛq�˂����N���ԓ��ł��Ȃ������B
���҂͔Ռ]���Ă�Ŏ��₷��ƁA�Ռ]�͂����Ɨ����オ���ė���œV�n���w�������B
�l�X�͂��̓������^�Q�����Ɠ`������B
��ɓ��҂͔Ռ]�̊J����L�O���āA���̂悤�Ȏ�����Ă���B
�ʌ{�i���傭�����j�k����j�i�����́j���ĖP���o������
�V�l�@�㐐���ςā@�S��@���R�ɊJ��
�������F
�Ռ]�̊J��͊k��j���ďo�Ă����P���̂悤�ɖڏo�x���B
�V�l���l�Ԃ����̂��炵���ꎖ�ɐS�Ⴊ���R�ɊJ���悤���B
��N�A�Z�\��ɂȂ����Ռ]�͓��҂����Â��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u���̎����҂̌����܂����̂́A����O�͐��������l����Ɛ\����܂������A
���̎����̒m���i�m���j�̒��ł��A�܂����҂��肪�悤�悤�Ə�������؋��ɗ����Ă����ꂽ
�悤�Ȃ��Ƃł�����ǂ��A����Ȃ���A����ł��\���ɂ͓��҂��m���܂��Ȃ������������킢�B
�����̎��̂��Ƃ��v���܂���A�����͓��҂��\���ɂ͋����͂��܂����B
�������҂��A���߂��ꂸ�A�������܂œ��{�ɐ����Ă������܂������A
�����Ƃ悢�l�ɂ��Ă��܂��傤���̂��A
�������ɂ��܂��āA�s�d���킹�Ȑl�ł����������A
���ꂪ�c�葽���i�傢�ɐS�c��Łj�������v
�Ռ]�����̂悤�Ɍ������̂́A���҂̉�i�����j�ő厖���L�i��������傤�Ђj�̌���A
�X�Ɏ����̋��U�����グ�Č���̈�H��簐i�������ʂƌ����邾�낤�B
�Ռ]�͌����A
�u�T���Q������Í��̎҂ŁA�ЂƂ��ь���҂����Ȃ���ł͂Ȃ��B
�������A����ɐK�������Č����ӂ�A���Ė������Ă��܂����ƂɂȂ��B
���̌�A��قǑ�@�ɐ؎��łȂ���A�@�̉~�n�͊��҂ł��Ȃ��v
�܂��A�ނ͂����������Ă���B
�u�g�ǂ�����\�Z�̎��A�d�B�ԕ�S�쒆���ň����i���j�̎��ɑ̓������������A
�܂����҂ɑ������āi�C�s���A�́j��ؖ������ƍ����Ƃł��A
���̓����ɂ����Ă͂��̎O�x�̊Ԃɂ��������̈Ⴂ�͂Ȃ��B
�������A�@�Ⴊ�~���ɂȂ��@�ɒʒB���đ厩�݂��Ƃ����_�ł��A
���҂Ɉ��������ƍ����Ƃł͓V�nꡂ��Ɋu����قǂł����B
����O���������������Ƃ����邱�Ƃ�M���āA�ǂ����@�ᐬ�A�̓��������Ă��炢�����v
�O�\�̎��A�Ռ]�͓��҂̈���B
�R�P�̎��A���̏C�Ƃ̂��ߓ���𗣂�ēޗǂ̋g��R�i�ޗnj��g��S���ꑺ�}�j
�ɓ����Ĉ������B
�����̏ꏊ�ɂ́A�u�Ռ]�a��������Ձv�̔肪�����Ă���B
�Ռ]���R�������ɓ������Ă͂��Ƃ̂ق��ہi�Ђł�j���������̂ŁA
�y�n�̕S���͉J���ɂ����B
�������A�J�͈���ɍ~��Ȃ������̂ŁA�S���B�͑T�t�ɉJ������肢�����B
�����ŁA�Ռ]�́u�����������v�����S���ɗ^���A��������{�ʼn̂��A�x��悤�Ɍ������B
�����A�V��j�������{�ŏW�܂��ėx�����Ƃ���
�A�J���v���܂܂ɍ~�葺�l�͂������Ɋ�Ɠ`�����Ă���B
�u�����������v�Ƃ͉P�̂Ƃ������A�P��������������肵�Ȃ���̂��J���̂̂��Ƃł���B
�u�����������v�͔Ռ]�̕s���E�{�S�E�{���̖ʖڂ̌����̂������̂ł���B
�u�����������v�͓����̔Ռ]�̌勫��ǂ��������킵�Ă���B
�l�X��������̂��x�邤���ɁA�̂́@�^�ӂ�������悤�ɍH�v����A�Ɠ��̖��͂������Ă���B
�ȉ��Ɂu�����������v�̒����炢�������p����B
�s���s�ł̖{�S�Ȃ�A�@�n���Ε��͉��̏h
�i�s���s�ł̖{�S���h�邱�̐g�̂͒n���Ε��̎l�匳�f����Ȃ鉼�̏h�̂悤�Ȃ��̂��B�j
���ꗈ�肵���ɂ����₦�A�����v��ʂ��̐S
�i�䂪�g�����̐��ɐ��܂�ė����̂��l����ƁA
�����v��Ȃ����O���z�̐���{���S�Ƌ��ɒa�������̂��B
�ϔY�͂��̌�ɐg�ɂ������̂Ō��X�͖��������̂��B�j
����@���ɐS�����Ă@���ɂ��̐g�����@��
�i���̐��ɐ��܂�ė����̖̂��S�Ȑ���S�ɗ����Ԃ�A���̂܂܂��̐g���������ł���B�j
�������͂��Ɩ������̂���A�e�������ʏK������
�i�s���̖{�S�͐e���狳�����ďK���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A������������X�������̂��B�j
���ׂ̐S�͂��Ƃ��s���A�L�ׂ������̖�������
�i�s���̖{�S�ɂ͌�����A�͂��炢��ω��͂Ȃ��̂ŐS�ɖ����������B�j
�����߂ł���V���ʌN�ɁA�q�ˉ������ЂƂ�
�i�������ڏo�x�����ƂɁA�s�V�s���̕s���̖{�S�ɐ��ɉ���Ƃ��ł������A
����Č������́@�^�̎������g�ł������B�j
�����C�s���Ƃ߂���́A�����ς��͓��ʂ��̂�
�i�����C�s�ɗ���ʁA���������ǂ��ȑO�Ɠ��ɕς��͂Ȃ��B�j
��s�v�c�͈���������A�m��ɂᐢ�E���F�s�v�c
�i����Č���ƁA���E�̈������̂܂܂Ɍ����Ă���B�����ɂ͊�ŕs�v�c�Ȃ��Ƃ͈�������B
�ނ�����O�̕����F�s�v�c�Ɍ��������̂��B�j
�����Ƃ��̍����˂A���̐Q���߂��C���y���@
�i���̍��͌�낤��낤�Ƌ��߂�S���~�̂ŁA������������Ɩڊo�ߐS���y�����̂��B�j
�����{����y�͂�����A�ܖ��ܖ��̉�������
�i���{��y�i���Ɋy��y�j�́A���o�ɐ������悤�ɁA
�����\���i�ܖ��ܖ��j���y�̉����ɂ���̂ł͂Ȃ��B
�ϔY�ꊳ�������^�̋Ɋy��y�͍����̉䂪�g�ɂ���̂��B�j
���{��y�͂������O�ɁA�ܖ��ܖ��̉�������
�i���{��y�i���Ɋy��y�j�́A���o�ɐ������悤�ɁA
�����\���i�ܖ��ܖ��j���y�̉����ɂ���̂ł͂Ȃ��B�@
�������ɂ���̂ł����āA���̐g�̊O�ɂ���̂ł͂Ȃ��B�j
�ܖ��ܖ��̉��������A���{��y�͂����������
�i���{��y�i���Ɋy��y�j�́A�����\���i�ܖ��ܖ��j���y�̉����ɂ���̂ł͂Ȃ��B
�@���A���̐g�ɂ���̂��B�j
��Ə�y�����Â˂Č�����A�������Ɍ���ꂽ
�i�^�̎��ȂƏ�y���O�ɋ��߂Đq�˂���A�����O��̂��Ƃ�����Ȃƕ��ɂ�������ꂽ���̂��B�j
���ʗ�R�킪�Ȃ����Ƃ��A�m��Ŗ����͐g�̂Ђ���
�i���ʂ̖@����m�炸�ɁA���Ƃ��d�˂Ė����͉̂䎷�E�g�т������炭����̂��B�j
���̉Α�ɐS���~�߂āA��ƔR�₵�Đg���ł���
�i�Α�ɚg�����邱�̐��̌ܗ~
�i���Y�~�A�F�~�A�H�~�A���_�~�A�����~�j�Ɏ������ǂ����߂�̂́A
��Ɖ䂪�g��R���ł����悤�Ȃ��̂��B�j
�ɂ���~����Ǝv��ʌ̂ɁA����ΐ��E���F�킪���̂���
�i���̐��̌ܗ~�i���Y�~�A�F�~�A�H�~�A���_�~�A�����~�j
�ւ̎������痣��Ă݂�A���̐��E�̈���䂪���̂ƂȂ�B�j
�̎v���Η[�ׂ̖�����A�Ƃ����v���͊F��������
�i�̎v�������Ă����̂����v���A�͂��Ȃ������閲�̂悤�Ȃ��̂ŁA�{���ł͂Ȃ��j
���̗�Ɍ���悤�ɁA�Ռ]�́u�����������v�͕s���̖{�S����Ղ��r�������̂������B
���̂��߁A�u�{�S���v�Ƃ��Ă��B
�g�삩��Ăє��Z�Ɉڂ����Ռ]�́A�ʗ����Ɉ��������B
�������ď\���l�̎҂����������Ƃ����B
���̎��̈�b�Ƃ��āAᚕa�̌�H�����X����ė���̂��F�������������A
�Ռ]�͎����̎����i���͂j�Ŗ���ᚕa�l�ɐH�ׂ������̂ŁA
�ꓯ�͜Μ������Ƃ����b���`�����Ă���B
����N�i�P�U�T�T�j�O�\�l�̎��A�Ռ]�͌ܐl�̉_�Ӂi����̂��A�T�̏C�s�ҁj
�Ƌ��ɒ���̓��Ғ������ĖK�����B
�����A���҂̖@�i�i�ق����キ�j�̉B�����������A���k�Ԃ��a瀁i���ꂫ�A���C�j
���������̂ŁA���҂͖����ɋA�炴��Ȃ��Ȃ����B
�B���͂��̌�A���s�̉F���ɉ��@�R���������J�n���ĉ��@�@�i���������イ�j���O�߂��B
�Ռ]�͒��肩�畽�˂Ɉڂ�A���˔ˎ�E���Y���M�i�܂炵���̂ԁj�̑��M�����B
�z�O����̑�����ł͖��m�̗_�ꍂ������@�z�i���������������A���t�̓��F�j
�ɑ����A�ⓚ���ʂ��Ă���B
�O�\�l�̎��A�Ռ]�͍]�˂ɏo�������Ռ]�́A�u���̏C�s�v�Ƃ���
��`���t�߂Ō�H�����Č��̏C�s�����Ă����Ɠ`������B
�Ռ]�O�\�Z�̎��A�l���ɗ\�̑�F�i�������j�ˎ�������i���Ƃ��₷�����A
��F�˓��ˎ�A�P�U�P�P�`�P�U�V�W�j�͕ԏƈ����������ĔՌ]���������B
�H�ɂ͔Ռ]�͋����ɋA��A���������ċ����A�~�ɂ͔��O���R�̎O�F���ɂ�����
�@�Z�̖q���c���a�����k�@�̈����B
�z���ĎO�\���̎��A���s�ɏ��A��{�R���S���̑O�ŐE�ɓ]���A�u�Ռ]�v�Ə̂��邱�ƂƂȂ����B
�Ռ]�͂�����e�n������Đ��@��ۉ�(����)�i�O���ϓx�j�ɋ߂�B
���̋��_�ƂȂ����̂́A�Ռ]�n���̎O�厛�Ƃ��Ēm����A
�Ԋ�(���ڂ�)�̗��厛�E��F�̔@�@���E�]�˂̌��ю��ł���B
�l�\�O�̎��A���s�̎R�Ȃɒn�������ċ����A�����\��N�i�P�U�V�Q�j�Ռ]�\��̎��A
���S����Q�P�W���̏Z���ƂȂ�A���߂��������B
�Ռ]�l�\�̎��A�|�n�̗F�ł��鋽���l�c�̕x���剮�E���X�ؓ��킪
��l�̒�Ƌ��ɁA�Ռ]���J�R�Ƃ��间�厛�����������B
���厛�͔Ռ]�T�̍��{����ƂȂ����B
���厛�n�������̂��̂Ǝv�������i������j���c���Ă���B�@
�����Ƃ�e���v����
�������ĉ��l���|�тɓ���
���ׂ͌Â��i�͍�����Ƃ̋�
���V�x�n�i�ӂĂ����j�m�����i������܂�j�Ȃ�
�������F
���̗��厛�ɊՋ����Č��̂Ȃ��Ձi�����ʒq�j�Ō��̉̂����t�i���ȁj�łĂ���B
�ʂ��Ă��̒|�ь��i�Ռ]�̋����j��K���҂̂����A���̐^�ӂ���҂��ǂ�قǂ��邾�낤���B
�킽�����������@�̒��ׂ͌Â��i���͍����B
���̍L���V�������n���Č��Ă����̌勫�����Ă����l�͏��Ȃ��B
�Ⴂ������̋�C�̂����ŕa��ł������Ռ]�́A�l�\�O�̎��ɋ��s�R�Ȃ̒n�����ɏZ���Ĉȗ��A
���̒n�̊ՐÂ��������Ă��т��ѕւ����B
�u�ցv�Ƃ͌ł���˂�����č��T�C�s�ɏW�����邱�Ƃł���B
�Ռ]���g�͓����̐l�X�̐S�̓��������āA���Ƃ����Ĉꌾ�Ől�X�̐S�ɓ`�������Ǝv���A
�w�s���x�Ƃ������Ƃ�������������T��n�n�����B
�Ռ]�l�\���̎��A��F�ˎ�������i���Ƃ��₷�����A�P�U�P�P�`�P�U�V�W�j��
�ɗ\�̑�F�ɔ@�@����n�����A�Ռ]���J�R�Ƃ��Č}�����B
�Ռ]�͔@�@���̗��R���R�������▭�Ȃ̂Ɋ��Q���A
�����ɉ��|���i����������j�Ƃ������������Ăĕւ����B
��ɔՌ]�͌��Ă�r�˂���悤�ɂȂ邪�A���̍��͂܂����Ă��g�p���ďC�s�҂�
�ړ����Ă����Ɠ`������B
�M�k�����ڂɉɁi���Ƃ܁j���Ȃ��قǎE�����Ă���̂ŁA
�\�̓~�ɂ͉p�슿��\�����������A��čĂщ��|���ɕւ��A
��~�̊Ԃɉ��ɂȂ��ĐQ��҂���l�����Ȃ��悤�Ȍ������C�s���s�������ʁA
���҂����������Ƃ����B
�������āA���\�Z�N�i�P�U�X�R�j�㌎�O���Ɏ��\��ŗ��厛�ɂ����đJ���i���A�����j����܂ŁA
�Ռ]�͏����Ō����i�C�s�m�̊����߂Ă̏W�c�I�C�s�j���邱�Ə\�ܓx�ɋy�B
���\�l�N�i���\�̎��j�̗��厛�ł̌����ł́A���ɐ�O�S�l�̑m�������W�����Ƃ����B
�ݑ��̒j���̒����ɎQ�W����҂��̐���m�炸�A�����e�h�̑m�����҂܂ł�����q�̗�����A
���̎w�������Ƃ����B
�Ռ]�̒�q�̐����A�j�m�l�S�l���܂�A��m��S���\�l�A�@������������q�̗���Ƃ�����
�ܖ��l���܂�Ɠ`������B
�ނ̊J�n�������@�͎l�\���A�f��Ɋ����i���傤�j���ĊJ�R�Ƃ������@���S�\���܂�ɂ̂ڂ�B
���̕����Ɠ��̉e���͂��@���ɍL��Ȃ��̂ł����������m����B
�Ռ]�͘Z�\��̎��A���R�V�c����u���q�O�ρv�Ƃ����T�t�������B
����T�O�N���ɂ͍����V�c����u��@����v�Ƃ������t����ꂽ�B
�Ռ]�̐l�i�ɂ��āA
�u���i�͒���ł���A�������~�������v
�ƕ]����Ă���B
�厜�ߐS�̌����i���j
�Ƃ������Ƃ��낪�������B
�������A������������Ռ]�͎��݂ɐl�����O���āA�����������l�����A��������q�d�̐l�ł��������B
���̑T����
�u�g�ǂ��͕��@�����������A�܂��T�@�����������v
�Ƃ����A
�����u�g�̏�ᔻ�v������
�u�s���̕��S�v
����������ł��������߁A
�u�s���T�v
�ƌĂ�Ă���B
�×��̖_�����s���ė����T�m�Ƃ͈قȂ�A�Ռ]�͎���̑̌��̐^����`���邽�߁A
�����ɂ�炸������Ղ����b��p���Đ��@�����B
�ܖ��l�Ƃ������鑽���̑m�������S�����������ƌ�����B
�����ɑ�����@�ɂ����ẮA
�u�s���̕��S�͕����ł����v
�Ƃ����l���Ɋ�Â��āA
�������j���̊u�Ă͖����ƌ�������ł������B
�j�Ƃ����Ƃ��́A��O����������̖��O�ł����āA
�s���̏�ł͒j���̑��i���ʁj�͖����Ƌ����Ă���B
���鏗����
�u���͋Ƃ��[�������͓���ƕ����Ă��邪�A�{���ł��傤���H�v
�ƕ������̂ɑ��A
�Ռ]�́A
�u���Ȃ��͂��̊ԂɁA�s���̕��S���Ɛ[�����ɂ���ւ��Ă��܂������v
�Ɠ����A
�j���̍��ɂƂ��ꂽ�S��Ŕj���悤�Ƃ��Ă���B
�Ռ]�͒�q�B������ʈ��������̂��������B
�n�����ɂ������̂��ƁA�֎��ɂȂ����̂ŐH���������B
�Ռ]�͌������A
�u�����̐H���͗ǂ��ς��Ė����ǂ����v�B
���d�̏��m���������A
�u�a������̏����オ���Ă���̂́A��̒��őI��ō����グ�Ă���̂ł��B�v
�Ռ]�͌������A
�u�N�����̐H�������̂��H�v
���m���������A
�u�c������ł��v�B
�Ռ]�͌������A
�u�����܂������Ƃ��B��̓��ō��ʂ����Ă���ł͂Ȃ����v�B
�Ռ]�͂��������āA���̌ジ���ƐH����H�ׂȂ������B
���������q�̑c���������悤�ɐH�������Ȃ������B
���̂悤�ɂ��Đ������������B
�Ռ]�͒�q�̑c���������悤�ɐH�������Ȃ����Ƃ��A�n�߂ĐH���������Ƃ̂��Ƃł���B
���l�Ȃ��Ƃ͂悭�������Ɠ`�����Ă���B
�܂��A���鎞�A��{������肨��̎����@�a�֏������֎q�̏��Ȃ������コ��ė����B
�����@�͂����@�@�����サ���B
�T���̑c�O�͏����ȉ֎q��ł͑�O�F�ɐH�ׂ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����
�t�i�Ռ]�j��l�ɏ`�̋�ɂ��č����グ���B
�Ռ]�͏����H�ׂĂ��猾�����A
�u�����邩�猣�コ��ė����֎q�͂ǂ������̂��H�v
�c�O�͍�����������̂܂܂Ɍ������B
����ƔՌ]�͑�ϓ{���āA
�u�킵�ɓł�H�ׂ�����̂��v
�ƌ����Ă��̏`��H�ׂȂ������B
�����̏��H�������̐H�����H�ׂ悤�Ƃ��Ȃ������B
�c�O�͂��ߘV�m�B�F�����낢��Ƃ�т��������̂ŁA�悤�₭�H��������悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł���B
���̗�Ɍ�����悤�ɁA�Ռ]�͐g�������Ē�q�B�������������Ƃ�������B
�ނ͗ՍϏ@�ɑ�����m�ł��������A���Ă��قƂ�Ǘp���Ȃ������B
�Ջ@���ς̊��엪(��������Ⴍ�A�������������Ή��j�ɂ��
�����ǂ���Ɋw�l�̊���J�������Ƃ���ɔՌ]�T�̓���������B
�ނ͑���A��R�A�ߊO�A�c�ʁA�∢�A���ԁA���@�ȂǂƑ����D�G�Ȓ�q����Ă��B
�������A���̖@�n�͒��������Ȃ������B
�s���T�͔Ռ]�P�l�̈��|�I�Ȑl�i�Ɉˑ������Ƃ��낪�傫�������悤�ł���B
�Ռ]�̖@�n�͔��B�ɔ�ג��������Ȃ������̂͐ɂ��܂�ĂȂ�Ȃ��B
���厛�n�������̂��̂Ǝv����Ռ]�̘���ɏo�Ă����v�����Ƃ������t��
�T�m�B�ɍD�܂ꂽ�悤�ł���B
�NJ��T�t�i�P�V�T�W�`�P�W�R�P�j�́u�Ö鑐���̗��v�Ƃ������ɂ����̂悤�ɗp�����Ă���B
�NJ��̎��Ɍ���v����
�u�Ö鑐���̗��v
�Ƃ�t���v����
���ׂ͕��_�ɓ���Đ₦
���͗����ɘa���Đ[��
�m�X�Ƃ��Čk�J�ɉm�i�݁j��
�D�X�Ƃ��ĎR�т�n��
���W���i��ځj�ɔ�����
�N���������
���쐴�������������F
�Â��Ȃ��A�����̗��B
�Ƃ�A�����̋Ղ�t�łĂ݂�B
���ׂ́A���ɘa���A�_�ɂƂ낯�Đ₦����A
���͗����̋����ɏ]���Đ[���m�X�Ƃ��Čk�J�ɉm�i�݁j���A
�D�X�Ƃ��ĎR�т�n��B
���W���i��ځj�łȂ�������N�����̗ފ�i�������܂�j�Ȃ鐺�������̂����낤���B
�܂��Ƃ̎��W���i��ځj�����A���̓V�ۂ̐���������̂��B
�NJ��̂��̎��͊Ջ��̋��U����L���ɉ̂��Ă���B����ɖv���ՂƂ������t���o�Ă���B
�܂��掵��Ɣ���͖v���ՂƂ͉�����������Ă���B
�u�^�̎��W���������V�ۂ̐��������Ƃ��ł���v�Ƃ͖����ʒq�̖{�̂�
���ӎ��̉��w�]�i���^�̎��W���j�ł��邱�Ƃ��͂�����\�킵�Ă���B
�NJ��̎��͔Ռ]�̘���Ǝ����Ƃ��낪���邪�A�NJ��̎��̕������w�I��ɂ��ӂꕪ����Ղ��B
���F
���쐴���F �NJ��̌����ҁi�P�W�W�W�`�P�X�U�Q�j�Œ����Ɂu�NJ��̎����v������B
�Ռ]�̕s���T�͓��{�Ő��܂ꂽ���{�I�ȑT�ƌ����邾�낤�B
�Ƃ��낪�s���T�̕s���Ƃ������t�̗R�����ǂ����痈���̂��͂����肵�Ȃ��B
�s���T���s���Ƃ������t�͂ǂ��ɗR������̂��낤���B
�Ռ]�T�t�̖@��ɂ�
�u���܂ꕍ������S���A�s���s�ł̘ŐS��B�s���ɂ��ė얾�Ȃ��̂��ŐS�A
�ŐS�͕s���ɂ��āA��؎����ƂƂ̂��B�v�ƌ������t��������B
������s���Ƃ͐��܂�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ�
�s���s��
�Ƃ����Ӗ��ł��邱�Ƃ�������B
�������A�Ռ]�̂��̍l�����͌���̉�X���猩��Ƃ��������B
�S�͐Ԃ�V�̒a���Ƌ��ɔ]�̐_�o�זE�̃l�b�g���[�N�̒��Ő��܂�A
�炿�Ȃ���ω�����B
�S�̌��ƂȂ�]�̐_�o�l�b�g���[�N��
�a�����������V������
�̃v���Z�X���o�ĕω�����B
����T�m����l�ɂȂ��đT�C�Ƃ����Č�������A
�u���܂�Ȃ���ɂ��Ď����Ă���S���A�s���s�ł̘ŐS�ł����B
�s���ɂ��ė얾�Ȃ��̂��ŐS�ł����B
�ŐS�͕s���ɂ��āA��̎����ƂƂ̂��B�v
�Ǝv�����ɂ��Ă��A
����͊J��̎��Ɋ������ނ̎������ۂɉ߂��Ȃ��B
�c�����̐S���ǂ��ł��������͂Ƃ����ɖY��Ă���B
�����܂ł��̎������ɉ߂��Ȃ����낤�B
�V�N�ɂȂ��āA
�]���V�����ĔF�m�ǁi�A���c�n�C�}�[�a�Ȃǁj
���o�Ă��邱�Ƃ͍��ł͂悭������a�C�ł���B
�F�m�ǁi�A���c�n�C�}�[�a�Ȃǁj�͂V�l�ɂP�l�����ƌ����A
���ł͑傫�ȎЉ���ƂȂ��Ă���قǂł���B
�����̑T�m�ɂ��āA���̎��ǂ��ł��������̋L�q�͗ǂ�������B
�������A���̑T�m���V���Ď��Ɏ���ŔӔN�܂Ń{�P�Ȃ��ŁA
�s���s�ł̘ŐS���ێ�����ӎ��A�L�����ێ�����
�ӎ����N���A�[�ł��������ǂ����ɂ��Ă̌��͖w�ǂȂ��B
�Ռ]���咣����u�s���s�ł̘ŐS�v�Ƃ����F���͑剞���t�ɂ�������B
�]�Ȋw�̊ϓ_����́A�u�Ռ]���s���s�ł̘ŐS�v�Ƃ����F�������炩�ȊԈႢ�Ƃ����ėǂ����낤�B
�H�����a���͔Ռ]�̕s���T�́u�s���v�Ƃ������t�͐^�������������{�s������
�o�����̂ł͂Ȃ����Ɛ��@���Ă�����B
�����ςƂ͞����̈��������Ȃ����ґz�i���T�j����C���[�W�ґz�@�̂��Ƃł���B
�����͞����̐擪�̕����ŕ����̍�����\�킵�Ă���B
�����͏W���_�ł̓[���ɁA�Ղł͑��ɂɑ�������B
��������S�����\�킵�Ă���B�_�b�ł͉F���ݏo�������ׁi�J�I�X�j�ł���B
����@���̖@�E�̐��q�͎�������Ȓq�d���Ƃ���Ă���̂���������S�ɋ߂��Ƃ��낪����B
���̂��ߖ{�s���i���҂�������܂�Ă��Ȃ��j�̑��݂ł���B
���̒��ɑS�Ă����A�����ɑS�Ă̂��̂����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B
�����ς́A�������ς��邱�Ƃɂ���āA���@�{�s���̗������A����̕��������o�����ґz���ƍl�����Ă���B
�����ς͓����E�䖧�o���ōs��ꂽ�B���b��l�������ς��s�����Ɠ`������B
�Ռ]���Q�T����O�ɂ͋����̉~�Z���̉��Y�@�t�̉��Ŗ������w��ł���̂�
�^�������������{�s���Ƃ����l������m���Ă����\���͍����B
�ȏ�̂��Ƃ���A���̐��ɂ͐����͂�����B
�^�������́u��؏��@�{�s���v�Ƃ�
�u�S�Ă̂��̂͂��邪�܂܊��Ɍ���Ă���A�V���ɐ������̂͂Ȃ��v
�Ƃ����Ӗ��ł���B�Ռ]�̕s���T�͂��̍l���ɋ߂��悤�Ɏv����B
����̑��d�C�i�n�c����̖@�k�j�͂��̒��u�ڌ�v��v�ŕs���ɂ��āA
�u�ϔO�����Ƃ��s���ŁA�ł���Ǝ���̂��T�ł����B�v
�Əq�ׂĂ���B
���̍l�����ƕs���Ƃ�
�ϔO�����������ȐS�i����������S�j
�ƌ������Ƃ��ł��悤�B
�u�Ռ]�������s���̕��S��������������S���v
�ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
�i ��������S�ɂ��Ă͖@�E�̐��q�ƈ������D���Q���j
�Ռ]�͕s���̕��S�ɂ��Ď����̂悤�Ɍ����Ă���B
�u���Ȃ��̉��̂����Ђ����Ȃ��Ă�����ɁA�����납�点�Ȃ���l�����œ˂����A
�ɂӊo���₤���A�o���܂����B�ɂӊo���₤�����B�v
�@�i�Ռ]���q�O�ϑT�t�䎦�����j�B
�u���̉���ɂẮA���ꂪ�����\�����������A���������ӂƂ��ڂ��߂��O���ł�������A
�����̊O�ɂČ��̐��╨����̐��̂�����A�����@�̓��ɕ�������ӂƂ͂Ȃ���ǂ��A
�ʁX���ɕ������܂���B���s���S�Ɛ\�����̂ł������B
���Ƃ��Εs���Ɛ\�����̂́A���炩�Ȃ鋾�̂悤�Ȃ��̂ł������B
���Ƃ������͉�ɉ��ɂĂ��ڂ肽��A���悤�Ƃ͑����˂ǂ��A
���ɂĂ����Ɍ����A���̖e���ʂ�܂����ł͊�����B�v
�i�Ռ]�T�t�䎦�����j�B
�@�u�T�t�O�Ɏ����ĞH���A�F�e�̎Y�ݕt���Ă��������́A���S��ł������B
�]�̂��͈̂���Y�ݕt���͂��܂��ʁB���̐e�̂��ݕ��Ă����������S�͕s���ɂ���
�얾�Ȃ��̂ɋɂ�܂����B�s���ȕ��S�A���S�͕s���ɂ��ė얾�Ȃ��̂ł��������A
�s���ň�؎����ƂƂ̂Ђ܂����Ђ��B
���̕s���łƂƂ̂Ђ܂���s���̏؋����A
�F�̏O��������ނЂāA�g�ǂ������Ӊ]�������Ă����邤�����A
��ɂĉG�̐����̐��A���ꂼ��̐������ƁA�v���O�����ɋ�����A
�G�̐����̐����ʂ��킩��āA�Ԉ�킸�ɕ��������A
�s���ŕ����Ƃ��ӂ��̂ł������Ђ��B�v
�@�i�Ռ]�T�t�䎦�����j�B
�t�O�Ɏ����ĞH���A�u�g�ǂ����e�։]���������܂���@�͕ʂ̎��ɂ��炸�B
�l�X���܂����肽��s���̘ŐS�̂��ƂȂ��B
���̌̂�����Ɖ]���ɁA���̍��̖ʁX�g�ǂ����@�����T�����A
���̎��̊O�ɁA�����i����Ό��ƒm��A�낪������ƒm���A
���邢�͂܂��ڂɍ����̐F�A�j���̍��ʂ��������邱���A
�@��̓��ɁA���̐���̐����A
�����j���̐F������Ǝv���O���͂Ȃ���ǂ��A
���̍��ɉ����āA����c�����A���ʌȑO�Ɍ��������T�B�v
�i�Œq�O�ϑT�t�@���j
��P�ł͕s�ӂɔw����˂���Ēɂ��Ɗ������A
���ꂪ�s���̕��S���ƌ����Ă���B
����͒Ɋo�̎�i�]�j��s���̕��S���ƌ����Ă���B�@
��Q�ł͕������Ƃ͎v��Ȃ��Ă���������
�G�̐��␝�̐����Ă�����
�s���̕��S���ƌ����Ă���B
����͖����ʂŕ������o�̎��s���̕��S���ƌ����Ă���̂ł���B
�Ɋo�⒮�o�̎�͔̂]�ł���B
�Ռ]�̂����s���̕��S�͔]���w���Ă������Ƃ͖��炩�ł���B
�������A�P�Ȃ�]�ł͂Ȃ��B���T�C�s��ʂ��Ė���ȏ�Ԃɂ܂łȂ����]�̂��Ƃł���B
���T�C�s�ł͎�Ƃ��ĉ��w�]�����������S�]�����N�ɂȂ�B
�i �u�T�Ɣ]�Ȋw�P�v���Q���j
���T�C�s��ʂ�������Ƃ��]����l�Ȍ��N�ȏ�ԂɂȂ����]
�i�����ʒq�̖{���j�ł���ƌ����邾�낤�B
�������R�ł����l�ł���B
��R�Œ��ڂ����̂�
�u����c�����A���ʌȑO�Ɍ��������T�v
�ƕ��ʈӎ���������ȑO�Ɍ������铭���ł���Ƃ͂����茾�����Ă���B
�Ռ]�͂��̓����������ʒq�ł���Ƃ͂�����F�����Ă����̂ł���B
����ŔՌ]�̉]���s���̘ŐS�Ƃ́������ʒq�̖{����
�i���w�]�D���̔]�Ƃ��̓����j�ł��邱�Ƃ�������B
�Ռ]�́A���S�͐e���琶�܂ꂽ�Ƃ��Ɏp�������̂ł����ĕs���s�łȂ��̂ł���Ɛ����B
�������A���S�����������Đ��܂ꂽ���̂́A�����ɂ�Ċ�{���y�́u�O�v��
�o���Ă��܂��A�O�Ɏ����ĕ��S�������Ă��邱�Ƃ�Y��邱�Ƃ�
���ł���ƌ����B
���������~�����ɂ����Ƃ������O�͎����ɑ���u�g�т����v����
��������̂ł���A
�O�Ɏ���ꂸ���S�̂܂܂ɐ����邱�Ƃ��ł����
���̐l�͂��̂܂ܕ��ł���Ɛ����Ă���B
�u�ϑz��Â߂邱�Ƃ͓���̂ł����v�Ɛq�˂�ꂽ�Ռ]�T�t�́A
�u�Â߂悤�Ǝv���̂��u�O�v�ł��邩��A�Â߂悤�Ƃ��Â߂܂��Ƃ��l���Ȃ��ق����悢�B�v
�u�������D���ň��݂����Ǝv���Ă��A���܂Ȃ���Ό��N�ł�����B
�O�������Ă��A������܂�����܂܂ɂ��āA�O��p�����������������Ȃ���A
�s���̐S�̒��ւƏ��ł��Ă��܂����̂ł���B�v
�u�O�Ƃ͎��̂�������̂ł͂Ȃ��A�Ⴆ�Č����A���ɉf��e�̂悤�Ȃ��̂ł���A
���͌������ɂ�����̂��f�����A���̒��ɉe�𗯂߂邱�Ƃ͂��Ȃ��B
���S�͋��������{�����炩�ŗ얭�Ȃ��̂ł��邩��A
��̔O�͂��̌��̒��֏����ĐՌ`�������Ȃ�B�v
�Ɠ����Ă���B
�Ռ]�̕s���T�͂�������u���R�C�܂܁v�ƌ������₷���B
�������A�����܂ł��u�O�v�Ɏ����邱�Ƃ����������߁A
���S�̂܂܂ł���悤�����������������Ƃ���X�ɋ��߂Ă���̂ł���B
�Ռ]�T�t�̕s���T�͓��{�Ő��܂ꂽ���{�I�ȑT�ƌ����邾�낤�B
�Ռ]�T�t�͂��̌�^��ǂނƎ��Ɍ��I�Ŗ��͓I�Ȑl���ł��������Ƃ�������B
�s���T�͓��{�Ő��܂ꂽ�����I�ȑT�ƌ�����B�������A���̖@�n�͌��݂܂Ŏ����Ă��Ȃ��B
���̑T�͓��{�I�ł��邪�^�ɓƑn�I�Ȃ��̂ł��������ƌ����Ƌ^��ł���B
�u�s���̘ŐS�v�͔n�c����T�t�ȗ��́u���S�����i�������S�����j�v
�̎v�z�Ɗ�{�I�ɓ������Ǝv���邩��ł���B
�i �u����ցv�R�O���u���S�����v���Q���j
�Ռ]�̑T�v�z�͈ꌾ�ŕ\������Ɓu�s�������i�s���̐S�Ŗ�(����)�Ē�(�ƂƂ�)���j�v�ł��낤�B
�Ռ]�T�t�͌��đT�ɂ��Ď��₵���m�ɑ�
�u�g�ǂ������ő��̂悤�ȌÂق����̑F�c�͂��������B�v
�Ɠ����Ă���B
�܂��u�Ðl�����ĂȂǂŒ���(�Ă���������������)�̂͊w���̂��߂ɂȂ�ł��傤���H�v
�Ƃ�������ɂ́u�n���A�D���̂��Ƃ܂Œm������̂ł͂Ȃ��B�v�Ɠ����Ă���B
�Ռ]�T�t�͌��Ă��u�Âق����v�ł���Ƃ��Ă���Ȃɏd�v�����Ă��Ȃ��B
�u�Âق����v�Ƃ͏������Ȃ��̌Î��̂��Ƃł���B
�Ռ]�̎��R�Ŏ�̓I�ȍl�������f���Ėʔ����B
�u�ՍϘ^�v�̎��O�ŗՍς́u��̌o�T�͂��ׂĕs���@�����Î��ł����B�v�ƌ����Ă���B
�i �u�ՍϘ^�v���O�P�O�|�P���Q���j
���̔��Î����Âق����ƌ����Ă���Ƃ���ΗՍς̌����Ă���o�T�̑����
���Ă�u�����������̂ł��邱�Ƃ�������B
���Ă��u�Âق����v�ł���ƌ����Ռ]�̎v�z�͗Սς̎��R�Ȕᔻ���_�ɒʂ�����̂�����B
��_���ł́u�����v��u�R�[�����v����ɑ�ɂ���B
������_���̐��E�ŁA�u�����v��u�R�[�����v���u�s���@�����Î��i�K�ӂ����j�ł���B�v
�Ƃ��u�Âق����v�ł���ƌ�������Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ낤�B
�M�҂ɂ͌o�T����Ă��u�Âق����v�ł���ƌ����Ռ]��Սς����R�Ȕᔻ���_��
��_�����͂邩�ɐi�v�z�̂悤�Ɏv����B
�u����̎v�z�v���d�����镧���ƈ�_���̈Ⴂ���낤���H
�Ռ]�T�t��
�u���{�l�͓��{�l�Ɏ��������悤�ɁA����Ŗ�ӂ��悤�������B
���{�l�͊���ɂ��Ȃ��������āA����̖ⓚ�ł͎v���₤�ɖ�Ђ�����ʂ��̂ł������B�v
�Ɛ����B
�Ռ]�T�t�͊�����Ȃ�ׂ��p�������{�l���b��������p���Đ������B
�H�����a���͓��{�T�����̎O�嗬�ɕ����čl���Ă�����B
�P�D�����̓��{�����@
�Q�D���E���E�ցi�剞�A�哔�A�֎R�j���甒�B�ɗ��ꂽ���{�ՍϏ@
�R�D�Ռ]�̕s���T
�P�A�Q�͊�{�I�ɂ͒����T�̗���ł���̂ɑ��A
�R�̕s���T�͗Սόn�̑T���琶�܂�Ă��邪�ɂ߂ē��{�I�ȑT�ƌ�����̂����m��Ȃ��B

�P�U�W�T�N�F
�x�B�x���S�������i���݂̐É������Îs���j�Ő��܂��B�c���⎟�Y�B
���B�͓V�������ŋL���͂��ǂ������Ɠ`�����Ă���B
�P�U�X�X�N�@�i�P�T�ˁj�F
�o�Ƃ̎u�������A���ɗ��e�͏o�Ƃ��������B
�P�T�̎��A�ނ͏������O���P��c�`�a���ɂ��ďo�Ɠ��x�����B
�P�V�O�W�N�i�Q�S�ˁj�F
�z�㍂�c�̉p�����Ő��O�a���́u�l�V��ځv�̍u�`�ɏo�Ȃ����B
���̎����B�͎��̗��̂����œO�ꂵ�č��T�ɐ�S���A
�u��B�����v�̌��ĂɎ��g��ł����B
�i �u����ցv��P���u��B��q�v���Q���j
�\�]�����o�āA���łɎ���܂ō��T���āA���̐����Č��������B
���̎����B��
�u�����A�ޓ��a���͂܂ߑ��Ђł������킢�I�ޓ��a���͂܂ߑ��Ђł������킢�I�v
�Ǝv�킸���Ɠ`������B
��債�����B�͏����𐫓O�a���ɒ悵�����A����ɂ���Ȃ������B
�������A���B��
�u�O�S�N���A�����̂悤�ɒɉ��Ɍ�����҂͂��Ȃ������B
���̂悤�Ȏ����̋@�N�ɓ�����҂����悤���v
�Ɩ��S����Ɏ������B
���R�p�����ɂ����@�o�i����V�l�̒�q�j�����T�Ґ���V�l�i�����d�[�j�̂��Ƃ��A
�M�B�юR�̐�����ɍs���؍݂���B����V�l�ɎQ�T���邱�ƂW�����A
�����]�����ɂ߁A����V�l�̖@�k�ƂȂ����B
���̌㏼�����i���Îs�j�ɋA�����B�@
�P�V�P�O�N�i�Q�U�ˁj�F
�@������̋��E���A���ӊ��ɔY�܂����B�@
�Q�T�ɗ͂����߂������߁A���B�̐��_��Ԃ͋}���Ɉ�������B
�S�C�t��A�x���̒ɂ݁A���r�̗₦�A���o�A�����A�×�ԂɔY�ށB
���̕a���������߁A���s�k���͂̎R���ɏZ��ł������H�q�Ƃ�����l�ɉ�ɍs���A
���H�q������ς̔�@��������B���̓��ς̔�@�ɂ���ē�a�𐋂ɍ�������B
�P�V�P�W�N�i�R�S�ˁj�F
���B�ƍ����B
�P�V�Q�U�N�i�S�Q�ˁj�F
�H�̈��A�@�،o��ǂݒ^���Ă������A�����났�̂������������ɓ����Ă����B
���̎�歑R�Ƃ��Ė@�،o�̐[���^����������B
���̎�����V�l�̐S��������
�u�]�O�̌�𗹒m�͑傢�ɍ����Ă����v
�ƒm��o������������č��������ƌ�����B
���B�̔N���ł͂��̌�O�ȑO�����s�i�i���ȋ����̏C�s�̎����s�̎���j�̔��B�Ƃ��A
����ȍ~���ʍs�i�i�����Ɨ����s�̎���j�̔��B�Ƌ�ʂ��Ă���B
���B�T�̐^�����͂��̑̌��Ŗ��ĂɌ��ꂽ�ƍl�����Ă���B
�T�O�ˑ�`�U�O�ˑ�F
�����̎��ɏ�����ču�`�ɖ������閈���������B
���C�Ȗ@�{�̖������������V�X�˂ɂȂ��Ă�����ƕa�C�ɜ�������A
����ł��u�`����~�߂悤�Ƃ��Ȃ������B
�P�V�U�R�N�i�V�W�ˁj�F
�O���i�É����j�̗��V���𒆋����A�J�R�ƂȂ����B
�P�V�U�W�N�i�W�S�ˁj�F
�W�S�˂ɂȂ���������
�u�V�m���N�W�S���Ⴊ�A���̂悤�Ȑ����ɉ�����Ƃ��Ȃ��B
���������a���̂�������B�߂ł���I�߂ł���I�v
�ƌ������Ɠ`������B
���̔N�̂P�P���A�a���d���Ȃ��ď������ɋA�����B
��҂����B��f�āA
�u���̗l�q�ł͂����������Ƃ͂���܂����v
�ƌ������Ƃ���A���B��
�u�O���O�ɐl�̎���\�m�ł��Ȃ��悤�ł͗ǂ���҂Ƃ͌����Ȃ��B
����́A�߂����҂��v
�ƌ������B
�������Ă�Ō㎖���������A
�P�Q���P�P������݈ꐺ���Ď��������Ɠ`������B���N�W�S�ˁB
���a�U�N�i�P�V�U�X�N�j�A������V�c���_�@�Ɩ��T�t�A
�����P�V�N�����V�c��萳�@���t��拍����������B
���{�ՍϑT�����̑c�ƌ����锒�B�d�߂̖@�n�͎��̂悤�ł���B
�剞���t���哕���t���֎R�d���E�E�E���t�i���S���P�R�V���j
����������T�t��
����V�l�����d�[�����B�d��
����ɑ��A�Ռ]�i��̖@�n�͎��̂悤�ł���B
�剞���t���哕���t���֎R�d�����E�E�E��]�@�[�i�����^�ƑT�t�A�P�S�O�W�`�P�S�W�U�j
�E�E�E��i�@�ԁ��_��S�ˁ��q���c�����Ռ]�i��
���̂悤�ɁA���B�ƔՌ]�͋����剞���t���哕���t���֎R�d���E�E�E�̖@�n�A
�����u�����ւ̑T�v�̖@�n���p���ł���B
���ݓ��{�̗ՍϏ@�����B�@�ƌĂ�邭�炢���B�̖@�n�Ő�߂��Ă���B
���̈Ӗ��œ��{�ՍϏ@�́u�����ւ̑T�v�̖@�n���p�����Ă���ƌ�����B
��������̕����̑T�m�Ƃ��Ēm�����x�@���i�P�R�X�S�`�P�S�W�P�j���u�����ւ̑T�v�̖@�n�ł���B
�u�����ւ̑T�v�̉e���͂��@���ɑ傫���������������Ă���B
�����ł͑v�E����ȍ~�T�ƔO���̗Z�����i�݁A�T�͋}���ɐ��ނ��čs�����B
���B�͖����̑T�m�_���V���G(�������ケ���A1535�`1615�j��i�o�����̔O���T��ނ����B
�O���T�ł͔O���ƍ��T�̓�̏C�s��o�C���邱�Ƃŗ͂����U���A
�ǂ��������Ō������ł��Ȃ����ՂȑT�ɂȂ������炾�ƍl������B�B
�����u�M���q�v�ɂ����āA
���B��
�u�u�T��������y�����˂�A���̑T�͕K�������ɖS�т�ł��낤�v
�ƌ����Ă���B
���B�͍]�ˎ���ɉ��@�@��`�����B���T�t�i�P�T�X�Q�`�P�U�V�R�j
�𖭐S���Ɍ}���邱�Ƃɔ������B
�B���̉��@�@�ł͗ՍϑT�ɖ���̔O���T�������Ă������炾�ƍl������B
���ے����ł͐����ɓ���ƕ����͔O���T��F�ɂȂ�A
�@�E���ȗ��̏��@�͑S�Ďp�������A���B���������悤�ɁA�T�@���̂����S���čs�����B
���B�́u���k�^�J�������v�Ŏ����̂悤�ɐ����A
�u�Q�T�ɂ͎��̎O�v�i�O�v�f�j���K�v�ł���B
�P�D��M���A�Q�D��^���A�R�D�啮�u�@�̎O�ł���B
������M���A��^���A�啮�u
�Ŗ����֖̊��˔j����������B
�������A�u���k�^�J�������v�Ő����ꂽ��M���A��^��A�啮�u
�̎O�v�f�͔��B�̓Ƒn�ł͂Ȃ��悤���B
���N�n�̌�^�u�T�ƋT�Ӂv�ɂ�
�u�Q�T�ɂ͐{�炭�O�v����ׂ��B
��ɑ�M���L��B��ɑ啮�u�L��B�O�ɑ�^���B���₵�������̈���������A
�ܑ��̓C�̔@���B�I�ɔp��ƂȂ��B�v
�Əq�ׂ��Ă��邩��ł���B
���B�͂܂�
�u�������邱�ƂőT�̑��֖��˔j�����v
���Ƃ��厖�ł���ƍl�����B
�������A���������Ŗ������Ă͂��߂��Ƃ���B
�܂��u�����v���o��������A
�u���̏C�s�i���ْ��{�j�v�Ō���[�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�u�����v��
�u���̏C�s�v�̂Q��������đT�̊���������ƍl�����̂ł���B
�i�P�j�u�����v��
�i�Q�j�u���̏C�s�v
�̓�i�K�͔��B�T�̂Q�{���Ŕ��B�̓Ƒn�ƌ����邾�낤�B
���B�T�ł͑T�̍ő�֖̊�́u�����v�ł���Ƃ���B
�u�{���̖ʖ��v���o�m��������́A
�e�C�s�҂́u���̏C�s�v�ɂ����
���̓��e��[�߂邱�ƂɂȂ�B
���̍l�����͎��H�I�ɂ��ȒP�ŕ�����Ղ��B
�u���̏C�s�Ɛ��ْ��{�v��
�哕�A�֎R���d���������̂ł���A���{�T�̓����ƂȂ��Ă���B
�哕�͂Q�O�N�A�֎R�d����9�N�A
���B�̎t����V�l�i�����d�[�j��44�N�����ْ��{�̎��������Ă���B
���B�͂���������ꂽ�ƌ�����B
�ꐶ��ʂ����T�ƌ��̒Nj����l��������ł��낤�B
����́A�ꐶ�����œ��������ƍl������{�̃T�����[�}���̍l�����ɒʂ�����̂�����B
�}�T�D�V�Ɂ@�u�����v��
�u���̏C�s�v���琬�锒�B�T�̓�i�K�̑T�������B
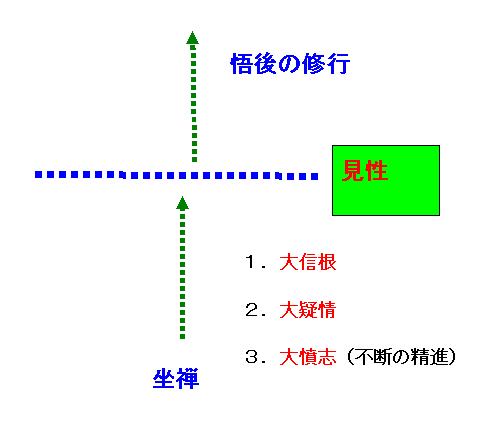
���B�̒����u����ďƁi�ق������傤�j�v�Ɏ��̌��t������B
�u��m�炸��O�̌����邱�Ƃ��A�֓�煔j�i����ρj�͕K���T�ɋ߂����B�v
���B�͊֓�煔j�̗E�҂ȍs�����͐��O�̑T�̐��_�ɋ߂��ƌ����č����]�����Ă������Ƃ�������B
煔j�Ƃ͐퍑����̔E�҂̂��Ƃōr����҂Ƃ��������̂��Ƃ��Ӗ�����B
���O�̑T�́u�m���s���T�v�ƌĂ��B
�u�m����s���̂悤�Ȍ������������S�������č��T���A���̋C��������������������B�v
�Ƃ����T�ł���B
�u�m���s���T�v�͐��̌����琶�܂ꂽ�T�ƌ�����B
���B�͌����ɂ͑�M���A��^��A�啮�u�̎O�i�O�v�j���K�v�ł���Ƃ����B
���B�͐�y���O�́u�m���s���T�v�ɑ啮�u�������̂ł͂Ȃ����낤���H
���B��
�u�����̐��O�H�v�͐Ò��̍H�v�ɏ����v
�ƌ����B
�T�蒆�ł́A�]���A��]�Ӊ��n�̖��ӎ������������Ă���B
���̎����������ɂ���~�S�ƝG���̂ɂ���n���̐S�͏[���R���g���[��������艻���Ă���B
�s�͑�]�O���t�̒m���◝���̎x�z���ɂ���B
���̂悤�ɁA�O�ł̓�
�u�n���v�̓�ł͒�́i�T��́j�ɂ���ď[���R���g���[������邵�A
�u�s�i���납���j�v
�̓ł͑�]�O���t�̗����̎x�z���ɂ����ď�������B
�@ �]���Ē�ƌd�������Ă����
�n�E�сE�s
�̎O�ł͌�����������B
���̂��Ƃ͒�ƌd�������Ă���Ή������s�v�ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B
���T�C�s���琶�܂��T��͂ɂ����
�n�E�сE�s
�̎O�ł͖����Ȃ邩��ł���B
����̑��d�C��
�u���E��E�d�v�̎O�w�͑T��ɓ���ł��邱�Ƃ��������B
�i�u�O�w�̓���v���Q�� �j
�u�O�w�����v�̍����������ɂ���ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
����̑��d�C�͂��̒��u�ڌ�v��v�ɂ����Ē�ƌd����퐶���ɓ������邱�Ƃ�
�u��d����v
�ƌ����Ă���B
�i�u��d��́v�̎v�z���Q�� �j
����͔��B�̌���
�u�����̐��O�H�v�v
�ɑ������邾�낤�B�@
�u�����̐��O�H�v�͐Ò��̍H�v�ɏ����v
�Ƃ������B�̍l�����ڎw�����̂�
���퐶���ɂ����Ē�͂Ɨ����i�d�j�����邱�Ƃŕn�E�сE�s�̎O�ł�
���������邱�Ƃɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�����l����ΐ��O�́u���@�����@�v�̍l���Ɠ����ł���B
�i�}�T�D�T�Q�Ƃ��� �j
�u�b�_���������Łu���O�v�Ɓu����v�������Ă���̂ŁA
�u�����̐��O�H�v�v
�͌��n�����́u�������v�ɂ��q����D�ꂽ�l�����Ƃ�����B
���B�T�t�ɂ́u�ǎ�̐����v�Ƃ����L���Ȍ��Ă�����B
���͗����ł��ď��߂ďo��B�ܘ_�Ў�ʼn����o���͂Ȃ�����ǎ�̐���
�������Ǝv���Ă��������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�C�s�҂͎t�Ƃ�
�u�ǎ�̐����܂����v
�Ɠ�����A
�u�Ў�ʼn����o���͂Ȃ��B�ǂ����Đǎ�̐������Ƃ��ł����̂��H�v
�Ɣ��₳���B
�����u�������Ƃ͂ł��܂���ł����B�v
�ƌ�����
�u���Ƃ����ĕ����ė����B�v
�Ɨv�������B
������A�t�Ƃ�
�u�ǎ�̐����܂����v
�Ɠ�����Ηǂ��̂��낤�ƍl���āA
�u�ǎ�̐����܂����v
�Ɠ�����A
�u�o�Ȃ������ǂ����ĕ������Ƃ��ł����̂��H�v
�Ɣ��₳���B
���̖ⓚ�̌J��Ԃ��ɂȂ�B
���̌J��Ԃ��ŏC�s�҂͂���ǂ����܂�A��̐▽�̂Ƃ���܂Œǂ��l�߂���B
���̖��͐��A��̔��f���i�闝�m�i��]�O���t�Ȃǂ̗��m�]�j�ł͉����ł��Ȃ��B
�Սς�
�u�����݁A�ڂ̑O�Œ��@���Ă�������g���c���ɑ��Ȃ�Ȃ��i��ʑO���@��j�j�B�v
�ƌ����Đ��@���Ă����́i�]�j���c�����ƌ����Ă���B
���̌��Ă̖ړI�́A
�����Ă����͉̂���
�Ƃ����₢�ɑS�ӎ����W�������邱�Ƃ�
���Ȗ{���̖ʖ��i���w�]����̂Ƃ���]�j���o�m������Ƃ���ɂ���ƍl������B
���T�ɂ���Ă��̌��ĂɑS�ӎ����W��������Ɣ]�����S�̖��ӎ��̐S�܂ł�
���������ĉ��Ƃ��������悤�Ƃ���B
���̂��ƂŎ��Ȗ{���̖ʖڂł��鉺�w�]�ɂ܂ŏW�����u�����v����
�Ƃ���ɂ���Ǝv����B
���Ă̑̌n���͊��q����̉~���ى~�i����ɂׂ�A�P�Q�O�Q�`�P�Q�W�O�j�Ɏn�܂�B
�ނ͐獷���ʂ̌��Ă��u���v�E�@�ցE����v
�̎O�ɕ��ނ����Ă̑̌n�������݂��B
�剞���t�i��Y�Ж��A�P�Q�R�T�`�P�R�O�X�j��
�u���̏@�ɎO�d�̋`����B�������u���v�E�@�ցE�����v����Ȃ�B
���v�Ƃ����́A�����̏����A���тɑc�t�̏����̐S�����̗���Ȃ��B
���ɋ@�ւƂ����́A�����c�t�̐^�̎��߂�������A
������@���Ђ˂����u�����ĉ]���A�w�D������сA�Δn���ɓ���x������Ȃ��B
�̂��̌���Ƃ����́A���c�̒����A���@�������A
�w�V�͂���V�A�n�͂���n�A�R�͂���R�A���͂��ꐅ�A��͉��A�@�͒��x������Ȃ��B�v
�ƌ����Ă���B
���̂悤�Ȍ��Ă̕��ނ�̌n���͒����v��̑T���B�ɂ���Ď��݂��Ă����ƍl������B
�������A���Ă̑̌n�����ӎ��I�ɐ����i�߁A�����̌��đT��听�����̂�
���B�d�߁i�P�U�W�T�`�P�V�U�W�j�Ƃ��̖剺�̓���~���i�P�V�Q�P�`�P�V�X�Q�j�ł���B
����́u���B���̌��đ̌n�v�ƌĂ�Ă���B
�u���B���̌��đ̌n�v�́u�@�g�A�@�ցA���F�A��A�����v�̌܂��Ȃ�B
����͉~���ى~��剞���t�́u���v�E�@�ցE�����v�̎O���ނ��ܕ��ނɂ����Ƃ�������B
�u���B���̌��đ̌n�v�́u�@�g�v�͉~���ى~��剞���t�́u���v�v�ɑΉ����A
�u�@�ցA���F�A��A�����v���u�@�ցE�����v�ɑΉ����Ă���B
�~���ى~��剞���t�̎O���ނ��ܕ��ނƕ��G�ɂȂ��Ă��邪�{���I�ɂ͓����ł���B
���đ̌n�̊e���ڂ͕�����Ղ������Ύ��̂悤�ȓ��e�ł���B
�u���v�v��u�@�g�v�Ƃ͑T�̌��̊�{�ƂȂ���Ă̂��Ƃ�
�A�~���ى~��剞���t�́u���v�v�Ɠ����ł���B
��B�̖����̌��ĂȂǁu�{���̖ʖځv��u�����v�ȂǂɊւ����{�I�Ȍ��Ă������B
���̌��Ă߂��邱�Ƃ�������u�����v�Ƃ����i�K�ł���B
�S�Ă̌��Ă݂͂Ȃ�������{�Ƃ��A�L�킱��ɋA������B
�u�{���̖ʖځv��u�����v�Ȃǂ�����̎������œ�����p�����ʂ�
�c�t�B���ǂ̂悤�ɑΏ�����������̓I�ȁu�T�ⓚ�v
�Ɍ��ĐS����[�߁A��������B
���̏C�s�̂��߂̌��Ăł���B
�s�������̑T�̌��Ɩ@�������t�łȂ�Ƃ��\�����邱�ƁB
�u�����o�v�ɂ͏@�ʁi�@�|�ɒʂ���j�Ƃ����ʁi�\���E�����ɒʂ���j
�ƌ���ꔒ�B���œ��ɉ�����ꂽ�J�e�S���[�ł���B
���B�����w�I�\�����d���������炾�Ǝv����B
���߂�����Ăł���B
�R��Ȃ��R����ƌ�����悤�ɑT�̌��̋��n�ɂ͏I��肪�Ȃ��B
�Ƃ�����Β�������Ȗ@���E����
�i�@�ѕ����d�Ă����Ɏ�����錩���E���n�j�����z���A
��ϑT�I�T�L�E��L�����߂̌��Ăł���B
�u���B���̌��đ̌n�v�͉~���ى~��剞���t�̎O���ނ��ܕ��ނƕ��G�ɂȂ��Ă��邪
�{���I�ɂ͓����ł��邱�Ƃ�������B
���B�T�t�́u�ܕS�N�s���o�v�ƌĂ���{�ՍϑT�����̑c�Ƃ����B
���{�̗ՍϏ@�͔��B�̖@�n�Ő�߂�ꔒ�B�@�Ƃł�������悤�Ȕ��W������B
���̗��R�Ƃ��Ĕ��B�̖@�k�ɂ͓���~���E������ḂȂǑ����̈̍ނ��������Ƃ̑��ɁA
���̂悤�ȁu���đ̌n�v���J���������Ƃ��l������B
�u���đ̌n�v�����H�Nj����čs���Β����Ɍ勫��[�߂邱�Ƃ��ł�������ł���B
���̈Ӗ��Łu���đ̌n�v�v�͑T�̃}�j���A���Ƃł������邾�낤�B
���B�͑T�������ɂ�������Ղ��������B�����̍��T�a�]���L���ł���B
�O���{�����Ȃ�B�@���ƕX�̂��Ƃ��ɂĐ��𗣂�ĕX�Ȃ��A
�O���̊O�ɕ��Ȃ��B
�O���߂���m�炸���āA�������ނ�͂��Ȃ����B
���Ƃ��ΐ��̒��ɋ��āA�������Ԃ��@���Ȃ��B
���҂̉Ƃ̎q�ƂȂ�āA�n���ɖ����ɈقȂ炸�B
�Z��։�̈����́A�Ȃ���s�̈Œn�Ȃ��B
�Œn�ɈŒn�݂��ւāA���������𗣂�ׂ��B
���ꖀ�d���̑T��́A�̒Q����ɗ]�肠���B
�z�{�⎝���̏��g�����A�O�������C�s�����i�������P�s�A
�F���̒��ɋA����Ȃ��B
����̌����Ȃ��l���A�ς݂����ʂ̍߂ق���A
����Â��ɂ���ʂׂ��A��y���������炸�B
�J�������̖@���A�ꂽ�ю��ɂӂ�T���A�]�V���삷��l���A
���邱�ƌ���Ȃ��B
���͂�⎩�������āA���Ɏ�����������A
�������������ɂāA���ɋY�_�𗣂ꂽ���B
���ʈ�@�̖�Ђ炯�A���O�̓������B
�����̑��𑊂Ƃ��āA�s�����A����]���Ȃ炸�A
���O�̔O��O�Ƃ��āA搂ӂ����ӂ��@�̐��A�O�����V�̋�Ђ낭�A
�l�q�~���̌��������B
�������������ނׂ��A��Ō��O����䂦�ɁA���������@�؍��A
���̐g�������Ȃ��B
��
�Z��F�@�V�E�l�E�C���E�{���E��S�E�n���̘Z�̖����̐��E�B�Z���Ƃ������B
�Z��։�F�@�V�E�l�E�C���E�{���E��S�E�n���̘Z�̖����̐��E�܂�ς�邱�ƁB
���d���i�܂�����j�F�@��敧���B
�g�����i�͂�݂j�F�@�z�{�A�����A�E�J�i�ɂ�ɂ��j�A���i�A�T��A�q�b�̘Z�̎��H���ځB
�Z�g�����̂��ƁB
�i�u�Z�g�����v���Q�� �j
���(�������j�F�@����ԏƁi�������ւ傤�j�A�{�S�𖾂�߂邱�ƁB
���ʈ�@�̖�F�����Ƃ��Ă̏O���͌��ʂł��镧�Ɠ����ł���Ƃ����@��B
�O���ƕ��͖{���I�ɓ����ł���Ƃ����@��B
���O�̓��F��ł��O�ł��Ȃ����ւ̈�̓��B
���֎����̓��B
�l�q�i�����j�F��~���q�i�������傤���j�A�������q�i�т傤�ǂ����傤���j�A
���ώ@�q�i�݂傤�����j�A������q�i���傤���傳���j�̎l�̒q�b�B
�l�q�͕��̒q�d�Ƃ����B
�@�؍��i������j�F���̍��B�Ɋy��y�B
������
�������͖{�����ł���B
����� ���傤�ǐ��ƕX�̂悤�Ȃ��̂Ő����Ȃ��ƕX���ł��Ȃ��̂Ɠ����悤��
�O���̑��ɕ��͂Ȃ��̂ł���B
�������͖{�����ł��邱�Ƃ� �m�炸�ɂ������� �T���܂��̂� �ނȂ������Ƃ��B
����́A���Ƃ��ΐ��̒��ɂ��Ȃ���A�u�A���������I�v�� ����ł���悤�Ȃ��̂��B
�{���͗T���ȉƁi���̉Ɓj�̎q�Ƃ��Đ��܂�āA�ƂĂ��K���Ȃ͂��Ȃ̂ɁA
���̂��ƂɋC�t�����A�u�킽���͕s�K���v�ƒQ���Ă���̂� �������Ƃ��B
���܂ł���̐��E���甲���o�����Ƃ��ł��Ȃ�������
�^����m�炸�Ɏ����̋��������悭��ƒQ�����߂��B
�����̈ł���ł�����Ă������ł͐����̋ꂵ�݂��炢����邱�Ƃ��ł��邾�낤���H
��敧���̑T��C�s�͓��ɑf���炵������������A�������̑傫�Ȏx���ƂȂ�B
�z�{�⎝���Ȃǂ̑P�s�O�������C�s���Ȃǂ��܂��܂ȑP�s�̂��ׂĂ�
�T��C�s�ɋA�蒅���̂ł���B
�ЂƂƂ��A�Â��ɍ��T������܂Őςݏd�˂��Y�݂��Ƃ�s���Ȃǂ͏��ł��Ă��܂��̂��B
�������ȂLj�̂ǂ��ɂ���Ƃ����̂��낤���B
�Ɋy��y�͉��������ɂ���̂ł͂Ȃ��B���A�����ɂ���ł͂Ȃ����B
���肪�������ƂɁA ���̋�������x�ł� ���ɂ������ɐ[���ق߂������āA
�����l�͂��Ȃ炸������Ȃ��K������ɓ���邾�낤�B
�܂��Ă�݂����獿�T���āu�{���̎����v�𖾂炩�ɂ���A
���Ȃ̖{���͖����ł���A���łɂ܂�Ȃ��c�_��ϔY���z���Ă���̂��B
���̎��A���ƈ�̂Ƃ����@�傪�J���A���ւ̌��̓������ʂ���̂��B
�ǂ��ɂ��{�����܂����`���Ȃ��A�ǂ��ɍs���Ă��S�Ɉ��炬������B
�S�ɂ͉���������肪�����̂ŁA�̂��Ă������Ă� ���̂܂ܕ��@�ɂ��Ȃ��������y���������₩���B
�S�͐��ݐ������̂悤�ɍL���萴�炩�Ȍ��̂悤�Ȍ��̐S���P���Ă���B
���̎��A�ق��ɉ������߂�K�v�����낤���B
�S���Â܂�A���ɂ̈��S������ꂽ���A���̐������̂܂܋Ɋy�ł���
���̐g�����̂܂ܕ��Ȃ̂��B
���̍��T�a�]��ǂ߂A���B�́u���̐g�������Ȃ��B�v�Ƃ��Ă���B
���̂��Ƃ��甒�B�͕��Ƃ��Ă̎��o�Ă������Ƃ�������B
���B�������T�@�͕��ɂȂ�i�����j�̂��߂́u�����v�ł���A
�u�P�Ȃ��F��i���j�ł͂Ȃ��v���Ƃ�������B
���B�͂Q�U�ˍ��A�Q�T�ɗ͂����C�s���邠�܂�A���_��Ԃ͋}���Ɉ��������B
���E���A���ӊ��A�S�C�t��A�x���̒ɂ݁A���r�̗₦�A���o�A�����A
�×�ԂȂǏ\���̋����ɔY�܂����悤�ɂȂ����B
������T�a�ƌ�����a�C�i�_�o�ǁA�m�C���[�[���邢�͌��j���H�j�ɜ�����̂ł���B
�ނ͂��̓�a�����Â��邽�ߋ��s�k����̎R���ɏZ�݁A
�[����p�ɒB���Ă����������H�q�i�͂��䂤���j�Ƃ�����l�̕]�����ĖK�˂��B
���H�q��苳���Ė�������ς̔�@�����H�������߁A�a�C������A
�������茳�C�����߂����Ƃ��ł����B
���B�͒����u��D�b�v�ɂ��̓��ς̔�@�������Ă���B
���H�q�����B�ɋ��������@�́u���ς̔�@�v�Ɓu����(�Ȃ�)�̖@�v�ł���B
���B�͌����A
�u���T�C�s�ɂ���āA�S���t�シ����A
�g�S�Ƃ��ɔ��A�ܑ��̒��a������邱�Ƃ������B
�����Ȃ��Âɂ���Ă��������Ƃ̂ł��Ȃ��a�ł��邪�A�����ɗ��O�̔錍�Ƃ������̂������B
��������H����Ȃ�ρA�K���ڊo�܂������ʂ�����ł��낤�B
���̔錍���C�߂�ɂ́A�Q�T�H�v�͂ЂƂ܂������āA�܂���������ꖰ�肷�邱�Ƃ��B
�܂�(�炵��)����ނ��āA���������荞�܂Ȃ����A
���r���������݂��낦��悤�ɒ����L�ς����A
�̒��̌��C�������`�ցA�C�C�A�O�c�A���r�A
�����đ��S�ɏ[�����悤�ɂ���.�����Ď��̂悤�Ȋϑz�i�C���[�W�j������̂ł����B�v
�P. �킪���̋C�C�O�c���r���S�A�܂��ɐ���킪�{���̖ʖځA�ʖڂȂ�̕@�E�������B
�i�@���̋C�C�O�c�A���r���S���܂��Ɏ��̖{���̖ʖڂł���B
���̖{���̖ʖڂ̕@�E�͂ǂ��ɂǂ̂悤�ɕt���Ă���̂��H�j
�Q. �킪���̋C�C�O�c�A�܂��ɐ���킪�{���̉Ƌ��A�Ƌ��Ȃ�̏����������B
�i���̂��̋C�C�O�c���܂��Ɏ��̖{���̉Ƌ��ł���B���̖{���̉Ƌ�����̏����͂ǂ��������̂��낤���H�j
�R. �킪���̋C�C�O�c�A�܂��ɐ���킪�B�S�̏�y�A��y�Ȃ�̑����������B
�i���̂��̋C�C�O�c���܂��Ɏ��̐S�̏�y�ł���B���̏�y�͂ǂ̂悤�ɑ�������Ă���̂��낤���H�j
�S. �킪���̋C�C�O�c�A�܂��ɐ���킪�Ȑg�̖�ɁA��ɂȂ�̖@���������B
�i ���̂��̋C�C�O�c���܂��Ɉ���ɕ��i�Ȑg�̖���j�ł���B
���̈���ɕ��i�Ȑg�̖���j�͂ǂ̂悤�ȕ��@������Ă���̂��낤���H�j
�ȏ�̂悤�ɌJ��Ԃ��ϑz�i�C���[�W�j���Ȃ���
�����ċC�̒O�c�ċz������̂����ς̔�@�ƌ�������̂ł���B
���B�͌����A
�u���̂悤�ɌJ��Ԃ��A�J��Ԃ��ϑz���Ă����Ȃ���A
�₪�āA��g�̌��C�͂��������r���S�ɏ[�����āA�`�̉����Z�\�̂悤�ɂӂ�����A
��ō�����d���R�f�̂悤�ɂȂ��B
���̂悤�Ȋϑz����T�ԂȂ����O�T�ԑ�����Ȃ�ρA����܂łܑ̌��Z�D�̋C�̑���A
�S�C�̐����̂��߂̗�⊾�A���Ƃ������Ǐ�͂������莡��ł��낤�B
��������Ȃ���A�V�m�̎������Ă���낵���v�B
���ς̔�@�̑�R���Ƒ�S��������Ε�����悤�ɁA
���B�́u�Ȑg�̖���v�̎v�z�������Ă������Ƃ�������B
�u�Ȑg�̖���v�̎v�z�͔��B�́u���T�a�]�v�ɂ�������B
����(�Ȃ�)�Ƃ͓�炩�ȃ`�[�Y���o�^�[�̂悤�Ȏ����L���ȓ`����̐H�ו��ł���B
�܂����T��g�ݐg�S���[�������b�N�X������B
��͔���ɊJ���A�ċz�𐮂�����A���̂悤�ȃC���[�W��S���őz������B
�u����(�Ȃ�)�i�����Ȑ�������Ċ��̗���Ɋۂ߂���炩���N���[����̖�j�v
������ɍڂ��Ă�B
���́u�����v�́A�F���������荂����ł���B
���ꂪ�A�̉��ŗn���āA���ꉺ��̂��ϑz�i�C���[�W�j����B
���́A��������G��A���߂��݂������A�������痼�r�A���܂ŗn�������̂����ݓn��B
�w�����������G�ꂻ�ڂ�A�畆��ʂ��ėn������ŁA
�݂������܂ł̏��튯�A�w����]���Ȃǂ܂ł������A�������Ɨ��ꂭ�����Ă䂭�B
�����ɁA�����ɂ�����E�ϔY�E��������A�g�̂̒ɂ݂Ȃǂ��A
���炳��Ɨ��ꂭ�����Ă䂭�̂�������B
��������ė��ꂭ���������i����(�Ȃ�)�j�͑��̗��܂ŏ����A
�����������ɂ��܂�悤�ɁA�̉��ŗn�������̍����܂ŗ��܂�A
���̂Ȃ��ʼn��������ԂɂȂ�B
���̊ԁA�����Ɨǂ�����������A
�S�g�̃o�����X���ǂ��Ȃ邱�Ƃ������A���C���o�Ă���̂����o����B
��q�̂悤�Ȉ��̃C���[�W�Ö@���u�u�����v�̖@�v�ƌĂ����̂ł���B�@
�����͕����ċz�@�ƃC���[�W�ґz��g�ݍ��킹���Ɠ��̌��N�@��
�u���B�̌��N�@�v�Ƃ��Č㐢�����̐l�ɉe����^�����B����͂��͂��@�ł����ł��Ȃ��B
���{�̑T�@�͑����@�ƗՍϏ@�ɑ�ʂł���B��ؑ�ٔ��m�ɂ��Ύ����̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B
���{�̑����@�͓����@�Ƃ������̂ɂȂ��ē����T�t���̐l�����肪�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B
�����@�͓����T�t�̐l�i�ɏW�����Ă���X���������B
�����T�t��ᔻ�I�Ɍ���悤�Ȃ��Ƃ͖w�ǂȂ��B
���̈Ӗ��������@�͓����@�ł���B
����ƑΏƓI�ɗՍϏ@�͓����T�t�̂悤�ɓ���̐l�𗧂Đ_�i������悤�ȌX���͂Ȃ��B
����Ŏ��R�ɖ@�ɏW������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��c�����B
�����@�͓����̒����u���@�ᑠ�v�̌����ɑ傫�ȃG�l���M�[���₷�B
�������������̂Ɉꐶ��v�����Ă���ƌ����Ă��������炢�ł���B
���{�̗ՍϏ@�͌��Ă𗧂Ă�Řb�T�ł��邪�A
�����@�͌��Ă𗧂Ă����Ǒō��ُ̖ƑT�ł���B
���{�̗ՍϏ@�͒����̑c�ł��锒�B�d�ߑT�t�̖@�n�ł���B
���B�T�t�͌��Ē��S�̑T���m���������ߌ��݂̗ՍϏ@�͌��Ē��S�̊Řb�T�ł���B
�����������Ŏt�������V���@��͒��������@�̖@�n�ł���B
�]���ē����̑T�͑����T�ƌ����Ă��ǂ����낤�B
�����͍݉Ƃɂ�鍿�T�C�s���ے肵�Ă��Ȃ����A
�o�Ƃ������Ƃ̊ւ�����؎Ւf���Ă̑T���ŏ�Ƃ���������������B
�������J�����ߑ����̂��̂ɋ߂Â����Ƃ���A
�����I�ȁu���`�̕��@�v�̒Nj�������
�������^�ʖ��i����߂�����j�Ƃ����邾�낤�B�@
�����̋����͏����ŕ��G�ȂƂ���͖����B
�Ƃ��낪�����̎���A
�ނ́u���`�̕��@�v�͒�q�B�̊Ԃłǂ�ǂ��I�E�V��I�Ȃ��̂�������A
�ϗe���čs�������ʂ������Ă����B
�����@�ł͓��������c���z��t�ƌĂԁB
�����͎ߑ��ȗ��́u���`�̕��@�v�������ɒNj����A�T�@��@�h�ɕ�������̂��������B
�����͑����@�̊J�c�ɂȂ�Ȃ�ď������l���Ȃ������ł��낤�B
�����@�ł͓��������c�ƌĂԁB
���c�Ƃ͉�����c�Ƃ����Ӗ�������A�����@�i���{�����@�j����������n�܂����Ƃ����Ӗ��ł��낤�B
�Ƃ��낪�A�����@�ɂ͏@�c�����ȊO�ɂ��d�v�͐l�����݂���B
���ꂪ���c�ƌĂ�����R�����i�������傤����A�P�Q�U�W�`�P�R�Q�T�j�ł���B
�����@�ł͓��������ɓ����鑶�݂ł���Ƃ���A���R�T�t����ɓ����鑶�݂Ƃ���Ă���B
���̂悤�ȍ��c�⑾�c�ƌĂ�鑶�݂����@�h�͑��ɂ͗�����Ȃ��B
���R�����͖@�n��ŕ��i���c�j�Ƃ���铹���ɉ�������Ƃ͂Ȃ��B
�����̎���P�T�N��ɐ��܂ꂽ�l�ł��邩�炾�B
���R�����͖������w�B��䂸��̊ω��M�ɓĂ��T�t�ł������B
�ނ͐��`�̕��@��Nj�������A
���O�ɕz�����邱�Ƃő����@�̋��B���g�傷�邱�Ƃɓw�͂����l�ł���B
�����Ƃ͂ǂ����ѐF���Ⴄ�B
壎R�T�t�����c�ƌĂ��̂͑����@���@�h�Ƃ��Ĕނɂ���Đ������唭�W����������ł���B
�����@�̎�����̊J�c�ƍl���Ă��ǂ��قǏd�v�Ȑl���ł���B
���c�Ƃ͈�@��h���J�������m�������B
���c�́A��������������n�܂����������Ƃ̎n�c�������B
�����͑����@�̌���������n�n�����l�A
���R�����͓��{�����@�����ۏ㐬���������l�Ƃ����Ӗ��ł��낤���B
��������̐}�T�D�W�Ɏ����B
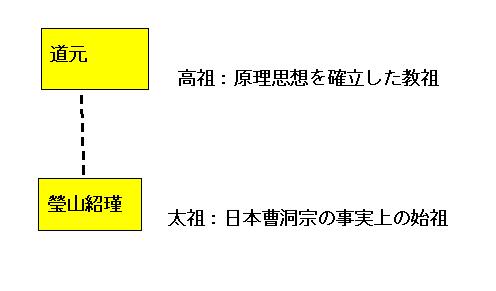
���R�����͑T�����łȂ��������w�B�ω��M�ɓĂ��T�t�ł������B
壎R�T�t�����c�ƌĂ��̂͑����@�����ۏセ������唭�W����������ł���B
�������c�͂���܂ő����@�Ƃ��Ă��Ȃ������B
���܂�ɂ������ȋ��c�ł���������ł���B
�����@�i���{�����@�j�̕��G�ȂƂ���͂��̑�{�R�ɂ�������B
�����@�̑�{�R�͓����̂ł���B
�ЂƂ́A��[�����䌧�i���������i�����A
�����ЂƂ́A���݁A���l�s�ߌ���ɂ����������ł���B
���̂ق��ɂ́A�����@�ɖ{�R�͂Ȃ��B
�������{�����@�m�c���Łu�O�㑊�_�i�����������j�v�ƌĂ�镴���������������������Ƃ��m���Ă���B
�u�O�㑊�_�v�Ƃ͉i����3���O�ʋ`�������鑈���ł���Ƃ����B
�������A���̓��e����j�I�o�܂ɂ��Ăِ͈��������A
�u�O�㑊�_�v�������Ӗ����邩�ɂ��Ė������_�͏o�Ă��Ȃ��B�@
�O�㑊�_�Ƃ́A���i4�N�i1267�N�j���炨�悻50�N�Ԃɂ킽���������@���̏@��Η��̑��̂ł���B
�J�c�����̈╗�����炷��ێ�h�Ɩ��O�������d���������v�h�̑Η��ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�i�����̑T���͓����̖v��A��������i1198�`1280�N�j���o����O��O�ʋ`��̎��傫�ȓ]�������}����B
�i�����O���ƂȂ����O�ʋ`��̑T�̓����͓O�ʋ`��i�i�����O���j�Ƃ��̈�}�ɂ͐^���@�̏o�g�҂������������Ƃł���B
�`��J���������掛�͒n���̗L�͎҂��^���@�̑m���̂��߂Ɍ��������^���@���@�������B
�`��g���V��@���w�B
���̂��Ƃ�����O�ʋ`��̑T�͑T�����C�ɋ߂��ƌ����邾�낤�B
�`��͉����i�i�����j�̗v���ɂ���ē��v���A�S�N�Ԋe�n�̖�����������Ƃ������Ă���B
�A����͓��v���Ŋw��ŗ������ʂ��i�����̉���������e��̋V���̋K�͐����ɔ��f�����A�i�����̉^�c�ɓw�͂����B
�ނ͏o�Ǝ҂̂��߂����̉i�����ł͂Ȃ��A�����ւ̕z���ƒ��a���W��}�낤�Ƃ����ƍl������B
���̂悤�ȘH���͓����̏o�Ǝ҂𒆐S�Ƃ���C�s���S�i���Ǒō��j�̘H���Ɩ��炩�ɈႤ�B
���̂��߁A�����̐����������I�ȑT����葱���悤�Ƃ����~���͂��߁A
�i������l��`�����̕ێ�h�i�����̈╗����錴����`�h�j�ƈӌ��̑Η��������A
1272�N�O�ʋ`��͉i������ނ��A�剺�ł������R������Ƌ��ɑ�掛�ֈڂ����B�@
���ꂪ������u�O�㑊�_�v�ƌ����鑂���@�����̕����̐^�����ƍl�����邾�낤�B
����͎��̂悤�ȕێ�h�Ɗv�V�h�̑Η��̐}�ɂ���ƕ�����₷���B
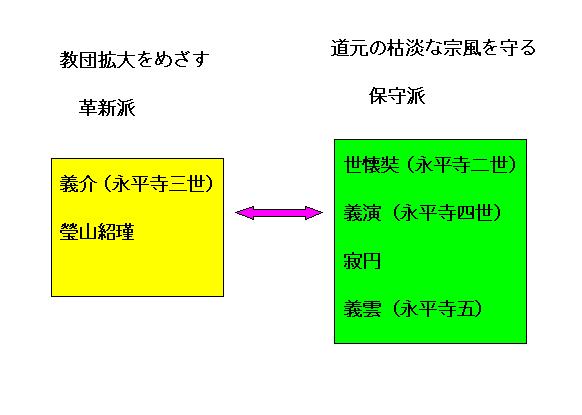
���̕����͓����̈╗����낤�Ƃ���ێ�h�̏����ɋA���A�i�����l���͕ێ�h�̋`���A�i�����ܐ����ێ�h�̋`�_�ɂȂ����B
�i�����ܐ��̋`�_�͈�U�r�p�����i�����̍ċ��ɗ͂�s���������߁A�u�ܐ������`�_��a���v�ƌĂ�Ă���B
�`�_�͕ێ�h�̎�~�̍���ł������B
�`�_�̌�@�i�����Z���͂Q�S���Ɏ���܂ŕ�c���i�ق����傤���A���䌧���s�j��������Ă���B
�@��c���͎�~�T�t���J�R�ƂȂ����ێ�h�̎��ł���B
���̂悤�ɁA�u�O�㑊�_�v�̌�i�����͓����̈╗����鎛�Ƃ��đ��������B
�����̈╗����鎛�Ƃ��Ă̓`���͌��݂ɂ܂Ŏ����Ă���B
�O�㑊�_�̌���A�������c�͑��ς�炸�������܂܂ŁA����Ȃ������B
�ނ���A�@���̂܂܂ł͏�������^���ɂ������ƌ����邾�낤�B�@
�����������Ɍ�ɑ����@�̑��c�Ƃ�����ꂽ�l�����o�ꂷ��B
�O�㑊�_�Ŕs�ꂽ�O�ʋ`��i�i�����O���j�̍����
��掛�����R�����i�P�Q�U�W�`�P�R�Q�T�j�ł���B
���R�͎t�m�`��̈�u���p�������ȗ��̏o�ƏC�s�ɉ����āA
�����I�ȉ����A�F���A��Ȃǂ�������A
�i������`���̋��_�Ƃ��ĉ������m�⏤�l�ɑT���L���ďC�s�l���̊g��������炵���B
����ɂ́A���R���ˋ��������@���A
�ȑO�̔��R�n�̎R�x�@���ł���V�䎛�@�i�V�䔒�R�n�j�ł��������Ƃ�A
�T�����C�I�X���̖@���h�̑T�m�����R�Ƃ̖��ڂȊW���e�����y�ڂ����Ƃ��l������B
�܂��A�ӔN�̓����͏����̏o�ƏC�s�ɔے�I�������Ƃ������Ă��邪�A
���R�͐ϋɓI�ɖ剺�̏������Z�E�ɓo�p���A���l�����̎v�z�𐄂��i�߂��B
�����̑����@�̗��������R�Ƃ��̖剺�ɂ����̂ł���ƌ����Ă悭�A
���̂��ߑ�4���ł���Ȃ���J�c�����Ƌ��ɏ@�c�Ƃ��đ�������Ă���B
�����������@�̌����I�v�z��ł����Ă��Ƃ�������R������
����O�ɐe���߂�M�ɂ����ƌ����邾�낤�B
���ۓ����̎v�z�͋M���I�����I�Ŗ��O�ɂ͐e���݂ɂ����B
�����@�����O�ɍ���ɂ����R�̂悤�Ȑl�����K�v�ƂȂ����Ǝv����B
�����@�����O�ɍ���ɍۂ��đ����V����d�������̂ő��������������B
�����̋����I�ȑ��Ǒō��Ɋ�Â��u���`�̕��@�v�͗]��ɂ������ł��������߁A
�ނ̌�p�҂ɂ͎����ꂸ�A
�S��̖@���ł������R�����ɂ���Đ������H���ɂ͂�����ƕω������̂ł���B
�܂��A���R�剺�ɂ͎l�N�ƌĂ�閾���f�N�A���U�q�^�A��R�АׁA��低���
���͂��߂Ƃ���r�p��ނ������y�o�������@���c�̋����̊�b���ł߂��B
���̂����A�����f�N�i�߂��ق����ĂA�P�Q�V�V�`�P�R�T�O�j
����R�А��i�����傤�����A�P�Q�V�T�`�P�R�U�U�j��
�u�@�̖����A�����̉�R�v�ƕ��я̂��ꂽ�B
�P�U�W�P�N�̒����ł͉i�����̖����P�C�R�V�O���ɑ��A�������̖����͂P�C�U�P�V�X���𐔂��Ă���B
���̐����͑������𒆐S�Ƃ������R�剺�ɂ���đ����@���c�������������Ƃ������Ă���B
���̂悤�ɂ��ē��{���\����悤�ȑ勳�c�����R�h�ɂ���Đ��������̂ł���B
�ȉ������R�̍s����������Ă݂�B
1285�N�A壎R�� �����s�r�ɗ��B
��c���Ɏ�~�i�����̈╗�����炷��ێ�h�̑T�t�j�Ȃǂ�K�ˁA
��b�R�ɏ���ēV�䋳�w���w�B
1286�N �A�`��̂��Ƃ��痣��A������K�˂��B
�܂���~�Ɋw�сA��ɁA���R�X�ƁA���_�d�ł�ՍϏ@�̏��t��K�ˁA
�I�ɗR�ǂ̋������ɐS�n�o�S�i�ՍϏ@�̑T�t�j��K�˂��B
1321�N �\�o�Ŋ�i���ꂽ���@�n�̎��@��T�@�����đ��������J�R����B
��̗�Ɍ���悤�ɁA���R�����͓V�䋳�w���w��A�Սόn�̑T��S�n�o�S�Ɋw��ł���B
���R���K�ꂽ�A���R�X�ƁA���_�d�ŁA�S�n�o�S�͑T�����C�̑T�t�ł���B
�\�o�ł͗��@�n�̎��@����i����A�T�@�����đ��������J�R���Ă���B
���̂悤�ȗ�Ɍ�����悤�ɔނ̍s���͕��L��������肪�Ȃ��B
�����ƈقȂ�L������Ǝv�z���������l���������Ƃ����邾�낤�B
����ɂ����R�̎t�m�ł������`��T�t�̉e�����l�����邾�낤�B
�lj_�����i�������傤�A�i�����A�P�P�X�W�`�P�Q�W�O�j�F
���ƓV��@�̑m�ŏ�y���▧�����w�сA
���{�B���@�̕��n�o��ɎQ���đT���w�B
���n�o��͒B���@�̊J�c����\�E�̍���ł���B
�P�Q�R�S�N������K�˒�q�ƂȂ����B
�����͕��n�o��̊��߂œ����̖��@���Ɏ������ƌ����Ă���B
���Q�͓�������ΔN���̒�q�ł������B
���{�B���@�̊J�c����\�E�̎���A
�B���@���琔�\�����W�c���@���������c�ɋA�˂����B
���̏W�c���@�͒B���@�̏o�g�ł�����Q�����U�������߂ƍl�����Ă���B
���{�B���@�Ɣ�b�R�Ƃ͓G�ΊW�ɂ������B
���̂��Ƃ������œ������c�͔�b�R�ƕs�a�ɂȂ�A
�����͉z�O�Ɉړ����i���������Ă��ƍl�����Ă���B�@
�����̐M�����Ă������̎���i�����Z���ƂȂ����B
�O�ʋ`���i�Ă����������A�i�����O���A�P�Q�P�X�`�P�R�O�X�j�F
�g���������{�B���@�̉��ӂ̉��łP�Q�R�P�N���o�Ƃ����B
��b�R�Ŏ�������㋻�����œ����̒�q�ƂȂ�B�����掛�̊J�R�ƂȂ�B�v�V�h�B
�`���i������A�i�����S���A�H�`�P�R�P�S�j�F
�`���͌��X�A�z�O�����{�B���@�̔g�����œ��{�B���@�̉��ӂ̉��ŕ��@���w�сA
�m���Q�N�i1241�j�ɏ��߂ē����T�t�ɉ���āA��q�ƂȂ����B
�����T�t�̐��O���ɂ́A���҂Ƃ��Ďd���A
��Ɂu�i���L�^�v��ҏW����ɓ����蒆�S�I�������ʂ������B
�����̌͒W�ȑT���𒉎��Ɏ�낤�Ƃ���ێ�h�̑T�t�B
��~�i���Ⴍ����A1207�`1299�j�F
�����E���z�o�g�̒����l�ł���B
�����i��v�j�̓V���@��T�t�̉��ŏC�s���Ă��������T�t�ɏo���������Ƃ��@���Ƃ��āA
��ɓ��������ē��{�ɗ������Ă��̖�l�ɂȂ����B
�@�����T�t�S����ɉ��Q�T�t�̖@�k�ƂȂ�B
�z�O�����ɕ�c�����J�����B
��~�T�t�̌n���͎�~�h�ƌĂ�A�����̈╗����낤�Ƃ���ێ�h�Ƃ��Ēm����B
���n���͌�X�܂ʼni�����̏Z���߂邱�ƂɂȂ�B
�����V���R�̔@��T�t�̉��ŏC�s���Ă���Ƃ��ɁA���{���痈�������T�t�ɏo�����A
���̓��S�Ă����ƂɊ�������B
�����ŁA�@��T�t���S���Ȃ�ƁA���{�ɗ��ē����T�t�̒�q�ɂȂ邱�Ƃ��肢�A
���̑������������B
�����̎����͈���Q�N�i1228�j�ł������Ɓi����ɂ͂��̑O�N�j����Ă���B
���{�ɗ��Ă���̎�~�T�t���ǂ̂悤�ȏC�s�����Ă������͏ڂ����͒m���Ȃ��B
�����T�t������������i�����Ɉڂ�ۂɓ��s���āA
�i�����Ɍ��Ă�ꂽ�@��T�t�̓����ł��鏳�z���̓��i�߂��B
�����T�t�����₷��ƁA���̒�q�ł�����Q�T�t�ɎQ���āA�����J���Ė@�k�ƂȂ����B
���̌�A�m�~����Ƃ����҂��z�O���ɕ�c�����J���ƁA
��~�T�t��q���������߁A���̊J�R�Ƃ��Ď��ɓ��邱�ƂɂȂ����B
�Ȃ��A���݂ł���c���̋߂��ɂ́A��~�T�t�����T�������Ƃ������T��Ƃ������̂�����B
�`�_�i������A�i����5���A�P�Q�T�R�`�P�R�R�R�j�j�F�@
�i����5���Ƃ��ĐW�Z���A�i�����̒����Ə̂��ꂽ�B
���s�̌����̉Ƃɐ��܂ꂽ�`�_�T�t�́A�n�ߋ��s�̋��@���@�ɂďo�Ƃ��A
�،��E�@�̑`��ʂ��āA���w���w�B
24�̎��ɁA�T�@�ɓ]���āA�z�O���̕�c���Ɏ�~�T�t��K�˂��B
��~�T�t�̍��E�Ɏ����āA20�N�ɂ��Ă悤�₭���̓����̌��|�𗹓����A�k�@�����B
�������N�i1299�j��~�T�t���J������ƁA���̈⌾�ɂ��������āA��c����2���Ƃ��ē������B
�i����4���ł������`���T�t���J������ƁA��h�߂̔g���쎁�͋`�_�T�t�𐿂������߁A
62�̎��ɉi����5���Ƃ��ĐW�Z�����B
�����̉i�����́A�O�㑊�_�̉e���Ȃǂ������čr�p���i��ł����Ƃ���Ă���A
�`�_�T�t�͕�c������Y���������o���ĉi�����̉��������ɓw�߁A
�Z���Ƃ��Ă�10�N�]��̊����ɂ���Ē����Ə̂���Ă���B
���ދ`���i������A�P�Q�P�V�`�P�R�O�O�j�F
�㒹�H�V�c�̑�O�c�q�B�P�T�˂̎���b�R�ŏo�Ƃ��V�䋳�w���w�B
�������{�B���@�̑���\�E�̉��ŗՍϑT���w�B
�P�Q�S�P�N�R�鍑�[���̓����̉��ő����T���C�s����B
�Q�x�����v����B�P�Q�U�V�N�v����A���̑D���Ń_�L�j�V����_����Ⴄ�B
���̎p�����g�̎�ō��ݏI�����_�Ƃ��ĐM�����B
�T�����ł͂Ȃ������ɂ��S���������l�Ǝv����B
�L���ׂ̐瓪�ʉ@�̖{�����ω��͊��ދ`���`���̕����Ƃ���邱�Ƃ���
�ω��M�̐l�Ƃ��v����B
�L���ׂ͐����ɂ͖L��t�������Ə̂��鑂���@�̎��ł���B
�������͊��ދ`������6��ڂ̖@���A���C�`�ՑT�t(�Ƃ���������������)�ɂ��J�n����A
�_�L�j�V���J�閼���Ƃ��Ēm���Ă���B
���{�B���@�͑���\�E���J�c�Ƃ�����{���̑T�@�ł���B
�B���@�̔��W�Ɋ�@�����������V��@�Ɉ�������A�J�c����\�E�͖d�E���ꂽ���ʁA
�����͎��Ă��A��q�B���U��U��ɂȂ������߂��̏ڍׂ͂͂����肵�Ȃ��B
���������@�̑T�t�B�̒��ŁA�ڂɕt���̂͑���\�E�̍��핧�n�o��̖@�n�̐l�O��
�i�����A�`��A�`���j���i��������i�Q�C�R�C�S���j�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���B
�܂��A�����剺�ɓ��������ӁA�����A�`��A�`���̎l����
�ꎞ���{�B���@�ŏo�Ƃ������ɑ����Ă����B
���ӁA�����A�`��A�͂��ߑ����̒B���@�̐l���������c�ɓ��M��������
�B���@�̋����͐������ƍl�����Ă���B
�B���@���猩���ޓ��̖@�n�}�������̐}�T�D�P�O�Ɏ����B
�O�㑊�_�̎����`��B���@�̏o�g�ł��邱�Ƃ���莋���ꂽ�Ƃ��`�����Ă���B
�B���@�̑T�͗ՍϏ@��d�h�ɋ߂��Ƃ���Ă���B
�����̂��Ƃ���A�����@�̏����̗��j�ɂ����ĒB���@�̉��炩�̉e�����������Ƃ��l������B
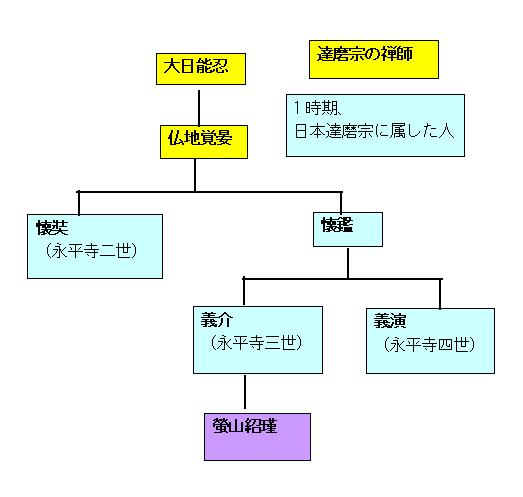
���R�����͋`��̍���ł���B
�ނ͂P�R�Q�R�N�i�����R�N�A�T�U�j�̎��A
�i�����R���ɑ����T�̎k��������킷���������������B
�@��̌�^�A�����̈⍜�A�����̌��o�A�`������R�֓`����ꂽ���{�B���@�̎k�������߁A
�����T�̎k���Ɠ`�߂݂̂��c�����B
���̂��Ƃ������{�B���@�̉e�������R�����ɂ��y��ł����ƌ�����̂����m��Ȃ��B
���F�@�@�@�k���@
�����@�ŏd�������k���Ƃ͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�T�@�ł́A��q���k�@������Ƃ��āA�t����n����������ꂽ�B
������w�k���x�Ƃ����B�����͎����T�@���h�ɂ���ĈقȂ��Ă���B
�ʏ�A�ߋ��������琼�V��\���c�E���y�Z�c���o�Ċe�h�̌n���ɘA�Ȃ�
�c�t�̖��O���L����Ă���B
�Ȃ��A����m�����̏Z���ƂȂ�A���̏ؖ������߂�ꍇ�ɁA
�t�Ƃ��ׂ��҂ɑ��đ����鏑�ނ����w�k���x�{���̎p�ł���Ƃ̐�������B
�P�Q�S�V�N�A�����i�S�W�̎��j�́A
�z�O�̌�Ɛl�ł���g����`�d�̐i���Ǝ����k�������̋��߂ŁA���q�ɍs�����B
�����́A�����̂��߂ɁA���s�̌��m����藧�h�ȑT�������q�Ɍ������A
�������J�c�Ƃ��Č}�������Ɛ\���o���B
�������A�����͂��̐\���o��f��A�z�O�̉i�����ɋA�����B
�����́u�z�O�̓y�n�����B���̑���Ɋ��q�ɂ��@������ɗ��ė~�����v
�Ƃ����w��i���x�����q�Ɏc���Ă��������̒�q�����Ɏ��������B
�i�����ɈӋC�g�g�ƋA���ė��������́A
�傫�Ȑ��Łu���q�����k���������܂���̊�i�����v�ƌ����āA�����̕����ɓ������B
���R�A�����͒P�Ȃ�D�ӂł������Ƃł���A
�������f���ɂ��̂��Ƃ��t�����ł����Ǝv�������낤�B
�������A�ӊO�ɂ��A������⓹���͗�̔@���{�����B
�����́u���̂悤�ȕ��́A�~��������O�Ɏ����悤�v�ƁA�������j��ɂ����B
�����͂������܌����̖@�߂�����Ď�����Ǖ��������A���ꂾ���Ŕނ̓{��͎��܂�Ȃ������B
���������T�����鎞�Ɍ��߂��Ă������Ȃ��̂ċ���A
���ꂾ���ł��q��͗����ʂƂ���ɁA���̏����̓y��x��̂Ă邱�Ǝ��ڂɋy�Ƃ����B
�����̂��̈�b�͑����Ɍ㐢�̏��F����������Ǝv����B
���������{�ɋA������ɓ�����A�t�̔@��͓����ɁA
�w��W�ڗ��ɏZ�ނ��Ɩ܂�A������b�ɋ߂Â����Ɩ܂��A
�[�R�H�J�ɋ����āA��Ӕ��ӂ�ړ����A�䂪�@��f�₹���ނ邱�Ɩ܂��x�Ƌ����r�߂��B
�����͎t�@��̂��̌P�r�𒉎��Ɏ�����ƌ�����B
���͂ɋ߂Â����Ƃő������@���Ƃ��������Ƃ��܂������ł���A
�ނ����̂��Ƃ��ł����߂��C�������킩��ʂł͂Ȃ��B
�����́u���@�ᑠ�v�s���̊����ɂ����Ď����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u��t�V���a���͉Ò�̍c���莇�ߎt��������Ƃ����ǂ����Ɏ��A�C�\���ӂ��B
�܂��Ƃɂ���^���̍s���Ȃ�B���̌̂́A�����͔Ƌւ��������B
�Ƌւ͈ꎞ�̔�Ȃ�A�����͈ꐶ�̗݂Ȃ�B���납�ɂ��Ď̂Ă��邱�ƂȂ���B�v
�����́A�h�_���~�����A���������Ƃ���������������s�ׂ�
�ꐶ�U�ɗ݂��y�ڂ����{�I�ȍ߈����ƍl���Ă��邱�Ƃ�������B
���̂悤�ȍl�����������ɂƂ��āA
��q�����̖�����������s�ׂ͋����Ȃ��s�ׂ������ɈႢ�Ȃ��B
�������A���������T������Ȃ��̂ċ���A���ꂾ���ł��q��͗����ʂƂ���ɁA
���̏����̓y��x��̂Ă邱�Ǝ��ڂɋy�Ƃ����b�ɂ�
�����̌��ȏǂɋ߂����i��������͕̂M�҂������낤���H
�����̂��̐M�O��i���l���鎞�A
�u���R�����̐����Ƃ̒��a��`��F���I�����i�����j�ւ̐ڋ߂ɂ��
�����@�̋��B�g��H���͓������`�̕��@�ł͂Ȃ��v
�Ƃ��Ĕے肳���͓̂��R�̂��Ƃł��낤�B
���ہA�����̈╗�����`�����~��̕ێ�h��
�O�ʋ`������R������̊v�V�h�i�����g��H���h�j���i��������ǂ��o�����B
���̌��ʁA�����̑T������낤�Ƃ��錴����`�H���͉i�����𒆐S�Ɏc�����B
�`������R������̋��B�g��H���h�͉i�������o�āA�������𒆐S�Ɋ��������B
���̂悤�ɍl����Ƒ����@�ɓ�̖{�R�����邱�Ƃ��c�i���c�Ƒ��c�j
�����镡�G�ȗ��R���X�b�L�������ł���B
�苖�ɂ��鑂���@���T�̓��e���y�[�W���ĂŌ���Ǝ��̕\�T�D�T�̂悤�ɂȂ�B
| ���ځi���ҁj | �y�[�W | �y�[�W�� |
| �������T�V�Ɗw���p�S�W�i�����j | �P�`�P�V | �P�U |
| ���@�ᑠ�i�����j | �P�V�`�V�O�V | �U�X�O |
| ���T�p�S�L�ƎO�����T���i���R�j | �V�P�R�`�V�Q�R | �P�O |
| ��������C�؋` | �V�Q�T�`�V�R�Q | �V�@ |
�\�T�D�T�̊e���ڂ̒��Җ��ɂ���đ����@���T�̓��e�͂���Ǝ��̕\�T�D�U�ɂȂ�B
| ���ڂ̒��Җ��j | �y�[�W�� | �y�[�W���́� |
| �����@ | �V�O�U | �X�V�D�U�� |
| ���R���� | �P�O | �P�D�S�� |
| ��������@ | �V | �P�D�O�� |
| ���v | �V�Q�R | �P�O�O���@ |
���̕\�T�D�U�ŕ�����悤�ɁA�����̒��삪�X�V�D�U�����߁A���|�I�ɑ����B
����͑����@�̌����Ǝv�z�����|�I�ɓ����i���c�j�P�l�Ɉˑ����Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�����@�̋��������݂̑�@�h�Ɋg�債�����R�����i���c�j�̒���͋͂��P�D�S���ɉ߂��Ȃ��B
�����u�T�Ƃ͉����H�v�ɂ����āA��ؑ�ٔ��m��
�u���{�̑����@�͓����@�Ƃ������̂ɂȂ���
�����T�t���̐l�����肪�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B
�����@�͓����T�t�̐l�i�ɏW�����Ă���X���������B
���̈Ӗ��ő����@�͓����@�ł���B�v�Əq�ׂĂ���B
�\�T�D�U�̑����@���T�̓��e���͂̌��ʂ͂܂��ɗ�ؑ�ٔ��m�������Ƃ���ł���B
�����@�̏ꍇ�Ɠ����l�ɁA�ՍϏ@���T�̓��e���y�[�W���ĂŌ���Ǝ��̕\�T�D�V�̂悤�ɂȂ�B
| ���ځi���ҁj | �y�[�W | �y�[�W�� |
| �ՍϘ^�i�Սρj | �P�`�S�X | �S�W |
| �Ɋޘ^�i���华�j | �S�X�`�P�V�P | �P�Q�Q |
| ����ցi����j | �P�V�P�`�Q�O�V | �R�U |
| �܉Ɛ��@�^�i��ՏГ܁j | �Q�O�V�`�S�O�P | �P�X�S |
| ���k�^�i���B�d�߁j | �S�U�X�`�T�R�X | �V�O�@ |
| ���@�a�����a�W�i�B���j | �T�R�X�`�U�P�U | �V�V�@ |
���F
��̕\�ɂ����ėՍϘ^�̒��҂͗Սςł͂Ȃ��Սς̖@�k�O���d�R�ɂ��ҏW�Ƃ���Ă���B
�������A�Սς���l���ɂ�����^�Ȃ̂Œ��҂�Սςƌ��Ȃ����B
�\�T�D�V�̍��ڂ������ɂ���ē��e�͂���Ǝ��̕\�T�D�W�̂悤�ɂȂ�B
| ���ځi�����j | �y�[�W�� | �y�[�W���́� |
| �ՍϘ^�A�Ɋޘ^�A����ց@ | �Q�O�U | �R�V�D�V�� |
| �܉Ɛ��@�^�i��ՏГ܁j | �P�X�S | �R�T�D�T�� |
| ���k�^�i���B�d�߁j�@ | �V�O | �P�Q�D�W�� |
| ���@�a�����a�W�i�B���j | �V�V | �P�S�D�P���@ |
�\�T�D�W�Ɍ�����悤�ɁA�ՍϏ@���T�ɂ͗ՍϘ^�̑���X�̌�^�⒘�삪���߂�ꑽ�ʂł���B
����͕\�T�D�U�̑����@���T�̕��͌��ʂƑΏƓI�ł���B
�����u�T�Ƃ͉����H�v�ɂ����āA��ؑ�ٔ��m��
�u�����@�ƑΏƓI�ɗՍϏ@�͓����T�t�̂悤��
����̐l�𗧂Đ_�i������悤�ȌX���͂Ȃ��B
����Ŏ��R�ɖ@�ɏW������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��c�����B�v�Əq�ׂĂ���B
�\�T�D�W�̗ՍϏ@���T�̓��e���͂̌��ʂ͂܂��ɗ�ؑ�ٔ��m�������Ƃ���A
�ՍϏ@�ł͓���̐l�𗧂Đ_�i������悤�ȌX���͂Ȃ����Ƃ������Ă���B
���F
�u�܉Ɛ��@�^�v�F ��v�̊�ՏГ܁i�����t�̖͂@�k�j�̐�B��S��N�i1254�j�ɐ���B
���c���B�����܉Ƃ̊e�h�Ɏ���c�t���\�l�l�̗��`���f���āA
�e�h�̏@���̍j�v�𖾂炩�ɂ��Ă���B
��̕��͂ɗp���������@���T��
�@���a�V�[����呠�o�ҏW���A�������@�A
�u���a�V�[����呠�o�@�@�T���@��܊��@�����@���T�v�i�P�X�Q�X�N���s�j�A
�ՍϏ@���T�͏��a�Ҏ[����呠�o�ҏW���A�������@�A
�u����呠�o�@�T���@��Z���@�ՍϏ@���T�v�i�P�X�Q�X�N���s�j�ł���B
�����̐��T�͂Ƃ��ɂP�X�Q�X�N���s�̂��̂ŏ����Â��B
�������A���̖{���͌��݂܂ŕς���Ă��Ȃ��ƌ�����̂ŁA
�����œ���ꂽ���_�ɉe�����Ȃ��ƍl������B
�g�b�v�y�[�W��
��U�́@���ā@�֍s��
�y�[�W�̐擪�֍s��